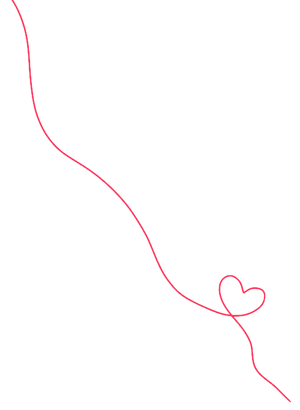
恋人がいる。年下の。 どんな女かと言えば――まぁ、どこにでもいるような、それこそ“平凡を絵に描いたような”女と言っていい。しかし、その平凡さがよかった。俺にとっては何よりも輝いて見えたし、素直に好意を見せてくる姿は、どうしようもなく愛らしく映った。アジーム家に出入りするような派手な女はもう見飽きていたし、男なんてこうすればすぐ靡く、とでも言いたげな視線を向けられるのはうんざりだったのだ。 俺はそこらの、目先の快楽でしか物を考えられないような阿呆ではないし、体を寄せられたくらいでだらしない顔を晒す馬鹿でもない。しかし、この女はどうだと差し出されるのは、そういう野郎にお似合いの女ばかりだった。随分と舐めてくれたもんだな、という話である。私にはもったいないお話ですので……とかなんとか言いながら、俺は毎回頭の中で中指を立てて唾を吐いていた。 そんな折に見つけたのが、彼女だった。 カリムと共に、輝石の国に商談に赴いた時、たまたま寄ったカフェで店員をしていた。カリムがいやに「あの子、かわいいな」だとか「ほら、ジャミル!」とうるさく声を掛けてくるので、いい加減にしろと小突いてやろうとしたその瞬間、顔を真っ赤に染めた彼女が俺の手を掴んだのだ。いや、掴んだというより、柔く握った、というほうが正しいかもしれない。 「……何か?」 人当たりの良いだろう笑顔を浮かべた俺に、ますます頬を染め上げる。鈍い男ではないから、なるほど、とその手を握り返した。すると彼女は、「あの、その、こ、これ!」と小さく折りたたまれた紙を押しつけて、呼び止める隙もなく店の奥へと走っていってしまった。 カリムが訳知り顔で、「かわいいなぁ。なあ、ジャミル」と言うので、今度こそ能天気な頭を小突いてやった。 その夜に、俺は押しつけられた紙にあったIDに連絡を入れて、輝石の国に滞在している間、暇とタイミングさえ合えば彼女と出かけた。観光地を紹介してほしいと言って、恋人ごっこをしていたわけだ。 彼女はよく笑った。その笑顔には俺への好意が溢れんばかりに満ちていたし、目を逸らした時に送られる視線は、いつだって熱っぽく、そして甘やかだった。景色を見るふりをしては、それを満足するまで受け止めた。 しかし、彼女は一度として、俺に好きだとは言わなかった。あからさまなまでに、俺が好きだと体いっぱいで示すくせして。 そうこうしているうちに、熱砂に戻る日がいよいよ迫った。子供じみた恋愛ごっこが、終わりに近づいていく。それでも、彼女は何も言わず、ただ笑顔を浮かべて、俺を甘やかな視線でもって雁字搦めにしていった。 ――好きだと、一度でも言ってくれさえすれば。 結局、焦れた俺が輝石の国を立つ前日、「俺の国に来てくれ」と跪くことになったのだ。 とは言っても、彼女は輝石の国で生まれ育った女で、家族も仕事もそこにあった。それをすべて捨てろと言えるほどの関係性にまでは育っていなかったし、俺にも立場や家の事情などがあるから、いわゆる遠距離恋愛というやつだ。 それでも、毎晩彼女が眠るまで通話して、毎朝モーニングコールをしてやった。そんなことしなくていいと言われても、そのくらいのことをしなければ、俺たちの関係はいつ終わったって不思議でない。相手を思う気持ちさえあれば? 愛さえあれば? そんな薄ら寒い恋物語などを信じるのは、頭の中に花畑でも持ってる馬鹿だけだ。 顔を合わせるにはいつだって、彼女のほうが熱砂までやってきた。俺が自由に動けることはそうないし、彼女のほうも観光気分でいたので、そう悪くはなかったろう。腹が立たないこともないが、俺たちを結びつけるきっかけになったカリムも、彼女がこちらに来ることを知れば融通を利かせるだけの気遣いは見せたので。 だから、問題などは何一つなかったはずなのだ。 「――ごめんなさい」 何を言われたのだか、一瞬理解ができなかった。 一世一代のプロポーズだ。跪いての、プロポーズだ。俺が彼女のそばに永遠に在り続けることに対する、許しを得るための。何度も何度もシミュレーションを重ねて、これ以上はないというほどに整えた舞台でのことだった。 ――そんな、馬鹿な。 付き合って三年だ。そろそろだと思っていたのだ。 俺の立場ももはや盤石と言っていい状態だし、彼女だってこれまで幾度となく熱砂に来ていたから、こちらのことは現地の人間と変わりないほどに詳しい。俺たちの間の信頼関係も十二分だし、愛情は衰えるどころか増していくばかりだ。だからプロポーズした。もちろん、彼女も同じくそう感じているだろう。そう思って。 断られるだなんて、まったく想像すらしていなかった。 「……すまない、何が問題なのか分からない。俺はもう二十八だし、君は……二十五で結婚は早いと思うのか?」 いつまでも跪いていたって仕方がないので、俺はゆっくりと立ち上がった。慎重に力を入れていかなければ、今にも膝から崩れ落ちそうだというのもある。 彼女は俺から逃げるように視線を逸らして俯くと、「いえ、そういうことじゃ」と言ったきり、黙ってしまった。しかし、たっぷりとした沈黙を挟んだあと、俺がなんとか絞り出した「……別れたいということか」という言葉には、慌てて顔を上げた。視線は合わないままだが。 「そうじゃなくて、」 彼女の友人が結婚しただとか、子どもができただとか。そう言う話も聞くようになった。その割に俺たちの話にはならないなと思ったこともあったが、周りがそうだからとするものでもないし、急かされるよりかはいいだろうと深くは考えていなかった、ちっとも。そう、断られるだなんてことは、砂の一粒分にだって思っちゃいなかったのだ。 努めて冷静にと、行き先を失った指輪に埋まる石を見つめる。 「……タイミングか、それとも指輪が気に入らなかったか」 「違うんです」 「じゃあなんなんだ」 ――ジャミルさんのことは好きだけど、結婚までは考えられないんです。 「……遠回しに振られてるでしょうそれは」 「ふざけんな振られてない」 ガンッとグラスをテーブルに叩きつけると、アズールは肩を竦めた。 こいつに相談なんかするつもりじゃなかったが、こいつの会社が手掛ける雑貨ブランドを彼女が気に入っているから、何かしら有益な情報を得られるんじゃないかと少し、少しは思ったもんだから呼び出したのだ。役に立ちそうにないが。いや、それでもだ。もうどんなものでもいいから縋りたい状況なのだ。それがアズール・アーシェングロットでも。 アズールがグラスを傾けると、中の氷がからりと音を立てた。 「別に結婚に拘る必要はないんじゃありませんか? 要するに結婚願望がないんでしょう、彼女」 泣きながら、俺に何度も頭を下げて立ち去った彼女の後ろ姿が思い出される。 あれから何度か連絡しているが、こっちが驚くくらいには“普通”だ。別れるとは言わない。しかし、プロポーズのことにも触れない。そうなると俺のほうもどうしたらいいのか分からないので、こちらも同じく、である。 壁に掛かっている時計をちらりと見て、そろそろ彼女がベッドに入る時間だな、とぼんやり思った。電話してやろうと考えながら、「なぜ」とアズールに返す。すると、不自然なほどにゆっくりした動作でグラスを置くので、ちらりと視線を向ける。 「……すみません、僕も遠回しに言いました。つまり、彼女にとってあなたは、結婚に向かない人間なんですよ」 「はァ?」 据わった目で睨めつけると、アズールは大袈裟に溜め息を吐いた。 「こう言ってはなんですが。ジャミルさんの几帳面なところが気になるんじゃないですかね」 今度は口にこそ出さなかったが、はァ? である。 「几帳面が悪いって言うのか、まさか。俺のよく気がつくところが好きだと言ったぞ、彼女」 ――わたしの心の中が、見えてるみたい。 そう照れたように笑った彼女に、俺はなんと返したんだったか。 やはり電話したほうがいいな、と思ってポケットを弄っていると、アズールが「ですから、」と俺の動きを制するように強く言い放った。 「恋人ならそれは嬉しいけれど、夫にするには気が引けるということですよ。あれはこうしろ、これはこうじゃないとか、あなたに要求されることに応える自信がない……いえ、合わせられない、合わせたくないということです」 は、と呟きとも溜め息とも取れない中途半端な音が喉から漏れた。……それじゃあまるで、「……振られたみたいじゃないか……」と言うと、アズールは可哀想にという顔つきで、「ですから、そう言いました」と返してくる。 「……どうすればいい」 「さぁ?」 「はァ? 少しは役に立てよッ!」 「急に呼び出しておいてなんですか酔っ払い!」 いや、他に何がある? 三年だぞ三年。俺にとっても彼女にとっても、決して軽いもんじゃない。十代の恋愛とは違うし、真剣に付き合ってきた。もちろん将来を見据えて。それが、結婚は無理? しかも、問題は俺だって? 「別れるなんて無理だぞ、俺は彼女じゃなくちゃ嫌だ」 そうだ。俺には彼女じゃなくちゃ駄目なのだ。 どこにでもいる、平凡な女だ。別にこれといった特技はない。料理なんかは俺のほうが上手いくらいだ。手先も器用じゃないし、うっかりも多い。初めて揃いで買ったマグカップなんて、翌日の朝には割ってみせたくらいだ。 だが、それでもいいのだ。 美人がいいわけでも、なんでもできる女がいいわけでもない。平凡でいい。彼女なら、俺はなんだっていいのだから。不自由で、物足りなさばかりがある関係でも、彼女はいつだって俺を優しい瞳で見つめてくれた。それ以外のものは、何も求めちゃいない。 仕事? 彼女一人養うことができない甲斐性なしになった覚えはない。 家事? そんなものは俺がしてやればいい話だ。別に嫌いというわけでもない。 育児? 俺の子どもだ、喜んでやる。 もちろん、彼女を愛し続けることだって、いくらでも。 彼女が不安に思うことも、不満を感じさせるようなことも、全部俺が取り除く。ただし、何をしてやったらいいのか、それを教えてもらえないことには何もできない。……どうする。どうすれば――。 「結婚は諦めて、今の関係を続ければいいのでは?」 「そんな中途半端ができるかッ!」 アズールは呆れたふうに、「彼女がそれを望んでいるなら、中途半端ではないでしょう」と言うが、俺にとって! 中途半端なんだよッ! いい加減、一緒に暮らしたい。一人、真っ暗な家に帰るのはさみしい。おかえりなさいと、お疲れさまと、他の誰でもない彼女に言ってもらいたい。 それから、子どもだってほしい。俺に似て賢くて、彼女に似ておっちょこちょいな、それでもとびきり愛らしい女の子がいい。誰にも負けない一番のプリンセスにしてやる。 これを現実にするには彼女が必要だし、彼女さえ頷いてくれればすべて叶う。逆に言えば――彼女が頷かない限り、これは永遠に夢のままなのだ。 くそ、彼女、一体何を考えてるんだ? 俺のことを愛してないって言うのか? 今更? 三年だぞ三年。そもそも俺が跪いてプロポーズしたことを覚えてるのか? それを断っておいて、どうして何事もなかったように“普通”でいられる? というか、なんだ? 細かい? なら大雑把になればいいのかカリムみたいに! はァ? カリム? ふざけるなクソッ、腹立ってきた! 「ジャミルさん。今後も彼女とのお付き合いを続けていきたいのなら、あなたが折れる必要があると思いますよ。彼女の気が変わらない限り」 気が変わらない限りだと? ああそうかよ、ならどんな方法を使ってでも変えてみせるさ! ユニーク魔法? そんなもん使ってたまるかッ! 俺は振られたわけでも、彼女から愛されてないわけでもないんだからな! 「俺は絶対に彼女と結婚するぞ! 誰にも文句なんか言わせるか! それが彼女であってもだ!」 そうだ、誰にも――彼女にだって無理とは言わせない。俺が愛した以上、俺に愛させた以上、その責任はしっかり取ってもらわなければ。 まぁ、現状は何をどうすればいいんだか、サッパリなわけだが。 アズールがまた溜め息を吐いて、しかも首を(横に)振ったので、「クソッタレ、」と呟いて冷たいテーブルに突っ伏した。 |
画像:irusu