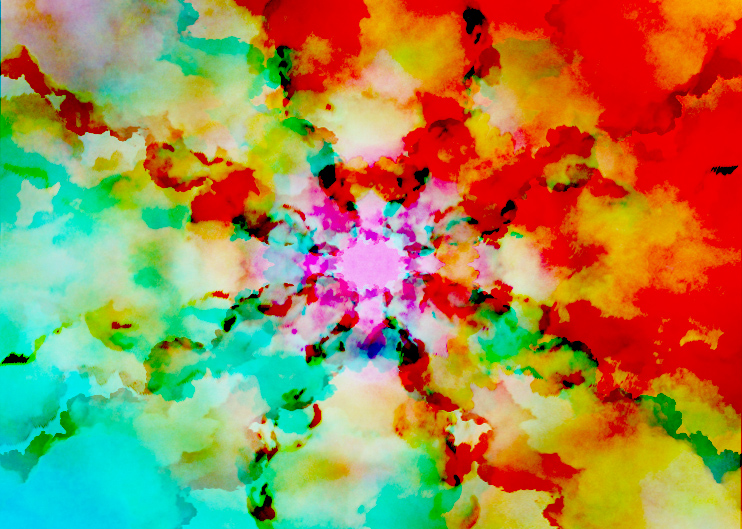
「……君って女は、どうしようもないな」 俺のベッドにうつ伏せに倒れている体の、白くほっそりとしたふくらはぎが目に痛い。ちらりと視線を動かすと、太腿まで無防備だ。 額に手を当てて、大袈裟に溜め息を吐く。彼女はゆっくりと体を起こすと、心底おかしいとでもいうように笑った。 「そーお? でも、そのどうしようもない女が好きでしょ、あなた」 ただの事実なので、俺も思わず笑ってしまった。反論の余地なしであるから、仕方ない。俺はただ、その肩を寝台に押しつけるしかなかった。彼女はますます笑う。くすぐったそうに体を捩って、しかし、俺の腕を、指先を、唇を、拒絶するようなことは一切せずに。 ふいに、視線が真正面から交わった。解いたばかりだった俺の髪が、彼女の頬にしな垂れる。ふふふ、という甘い声に自然と誘われて、柔い耳朶に歯を立てた。 「やぁだ、やらしいひと」 「ああ、そうだよ。君の前では、俺もただの男だ」 じっと、潤んだ瞳が俺を見上げる。 「……優秀なくせに?」 「優秀なせいで」 彼女との出会いは、何も特別なことではなかった。いや、些細な出来事すぎたのに、それがこうして実を結んだ時点で特別でないことはなかったのかもしれない。 市場が賑わう休日、俺は人混みの中を行こうとして、彼女はそこから飛び出してくるところだった。肩がぶつかってつんのめった彼女を抱き止めてから、俺たちは始まったのだ。笑える話だが、運命とやらに導かれて出会うものが、人生の中にいくつかあったとして。その一つはきっと彼女で、それもとびきり光る運命はこれだと思ったのだ。笑える話なのだが、俺は今でもこれを信じている。 だから、謝罪を口にして立ち去ろうとする彼女の腕を引いて、露天に並ぶ花を選ばせた。花を贈ったのだ。この女を逃せば、俺はきっと死ぬ間際にそれを思い出して未練を残すことになるだろうと思ったので、花を贈ったのだ。 あれから何度となく彼女の笑顔を見てきたが、やはりあの時のものが最も深く胸に刻まれている。思い出は美化されるというが、そうだとしたってあれは格別だった。あの日、照りつける太陽の下で。慣れた様子を見せながらも、彼女はそれを受け取った。今でも鮮明に思い出せる。そして、初心な少女のように喜んで、俺が指を絡めて手を引くことを許した。 ――あの日からこれまで、そしてこの先も。この女は、俺のものなのだ。 雨季に入った。雨が降っている。窓を叩きつける激しいスコールの音を聞きながら、目を閉じて椅子にしなだれかかるその姿を、じっと見つめる。海から這い出たような格好のせいで、体どころか髪からも、ひっきりなしに落ちていく雫が床を汚していくが、そんなことは少しも気にならなかった。 「お前、昨晩はどうした」 ひどい雨の中、俺を散々に待たせておいて、終ぞ現れずどこにいた。 彼女は薄らと目を開け、散々な俺の姿を興味なさげに眺める。それから、「どうしたって?」と溜め息交じりに呟いた。舌打ちする俺を見て、薄ら口元を緩めるだけの微笑みを浮かべる。傷つけてやろうと思っているのか、待ちぼうけの末に濡れ鼠に落ちぶれた男を嘲笑うことがしたいのか、どちらでも構わないが腹立たしい。 思い通りになどなってやるものかと思っても、結局、俺は傷ついているのだから。 しかし、そうと悟られるようではいけない。 俺を傷つけたのだ。笑っちまうほど健気に待った男を、傷つけた。それならば、こちらも同じだけ傷つけてやらねば気が済まない。冷え切っていたはずの体が、いやに熱を帯びていく。 「時計が読めなくなったか? それとも、待ち合わせ場所を忘れたか」 そう言って彼女を見下ろしたが、意に介さぬ調子で「優秀なのも困りものね。分かってるくせに、無理に逃げ道をつくろうとするんだから」と、呆れたふうに呟く。視線は、美しく整えられている爪から、ほんの少しだって動かない。 贈る相手を失ってしまった花は、かわいそうなので花瓶に活けた。わざわざ魔法までかけて持ち帰ったというのに、これを手にした時の鮮やかさも香りも、すっかり失われてしまっている。 彼女はちらりと目を向けて、それから、興味なさそうに部屋を出ていった。 なぜ、こうなってしまったのか。いつから、こうなっていったのか。俺には分からない。眩しいほど輝いていた笑顔が、こんな時に思い出される。 ――この花が一等好きなのだと、あの日笑っていたくせに。 寂しげな佇まいに耐えられず、花は花瓶ごとゴミ箱に投げ捨てた。 からりとした空気を撫でるように、風が吹く。 「おい、どういうつもりだクソ女」 今回のこれは、たまたまなどではない。出来すぎているのだから、故意のものだったと分かる。 見たこともない男と連れ立って歩いていたこの女は、いっそ清々しさまで感じる笑顔を浮かべていた。 すべてを従える女王にでもなったつもりか? お前が? 舌打ちをする俺を見て、思わずといった調子で忍び笑いを零す。憎らしいほど可憐な唇が、歌うようにして「あなたより彼のほうが素敵って、気づいちゃっただけよ」と微笑む。 テーブルを殴りつける俺を見て、女は鼻を鳴らした。 「いつもの冷静さはどこにいっちゃったの? 怖いわ」 「ほざけ。……もう一度聞く。どういうつもりだ」 彼女は長く、しかしきちんと整えられた爪で、こつこつとテーブルを叩く。また舌打ちする俺を見て、声を上げて笑った。 「なぁに、嫉妬してるの?」 嫉妬? 嫉妬だと? この俺が? この激情の正体がそうでないなら、一体何をそう表すのか。 「余計な口を利くな。……今ならどんな言い訳でも許してやる」 こつ、と音が止まった。 「ねえ、あなたにそんな権利がある?」 「俺にないなら誰にある」 「この世でいちばん素敵なひと」 上目遣いに俺を見つめて、さらにはあざとく小首傾げて言いやがる。 しかし、傷つくことはなかった。これまで――あの忌々しい日からずっと、俺はこの女を放し飼いにしてやっていたが、その間に何もせずにいたわけじゃない。それはそうだ。居心地良く環境を整えてやるからこそ、主人と言えるのだ。俺はそのための努力をしてきた。この女のために。 「ッハ! 笑わせるなよ、お前の目の前にいる」 彼女は、思ってもみなかった、というような顔をして、俺の目をじっと見つめた。何も考えずにいたツケだ。自分の姿を見てみろ。自分が置かれている現状を見てみろ。 完璧なかたちの爪も、絹糸ですら見劣りするかもしれない髪も、甘い色をした唇も。全部全部、俺がこの手で仕立ててやった。お前が着ているその服も、耳に飾られているピアスも、華奢な腕を守るように輝くバングルも。全部全部、俺が揃えて、俺が整えてやった。 馬鹿め、俺ほどの男がどこにいる。何なら、あの男を連れてくればいい。どちらが上だか、すぐに分かる。 ――主人は、この俺だ。 しばらくじっと黙っていたが、何やら納得した様子で彼女は頷いた。俺が何も言わないでいると、さらに深く頷いて「……そうね、うん、そうね。あなたくらい自分に自信があるひとって、そうはいないものね」と呟く。その体を抱き止めた腕を。手を引いた指先を。どうやらやっと思い出したらしい。 「そうさ。俺が謙虚を気取ってみろよ、世界中の男が死ぬ。情けなさでな」 彼女は笑った。あの日のように。 「今なら、何も聞かずに黙って許してやってもいい」 俺の言葉に、これまでのことへの罪悪感など一切感じていない調子で、「ほんと?」と胸に擦り寄って甘えた声を出す。 「嘘を吐いてどうする」 彼女は、そうねと小さく頷いて、「うん、ただいま」と俺の頬にキスをした。いつものように。いや、いつかのように。 まるで吐息みたいな笑い声を零して、俺は笑った。 「おかえり、馬鹿女。次は迷子にならないように、首輪でもつけておくか?」 柔い唇が、また頬に触れる。 「リードは?」という言葉は、あまりにもくだらない。 「必要か」 ほんの少し考えるような素振りを見せたが、結局「いらない」と返してきた。それから、「だって、あなたが世界でいちばん素敵よ」などと言う。 調子のいいこと言いやがって、と思ったが、気分がいいから許してやる。 「――当然だ、誰に言ってる?」 |
画像:はだし