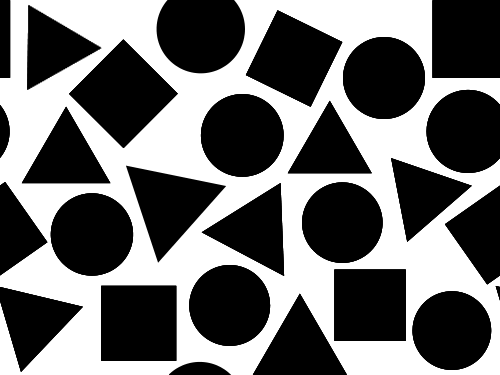
日当たりのいいこの席が、の気に入りだ。それから、ここのアイスティーも好きだ。だから大学の外で待ち合わせるときには、俺はこの店で落ち合おうといつも言う。は自分では気づいていないだろうが、子どものような顔で喜ぶ。俺がやってくるまで、は楽しそうにストローをくわえて待っている。まるで恋人を甘やかしているようで、俺はそのたび気分が良くなる。 「」 「ん?」 何度目かの俺の呼びかけに、はやっと反応した。何も考えていなさそうな顔をして、ただじっと道行く人を観察していた様子のだが、実際は真剣に何か考え込んでいたのは明白だった。それでも、はっとしたような顔はせず、ただのんびりとした声で応えてくるあたり、この女ほど胆が据わっているのもなかなかいるもんじゃないだろうと思った。 「何考えてる」 煙草に火をつけながら俺がそう尋ねると、はなんてことないように「え、あぁ、佐助のこと」と簡単に答えた。 ぴくっと眉が動いてしまったのが分かって、ちらっとの顔を見る。こちらの様子に気づいたようではない。それに安心して、ゆっくりと肺の中の濁った煙を吐き出す。 それでも、が男一人のことで“考える”ことをするなんてのは、付き合いが始まってからこれまで――少なくとも俺は――知らなかった。もし、という考えが浮かんで、いいや、と昨日の晩のの姿を必死に探した。 “いつも通り”だった。俺と楽しく酒を飲んで、散々に“楽しんだ”。朝のも、“いつもと同じ”ように笑っていた。それでも、どこか気色悪いものが抜けず、俺はもう一度煙を肺に溜め、またそれをゆっくり吐き出した。 「Ah? ……アイツとはもう終わったはずだろ」 俺の言葉に、は眉間に皺を寄せた。それから溜息を吐くと、「そうだよ。だけどさぁ、」と言ってストローを何度か噛んで、うんざりというように「佐助、昨日わたしが帰ってくるの待ってたんだよね」とアイスティーをすっと飲み込んだ。 なんだ、そういうことかと胸を撫でおろしたい思いになった俺に、はもう一度溜息を吐いたあと、「……あんなこと言い出さずにいてくれたら、ホントにイイ男だったからさぁ、もったいないって思って」とつまらなそうにまた道行く人へと視線をやる。 「……竜が猿に劣ると思うのか?」 思わず取り繕うのも忘れてそう口にした俺を、はきょとんと見つめた。何を言われたんだかよく分かっていないような顔だ。何か言葉を、と思った俺を待たずに「アッハハ! まさかぁ」との笑い声が響いた。 「でも政宗だって思わない? 佐助って、遊ぶにはイイ男じゃん。本人だって自分の魅力よく分かってて、だからこそ気持ちよく遊んでくれた」 “遊ぶ”にはイイ男――。そうでないなら、にとってはなんの価値もないのだろう。俺も“遊ぶ”にはイイ男から外れた瞬間、に他の男とこんな話をされるに違いない。 「……さぁな。俺は男になんざ興味ねえ」 はにこにこしながら、「それもそっか」と言って、またアイスティーを口に含んだ。赤い唇がいやに魅力的に映るが、それでいてどこか恐ろしいとも思った。 俺もいつ自分の立場が危うくなるか分からない。あの猿飛が、この女に本気を伝えてしまったからには。 それで自身が変わるだろうとか、そういう心配はしていない。この女は根っから“そういう”女なのだから。ただ、話を聞いてしまった以上、俺もうっかり「本気だ」と口にしてしまうのではないかと不安なのだ。と同じく、根っから“そういう”男であった猿飛が、「本気だ」なんて馬鹿なこと――俺はそうは思わないが、“そういう”人種からはそうなのだ――を言い出したのだから。それなら、本当に心の底からこの女を愛していて、“そういう”男の振りで誤魔化している俺はどうなる? 思わぬところで、“馬鹿なこと”を口に出してしまう可能性はないと言えるか? そんなことは、何があっても避けなければならない。そうでなければ、俺はの傍にはいられないのだから。 ――そんなこと、あってはならない。 は唇をなめると、俺の目を真っ直ぐに見つめる。 それから甘い笑顔を浮かべて言った。 「うーん、やっぱり政宗が一番イイ男ってことだね」 俺は笑ってしまいそうになったが、なんとも思っていないような顔をして煙草に口をつけた。 俺が一番“イイ男”? そうだろうな、徹底して“そういう”男を演じている。俺がの一番でなくてはおかしい。 そう考えると、猿飛よりも俺のほうが断然いい思いをしている。今こうしての傍にいることができて、この甘い笑顔は俺だけの――少なくとも今この瞬間は――もので、の瞳に映る男も俺だけだ。 大学では大抵二人でいることだし、外では俺と猿飛とがの“一番”をその時々で代わっていたが――今後は俺だけが本当のナンバーワンだ。の気に入る“次”が現れたとして、それはその時に考えればいい。 大分短くなった煙草を灰皿に押しつけると、その様子を見ても振り切ったように言った。まぁ実際のところ振り切るまでもなく、もう面倒だからそんなこと考えるのはやめよう、ということだろうが。 「まぁいいや、佐助の話は。それより聞いて! こないだの合コンでイイ男見つけたの。で、今度はお互いの友だち連れて遊ぼうって話になってさぁ。かすがはそういうの好きじゃないし、政宗は行ってくれるよね? イイコいるかもよ」 ――考えていたそばからこれだ。本当はの“一番”だなんてもんは存在していなくて、は自分が一番かわいいのだとよく分かる。舌打ちしたくなったが、それは“そういう”男がすることではない。 「……考えとく。で? お前はそのイイ男に“持ち帰り”される気か? 俺をフッて」 笑ってやると、も笑った。 「当たり前じゃん。まぁ、他にイイのがいたらそっちにするけど」 でも、と言葉が続く。この先は分かっている。こういう時のお決まりだ。 「もしお互い気に入らなかったら、政宗はわたしのこと“お持ち帰り”してくれる?」 その“お持ち帰り”ってやつで、「一度うちに持ち帰ったんだから、お前はずっと俺のもんだ」とできるというなら、喜んで頷いてやるところだ。けれどコイツの言うのはたった一度きりのもので、誰に持ち帰りされたって構わない。まぁ好き嫌いはあるが。だから保険として、気心が知れていて面倒でなくて、何より“同じ”である俺を取っておく。――こっちの気も知らないで、勝手な女だ。 「……そうなるだろうな」 それでも俺は、こうして甘い笑顔を浮かべる女を、いつかは恋人にしたいとずっと願ってやまない。それがいつになるかも分からないどころか、そんな保障はどこにもないというのに。だから俺は思うのだ。ただ、傍にいることができるなら、それでもいい。それだけでもいい。馬鹿な話だ。だが、そんな馬鹿な話でも受け入れてしまうほど、俺はこの女を愛している。 「うん、そうだよね。んー、わたしが思った通りの男だといいんだけどなぁ……。はぁー、やっぱり分かりきってるサッパリした関係って楽だよねえ。佐助でホンットそう思ったわ」 「そうか」 俺の返事に気を悪くしたらしいが、「……何? なんか政宗今日ノリ悪くない?」とストローを噛んだ。少し、考えすぎてしまったかもしれない。嫌味の一つでも言ってやろうかと思った。もう一度煙草に火をつける。 「別になんもねぇよ。ただ……俺もフラれただけだ」 俺のその言葉を聞くと、は打って変わって興味津々という顔で「えー、どの子?」とテーブルから身を乗り出した。ふぅん、という薄い反応であろうと思っていた。まさかが特別興味を示すとは思っていなかったので、思わず驚いた顔でもしそうになった。けれど、「っていうか政宗の相手って把握できてないから、聞いてもどうせわたし分かんないよね、あはは」という次の言葉で、期待するだけ馬鹿か、と思い直した。 「……だろうな。それで、お前今夜は?」 お前一人だ、と言えたら。それを嬉しいと言ってくれたなら、どんなにいいだろう。けれどそんなこと、この女に限ってありえないだろうことは分かっている。期待するだけ馬鹿だ、本当に。 俺の部屋にはの物がいくつも置いてあって、まぁしばらくうちにいたって生活には何の支障もないだろうというほどだ。このまま、ずっと俺のとこへいりゃあいいのにな、とまた馬鹿な期待をする。思い直したところで、何度だってそういう期待をしてしまう。俺はこの女を、馬鹿みたいに愛しているのだから。 「んー、佐助に荷物取りに来てって言ってあるから、政宗が他に約束ないなら行かせて」 なんでもないような顔をして当たり前に俺を頼るくせに、俺のものではないなんてどうかしている。 俺には他に約束を取りつける女なんて一人だって存在していない。適当にどこかで時間を潰して――“そういう”男の振りをする。まぁ怪しまれたら元も子もないので、時々は“そういう”女を相手にすることもあるが。 わざとらしく腕時計を確認して、「……そろそろ別の約束の時間だ。名残惜しいが一度ここでさよならだ」と言いながら伝票を取る。は何も気にした様子はない。 「……帰りはそうだな、二十二時頃になると思う。いいか?」 椅子に掛けていたジャケットを羽織る俺に、は不思議そうな顔をした。 「何? 確認することでもないでしょ、好きにして。わたしも好きに時間潰すから」 そう言いながら、はスマホにすぐさま指先を滑らせた。本当にこの女は、他に関心がない。それでも期待してやまない俺は、やはり馬鹿としか言いようがないだろう。それでもいい。それでもいいのだ。 もう俺のことは意識の外へと追い出しているを見て、俺はさっさと店を出た。 |