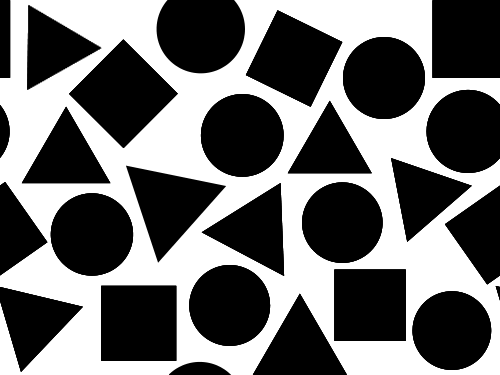
店員に案内されてきたに、いつものように手を挙げて挨拶する。するとぱっと表情を明るくさせて、向かいの席へとついた。こうして見る限りでは、“そういう”女にはとてもじゃないが見えないし、本当に俺の恋人であるんじゃないかと錯覚してしまう。そうであればいいと思うので、錯覚させてくれる、というほうが正しいかもしれない。俺はこの女が“そういう”女だとよく知っているくせして、どうともできずにいる。俺はそうであればいいと思っているが、のほうはそうではないのだから。 と俺とは、大学内では「あの二人は付き合っている」というふうに思われがちだが、まさか。ただ、二人で行動することが多いのは事実であるし、そう思われるのも通りだろう。本当のところは違うとしても。わざわざ訂正して回ることでもないでしょ? とは言う。それはが本気で、自分と俺が“同じ”であると思っているからだ。は自分の好きなように“遊ぶ”。俺もまたそうだと思っているのだ。だから平気で“お遊び”の合コンなんてものへ参加するし、時には自分で幹事を務めることだってある。俺とは“同じ”なのだから、お互いに干渉することはしない。俺ととの関係は、そうすることで成り立っている。 「ねえ、聞いてよ」 不機嫌そうに――いや、どちらかというと不本意だというような声音で、は言った。 「なんだよ、初っ端から御機嫌斜めだな、my kitty」 仕方ないとでも言うように俺は言ったが、何せどこまでもこの女に惚れている。どんなに仕方ないことであれ、俺はすべて許してやろうと思う。それがどんなものであれだ。ほんの少し唇の端が持ち上がるのを自分で感じながら、の言葉を待つ。は重い溜息を吐いて両手を組むと、そこへ細い顎を乗せた。 「佐助がさぁ」 その名前を聞いて僅かに眉がぴくりと反応したが、は気づいた様子なく続けた。 が言う“佐助”というのは、俺もよく知っている男だ。逆も然り。――猿飛佐助。俺との同期で、ある日の合コンでと遊びはじめた男だ。それがすべてだとは思わないが、俺とが付き合っていると噂で聞いて、ちょっかいをかけたところもあるだろう。実際のところは、俺との間に、世間一般で言うような恋愛関係は成り立っていないが。 はつまらなそうに――いや、“そのこと”にはもう興味なんてなんにもないといったような表情で言った。 「わたしと“付き合いたい”んだって」 何を言っているのか、どういうつもりでそれを俺に今言ったのか、咄嗟に判断できずに反応が遅れてしまった。 なんとか「……突然だな」と言うと、それからすぐに「お前らは“そういう”んじゃないと思っていたが。まさか俺と“別れ話”するつもりで来たのか?」と笑ってみせた。 俺は何も気にしたようでない調子で言ったつもりだし、冗談めかして余裕さえあるように振る舞ってみせたが、内心ではまともではいられそうにもないと思った。腸が煮えくり返るようでいて、それでいて心臓が凍りついていくような感覚におかしくなりそうだ。がそれにイエスと答えたのなら俺は――と考えはじめたところで、がくすりと笑った。 「それこそまさかだよ。佐助と付き合うとか無理。いや、佐助が嫌って意味じゃないんだけど。政宗なら分かってくれるよね?」 その言葉が俺にとってどれほど残酷かというのは、きっと俺しか――いや、俺だけではないかもしれない。今の話を聞く限りでは、少なくとも猿飛もそうだ。だが、これはこの女にだけは知られてはいけない。いいや、知ったとして、この女には分からないだろう。 自嘲の意味も込めて、俺は鼻で笑った。なんとなく、その話を二人がしているシーンが想像できた。その場にいたわけでもないのに、頭の中では細かに見えてしまう。不快だ。 「笑えるな。それほどつまらねェ“契約”なんてない。……猿は同じtypeだと思ってたがな」 「でしょ? なのに急に態度変えてきたから、『カギ返して』って言ったの。そしたらなんて言ってきたと思う?」 俺がもしに「お前を愛してる」と言ってみたとして、この女はなんと言うだろう。俺がヤツの立場だったとして――と思ったが、先はたとえ想像でもしたくはなかった。ただ答えないのも不自然な話なのだ。俺とは“同じ”タイプの人間でなければならない。俺とは“付き合っている”。実際のところはどうであれ、周囲の認識としてはそうだ。だが、それは違う。俺たちの“付き合い”というのは、お互いの都合のいいように――の都合のいいように計算されたものだ。それに俺は何も口出ししないどころか、なんでもないふりをして――まるで“同じ”であるかのように、“そういう”男を演じている。そうでなければ、は俺を簡単に切り捨てるだろう。今までそうであったように。ヤツが――猿飛が、そうされたように。 「……『ムリ』とか『イヤ』とか、どうせそんなところだろ」 俺の言葉には「そう、それ!」と言って手を組んでいたのをぱっとやめにして、「それで政宗のとこ行くって言ったら逆ギレするしマジで意味分かんない。ていうか政宗冴えてんねー。え、言われたことある?」なんて言い出した。冴えてる? 言われたことある? そんなもの、簡単な話だ。俺にも想像できることであるから答えられるだけだ。しかし、そんなことは言えない。 特別、台詞を考える時間はいらなかった。のパターンはいい加減に分かっているし、俺も今まで細心の注意を払ってきたことだ。それに、よく観察してきた。俺でない、俺と同じ気持ちを持った男たちのことを。自然と言葉は出てきた。 「俺は部屋のkeyは渡さねえ主義だ。だが予想はつく。アイツはお前と“付き合いたい”って言ったんだろ?」 ジャケットの胸ポケットからシガレットケースを取り出して、中から一本抜く。続いてライターを取り出すまえに、がさっと火を差し出した。それを受けて、今度は俺がシガレットケースをのまえに差し出す。は首を横に振った。それから「え? そうなの? わたしにはくれたじゃん」と言って、テーブルの端にある灰皿を引き寄せる。 「お前は“特別”だからだ」 俺が言うと、は思い切り顔をしかめた。それから「ちょっと待ってよ、政宗まで“そういう”こと言うつもり?」と俺の指先から煙草を奪うと、乱暴に灰皿に押しつぶした。やっぱりコイツはどうあっても“そういう”女で、俺がどんなに望んでも、俺だけのものには決してならない。俺はもう一本煙草を取り出して、今度は自分で火をつけた。 「……お前は一人に執着するtypeの女じゃねえって分かってるからだよ。他の女ならああだこうだとうるせえこと言うだろ。だからお前は俺にとって“特別”なんだよ」 俺の言葉を聞くと、はあからさまに安心した様子で、「だよねぇ」と笑った。それから、“そういう”男であると認識している俺にだからこそだろう。簡単に言い放った。ある意味では、信頼されているのかもしれない。 「あーあ、佐助のこと大事だったのにぃ」 この女から聞く言葉――特にこういうもの――は、まったく信用ならない。心の底からそう思って口にしているわけではないと、誰が聞いたって分かってしまうからだ。もう条件反射というような感じで、これにはこう答えると体に染みついてしまっているんだろう。口先だけというのは、こういうことだ。 「Ha! お前が言う“大事”ほど信用ならねえモンはねえな」 は笑った。この世のすべてを、嗤っているようだった。 人と人との間に自然と生まれる情というもの、すべてを。 友愛だとか家族愛だとか、人と人とが関わりを持てば自然と生まれるものがある。はそれを理解しているし、それを感じている友人もいれば、家族だっている。けれど、は知らない。愛情というものを。男と女の間に生まれる、愛情を。存在は知っていても、自分にはそんなものは必要ないと嗤っている。だからこそ“お遊び”が大好きで、を“本気”で「好きだ」と言った猿飛を嗤っている。 俺が抱くこの感情は、この女にだけは知られてはいけない。 他の誰より、分かってほしい相手であるとしても。 「……“おんなじ”くせに、よく言う。でもこれで幸村くんには嫌われちゃう〜。元からわたしのこと良く思ってないだろうけど。あの子、結構わたしの好きな顔してるんだよねえ。しかも年下だし。かわいくない?」 まるで気に入ってるかのような物言いだが、顔は小馬鹿にしている。現に続けて、「ま、もう関係ないけど」となんともない調子で言った。 猿飛との言う“幸村くん”――真田幸村は、まだ高校に通う甘っちょろい坊ちゃんだ。互いにそれぞれ学業で忙しい身分だ。いつでもどこでもというわけではないが、二人は互いの家の関係でよくつるんでいる。俺も同じく家の関係で、真田とはよく見知った仲である。今どき珍しい純情な――この女とは絶対に相いれないタイプ――男だ。実際、真田が“そういう”遊びを覚えたのなら話は変わってくるだろうが、今のところその様子はない。俺が思うに、今後もないだろう。だから俺は笑っていられる。俺は、の傍にいることができる男だ。そして、ふと思った。ありえないことだが、もしもがあんな風に――心根の真っ直ぐとした人間に変わったとしたら、どうなるだろうと。しかし、そんな馬鹿らしい考えはすぐ捨て去った。その感情の向かう先にいる相手が俺でない場合を考えれば、当然のことだ。 「馬鹿言え。真田だァ? 目の前に最高にイイ男がいるじゃねえか」 はそれは楽しそうな顔をして、「ふふ、それもそっか」と言って、テーブルに置いていた俺の手にすっと手を伸ばしてきた。そして甘えた声で「ねえ、わたし政宗が一番好き。なんでもわたしの好きにさせてくれるし、放っておいてくれるし、つまんない――頭おかしいこと言い出さないし。ホント、政宗ほどわたしに合ったイイ男なんていないと思う」と言って、やはり甘えた顔でじっと俺の目を見つめる。これだけあからさまに“遊び”だと言われても、俺の心はなんともならない。深く真っ直ぐと根を張ってしまって育ったこれは、揺らぐことがない。この女を、俺は心底愛している。そんな気は一切ないような素振りを見せるのは、苦痛だ。耐え難い。そのくせ俺は笑うのだ。 きっと、この憎らしい女と“同じ”ように。 「……お互い様ってヤツだな。だから俺もお前を愛してる。……、出ようぜ」 俺の言葉に、はきゅっと眉間に皺を刻んだ。 「は? 来たばっかなんだけど」 「俺の部屋で飲もうぜ。……ここまで言えば分かるだろ?」 「……ふふ、やっぱり政宗が一番好き」 まだ十分に吸える長さのある煙草を灰皿に押しつけると、ぐしゃっと音がするようだった。 |