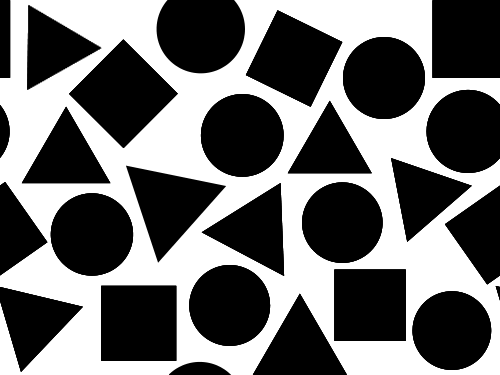
「ねえ」 俺の呼びかけに対して、はまともに返事をしようという態度を取らなかった。その視線は真っ直ぐにテレビ画面に引っついている。けれど、「何?」という言葉があったので、俺はここのところずっと伝えようとしていたことを、いよいよ口にしようと思った。 「ちゃんさぁ――」 「あ、続き言わないでね。わたし今の関係気に入ってるの」 けれど、まともに言わせてもらえないまま彼女は早口に、しかしはっきりと断った。そうなると俺に言えることなんてほんの少ししかなくて、その中でも一番言ってやりたいと思ったものを選んだ。 「……自分勝手だね」 するとはやっと俺のほうへ視線をもってきて、ハンッと嘲笑うように「それ知ってて離れないのは佐助のほうでしょ。嫌なら別の女のところいけばいいじゃない」と言って、いつだったか俺が選んでやったソファの背もたれへどさっと体を預けた。 一度はこんな反応が返ってくるだろうな、とはなんとなく思っていたので、俺はさほど驚きもしなかった。という女は、“そういう”女だから。なので特にその態度をどうこう言うまえに、言いたいことをさっさと言ってしまって話をまとめようと思った。もなんだかんだと言って、いつも事あるごとに見せる甘い笑顔を浮かべるに決まってると思っていた。なので俺はわざとらしく溜息を吐いて、「だっておかしいでしょ。ヤること全部ヤッといて、『付き合うのは無理』ってさ」とローテーブルに片手で頬杖をつく。 それに対しては、この話にはなんにも興味ありませんという調子で、抑揚なく「別に特別なことじゃないでしょ。同じことしてるひとなんてたくさんいるよ」とこちらもわざとらしいほどに面倒そうな溜息を吐いた。 「そういうことが言いたいんじゃないってば」 俺がそう言うと、はだらしなく身を預けていたソファの背もたれから体を起こして、剣呑な目で俺を貫いた。これにはちょっとうろたえてしまった。 「……“付き合う”とかさぁ、そういう契約みたいなのってそれほど重要?」 が言う。 「重要だよ。俺はちゃんが俺以外とアレとかコレとかするのイヤだから」 まぁ“ちょっと”という言葉では完全に甘すぎるほど“欠けている”女が相手なのだ。はっきりと、いくらか露骨でもいいから伝えるべきだった。まぁそれでも、女の子相手――それも心底惚れてる――に対して、“キス”はまだしも“セックス”なんて言葉を口にするのはちょっと躊躇われたので、俺はぼやっと誤魔化した。 は「……めんどくさ」と独り言のように呟くと、ソファに座ったまま、ローテーブルの下に手を伸ばした。鏡だな、と思ってそれを手渡すと、当たり前のように受け取って――まぁ実際、今までずっとそうだった――盛ってます〜という感じではないのに、しっかりカールしてある睫毛を人差し指でいじって気にしはじめた。これは暇だというときにするの癖だったので、余程この話には興味がないのだなと思った。次の言葉が決定打だった。 「佐助はわたしと“同じ”だと思ってたんだけどなぁ」 ――“同じ”。 もちろん俺もそう思ってた。 女の子なんてみんな一緒。そのとき、その場が気持ちよければいい。縛られることもなく、面倒な約束事もない。その都度、気まぐれであの子、この子と渡り歩いていく。楽だ。その気があってもなくても、女の子に困るということはなかったから、散々に好き勝手してきた。理由なんてものはない。ただそれが一番“楽”で、そのうえ“気持ちいい”からそうしてきただけ。 でも、そういう楽で気持ちよかったことが――好き勝手が苦しくなって、気持ちよくなくなってしまった。それもすべて、俺の眼前で暇だなっていうのをちっとも隠さない女のせいだ。俺は心底惚れてしまって、気づきたくもない癖まで知ってしまった。 そう簡単に頷くような女じゃないのは分かっていたことだ。だけどその辺の男ならともかく、俺が相手なら――と思っているのは抜けないのが実際だ。だって俺は、の好きなもの、嫌いなもの、全部知ってる。本人が気づいていない癖すら、知っているのだ。 睫毛をいじる指先をとめるために、細い腕をゆるく掴む。 ちら、との視線がこちらへ向いた。 「俺様だってそう思ってたけどしょうがないでしょ、本気になっちまったんだから」 ちょっとの沈黙の後、は言った。 「じゃあカギ返して」 「ハァ? なんでそうなるわけ? イヤに決まってんじゃん」 は付き合って半年ほどで、俺にポイッとこの部屋の鍵をよこした。まぁ“そういう”女だから俺も当たり前に受け取ったけれど、自分の部屋の鍵なんてそう簡単に男にくれてやるものじゃない。何があるか分からない。それは信頼の証であるのと同時に、弱味だ。――というのは一般論であって、(今までの)俺やにとっちゃ「そっちのほうが“楽”でいい」というだけだった。それだけ。俺は“そういう”男だったし、は“そういう”女だ。 けれど今はどうだ? 俺は、本気になってしまった。 「わたしは佐助と付き合う気ないから、佐助がそういうつもりなら一緒にいたくない」 「ハイそうですかって返すと思ってんの?」 使えるもんは使っとけという感じで言ってやった。まぁ、この女相手に通用しないのは分かっているけれど。多数のなかに入らない女だ。普通の女の子がこう言われたら、一体どうする? 別れたいと言った男に鍵を返してほしいと頼んだのに返してくれない、今まさに自分の部屋にいる、腕を掴まれている、逃げられない。――というような状況に陥ったら、どうやって逃げようとか、でも逃げたら何されるのか分からない、とか、とにかく“怖い”と感じるだろう。でも、この女相手では、やっぱり通用しなかった。俺のポケットの中にあるこの部屋の鍵は、今まさに使えないもんになった。ほんと、使えない。 は俺のゆるい拘束を乱暴に解くと、「勝手にすれば。じゃ、わたし出かけるから」と言ってソファから立ち上がると、床に放ってあったバッグ(女の子ならみんなが欲しがるブランドものだ。誰にもらったんだか)を手にしてさっさと玄関へ歩を進めていく。 「は? どこ行くのよ」 俺の言葉には即答した。 「政宗のとこ」 これがまったく素性の知れない男だったらまだマシだったものを――その名前は、よく知っている。 「……大事な話してるときに他の男の名前出すとかさぁ、どういう神経してんの? お前」 俺も立ち上がって、の隣に立つ。ちょっと緑がかった黒髪を、姿見で確認している。そこへ映り込んでいる俺の顔といったら、まぁとんでもなく使いもんにならない“無”だった。ちょっとでも同情をひくような――それでもこの女はちっとも意に介さないと知ってるけど!――顔ができたら、それなりの演出にもなっただろうに。 は俺のことなんてどうでもいいのだ。だから「前からしてた約束だもん。ていうか佐助が勝手に押しかけてきたんでしょ。カギ返さないなら返さないでいいから、出てくときはカギよろしく。あ、あとテレビ消しといて」なんてつれないことを言う。いや、分かってんだけど、“そういう”女だって。 「おい!」 ――分かってんだけど。 「……ったく、なんなんだよ……。……俺だってこんなつもりじゃなかったっての……」 「おっ、かわい子ちゃんの隣だ〜。やったね、俺様ってば今日はくじ運いいみたい!」 。名前だけは知っていた。それでも同じ大学に通っている同輩というだけで、それ以外に接点はなく、顔と名前を一致させたのはこの日が初めてだった。それでも俺は随分と前からこの女のことを意識していた。どうしてって、俺と“同じ”人間だろうなというのを、誰から聞くでもなく感じていたからだ。まぁ、そうでなくともは目立っていた。そのことは今は置いておくとして。 「あはは、えーと、佐助くん? だっけ。おもしろいね。あ、わたしの名前分かる?」 は一瞬だけれど、俺のことをよく“確認”した。俺もよくすることなので、どういうことだかはすぐに分かった。面倒がない上にこれだけ美人だなんて更にいいな、と思った。 俺はなんにも気づいてない振りをして、人好きのする顔で笑ってみせる。 「もちろん。ちゃんでしょ? 初めっから狙ってた」 「うわっ、チャラ〜」 はけらけら笑った。嫌味がなくて、お高くとまってる感じもない。“普通”にしていても十分にモテるだろうに、とんでもないなぁと思ったけれど、そもそも俺は人のことを言えない。まぁホント、根っから“こういう”人間で、だから俺も今日はこの子だと決めたのだ。そうでなくとも、この合コンで一番好みだったのはだったし――置いておいたことをここで明かすならば、このときからと伊達政宗――彼女がいう“政宗”だ――が付き合っているというのは、どこからともなく聞こえてきていた噂話だった。あれだけクセのある男と付き合っている。どう落として、どう付き合っているのか。俺がこの子に手を出したと知ったとき、あの男はどういう反応をするのか。まぁとにかく、色々な意味では俺の興味を煽った。なので今日は絶対に、と思っていたわけで、俺はやっぱり人好きのする――というか、女の子が好む――顔で、「え〜、なんでよ。それだけかわいいって自覚ないの?」とずいっと顔を近づけた。はなんともないように、「んー、どうかな。佐助くんにそう言われちゃったら、勘違いしちゃうかも」と言うくせに、口角は不自然にきゅっと上がっていた。 「ウソばっか。誘われたときから聞いてたぜ? ちゃんのこと」 「やだ、悪口本人に告げ口すんの?」 僻んでる女の子はいくらでもいそうだけれど、には人の良さそうな雰囲気があったので(あくまでも“雰囲気”)、表立って悪口なんかを言う子はいないだろう。もし悪い噂があれば、誰もこの合コンには来なかったはずだ。女の子の幹事はだった。まぁ彼女の企画ならいい男が来る、とか打算的な考えの子もいただろうけど。はそんなこと気にしないので関係ない。あいつが本当に信頼して、自分の懐に入れる相手というのは決まっているから。このときは俺のほうこそそんなこと気にしちゃいなかったので、「違うって。ちょーかわいいコ来るらしいよ〜ってさ」と当たり障りのない模範解答を出した。 ここでは、俺を完璧に“信用”したんだろう。笑って、「佐助くんやっぱチャラい!」と言って、ビールジョッキの中身を空けると、少し声をひそめて「でもそういうひと、わたし案外キライじゃないよ」と言った。このタイプは意識して人を操ってるくせして、そんなことないって振りがうまいからなぁ。俺も“同じ”だからよく分かるよ、と思いつつ、俺もそっと声をひそめた。 「うわ、人のこと言えないじゃん。ちゃんのがチャラい」 「そう? でもホントにそうだよ。佐助くんみたいなひと、大好き」 それが合図だった。 「……ね、ちゃんさ、早めにふたりで抜けない?」 「……それってどういう意味で言ってるの?」 「ちゃんのこと、“お持ち帰り”させてって意味」 「いいよ。わたしたち、“同じ”タイプみたいだし」 そうだ。“同じ”だった。俺とは。でも今はもう違う。 俺が先へ進んだのか、俺が取り残されているのかは分からない。 けれどこのときはまだ、俺もも“同じ”だった。 ――“同じ”だったのに。 |