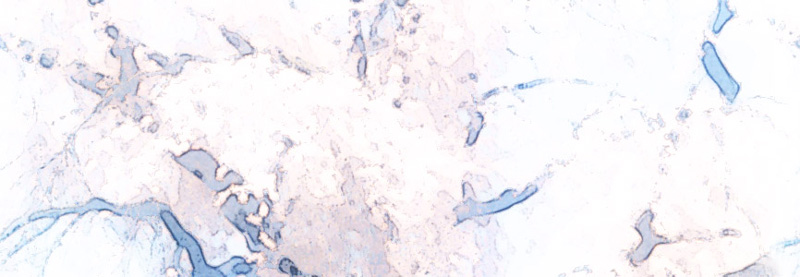
他人を自分の部屋に入れることなど考えたことがなかったし、それはそんなことが起こるわけもその気もないという表れだった。なのに、不思議だ。いつもの部屋に、彼女がいる。たったそれだけが、俺にはとても重要に思えるのだから。 ――だからこそ、俺は今日ここで話をまとめてしまう気でいる。 だって、これ以上彼女が泣く必要があるだろうか。あれほど、一人きりで隠れて泣いていたのに?俺はもうそんな必要はないと思うし、むしろ遅すぎたと思うくらいだ。最も確実だろうと似合わない役柄を演じてきたが、これは思わぬチャンスだ。なら、ここで決める以外にない。 彼女を泣かせることは、もうしない。少なくとも、一人きりでは。 「……俺はね、自分のことには興味がないけど――さんには、すごく興味があるんだ」 俺はこれまでずっと、彼女が俺を知らない頃から、彼女を見てきた。初めはただの興味だったし、そこに特別な感情などなかった。“あの”三好が構う女の子なのに、どうにも苦戦しているらしい。そうと分かれば尚のことだった。それがいつから、俺なら泣かせないだとか、俺ならこうしてやれるのにだとか、彼女のそばに自分が在ることを考えるようになったのか。 何かに、誰かに強く興味を持つこともなかったし、俺は俺が満足できる環境に身を置いていれば充分だった。そして、俺が満足できる環境とは、衣食住が整っていて、程よく遊べればいい。こんなものだったのだ。着るものはとりあえず質が良いものを揃えておけばどうとでもなるし、食べる物にもこれと言ってこだわりはない。この部屋も利便性で選んで、必要“そう”な物だけを最低限置いておいて、後は清潔さを保てる頻度で掃除する。要するに、俺は“面倒”が厭わしいんだろうと思う。省ける面倒をすべて省いた生活が、今だ。 それなのにどうしてだか、手のかかりそうな女の子のことが気がかりで仕方なかった。いや、仕方なくなった。いつからか、ずっと。 答えようもない言葉を投げたのはこちらなのに、頼りない「はい?」という返事にまで心がざわつくような気がして、細い両肩をそっと引き寄せて耳打ちする。 「だから俺は、きみの全部を知りたいし……きみには、俺を見つけてほしいと思うんだ。……“理想の王子様”はもう終わり。――俺の知らない、俺を教えて」 俺は、こんな“俺”を知らない。 彼女と出会わなければ、俺は何事も最低限で満足して、それで充分だっただろう。でも、今はそれじゃあ満足できないと思っている。彼女と――さんと二人で、同じ時間を共有するようになったら。俺は今まで必要ないものだと見向きもしなかったものを、愛おしく思う時がくるかもしれない。いつからか彼女の姿だけは、どこにいたって目に留まるようになったみたいに。 「え、田崎さ、」 戸惑った声は聞こえないふりをする。ただ、こんなにかよわい女の子をソファーに倒すとは、やっていることはやましさしかないなと笑えてくる。だが俺は、こうやって押し流してしまうほうが余程優しいのではないかと思うのだ。少なくとも、彼女をこれ以上泣かせずに済む方法を考えてみた時、一番に出てきたのはこれだった。だから、これでいい。 「……嫌なら、嫌って言って。でも俺は、もう泣いてるきみを、放っておけないんだ。あの頃みたいに知らない振りをするには、俺はきみを知りすぎた」 そうだ。俺はさんのことを知りすぎた。気づいてもらおうとも思わなかったが、本当に気づかれないまま、彼女の泣き言を幾度聞いてきただろう。言葉では強がっていても、その心が悲鳴を上げているのを知っていたのは、他の誰でもない俺だ。彼女の親友を名乗るあの子には悪いが、これは譲れない。 俺は“王子様”なんて柄じゃないが、そうすることが彼女の幸せならそれでいい。ただ、これまでのような男でいてやるのは無理だろう。始まりがこれでは言い訳のしようもないし、何より――。 「た、ざきさん、」 吐息ほどのか細い声も、今の俺には甘い囁きでしかないのだから。 「……だめかな、俺じゃ。――きみが一人になりたくないように、俺も、一人にはなりたくない」 「あ……」 本当は“一人”を誰より怖がっている子だと知っている。だからこそ、俺の言葉に瞳を揺すのだ。そのまま逃げるように視線が逸らされるが、俺はもうやめてやる気はない。ほっそりとした輪郭を、ゆっくりと唇でなぞっていく。小さく息を飲む音がした。 少し笑って、「……嫌とは、言わないんだね」と頬に手を滑らせながら瞳を覗き込むと、そこにはとてもじゃないが“王子様”とは呼べない男が映っていた。しかし、彼女は言った。 「……い、やじゃ、ないから、」 始めたのは、彼女のほうだ。そして俺は――それを止めてやる気はない。 「――ん、」 気を失うように眠ったさんの身動ぎが、もう目を覚ましてしまったのを知らせた。まぁそれでも、午前二時を回ったシンデレラに、もう行くあてなどはないだろうが。 「ごめん、起こしちゃったかな」 体を起こした俺を見ないようにと視線をうろつかせて、気まずいと言わんばかりの声で「……いえ、……あの、」と言葉を探すので、その先は言わせまいと口を開いた。 「俺は謝らないから、さんも謝らないでくれるかな。そうしたら、お互い様で済むだろう?」 どちらももう子どもじゃない。経験がないわけでもない。俺はきっかけさえあればそれでよかったから、あのまま彼女をベッドへ連れ込んでしまったが、やはりこのほうがずっと話が早い。これまでに時間をかけすぎたのだ。ここから急ぎ足にしたって、何も問題はない。 さんは、まるで自分の身を守るみたいにタオルケットを引き上げて、やっぱり俺のほうを見ようとはしない。いや、シャツの一枚でも羽織ってあげたなら、もしかしたら変わるかもしれないが。 「そ、んな、簡単に済む話じゃ、」 ――まぁ、何にせよ、という話だ。 「どうして? こうなった以上、俺はきみを返す気はないけど。……誰にもね」 もう深夜もいいところだ。電車はない。俺はアルコールを摂っているから運転はできないし、タクシーも呼んでやる気はない。そもそも、家に帰してやる気がないのだ。そして、このまま朝を迎えてさようなら、だなんて馬鹿げたことをしてやる気はもっとない。 彼女の肌も、声も、匂いも、すべてを知ってしまったから。 どこかへ隠れようとしたって無駄だ。他の誰ができずとも、俺なら見つけ出せる。一人で泣いていることを知っていた、俺になら。 こうなってしまえば、どうあってももう俺は“理想の王子様”ではいられない。けれど、“理想の王子様”ならあのまま彼女を家に帰していただろうし、もしこうなったとしても、すべて忘れると言うはずだ。だからこれでいい。“理想の王子様”でない俺は、もう彼女を誰かに渡す気はないし、親切に返してやる義理もない。散々泣かせたのはあちらだ、俺がどうしようと責められる謂れもない。唯一の懸念材料と言えば――。 「……わたし、」 いや、今はいい。そう思考を止めて、「後悔する? 俺とこうなったこと」と言いながら、さんの両肩をベッドに押しつけた。これまでの俺ならきっとしなかっただろう力加減だったが、さんは痛がるでも嫌がるでもなく、ただ行く先が途端に分からなくなったかのように、心細そうな顔をしている。 「……後悔とかじゃ、なくて、ただ――」 「“ごめんなさい”は聞かないよ。いや、きみの気が済むなら、いくらでも謝ってくれていいんだけどね」 俺の言葉にハッとした表情を浮かべた後、さんは小さく笑った。それから仕方なさそうに、「……田崎さんはいつも、わたしには何もさせてくれませんね、」と力なく言う。 また、自分の中でのみ、すべてを終わらせようとしているな、と思った。近づいたと思っても、まるで波のようにすっと引いていくのが彼女だ。ある観点からはそれは引き際がいいとか、それこそ耳に心地良い言葉になるだろうが、それが癖にまでなるとそうはいかない。 一人が怖いくせに、進んで一人になろうとする。そういうところをずっと見てきたせいか、あえて柔い部分を刺激するような言葉選びをするしかなくなる。もう“理想の王子様”ではないことだし、これでいい。もっとも、こちらには初めからその気はなかったが。しかし、状況は俺をいつでも都合良く見せてくれただろう。ただ、俺もそう簡単に人に本心を曝け出そうとは思わないし、もしもそんな気にさせる人間がいるとしたら。目の前で小さくなっている彼女の他、いないと思うのだ。 「そうかな。さんがいつも俺に選ばせてくれてるだけだと思うけど。……ああ、もう目が冴えちゃったかな。コーヒーでも淹れようか。まだ早いけど」 さんと俺でモーニングコーヒーとは、あの頃の俺が知ったらなんて言うだろうか。考えても仕方ないことだが、少し面白い気持ちになる。なんだかんだで、俺は浮ついているようだ。だとしても、何か言葉をと口を開きかけて、やめて、という彼女を放ってはおけないので、乱雑に放っていたシャツに手伸ばして羽織る。 「……さん、着替えられる?」 背中越しに「え、」と戸惑った声を聞きながら、俺はどんどん支度を進めていく。必要なものなど、何もないが。この身一つでいいのだ。それから――。 「少し出よう。朝焼けを見に行くのもいいかな」 「は……、え、いや、今日も仕事ですよ、」と言って目に見えてうろたえている、彼女がいれば。 おどおどしている様子に笑って、「うん、休んじゃおうか」と言うと、さんはサッと顔を青くした。真面目なことだな、とますます笑ってしまいそうになる。 「何言ってるんですか! ダメに決まってるじゃないですか! っていうか、そうだ、会社……帰らなきゃ、」 これまでの俺ならきっと、そうだね、冗談だよ、だなんて思ってもいないことを言って爽やかぶって笑ってみせただろうが、その必要はもうない。俺にはもう、さんのことで知らないことはないのだ。表面上のことなら、後からいくらでも情報は足していける。でも、本質的なことだけは、そうはいかない。 彼女がひた隠してきたそのすべてを知っている俺と、誰にも知られたくなかったであろう弱さを曝け出してしまった彼女。どちらに分があるかなど、誰にだって明らかだ。 「あはは、帰さないし、返さない。――もう俺のものだ」 すっかり身支度を整えた俺はそう言って、もう一度ベッドに乗り上げる。髪を耳にかけてやって、そのままそこにキスを落とすと、肩がぴくりと揺れた。つい数時間前までのことが思い出されて、今度は舌までも奪ってしまう。そこで気づいた。誰かと熱を分け合ったことを思い返すなど、これまでの人生ではなかったな、と。 さて、それはそうと。さんの不安というと、やはり大の親友だという彼女のことだろう。あの子のことだから、諸手を挙げて喜ぶに決まっている。状況が状況だし、元より口ではあれこれ言いつつも、俺については常に肯定的な態度を崩さなかったのだ。さんが俺を選ぶと言っても、彼女が想像しているようなことにはならない。 「気がかりなのは、あの子かな?説明しづらいとか、そういう」 頬にキスをしてからそう言うと、さんは顔を覆って「せ、説明も何も、こんなこと、」と震えた声で呟いた。まぁ、誰と寝たなんて人に言うようなことでもないし、さんのようなタイプなら、俺とのこんな馴れ初めを人に言うだなんてとてもじゃないが無理だろう。 「言えない? まぁそれもそうだろうけど……隠せはしないんだから、同じじゃないかな」 どうせ彼女には何もかも話す必要がある。もちろん、説明するのは俺だけでいい。あったことをそのまま、伝えるだけだ。さんは俺の手を振り払わなかった。今も「――」と名前を呼べば、反射的にであろうとも「っ、はい、」と素直に返事する。俺は“理想の王子様”でいることはもうできないが、彼女が望む“男”ではいてやれるだろう。 「大丈夫だよ、悪いようにはしない」 俺がそう言うと、さんは俺をじっと見上げて、今にも泣き出しそうに顔を歪めた。 「……田崎さん……、ご、めん、なさい、でもわたし、」 膝に額を押しつけて声を震わせるので、どうせなら本当に泣いてしまえばいいのに。俺はそう思いながら、つむじにキスをして「うん、いくらでも謝ってよ。彼女には俺から説明しておくから」と言って、白いドレスに手をかけてしまう。 「さあ、着替えようか。……俺が手伝ったほうがいい?」 さんは随分たっぷりと口を引き結んでいたが、観念したように「……自分でできます」と言った。 「ふふ、それは残念だ」と答えた俺は笑っていたが、本心では本当に残念だと思ったし、そのまま剥ぎ取ってしまえばよかった、とまで思っているので笑える話だ。けれど、もう誰も俺を咎めることはできないし、させはしない。 ――“理想の王子様”は、もう終わったのだから。 一番近い海岸まで車を走らせて、寂しさしかない駐車場の端に停めた。 さんは思わずと言った具合に、「……まっくら、」と零した。ちょうど月に雲がかかったところで、どっぷりとした闇色が一面に広がっている。これを気味が悪いと捉えるか、幻想的と捉えるか。人によって違うだろうが、この子はどちらだろうか。俺にはそういうことを考える機会がないから、彼女の言葉で教えてほしいと思う。 「そうだね」と俺が返したところで、月の光が一筋差し込んできて、真っ暗な水面が鈍色に光った。ここまで舞台が整えられてしまうと、ついまだ“王子様”をやらなくてはいけないんじゃないかと思えてくる。そう思って、「……何もないみたいだ、俺たち二人以外はね」と言うと、さんが俯いた。静かすぎて、波の音がうるさく感じるほどだ。その中で聞いた「……もし。もし、そうだったとしたら、」という言葉に、俺はひっそりと口端を吊り上げた。 「うん」 「わたしが、田崎さんに甘えても……、おこられませんか、」 顔を覗き込んでみると、瞳いっぱいに涙を溜めていて、もう誰かに怒られた後みたいだ。少し笑って、「誰がきみを怒るのかな? そんな権利、誰にもないのに」と俺が言うと、すぐに「でも、」と返ってきたが、涙だけは溢さないようにと気を張っているのか、言葉は続かなかった。 「せっかくだ、降りようか」 言いながらドアを押し開く俺に、引き止めようとしてかさんが慌ててシートベルトを外す。 「え、あ、危ないですよ、何も見えないし、」と言う本人の足元が覚束ないものだから、俺はあえてゆっくりとした動作で外から助手席に回った。 「だからだよ。転ばないように気をつけて」 差し出した手は、やはり拒まれることはなかった。 慎重に砂浜を歩いて波打ち際までくると、さんは案外しっかりした調子で「……ほんとに、なんにもないみたい」と言った。 「なんにもないよ、俺たち以外にはね」 さんは何も言わず、ただまっすぐに暗い水面を見つめている。そのまま足が進んでいったとしても、何らおかしくはない。夜の海には、そういう魔力があるらしい。細い手首を掴んで、「海、入りたい?」と俺が言ったところで、やっと気がついたようだった。 「……まさか。いくらなんでも風邪ひいちゃいますよ。――それに、」 「濡れたって構わないよ、俺は。きみと二人なら」 俺と彼女しかいないのだから、誰かに何かを咎められることはない。これは建前で、本当は俺が彼女と一緒に汚れたいのだ。理由はなんだっていいから、もう一度彼女を引きずり落としてやる必要がある。せっかくこの上なく素敵な舞台が用意されているのだ。今の俺を見たら、あの子はどんな役を当てはめるんだろうか。まぁなんだって構わないが。俺はどんな役だってこなせてしまう役者だ。それが彼女と二人でいるに必要なことなら、どこまでも完璧に演じきってみせる。 それに、先など見えない真っ暗闇だというのに、それを物欲しげに見つめている彼女が、「……車、汚しちゃう」などと言う。これは、“そういうこと”でいいんじゃないだろうか。 「じゃあ一緒に汚そうか」 進むごとに足は重たくなっていくが、心ばかりは軽やかだった。海で遊んだ記憶などいつが最後だったかも定かではないが、これはいい。 後ろから、「えっ、えっ、田崎さんっ!」と慌てた声がする。このまま聞こえないふりをしてみてもいいか、なんて思いもしたが――汚すのも、汚れるのも。二人、一緒にだ。 「ほら、おいで」 膝まで浸かったところで振り返って腕を伸ばすと、さんは不安を一切隠す気が見られない頼りない声音で「……たざきさん」と俺を呼ぶ。 「何かな」 嗤う俺は、彼女にはどう見えているだろう。 さんは両手をぎゅっと胸の前で握り締めて、絞り出すかのように言った。 「……わたしがこのまま……、田崎さんと、いたいって、言っても……、迷惑じゃありませんか、」 ……“迷惑”か、なるほど。 元の性質ももちろんあるだろうが、彼女はこれまでどれだけ気を張って生きてきたんだろうか。俺には想像できないことだが、あんなにも小さな体には辛いことだったに違いない。 誰かといたいと願うことは、確かに我儘なのかもしれない。もしかしたら、相手はそれを望んでいないかもしれない。もしかしたら、今にも離れたいと思っているかもしれない。けれど、相手も共に在ることを望んでいるかもしれないし、ずっと離れがたく思っていることもゼロなわけではない。 さんの目に今の俺がどう映っているにせよ、俺が彼女のことを迷惑と考えるとして、それは一体どういう場面だろうかと考えようとした。だが、すぐにやめてしまった。だって、笑えてきてしまって思考がまとまらない。 「願ってもない幸運だって、むしろ嬉しいよ」 ――彼女が今考えているのは、他の誰でもない、この俺のことなのだから。 「……わたしのこと、き、らいに、なりませんか、」 そのことがこんなに幸せなことだと思えるのに、俺はどうしたら彼女のことを“嫌い”になるんだろうか。“好き”すら、覚えたての子どもと変わらないような心地なのに。 「どうしてきみを嫌いになると思うの?」 どういう答えが返ってくるのか分かっていて、俺はそう言った。 「……だってこんなの――」 「……“間違ってる”?」 さんは何も言わない。波の音に掻き消されないように、俺は「いいじゃないか、間違っていても」ときっぱり言い切った。さんがあからさまに動揺した様子で「え……?」と言うと、足元の砂が不安げに崩れる。 彼女の真面目さはきっと美徳だろうが、それで自分を痛めるけることになるのなら、それは賢さとは程遠い。けれど、そうでありたいと願うこと、それを叶えようとすること自体を否定する気はないのだ。俺が彼女に興味を持ったのも、彼女が俺に近づこうとしているのを待っているのも、そういうところが理由の一つであると思うから。だから、否定はしない。けれど、ただ肯定するだけのこともしない。手助けが必要だと思えばそうするし、そうでなければそばで見守る。これを一番近い距離でしてやれるのは、彼女の親友のあの子か――彼女の、恋人だけだ。 「さん。きみが迷惑じゃないかって心配してる男は、そう言ってきみが離れていくことだけが心配なんだよ。嫌いにもなれない、だって――こんなに、愛おしいと思うんだ。もうきみと出会う前の俺には、戻れない」 今度は、名前を呼ぶ。さんはうんともすんとも言わないし、その場から動きもしない。 「さんは“いい子”すぎるんだよ。でも、それでいい。いい子でいたいなら、それで。ただ、いい子でいるために泣く必要があるなら、俺の隣で泣けばいいんじゃないかと思うんだ。それだけだよ」 は、と息を吐く音がした。さんは困ったように笑って、「……だめですね、わたし、」と呟いた。言いたいことは分かっているが、ここは彼女の口から引き出してやるべきだろうと「何が?」と分かっていないように振る舞う。 さんは言った。 「全部、田崎さんのせいにしようとしてる」 思わず、声を出して笑ってしまった。 「あはは、うん、それでいいよ。たまにはいいんじゃないかな、“悪い子”になっても。俺は、きみを叱らない」 俺の言葉を噛み締めるようにして何度も頷いて、さんは独り言のように「……そっか、」と呟いた。それを拾って、「うん、そうだよ」と俺が返すと、しばらく沈黙が下りた。そのうち、声を出したのはさんのほうだった。 「田崎さん」 その声に応えて、俺はもう一度腕を伸ばす。 「俺を選んでくれる?」 さんが一歩、進み出た。 「一緒に、いてくれますか」 俺のほうから距離を詰めていって、「きみが俺を選んでくれるなら、ずっと一緒にいるよ」と手を差し出すと、さんは安心したように笑った。 「……はい、一緒に、いてください」 しっかりとその手を握り締めて、ざぶざぶ海の中を進んでいく。月が、はっきりと顔を出した。俺が振り返ると、さんは首を傾げた。 「――じゃあ、しようか。二人だけで、悪いこと」 かわいいお姫様のかよわい腕を思い切り引くと、そのままどこかへ身を投じるように、二人で水飛沫を上げた。 |
画像:HELIUM