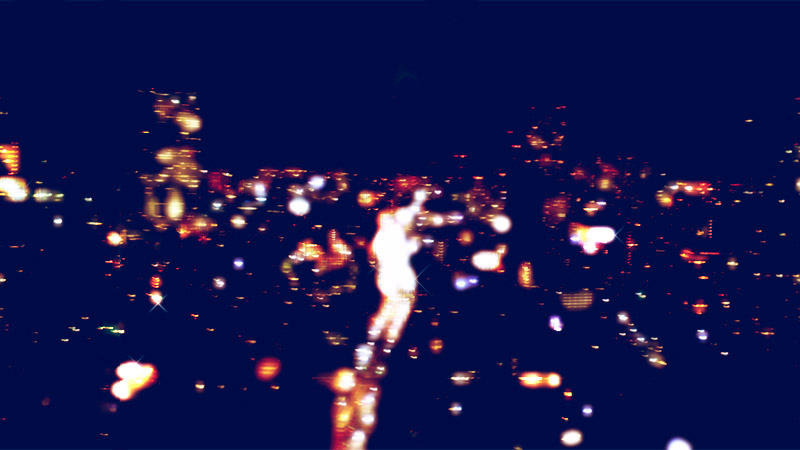
神永さんと別れてから、わたしはどこかぼうっとしながら、夜の街を歩いていた。ふいにまた涙が出てきてしまいそうで、ぐっと唇を噛む。わたしが泣いていいはずないのに、ほんと、ずるい人間だ。まるで自分が悲劇のヒロインにでもなったみたいに、情けない。 ――わたしが自分の力で前に進む、最後のチャンス。 ぱんっと両頬を叩くと、わたしはくるりと振り返って、歩き出した。 「……待ったか」 「ううん、全然。ごめんね、突然」 電話をかけるだけで、随分と時間をかけてしまった。この人ときちんと話をすることを、わたしはあれからずっと避けていたから。 突然の呼び出しに応じてくれたひろくんは、前みたいに優しい顔をしている。 ずっとずっと、この人が優しく笑うところが好きだった。ほんの少し口元を緩めるだけの笑顔が、あの頃のわたしには宝物で――。 ひろくんは「いや、いいんだ」と短く言った後、わたしを抱き寄せた。会いたかったという呟きは、きっと前のわたしなら喜んで、この人の背中に腕を回したと思う。でも、それはもう過去だ。 「……ひろくんのこと、信じきれなくてごめんなさい」 「……どういう意味だ」 ひろくんのこんな硬い声は、初めて聞いた。元々、そんなに口数の多い人ではなくて、それでいてわたしから話を引き出すのがとても上手だったし、その相槌はいつだって優しかったから。 もちろん、ずっと同じ道に進めるとは思っていなかったけれど、大学は大好きな大親友と離れて、これまでとは違った環境にひどく戸惑っていた。そんなわたしは、入学式で最初に声をかけてくれた女の子に誘われるまま、読書サークルに入る。ひろくんとの出会いは、その読書サークルでのことだ。なかなか人の輪に加わることができなかったわたしに声をかけてくれたのが、始まりだった。ひろくんのおかげでいつの間にか自然と馴染めるようになると、それをきっかけとして、ひろくんとの距離は少しずつ縮まっていって――熱い激情ではなかったけれど、わたしはすんなりとこの人のことが好きだと思うようになったし、だからこそ、ひろくんのほうから付き合ってほしいと言われた時にはその場ですぐに頷いた。わたしにとって、ひろくんは尊敬できる先輩であると同時に、ずっとずっと、いつまでも優しい時間を共有していける人だと初めて感じさせてくれた人で、大袈裟に言えば、きっとこの人がわたしの運命の人だ、だなんて真面目に考えたことだってあったほどだ。 だからこそ、ひろくんから距離を取って、「ちゃんと、話を聞くべきだった。一方的なことをして、ごめんなさい」と頭を下げたわたしに降ってきた言葉は、いくらもう過去のことだと踏ん切りをつけたはず、そうするべく今こうしているんだと思っても、複雑な感情を抱くには十分すぎた。 「……おまえに浮気を疑われるとは、正直思っていなかった。いつでも、俺を信じてくれていたから。……ただ、心当たりはあるんだ。確証できる材料なく、おまえが別れるなんて言い出すはずはないし――見たんだろう」 あの日に見た二人は、とても親しそうだった。いや、親しいという一言では言い表せられないような、わたしとひろくんとの間にはないものを見たと思った。けれど、彼女を労わるようにその腰に添えられた手を見た時、わたしは自分でも信じられないほどに落ち着いていた。ひろくんの様子がどこかおかしいことには、なんとなく気づいていたからだ。でも、ひろくんはなんでも一人で解決できてしまう人だし、いつもいつも彼に助けられてばかりのわたしに話すようなことでもないんだろうな、なんて思うようにしていた。 本当は不安だった。問い詰めたかった。でも、女の勘は当たる、なんてよく言うけれど、わたしが知るひろくんはいつも冷静で、その時々で正しい選択をする人だと分かっていたから。そんなことをして嫌われてしまったら? もういらないと言われたら? 手を差し伸べてくれた人だからこそ、わたしと一緒に過ごす時間が大切だと言ってくれたからこそ、わたしは全部飲み込んでしまおうと思った。だけど一度抱いてしまった暗い感情は、中途半端なわたしの覚悟の言うことをきくはずもなく、もしかして、と思ってしまったのだ。思い違いだったらいい。でも、ひろくんは何も言ってはくれないし、ずるいわたしも何も言わない。体調を崩している時すら、わたしとのデートの約束を律儀に守るような人で、心配することくらいはさせてほしいと言っても、一度だってそれを許してくれたことはない。少なくとも、わたしには。 「……なんて言ったら、いいのかな……あの人、今はどうしてるの? ……あと、お子さんは?」 ひろくんは視線をふいに落として、「……元気にしてる。子どもも」と答えた後、わたしの目をまっすぐに見つめながら「彼女は、俺の昔馴染みなんだ。子どもの頃、近所に住んでた。俺の面倒をよく見てくれた」と続けた。それに対して、わたしは「うん」とだけ答える。だって、もう自分の進みたい道を、自分で決めたから。 「……彼女が原因か」 確かに、あの日、あのシーンを目にすることがなかったとしたら。わたしは、今でもひろくんと一緒にいたんじゃないかと思う。 でも、今なら分かるのだ。そうして、わたしがありのままの気持ちを伝えることができないまま、何も変化することなく過ごすことになっていたとして、それは本当に正しいこと――いや、幸せなことではなかっただろうと。 「……きっかけには、なったと思う。でも、それだけだよ。わたしたち……きっと、いつかだめになってたと思うの。ひろくんのことを信じきれなかったのも、ひろくんから逃げてしまったのも、わたし自身のことが問題だったから」 優柔不断で、そのくせ人から下される自分への評価ばかりが気になって、自分で選ばなければいけないことを、誰かに合わせて選ぶことしかできなかった、そんなわたしの。 自分の本心すべてを人に語ることは、とても難しい。けれど、口に出して伝えなければならないことだってあるのだ。そんな当たり前のことを、わたしはわたしだけの事情で、ずっと避けてきた。それが正しいことだと、いつからか頑なに信じるようになっていたから。 でも――田崎さんがあの日に言ったように、何もかもにも正しいという唯一の答えなどは、どこにも存在していない。だって、人ってみんながみんな、色々な考え方をして、それに応じてそれぞれの行動へと繋がるのだ。なのに、わたしはいつからか唯一の正しさだけを求めて、結局は自分自身の行動を、考えを、その都度に誰かに委ねるばかりだった。 ただ、そんな自分と決別する覚悟を、自分を信じることを教えてくれる人は、いつだってすぐ近くにいてくれた。それならわたしは、その優しさや思いやりを、無駄にするわけにはいかない。 「……彼女――ちづ姉との再会は、本当に偶然だった。体調が悪そうに見えたから声をかけたら、それが彼女だったんだ」 「うん」 頷くわたしに、ひろくんは慎重そうな声音で言う。 「子どもの父親に騙されて、別れたばかりだった。一人で産んで、育てると聞いた。……俺は、それを聞いたら、」 分かってる、すべて。 わたしの至らなさ――というよりも、自分自身を見失っていたわたしに、いつでもただただ寄り添ってくれたひろくんが持つ、優しさや思いやりを。そして、わたしは彼がそういう真摯さの持ち主で、真面目が過ぎて、難しい顔をしている時でさえ、自分よりも人を大切にできる人だったからこそ、この人のことが心の底から愛しかった。そばにいられることが、あの時のわたしの幸せだった。 だから、わたしが伝えたいことは、一つだけだ。 「うん。ひろくんなら、そうしたと思うよ。――だからお願い、謝らないで」 ひろくんは静かに、「……、戻ってきて、くれないか」と言った。きっと、これまでのわたしであったなら、手放しで喜んだだろうと思う。けれど、やっぱりそれはもう過去のことであって、今のわたしが選びたい道ではない。 「……あの日。きっと、タイミングが悪かったんだよね、全部の。わたしが気まぐれで散歩しなければ、ひろくんと……彼女が二人でいるところは見なかった。あの時、近所のおばさまが二人に、夫婦仲が良いわねなんて言わなかったら、もしかしたらもう少し、流れは変わってたかもしれない。でも一番は、わたしがひろくんから逃げたことが原因なの」 臆病でずるくて、いつでも誰かの助けがなければ何も選べない。そんなわたしだけど、もう逃げることはしない。そして、自分で自分の道を選ぶことを、もう決めたから。それこそが、これから先を生きていくわたしのために必要なことだと思えるようになったのだ。 わたしが望んでいた、自分自身を信じる方法を教えてもらった。そんな優しさや思いやりを与えてもらって、わたしは無意味に悲観的になることからも卒業すると決めて、こうして彼と向き合っている。もう、迷うことはしない。 ひろくんは眉を寄せて「……俺が、おまえとの約束を選んでいれば――いや、彼女のことを話していれば、そもそもこんな行き違いは起きなかった。どうして俺を責めない」と言った。こんな場面でさえ、わたしの気持ちを優先させようとしてくれる。ずっとずっと逃げ続けていたわたしには、やっぱりこの人はもったいない人だ。ひろくんこそ、もっと自分のために生きていってほしい。自分勝手でお節介な考えだとも思うけれど、わたしがこの人のことを心底好きで、いつだって尊敬していたその過去は、確かに存在していたのだから。 だからわたしは、何の躊躇いもなく言える。 「責める理由がないから」 もうこの先は、わたしのためにも――この優しすぎる人のためにも、別々の道を歩むべきなのだ。そうでなければ、わたしはまた変わるチャンスを逃して、ひろくんのような誠実な人も、本当の意味で満たされることはなくなってしまうから。 「……だって、わたしが好きだったひろくんは、困ってる人を放っておくなんて、どうしたってできない人だったもん。それに、もし、ちづさんの話をされていたとしても、わたしはこうなってたと思うよ」 ひろくんは一度唇を引き結んだ後、表情を歪めた。 「俺が愛してるのは、後にも先にも――」 「わたし、ひろくんが思ってるような“女の子”じゃないの」 嫌われたくない、傷つきたくない、失望されたくない。そうして、自分で自分を誤魔化し続けていたのだ。ひろくんがわたしの本当の心を知る機会なんて、一度もなかっただろう。だからこそ、これまでずっと、わたしのことを待っていてくれたんだろうと思うから。 わたしはこの人と過ごせた時間を忘れはしないだろうし、ふいに懐かしく思ったり、もしかしたらあの頃に戻りたいと思うことすらあるかもしれない。それでも、もうこの人に嘘ばっかりの人間ではいたくないと思うし、今度こそ、わたしが憧れて惹かれたその理由のように、誠実になりたい。 「……わたしは、嫉妬だってするし、傷つきたくもないし、そのためには逃げることだってする。今まで、ひろくんから逃げてたみたいに。……いい子なんかじゃ、ないの。だから、いつか結局終わってた」 「……俺は、おまえに無理をさせていたか」というひろくんの言葉に、わたしは当時のことがふいに思い出されて、思わず口元を緩めた。ひろくんはいつだって、そうしてわたしのことだけを考えてくれていたから。 こんな場面ですら、そんな優しさと思いやりを忘れない人。わたしは本当に本当に、この人のことをどこまでも信じて、何もかもを預けて――愛していたのだ。 「わたしがずるかっただけだよ。ひろくんに、嫌われたくなかった。でも、そのためにわたしがしてきたことは、逃げることだけで、わたし自身が傷つきたくなかったから。それだけなの」 上手く笑えているのかは確認のしようがないけれど、温かい時間をたくさんたくさん共有した過去を思えば――本当の別れであるこの時ばかりは。最後の最後だからこそ、笑っていたい。 「だから、謝ったりしないで。ひろくんが謝ったりなんかしたら、ひろくんの優しさが、そうじゃなくなっちゃう」 ひろくんが浮かべた表情は硬く、それでいて、やっぱりその誠実さは隠しきれていない。 「……、俺はおまえに、何かしてやれたか?」 この人と過ごした時間は、わたしにとって幸せだった。そのことだけは、変わらず、そして忘れることもないだろう。 「何言ってるの。……ひろくんのこと、大好きだった。あの頃、ひろくんがわたしの全部だった」 ひろくんは僅かに口角を下げて、仕方なさそうに笑った。 「……そうか。――変わったな、おまえ」 「そう、かな? 変われてると、思う?」 いつだって、わたしのことを真っ直ぐに見つめてくれた瞳が、柔らかく細められた。 「……思うよ。あの頃より、もっと、綺麗になった」 なんとも返さないわたしの頬を、ひろくんはそっと撫でた。 「……名残惜しくなるから、もう行く。きちんと、迎えにきてもらえよ」 「もう子どもじゃないよ」と応えて、わたしも笑った。ひろくんは困ったような、寂しそうな表情を浮かべながら「……そう、だな。……それじゃあ」と背を向ける。そしてゆっくりと遠ざかっていく後ろ姿に、わたしは小さく呟く。 「――さようなら」 あぁ、ぜんぶ、終わった。ほんとに、全部。次は――次は、どうすればいいんだろう。何もかもが終わってしまったら、途端にここまで走り抜けるように込めていた力が、すべて失われてしまったような気持ちだ。 わたしが自分で選んで、わたしの進みたい道へ進むのがいい。そう言ってもらった。大好きな大親友にも、わたしの心の内をさらけ出した人にも、わたしを許そうとしてくれた人にも。でも、その進みたい道への矢印なんて見えやしない。わたしは、どうしたらいいんだろう。 「……進み方が、分からないなぁ……」 こんな時、あの人ならどうするだろう。 いつでも真っ直ぐで、まったく融通が利かない人だ。自分のルールで何もかもを押し通すくせに、その考えをちっとも語らない。だけど、いつだって自分は正しいと信じる強さが、わたしには眩しく見えた。だから、分かりたいと思った。その方法は今も分からないし、これからも分かるだなんてちっとも思えやしないけれど。でも、人間ってそういうものだ。そういうものだから、人に寄り添うための努力を忘れないんだと思う。わたしの思う生き方は、これだ。 でも、分かりたいことに振り回されて自分を見失ってしまえば、その努力は意味がなくなってしまう。結局、誰かを傷つけることになってしまうから。 ここまで時間がかかりすぎてしまったし、これまで傷つけてしまった人もたくさんいるはずだ。でも、そうしてやっと学ぶことができた。これを、無駄にするようなことだけは、絶対にしない。 「――あ、流れ星だ」 難しいことは全部抜きにして、もっと単純に考えてみようか。あの流れ星が、わたしのお願いを聞いてくれる――そんなふうに、もっと軽やかに。 そうすることで、わたしはきっと、自由になれるはずだから。 オフィスに激震が走った。なんでって? ……三好さんが“あの”秘書課の美人と別れたってニュースが飛び込んできたからだよッ!!!! いやなんでだよッ!! 急になんでッ?! 付き合ったのも突然であれば別れが突然も道理かッ?! ンなわけあるかいッ!!!! すべてを知る私の動揺はもちろんだが、これにはさすがのも目を丸くしていた。そらそうだ。 でも、贔屓の私からすれば、これはとてもタイミングがいい話だなと思ってしまう……。昨日、から小田切さんと話がついた、という連絡を受けていたからだ。三好さんはエスパーか???? ちゃんセンサーに何らかの反応があったんか???? 「……」 これでもかってほどに緊張しながら、私はなんとかに声をかけることに成功した。ただ、その声がとんでもなく震えてることについては許してほしいマジで……。 しかしながら、のほうはいつも通りのキューティーフェイスで小首を傾げ「うん?」なんて返してくるもんだから……三好さんの話題が出ようが本人と会話せざるをえない場面でもケロッとしてるに、こっちもケロッとサラッと三好さんの話題ふれるかってどう考えても無理でしょ……? というわけで、私は「あの……あの……みっ…………」と、言葉にすらなっていない音だけを吐き出すことになった。ちゃん、どう反応してくるかな……ほっといてって思ってるかなそれとも…なんて考えていると、は簡単そうに口にした。 「三好さんのこと?」 「ウグッ……そ、そうなんだけど……」 そうなんだけど……そうなんだけどさ?! なんでそんなケロッとしてられるの?!?! 三好さんが“あの”女と付き合ったこともハァ?? 舐めてんのか???? って話だったのに、今度はサッサと縁切ったっていうんだよ?! しかもちゃんには珍しく、あの女からの嫌味も華麗にスルーしてたじゃんなのにその反応?!?! ……やっぱり、小田切さんときちんとお別れしたことで、何かしらの感情を抱いたというか、頭の中を整理することができたのかな……。いやでも私にはその二人の間でどんな話があったのか詳しくは知らないし、ちゃん今何考えてるの……私のバイブ機能がいよいよオンになりそうなのですが……。 は困ったように笑うと、「うーん……三好さんの考えることは、わたしには分かんないからなぁ……」と言って、手元にある書類をトントンしながらまとめた。え? これを聞いて私が思ったこと? ………………。 「だよね?!?! 私もサッパリ!!!!」 よかったやっぱりあの独特な摩訶不思議三好ワールドって意味分からんよね?! よかったちゃんもそうなら私正常ねオッケーやっぱあの人意味分からん!!!! そんなことを思いながらウンウン頷いていると、がぽつりと呟いた。 「でも、三好さん……あの人のこと、好きなようには見えなかったから」 …………待って? ちょっと待ってね?? うん???? 「え……?」 はきゅっと口元を引き結んで、俯きがちに「……性格悪いなって、思うよね」と罪悪感でいっぱいなんだろうと思わせる頼りなげな声音で言った。 ……待って待って? 今ものすんごいこと起きてる……。私の中でビッグバン起こってる……。だ、だってさ? だってさ???? 私はの両肩をガシッと力強く掴んで、感動に打ち震えながらもアドレナリン大放出高鳴る鼓動が止められない状態で細い肩を揺さぶりつつ、もう涙交じりに言葉を吐き出した。 「いや、そうじゃない……そうだけどそうじゃない……ッ! がそんな人間味のある正直な感想をドストレートに口にしたことに感動してるッ!!!! そうそう! それでいいの! 別れた? ラッキー! くらい思ったってそれは正常ッ! 性格悪いって思われないように口にしないのが大半だけどぶっちゃけこのタイミングなら多くの人間が思うことだからセーフッ!! えっいやっそんな本音中の本音を私に言ってくれたとかの中で私のランク上がった気がして泣きそうッ!!!!」 いやだって真面目が過ぎて、自分の感情や事情よりも人の気持ちを何より優先するちゃんが、三好さんがどうとか秘書課のあの女がどうとかいう前に自分が感じたリアルな本心をさらけ出してくれたんだよ泣くなってほうが無理だしそんな心の奥深くをさ……教えてくれるってさ……どう考えても私がちゃんのナンバーワンのオンリーワンってことじゃんやば……。 私が胸を熱くさせながら感動の涙を堪えていると、が私の手に手を重ねた。まるで隠し切ることはどうにもできないというように、触れている手のひらはひどく熱っぽい。そして、何よりも瞳が物語っている。 「……ねえ。……一度しか聞かないって言ってたこと、今なら答えられるよ」 の言葉に、私は慎重に口を開いた。ここからが、本当の正念場だ。 「……じゃあ、聞くよ、がそう言うなら。……、三好さんのこと……好き?」 真正面から視線を交わらせる。私も、そしても、お互いに目を逸らすことはしない。これがの覚悟とけじめで、これが私なりの精一杯のエールだ。は困ったように、それでいて何もかも受け入れるような優しい笑顔を浮かべて、はっきりと言い切った。 「――うん、好きだよ。きっと、今よりもずっと前から」 ようやく、本当のに会えたような気がする。いや、もちろん今まで一緒に過ごしてきた時間や共有してきたものが偽りだったとは決して思わないけど。でも、誰にも譲れない、譲りたくないというような決意を持った言葉を聞いたのは、初めてのことだと思うのだ。こうなれば、私にできることは何もない。だってうちのちゃんは、誰も目を向けないことにまで気遣いを見せられるようなエンジェルである。そんなが、他人のことなんざお構いなしってくらいの決意を持っている。それがこんなにも強く感じられるのであれば、誰が何と言おうと、私はの味方であり続けなければいけない。だって、それが私の役目だ。の“大親友”である、私だけの。 「その気持ち、三好さんに伝える予定はある?」 は「……どうだろう。なんか、進む道に困ってる」と答えた後、少しの沈黙を挟んで笑った。なんつー下手くそな笑顔なんだよちゃん……もう私には通じないよいくらちゃん第一主義者の私にでも……っていうかだからこそ見逃さない。悲しいのを無理矢理に押し込めたような、どう見たってあからさまな作り笑いなんかお見通しですッ!!!! 迷子になってしまった子どもみたく、「三好さんには……もう、信じてもらえないんじゃないかって、」と心細そうに呟くの手を、私はきつく握りしめる。 「その信じる信じないを判断するのは、じゃなくて三好さんでしょ? 三好さんはポンコツで使えねえんだから、から行動しないとずっとこのままだよ。それでいいの?」 顔をくしゃっと歪めて、今にも泣きそうな表情をしながらも、の返答は力強かった。 「、よくっ、ない!」 さっ、ここからがハッピーエンドへのレッドカーペットですよ皆さんッ!!!! 「よし、じゃあ突撃するしかないですね!! さっ、とりあえず仕事ちゃっちゃと片付けちゃって、また飲みながら作戦考えてこ!」 初めこそ明るいトーンで、気持ちいいほどポンポンポンポン話をしていたのですが。何かを決めたような顔をして、が席を立った。 「どこ行くの」と聞くと、「ごめん、わたし、」と言葉を詰まらせたに、わたしは言った。 「……いってらっしゃい」 強く頷いたの後ろ姿を見送りながら、私はどこか寂しくて、でも、これがあの子があの子らしく生きるために、自分を認めてあげるために必要なことなんだと思ったら、私だって覚悟を決めるしかない。だってが自分で選んで、自分で覚悟を決めたなら、そこにはもう私が関与する必要はないだろうから。いやこれ昼間決意したじゃん何を今更ビビってんだよどっかの三好さんじゃあるまいし……。 でも……やっぱりさみしいなあ。のハッピーエンドは私にもハッピーエンドって決まってるけど。 前に進むチャンスをせっかくもらったんだから、は絶対に引き下がらない。 「――あ、もしもし、三好さん? のことなんですけど。……アンタがホントにのことを好きでマジのド根性あるなら、迎えにいってやってください。多分、あの公園だと思いますよ。小田切さんとうっかりエンカウントした公園」 あの頃の私は、今日みたいな日がくるだなんてこと、想像すらしていなかった。だって三好さんは私をとことん嫌っていて、私もそうしようと思ってこれまで過ごしてきたんだから。 思い返すと、三好さんとの思い出はどれも苦笑いしかできないようなものばかりだ。 「この書類、上の会議室に持ってくるよう手配したはずですが、ここのインターン生に任せたと聞きました。請け負ったのはどなたですか」 わざわざ離れた部署のオフィスから出向いてきた三好さんが、不機嫌そうに腕を組んでいるだけで、私はとんでもなく恐ろしい目に遭っているような気持ちで「はっ、はい! わたしです!」と上擦った声で返事をするのが精一杯だった。 この日はちょっとした会議をするからと、その会議室のセッティングを頼まれていて、私は指示された通りにそれをこなした。仰々しいものじゃないからと、この仕事という名のお手伝いを任されたのはわたし一人きりだったのだけれど、整えた会議室を最後に確認した先輩にはオーケーをもらっていたので、やっと一息つけるな、というタイミングで訪ねてきた三好さんを見て涼しい顔なんてしていられるわけがない。この時にはすでに、三好さんは当時わたしが勉強させてもらった部署へ何度も何度も足を運んできていて、その度に何かしらの小言をぶつけられていたから。 「各席に一部ずつ配置したのはなぜです?」 「えっ、そ、そのように言われたので……」 三好さんは苦い顔で「言われたことを言われた通りに実行するのは、組織に属する以上は当然のことです。ですがね、あの配置はあんまりですよ。どうしてまっすぐに揃えられなかったんです? あれでは、束で置かれていたほうが余程マシでした」と冷たく言い放って、わたしの目をじっと見つめる。あちこちから同情の視線を向けられていることを感じながらも、わたしは堪えきれずに震えた声で、「……も、申し訳ありません……」と俯いた。三好さんはしばらく黙ったままだったけれど、その間もまだまだ物言いたげな視線が向けられているのははっきりと分かってしまって、わたしは手のひらにぎゅっと力込めながら唇を噛むことしかできなかった。 けれど、次は何を言われるんだろうと構えようとすると、三好さんは「……次からは気をつけるように。さん」と言ってさっさとオフィスを出ていくので、わたしは何がなんだか分からず、それでも良い印象を持たれていないことだけは確かだと感じていた。 「――っていうことがあって……わたし、なんで三好さんに嫌われてるんだろう……」 わたしの話をいつでも真面目に聞いてくれて、一緒に悩んだり怒ってくれたり――いや、わたしよりもずっとわたしを大切にしてくれている大の親友につい愚痴をこぼすと、彼女は眉間に深い皺を刻んで「はぁ?」と目を鋭くさせた。 「また例の人? そのミヨシさんって人なんなの?? 私は絡みないからよく知らないけどっていうか部署違うのになんでわざわざピンポイントにイジメに来るわけ?? 訴える????」 本当に、誰よりわたしを分かろうと歩み寄ってくれて、いつだって寄り添ってくれる自慢の大親友だ。だからわたしも、ついつい彼女には甘えてしまって、迷惑だって心配だってたくさんかけてきたなぁと思う。 わたしはぼんやりしながら、「そうなんだよね……三好さんに迷惑をかけるような真似はしてないはず、なんだけど、なんでかなあ……」と呟いて、誰にも近づかれたくないと言わんばかりの難しい表情をした三好さんのことを、なんとなく思い返した。いつも去り際の後ろ姿は寂しげだな、ということも。 「さん」 三好さんの声だ、と思うと「はい!」と裏返った声ではあるものの、反射的に返事をしてしまうようになった。三好さんの表情も声の調子も言葉も、何も変わりはしなかったけれど。 「正式な社員ではないからと甘えられては困ります。仕事において“雑務”などありません。なんでも簡単に引き受けて、適当に扱われては困ります」 「て、適当になんて、」 この頃にはもう、三好さんの心の内を知りたいとか、わたしに一度だけ見せてくれた優しさが欲しいなんてことは思わなくなっていた。今になって振り返ってみれば、あの時はただただ混乱していて、そのうちそれを苛立ちに変化させていったような気がする。本当は、期待したところで悲しくなるだけだということを、どこかでは自覚していたのかもしれない。 ただ、たまたまわたしが困っているところを助けてくれた波多野くんとの距離が縮まっていたこともあって、みんなが見て見ぬふりをする中、随分と助けてもらった。 わたしを見下ろす三好さんの前に立って、「さん、俺がそれ引き受けるよ。三好サンも、それでいいですよね」なんて言って、さらには「――っていうか、わざわざこんな離れたとこまでやってきて、三好サンのほうこそ大丈夫ですか? ご自分の仕事のほうは」とまで言うものだから、わたしの心臓は緊張で爆発でもしてしまうんじゃないかと気が気じゃなかった。 「は、波多野く――」 三好さんは波多野くんの肩越しにわたしの視線を捉えると、「……自分の手に余るような仕事は、引き受けないように。いいですね、さん」とだけ言って、やっぱりなんだか不安になりそうな後ろ姿を見せて去っていった。その背中に「はっ、はい!」と答えても、返事はなかったけれど。 いつから、あの人に認められたいと――わたしのことを好きになってほしいと、思うようになってたんだろう。あんなに意地悪をされたのに。でも、今思えばどの意地悪も、意地悪なんかじゃなかったのかもしれない。三好さんの真意はどうしたって分からないけれど、今のわたしにはそう思える。 わたしがいっぱいいっぱいになってる時に、あの人はわざわざわたしのところまでやってきて、あれがダメ、これもダメってダメ出しばっかりだったけれど、それはわたしのためのダメ出しだったんじゃないかと。わたしが無理をしてでもなんでも引き受けること、それ自体がダメだって、そう言ってくれてたんだって、今ならそんなふうに思えるのだ。えらく自分に都合のいい考えかもしれないけれど、あれが、あの人なりの優しさだったんだろうと。 でも、人からどう見られるかだけが気がかりだったわたしは、至らないと言われれば言われるほど悲しくて、つらくて、ムキになる一方だった。挫けそうになった時、そんなわたしを見つけてくれたたった一度の出来事を思えば、だからこそ認められたかったから。 けど、三好さんのほうだって、他に言いようはあったはずなのに。……あの人、損な人だなあ。それで、なんて不器用な人なんだろう。わたしの強情さも大概だったのだろうけれど、あの人の分かりにくさだってそう言える。 ――会いたいなぁ。今、すぐにでも。わたしが臆病さに負けて逃げていた分、そのすべてをあの人に打ち明けたい。本当は、あなたにいつだって認められたくて、それはあなたの隣に立ちたかったからだと。好きと伝えるには怖いけれど、もう逃げは選ばないと決めたから。 でも、なんて言えば、いいんだろう。わたしの気持ちを正しく伝えるにしても、上手な言葉なんて見つけられると思えないし、拙いわたしの言葉を、気難しいあの人がどう受け取るかも分からない。だけど――。 スマホの連絡帳を開いて、通話ボタンを押した。 「……はい」 たったそれだけの声を聞いただけで、こんなにも切ないことを、どうしたら伝えられるだろう。こんなに、こんなに好きだって。本当はずっとずっと前から、あなたに近づきたかった。寂しそうな後ろ姿を眺めているんじゃなく、その隣に並ぶことができたらいいのに。そう思っていたことを、今なら素直に伝えられると思うから。でも、言葉を探すよりも早く、感情が先走ってしまう。だって――。 「――あ、会いたいんです……っ、三好さんに、会いたいんです……っ」 あからさまに煽られているなと思いながらも、もう振り切ろうと決意したことすら棚に上げて、たとえ罵られようとも軽蔑されようとも、僕にはやはり彼女が必要で、彼女でなければならないという心はもう迷うことはなかった。欠けていた僕に与えてくれたのは、彼女だった。僕の心を動かすのも、ただ繰り返すだけだった日々に彩りを与えてくれたのも、すべて彼女だったのだから。もう、なりふり構ってはいられない。散々に傷つけてきたことも、疑うばかりだったことも、取り返しのつくことではない。そうして、ただただ夢中に彼女のことを考えながら、夜を走る。 ――ああ、彼女だ。 見つけた姿は、今にも見失ってしまいそうに頼りない。ベンチに座って俯いている体は、時折小さく震えている。あの時のように、心細い思いをしているんだろうか。僕のことを、待ちながら。 「……どこに、いるんです? 場所が分からなくては、会いに行けません」 僕の言葉に、さんが息を呑んだのが分かった。違う、もっと、もっと他に、かけるべき言葉はあるはずだ。そうは思っても、僕はふさわしい言葉なんて思いつきやしない。今までずっとそうだった。まだ幼かった頃のまま、僕の時は止まってしまっていたのだ。けれど、さんとの再会が、共有した時間が、また僕の時間を動かしてくれた。心の成長は止まったまま、大人ぶっていただけの僕には、それを思うように伝えるすべを知らなかったけれど。 「、さん……」 もっと他に、声のかけ方はあっただろうに。 髪も、服も、いつものような僕ではなくて、あちこち乱れて見れたもんじゃないかもしれない。そう考えても、もう遅い。俯いていた顔を勢いよく上げたさんを見れば、そんなことはどうだっていいのだと思うのだ。この人さえいれば、欠けている僕の心はこんなにも満たされる。充分すぎるほどに、幸せなのだ。 さんは「み、よし、さん、なんで――」と震えた声で呟いて、表情を歪めた。堪らず、僕は膝をついた。覗き込んだ彼女の頬に、涙が伝う。 そっと触れた眦は、冷たく濡れていた。 「……あなたの心は、僕が守ると決めていたのに……あなたを傷つけるのはいつだって僕だ」 さんは「え……」と呟いたきり、僕の言葉を待つように唇を結んだ。 あなたは、いつでもそうだった。僕は心を与えられておきながら、その心がなんたるものかを考えたことはなかったし、相手の心を思いやるという優しさまでは学べなかった。 僕はここへ――彼女のもとに辿り着くまで、一体どれほどの人を傷つけてきたんだろうか。けれど、そうして僕の勝手で積み上げてしまった犠牲のことを思いやれるほど、僕の心は足りていない。ただ一つ言えるのは、そうまでしても、彼女の手を取ることだけが僕のすべてだということのみだ。そうとしか、言いようがないのだ。 まだまだ欠けている僕に、足りないものを教えてくれるのは、今この目の前で泣いている彼女一人っきりなのだから。 「ですが、僕は――きっと、変わってみせます。あなたの望む男になってみせます。優しい男がいいなら、誰を、何を差し置いても、あなたにだけは優しくします。仕事ができる男がいいなら、もっと励みます。あなたはもう忘れているでしょうが……この言葉には、今も嘘はありません。僕はきっと、またあなたを傷つけてしまうでしょう。勝手を言っているのは分かっています。それでも僕は――あなたを、愛しているんです」 ただただ静かに涙を流す彼女を見て、漠然と思った。彼女に返す時なのかもしれない、と。あの時、僕が与えられたような、相手を慈しむ心を。いいや、今度はきっと、僕が与えられる存在にならなくてはいけないのだと。 これまで無感動に同じことを繰り返してきた僕が、突然変わることはないだろう。そして、その変化は一人では叶えられない。彼女が、いてくれなければ。他の誰でもない、彼女だけが与えてくれるものを、僕も同じだけ返したい。きっとそう思うことすら、この人以外にはありえないのだから。 大切に、壊さないようにと守ってきた僕の“心”を、胸ポケットから取り出す。不思議だ。手放すこと、失うことを何より恐れていたものなのに、彼女に差し出すことには何の躊躇いもない。 僕が差し出したキーホルダーを見て、さんは「……四つ葉の、クローバー……?」と小さく呟いた。僕はその瞬間、幼かったあの日の彼女を思い出して、今にも泣きたくなった。 キーホルダーを握らせたさんの手を、ぎゅっと握りしめる。もう二度と、失いたくはない。もしも僕が道を誤ったなら、もしも僕が誰かを傷つけたなら、それを僕に教えて正しく導いてくれるのは、あの日あの時、泣きながらも笑ってくれた天使だけだ。 今の僕は何も恰好がつかないであろうけれど、そんなことよりも大切なことがある。 誰が何と言おうと、僕には彼女だけだ。大切なことは、初めからこれだけだったのだ。 「え、み、三好さ――」 「さん」 緊張しきった声音で、さんが「は、はい、」と返事する。僕は祈るように彼女の手を握りしめて、頭を垂れた。 「僕の、僕の恋人に、なってください。僕を、あなたの……あなたの、恋人にしてください」 さんはしばらく黙ったままだった。沈黙が恐ろしいと思ったのは、これが初めてだ。 彼女が、ゆっくりと立ち上がって、僕の目の高さに屈んだ。あの時のような泣き笑いの表情を浮かべながら、僕と同じだけの強さで手を握り返してくるのが分かって、今度こそ僕は泣いてしまうのではないかと思う。 僕には眩しすぎる、だからこそ僕を照らし出してほしい光が、ゆっくりと僕に寄り添って温めてくれる。 「……わたし、かわいい子じゃありません。ずるいし、嫌なことだって考えたりします。三好さんの機嫌を損ねること、きっとたくさんあります」 僕は至極真面目に、「あなたが損ねた機嫌なら、あなたが責任持って直してください。僕はあなたがそばにいてくれさえすれば、いつだって幸せです」と言い切った。しかし、さんは続ける。 「優柔不断だから、三好さんのこと困らせます」 それで結構だ。僕を好きなだけ振り回して、この心を乱してくれたらいい。 「あなたが決めきれないことは、僕が決めます」 さんは瞳いっぱいに涙を浮かべて、不安げに声を震わせた。 「それに、すごくうじうじした人間です。三好さん、たくさんイライラしますよ」 あなたが与えてくれるものは、僕にとってはすべてが大切で、この世の何より価値がある。欠けていたものを、今もなお足りないものを与えてくれるのは、どうしたってあなただけなのだから。 「僕があなたにイライラする? そんなこと、どうしてあなたに分かるんです。それはあなたが決めることではありませんよ」 さんはいよいよ大粒の涙を零して、か細く「わたし、三好さんには、失望されたくないんです、」と言って手の力を弱めた。僕はその分、強く握り返す。 ねえ、こんなに勝手な僕とのバランスが取れる人なんて、叱れる人なんて――お人好しで誰より強いあなたしかいないに決まってる。そうでしょう? 「……もう言い訳は結構です。僕はただ、あなたの気持ちだけが知りたい。あなたが僕を選んでくれるのか、問題はそれだけですよ。――さん、僕をあなたの恋人にしてください。僕の、たった一つのこの望みを叶えられるのは、あなたしかいないんです」 たっぷりとした沈黙の後、さんは僕の目をまっすぐに捉えた。 「……わたしで、いいんですか」 どうしてだか僕は笑いたくなって、口元を緩めた。馬鹿な人だ。そんなことは決まっているのに。そうでなければ、僕がなりふり構わず恰好を乱すことも、膝をつくなんてこともありえないのに。さんこそが一番、よく知っているはずだ。僕のプライドは山よりずっと高く、海よりもっと深い頑固なものであると。 「あなたでなくては駄目なんです」 躊躇う彼女の頬に、手を伸ばす。 「あなたの口からは、イエスしか聞きたくありません」 今まで聞いた彼女のどんな声より、それは甘く聞こえた。 「……はい、喜んで」 いやぁ〜〜今日もこれから労働しなくちゃいけないとかやんなっちゃうよね〜〜〜〜!! と心の中でクソデカ溜め息を吐いた私ですが、私の大天使・ちゃんの後ろ姿を前にすれば何もかもオールオッケー今日もうちの子かわいい尊すぎて涙出る……と思いながら、完全に同じ人間とかウソでしょこんな大天使が……とめまいさえ起こしそうなキラキラオーラ眩しいちゃんの隣へすぐ駆け寄った。 「! おはよう〜〜っ!」 私の顔を見ると、パッとお花さんが咲き誇るように明るい表情を浮かべるはやっぱり私のエンジェル……労働クソとか思わない浄化される……だってちゃんとデスクは隣ですし、そのちゃんはお仕事一生懸命頑張る系女子なのでそりゃ私も仕事くらいしますわってモンだよ……。 神よ……今日もちゃんという大天使をこの世に送り出してくれたことに感謝いっぱいです……と目頭を押さえている私に、は「おはよう」と笑った後、唇をむずむずさせる。何どうしたのちゃん……昨日私が三好さんけしかけたこと、もしかして怒ってる……? え……それともあの根性ナシの顔だけエリートになんかされたのどっち……? と生唾を飲み込んだ。は躊躇いがちに口を開く。 「……あのね、実は――」 「おはようございます、さん」 …………前からずっとそうなんで今更すぎるけどアンタって人はホンッッッットにタイミング悪いというか空気読まねえな?! 苦い顔をしながら三好さんをジロリと…………ちょっと待って三好さん今なんて言った???? 私の聴覚おかしくなった???? な、なんか今、三好さんボイスでかわいいうちの子の名前呼ばれたような気がす「三好さ……! っか、会社では名前で呼ばないって、昨日約束しましたよ……っ」…………ねえ!!!! 待って?!?!?! あまりにもショッキングな事態に混乱するしかない私だが、やっぱり三好さんは三好さんである。ちゃん以外はすべて路傍の石。 優しく目を細めた三好さんが、そっとの頬を撫でる。……待ってやっぱおかしいよ何この三好×ちゃんみたいな展開……。 しかし、三好さんは絶好調らしいので「そうでしたか? ふふ、そんなことより、ねえ、今晩はどうします? 僕の部屋に来ますか」なんて言って今日の大好きオーラも激マブである。 「そういう話会社ではしないって約束もしましたっ!」 さて……顔を真っ赤にさせて三好さんの手を払うのこの反応…………。 「…………待って待って待って急に望んでたかたちの三好×なんだけどどうしたのッ?!?!」 が「……えっと、」と言葉を選んでいるのを遮って、三好さんは言った。 「お付き合いすることになったんです、僕たち。ね、さん」 ………………。 い、いや、うん、私は分かってるからね。今までココッ!!!! ってタイミングを何もかも逃すか自分の手でフラグ折りまくりのある種の天才か???? っていう三好さんが言う“お付き合い”……散々期待させるだけさせといて何度も裏切られてきた私が言えるのは、「んんんん〜〜〜〜?!?! それはどういう“お付き合い”ですかね?!?!」ということだけである。 三好さんは朝が始まったばかりの、しかも会社の、エントランスでするような顔で色っぽく囁いたやっぱ上の上ではあるよな黙って立ってるだけな「男女交際以外に、意味がありますか?」………アッ〜〜〜〜!!!!!!!! 「……ちゃんや」と声を震わせる私に、は恥ずかしそうに笑った。 「……今日は金曜日じゃないけど、いいかな? いつものところで。……この話、したくて」 泣いた。全私が泣いた。 痛いほど高鳴っている心臓をぎゅっと押さえつけながら、私はなんとか「いいよもちろんッ!!!! もう〜ッ! ここまで長かったんだから根掘り葉掘り全部話してよねッ!!!!」と、のことをぎゅうぎゅう抱きしめる。 ちゃんさえいてくれれば、たとえそこが地獄であろうとも楽園だと確信している私である。……こんな嬉しいことって、そうないよね。エッ、アッ、待って待ってほんとすごい、何がどうなって三好さんがちゃんを頷かせたのか気になりすぎるけど、それは今晩根掘り葉掘り聞き出す――というかどうせ三好さんも来るに決まってるし聞かなくても聞かせてくるからとりあえず今はいい。今はな。 だから、私が言えるのはたった一つだけだ。 「――、よかったね、ホントに」 幸せでいっぱいで、とにかく満たされてるっていうのがよく分かる表情で、は「……うん。ありがとう、ずっと、一緒にいてくれて」と――。 「……やめてッ!!!! まるで今すぐにでも嫁に行くみたいな発言やめてッ!!!! まだまだ私アンタと一緒にいるよッ?!?! オイ三好さんテメー調子乗んなよッ?!?! ちゃんの一番はこの私ッ!!!! 私だかんなッ?!?!」 思わず三好さんの胸倉を引っ掴んだけれど、涼しい顔してビクともしねえ……そういやこの人も化け物エリートだったわクソ……悔しい以外に言葉がない上にドヤ顔で「調子に乗るも何も、さんは僕を選びました。この僕をね」とか言って……その後、目を甘く溶かしてを見つめるんだからしゃあない。 「〜っクソッ!! 腹立つけど……腹立つけど……ッ最高にハッピーだよドちくしょうッ!!!! 持ってけドロボーッ!!!! まぁまだ嫁には出さんけどなッ?!?!」 三好さんは小さく笑って、の肩を抱き寄せた。 「決めるのはさんです。どうします? 僕は今すぐにだって、あなたと――」 「おはよう、いい朝だね。……その様子だと、上手くいったのかな? よかったね、さん」 振り返ると、いつもの読めない微笑みを浮かべた田崎さんが立っていた。相変わらずコンビニのコーヒーすらシャレオツ感を感じさせる色男だな……と思いながら、ちらりとの様子を窺う。どこかスッキリした表情で「おはようございます、田崎さん。……ご心配おかけしました」と言うと、田崎さんは笑った。 「あはは、何も心配なんてしてないさ。なぁ、神永」 その声に応えるように肩を竦めた神永さんが、簡単そうに「納まるべきところに納まっただけだろ」とか言うからいやここまでくるのにどれだけの犠牲と苦労あったのか忘れたとか言わせねえけど???? けれど、「おはよ、ちゃん。今日はとびっきりかわいいね」と笑う神永さんの言葉に、も「おはようございます。神永さんはいつも通り素敵ですよ」と目を細めた。 そして結局揃ったいつものメンバーそれぞれに視線をやると、「で? 今晩飲みに行くって? 俺たちも一緒していい?」とか神永さんが言い出すので「オイどっから話聞いてたッ?!?!」っていう。スーパーエリートって忍びの者の技術とか持ってんの???? 「三好にゃちゃんはもったいないからなぁ。俺と田崎が、エスコートの仕方を教えてやるんだよ」 おもしろそうに笑う神永さんに表情を歪めて、大好きマンの三好さんは「余計な世話だ」と吐き捨てた。いや心配になるのはごもっとも! っていう振る舞いしかしてこなかったでしょあなた……。 どう話をまとめりゃいいんだ就業時間始まるぞオイ……と溜め息を吐いたところで「あ、おはよ〜。飲みの相談なら、俺も連れてって。おーい、波多野〜! 今晩空いてる〜?」とか言いながら甘利さんが近づいてくるのでマジで一回どう片付けるこの話?? この人って空気読まないからホント困るのに……っていうか波多野クソガキまで呼ぶなソイツはいらんだろ余計なことすんな甘利さんッ!!!! 波多野は眠たげな目をしながら「朝っぱらからうるせえな……」と毒づいたものの、の姿を認めると「おはよ、」と爽やかぶって笑顔を浮かべたので波多野テメーそういうとこだぞ……。 ――まぁ、でも。 「おはよう、波多野くん。甘利さんも、おはようございます」 今日くらいはいいか、と思うくらいには私はハッピッピである。 「甘利さんはともかくクソガキ波多野はいらないんですけどッ?!?! ……って言いたけど……まぁいいや、今日くらい。よし、今夜はパーッとやりましょうッ!!!! ――三好×成立記念パーティーだッ!!!!!!!!」 ……というわけでやっと悲願が達成されたけれど、まさかこれで終われるわけがないよね。そうそう、本番はこっから、これまでのはいわゆる“告知”とかと一緒。前フリ。だって私が見たいのは三好×カップルの幸せしかないラブラブシーンである。 ――ね、そうでしょ? こっからこそが真の三好×ちゃんですよろしくお願いします私はとりあえず新しいノートを用意するところから始めますね!!!! いやだって、新しい物語には新しいノートでしょ? さっ、ひとまずは仕事だ仕事! 夜までの時間潰しとしか思えないけど今日も頑張ってるフリだけはしようと思います!!!! |
吹けども吹けども、きみは踊らず
・
・
・
→NEXT?