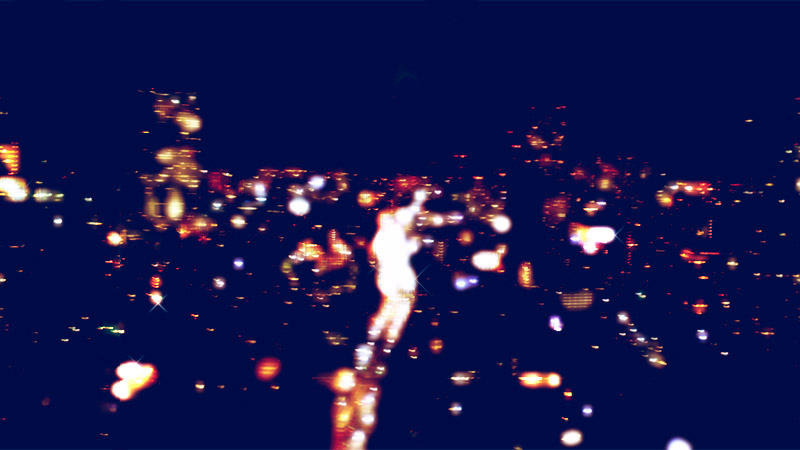
あの子は約束を守ってくれた。 体調が悪いという彼女の申告を受けて、ちゃんは今日の予定は延期しようと言ったが、そう言うのはもちろん分かっていたことだ。 ――もう車出しちゃってるから、それなら二人で出かけようよ。 この提案とは名ばかりの強引な誘いは、ちゃんにはちょっとかわいそうだったなと思う。断れるわけがないと、俺もあの子も知っていた。これは計画的な犯行だ。主犯は俺だが、共犯のあの子はちゃんが一番に信頼している親友だ。やっぱり、かわいそうなことをしてしまったと思う。 でも、こんなことはこれっきりだから、許してほしい。 「さぁて、今日は何しよっか?」 助手席に座るちゃんは、「んん、」と気まずそうに唸った。それにちょっと笑って、「天気良いし、とりあえず適当に走ってみるかぁ。どこまで行けるか試してみる?」とハンドルを抱え込んでじっとその瞳を覗く。あからさまに戸惑った視線が、そろりと動いた。 「どこまでって、」 「行けるとこまで」 俺はこの時、もちろん本気だった。彼女が望むならどこへだって連れていくし、どこまでだって――それがどんな場所であったって、寄り添ってやろうと。彼女自身が自分を許さなくとも、俺は何もかもを許して、彼女を迎え入れようと思っていた。 「えっ」 だから、あんなバカな男のことは忘れたいと、そういう素振りの一つでも見せてくれたなら。 「あはは、ちゃんと帰せるとこまでだから大丈夫だよ。でも、ちゃんがずっと遠くがいいって言うなら、日本から出ちゃっても俺は全然平気」 「えっ?!」 俺は誰に後ろ指さされたって、卑怯だ卑劣だと罵られたって、きみだけを選ぶ。きみだけを選べる。 情けなく眉尻を下げる顔に笑って、「冗談だと思う?まぁ、とりあえずさ」と彼女の手を握った。 「今日はずっと、二人でいよう」 ここのところの記憶が曖昧だ。けれど、それでいい。 僕はこういう時に、やはり仕事はいいなと思う。僕のような人間だからこそ打ち込むにはふさわしい。他に特別関心がないなら、生きるために必要なことを極めていくだけだ。仕事はそのうちの一つで、成果も目に見えて分かる。単純明快だ。何も複雑なことはない。 そうやって気を逸らすことは簡単だというのに、僕はどこか落ち着かない心地で日々を送っている。思い当たることはたった一つしかないが、今それを気にしたところで意味はない。僕は自分で選んだことを後悔したことなどないし、いつだって最善を選んできた自負もある。だからこそ、今の僕があるのだ。僕が、しつこく伸ばしていた手を引っ込めたことだって、絶対に正しいのだ。 それなのに、どうして僕は――。 「三好さん、」 何か言いたげな視線には気づかぬふりをして、“恋人”の体をそっと抱き寄せる。その体から、あの匂いがした。甘いようでいて、それを感じさせない。この匂いは、いつだって僕のそばにあったけれど、いつから忘れていたんだろうか。このフレグランスは、好きな香りだ。 吸い寄せられるように首筋に鼻先を埋めて、目を閉じる。すると、あの時のことが頭を過ぎった。彼女は、あの時――。 「っ、」 「……三好さん?」 頭で考えるよりも先に、体がまず反応したような感覚だった。突き放してしまった女性の訝しげな視線が、僕を見上げている。しかし、僕の意識は目の前の女性ではなく、もう取り戻せない過去に引きずられていく。僕は、どこまでも身勝手な男だ。“恋人”がいながら、その恋人を抱き寄せながら、別の人のことを考えるなど。 そもそも、僕を好きだと言うこの恋人を受け入れたのだって、過去との決別のためだったのに。それさえできずにいて、果たしてこのことに意味はあるのだろうか。 ――分かっている。救いようがないと。 そうまでして追い払おうとしても、できないのだから。今だってそうだ。今、僕は恋人を抱き寄せながら、あの人のことを考えた。 あの匂いは、こんなふうに強く香ってやしなかった。むしろ、その存在は隠れるように彼女に溶けていたはずだ。そして、あの頼りない腕は躊躇うように彷徨って、結局、僕の背に回ることなく離れていったじゃないか。こんなふうに、僕を引き留めようとはしなかった。 どうして僕は、今になってこんなことを思い出してしまうんだろうか。 僕には恋人がいるのだ。それも誰もが目を止めるような美人だし、仕事もできる。何より、僕を愛してると囁いてくれるのだ。 僕がこうしているように、彼女にもそう遠くない未来に恋人ができるはずだ。そいつはきっと彼女を大切にして、彼女の望むことをしてやれる。だから、これでいいのだ。僕は間違ってなんかいやしない。なのに、思い出にどんどん引きずられていく。 あの時僕は、彼女の腕が迷っていることを分かっていて、その上そのことに気づいていたのに、守ると言っておきながら逃げてしまった。彼女のことを信じることができなかったのは、失うことを一等恐れていたからだ。 どうして今、僕は気づいてしまったんだろうか。 ――あの時、抱き寄せた体は、すぐに強ばった。 あの女が僕に言ったことは、間違っていない。 ひっそりとした静かな空間だった。そんなことがあるわけがないというのに、まるで二人しかいないと錯覚してしまえるような、僕と彼女だけの、静かな世界だった。 「三好さ、」 「……さん」 立ち入り禁止とされている屋上へと続くここに、わざわざ人が来ることはない。自分の立場を悪くするような振る舞いをあの女がするはずはなかったが、さん一人をいいように言いくるめることはいくらでもできただろう。 僕はそっと息を吐いて、それから、思わず笑ってしまいそうになった。愚かなだけの自分に。 もっと早くに行動すべきだった。そうすれば、こんなことは起きずに済んだのだ。あの女が言ったことは、間違っちゃいない。そういう自分を知られてしまうことを恐れたから、傷つけてしまった。 「は、はい」 さんの緊張した声は、僕の声も震わせた。 「……どこも、痛くはありませんか?」 「……え、」 僕は咄嗟に、「お怪我は?」と言ったけれど、もちろん体に傷がないことは分かっている。 体の傷は目に見えるから、いつか癒えて消えてしまう。けれど、心のほうは? 僕はその答えを、知っていた。僕にも心があるからだ。心を、与えられたからだ。 さんの不思議そうな声は、「え、怪我? え、どこもしてないですけど……?」と戸惑っている。それに僕は「そうですか」と応えて、それから――。 「……他は、どうです」 目に見えない傷は、癒えたかどうか確認する術はない。それは、癒えないことと変わりない。 「はい?」と僕を見上げる瞳はどこまでも無垢で、自分の後ろめたさゆえに彼女を傷つけてしまったことを、それを招いた自分の愚かさをさらに恥ずかしく思う。 それでも、こんな僕をあなたに知られたら、あなたは一体どう思うだろうと考えると、僕はやはり恐ろしくなるのだ。 「……あなたはあの女を、信頼、していたでしょう」 「? え、あ、あぁ、はい、そうですね、えい子さんてほんとに親切で――」 何も、疑うことをしない人だ。僕をも、信じてしまうような危うい人だ。 「……やっぱり、あなたは僕がそばにいないとだめな人だ。疑うことを知らないあなたには……僕がそばにいなくちゃあ、だめなんです。……あなたの、あなたの心は、今度は僕が守ります」 あの時、僕はそう、誓ったはずだったのに。 「――すみません」 僕の突然の謝罪に、“恋人”は眉をひそめた。 「え?」 「僕はあなたに、責任を持てない」 彼女は訝しげな表情を浮かべて、探るように僕をじっと見る。 「……どういう意味ですか?」という言葉は、何かを――僕の心の居所を確かめるような響きを持っていた。 これまでも今この瞬間も、僕は誠実さとは無縁な男だ。 「あなたには、愛すると誓って、必ず何からも守るという責任を、果たせない」 「せ、責任なんて、そんな――」 彼女の震える声はますます僕の恋しさを煽るが、ぽっかり空いた穴を埋めてくれる人は、やはりたった一人なのだ。元々なかったものを与えて、欠けていた部分を埋めてくれたのは、彼女なのだから。 「……すみません。僕はやはり、あやふやなものは信じることができない無感動な人間なんです。だから、僕が人を愛するには、その証明として――責任を果たさなければならないんです。僕はあなたに、責任を持てない」 こんな身勝手な男を、彼女はきっと許さないだろう。けれど、いつかのように感情を爆発させて、僕を叱ってくれたらいいのだ。僕のせいでと、泣いて怒ったらいい。僕のせいで人が傷ついたと、責めてほしい。自分だって優しい男と一緒になれたかもしれないのに、僕のせいで選べなくなったと。 けれどその後に、また前のように呆れてほしい。僕を駄目な人間だと、だから、仕方がないからそばにいてやろうと、そう思ってくれたらいいのだ。僕は勝手で自己中心的な人間だから、彼女のようなお人好しにはピッタリだ。ねえ、そうでしょう? こんなことを考えること自体、僕はやっぱり“足りない”人間なんだろう。このような時にどういう感情を抱くべきなのか、それは知っているはずなのに、自分に当てはめることはできないのだから。しかし、僕にはもう、失うものなんて何一つない。隣に彼女がいないことが、すべての答えだ。 何も言わずに俯く女性の姿を目に焼きつけて、部屋を出た。 「――観覧車、乗ろうか」 なんとなく俯いていた顔を思わず持ち上げると、かち合った瞳はひどく優しくて、喉が詰まってしまった。 何か、言わなくちゃ。ぽつぽつ点灯し始めていたイルミネーションが、そろそろ完成するはずだ。観覧車から見下ろしたら、きっと綺麗で――。 「――さん、今日は、一日、どうでしたか」 三好さんはなんだか小難しい顔をして、そう言った。どうでしたかなんて、わたしのほうが聞きたい。でもそんなことが言えるはずないから、わたしは「……ど、どう……とは……」と恐る恐る聞き返した。だって三好さんと遊園地なんてミスマッチもいいところだし、今日はずっとわたしの行動に合わせて……変だ。初めの食事の時だって、わたしが迷ってることに気づいてくれたし、それだけじゃなくて、あっちにこっちにと言うわたしに黙って付き合ってくれたりして。 「楽しかったかと聞いているんです」 あんまり真剣そうに言うから、ちょっとびっくりしてしまった。ただでさえ、こんなに狭い観覧車の中で三好さんと二人っきりなんて、心臓が痛いのに。なのに、まるでわたしが楽しかったかどうか、それが今一番大事なことみたいなトーンで言われてしまうと戸惑う。 三好さんはなんでも完璧にこなしたい人だし、わたしがつまらなかったと言うのは許せないだろうな。遊びなのに。 そう思いながら、わたしは今日のことを初めから思い返した。 車で迎えにきてくれたこと。洋服を褒めてくれたこと。わたしに靴を履き替える時間をくれたこと。パスタを分け合ったこと。自分で行きたいと言ったくせに、お化け屋敷で怖がるわたしを連れ出してくれたこと。三好さんにとっては何も特別じゃないのかもしれないけれど、以前ならこの人とそんなふうに過ごすなんて思いつきもしなかった。だから、わたしにとっては特別な時間だった。三好さんらしくないと思うのに、変だって思うのに。 三好さんの考えることなんて、わたしには想像もつかないけれど、でも、わたしの素直な感想は――。 「楽しかったですよ。遊園地なんて久しぶりでしたし。やっぱりこう、童心に返るって言うんでしょうか、はしゃいじゃって」 三好さんはどこかほっとしたように、「そうですか」と言って窓の外に視線を移した。それっきり何も言わないので、居心地が悪い。 「……あ、えっと、三好さんは! 三好さんはどうでしたか?」 三好さんは驚いたようにわたしを見つめて、それから少し笑った。そして、見たことないような優しい表情を浮かべる。 「……楽しかったですよ、とても。あなたが、笑うから」 「え」 なんだかくすぐったくて、わたしは誤魔化すように口を開いた。変に上擦った声で「……えっと……あ、あ、あ! あのっ、お、お化け屋敷!」と言うと、三好さんは首を傾げる。 「はい?」 その様子に、やっぱり特別なことではなかったんだと、どこか安心してしまう。それと同時に、やっぱりこの人のことは分からないな、と思った。あんなこと誰にでもするんなら、みんな勘違いしてしまうに決まってる。だってわたしだって、あの時だけは三好さんの声と力強い腕に頼りたいと、そう思ってしまったから。なんだかわたしも、今日はおかしいみたい。三好さんとはいつも一定の距離があって、わたしはそれを守ろうとしていたのに。これじゃあまるで、恋でもしてるみたい。――そんな、まさか。 誰にも聞かれない心の内の声だったのに、わたしは言い訳でもするように「あのっ、すみませんでした、あの、つい、いつものくせで……」と言って、三好さんから視線を外した。 「……いつもの?」 低くなった声に「……お化け屋敷、苦手で……」と答えると、呆れた溜め息を吐かれてしまった。 「……それで入ろうと思う気が知れませんね。どうして入りたいと思うんです?」 わたしはその言葉に、間抜けに「え、」と呟く。咄嗟に三好さんの表情を確認すると、三好さんは「え、とは?」と眉間に皺を寄せていた。でも、わたしのほうが聞き返したい。だってそれじゃあ、三好さんがわたしのことに興味あるみたいに聞こえる。 「い、いえ、そんなこと聞かれるとは思わなくて……すみません、」 長年の癖で、つい頭が下がっていく。すると、三好さんは心底驚いているような声音で、「なぜ謝るんです? 分からない人だな、」と言った。 分からない人? あなたのほうが、よっぽどそうなのに。 「……だって三好さん、」 「僕がなんです」 「……そういう、わたしの個人的なことなんて、興味ないでしょう」 少しの沈黙の後、「……そうですか? 僕はいつでも、あなたのことばかり気にしていますが」と――。 「……はい?」 思わず三好さんの表情を確認すると、口元を緩めて「ですから、今日はいい休日でした。見たことがないあなたの顔を、いくつも見られた」と言った。……やだな、勘違いしそう。 なんと返したらいいのか迷っていると、「さん、ほら、もう頂上ですよ」と三好さんが言うので、わたしは慌てて窓の外に顔を向けた。 「えっ、あ……わあ、すごい……! 三好さん三好さん、ほら、人があんなに小さいですよ! これ、ライトアップの時間になったら、きっと綺麗ですね!」 くるりと三好さんを振り返ると、三好さんはじっとわたしの目を見つめて言った。 「夜までここで過ごしますか」 「え……」 すぐに「冗談ですよ」と笑ったけれど、わたしにはそれが冗談に聞こえなかったから、ちょっとだけ、がっかりしてしまった。ライトアップをこの人と見たら、どうなるんだろう。何か変わってくれるかもしれない。そういう邪な期待があったからだ。 「それより」 「えっ、あっ、なんですか!」 三好さんがゆっくり立ち上がって、わたしの前に膝をついた。わたしも咄嗟に立ち上がろうとすると、「揺れます、動かないで」と――。 「えっえっでも、」 「じっとして」 三好さんが抱きしめるように、わたしの肩を両腕で引き寄せた。 「っ、み、三好さ、何して――っえ、」 三好さんの柔らかい声が耳を打つ。 「プレゼントです」 首元に手をやってみると、今日はしていなかったのに、ネックレスがある。 「……はっ?! えっ、なんで?! えっ、あっ、なんでですか? えっ、もらえません!」 慌てて外そうとすると、その手を三好さんが掴んだ。 「今日一日、僕に付き合っていただいたので。……佐久間さんとの約束を、あなたに破らせて」 どきりとした。 「……それは、」 何も言葉を返せないわたしに、三好さんは言った。どこか甘くて、でも、それでいてなんだか悲しくなるような、そんな声で。 「ずっと持っていてくれさえすれば、それでいいんです。僕が願っているのは、たった一つだから。――どんな形でもいい、ただ、僕のそばにはいてください」 ただ、三好さんを尊敬していられたら、それでよかった。なのに、どうしてわたしは一瞬でも、この人の隣に立ってみたいと思ってしまったの? ――バカだなぁ、わたし。あんなのただの口約束で、それだって何か特別な意味があったとは思えないのに。きっとプライドの高い三好さんのことだから、自分が選んだものを突っ返されたり、引き出しの奥で眠らされたりすることが許せないとか、そんな理由だったのに。なのにわたしは、なんであんな口約束を守ってるんだろう。 それが、わたしの邪な気持ちの証拠のようで、観覧車から降りた時にはひどく緊張していた。 三好さんの意に沿わないのなら、自分の感情なんてものは誤魔化すことができていたのに。わたしはただ、三好さんの近くで、その背中を尊敬していられたら、それでよかったのに。いつの間に、あの人に対して、やましい感情を持ってしまったんだろう。 ここで神永さんと観覧車から夜景を見下ろしたら、何もかも忘れられる。ずっと持っていてほしいなんて口約束も、その証拠のネックレスを捨てちゃえば誰にも知られない。だって、あのことはわたしと、三好さんだけの思い出だから。 ――それなのに。 「……ごめん、なさい、」 声が震えてしまった。神永さんは優しい声で、「なんで謝るの? 観覧車、好きじゃない?」と言って、わたしの手を握って顔を覗き込んできた。きっとわたしは、情けない顔をしている。 「わたし、」 神永さんはわたしの手を握りながら、一歩後ろに下がった。 「俺は、ちゃんが泣くくらいなら、そんなのやめちまえって言いたいよ。選ばなくていいことだと思うから」 何を言われているのか分かってしまって、思わず手を握り返してしまう。 神永さんは笑った。 「……でも、ちゃんみたいな真面目ちゃんは、泣かせられたんだから絶対諦めないって言い出すんだよな。なんでわざわざって思うけど」 神永さんとの距離が、一歩分また遠くなる。 「だから、今が最後のチャンスだよ」 わたしが中途半端でずるいこと、この人は気づいているはずなのに。優しい声でわたしに選ばせようとしてくれることが、今はとても苦しい。 この人はいつだってそうだった。わたしに選択肢を与えてくれて、選ばせてくれた。自分だけなら身軽にどこへでも行けるのに、わたしに歩幅を合わせてくれていたのだ。まるで、中途半端でずるいわたしを、全部許してしまうみたいに。 「これが、きみが自分の力で前に進む、最後のチャンスだ」 しばらくの沈黙の後、わたしは、神永さんの手から、そっと手を引き抜いた。引き止めるような素振りも見せずに、神永さんも、手を離す。するりと簡単に外れたのに、最後に一度だけ、指先がわたしの薬指をなぞった。視界がこれでもかというほどにぼやけて、何もはっきり見えない。それなのに、神永さんが笑っていることだけは分かってしまって、わたしにはそんな資格ないくせに、ますます涙が溢れてくる。 「……すごく、楽しかったです。たくさん、笑わせてくれて、」 神永さんは言った。 「なら最後まで笑っててよ。女の子の泣き顔って、好きじゃないんだ」 が去っていったのを確認してから、私は神永さんのところへゆっくりと近づいていく。 そろそろ終わるからと私を呼びつけたのには、どういう意図があったんだろう。まさか――盛大にフラれるところを見届けさせようとしたのなら、この人はホンットにバカである。 神永さんは振り返りもせずに、なんともないふうに言った。 「ま、最終的には丸く収まるって決まってる。きみもそう心配することないんじゃないか? ちゃんが自分で選んだんだ、後悔したって彼女は構わないって言うだろ」 私は神永さんの隣に並んで、きらきら光るライトを見つめる。眩しいったらないけれど、子どもがはしゃぐ声と、顔を寄せ合って何か囁き合っているカップルを見たら、まぁしゃーねえな、という気持ちだ。 物語はいつでもハッピーエンド。でも、たった一つのハッピーエンドのためには、誰かの何かが失われる。これもお約束だ。 「……なんで私を呼びつけたんですか? 私どう考えてもいらないっていうか、いたら、ダメでしょ。言っときますけど慰める的なアレは期待されても無理ですよ」 私の言葉に、神永さんは低く笑った。 「ちゃんは、自分で選べる子になっちゃったんだよ。どっかのヤローがぐずぐずしてるから、彼女のほうが大人になってやったんだ」 ……ヤバイ、月9枠は田崎さんの担当だったのに!!!! ドラマ感やべえ!!!! 私はワッとその場にしゃがみ込んだ。だって今神永さんの顔なんて見てしまったら、なんていうか、なんていうかこう、いつもの調子で笑い飛ばすことなんてできやしないから!! クソッ、すっかり真面目で誠実な男になりやがって!!!! っつーかこの人はなんで大事な場面にこそ私を立ち合わせようとすんだよッ!!!! ――いや、私に笑い飛ばしてほしくて、諦めろって言われたいんだよね、分かってる分かってる。 でもさぁ、私も人の子だから、そんな、いつでもどんなシーンでも笑い飛ばすなんてことは、上手にできない。だからこそ、私はいつもよりも大袈裟に、空気なんて読まずにいなくてはいけないんだけど。 「うわ、すんません、なんか私が泣きそう!!!! うちのがついに嫁に……!」 「――だから、見守ってやるべきなんだ」 私はそれに応えようとしたけれど、神永さんは饒舌だった。煙草を取り出して、堂々それに火をつける。そして、幸せそうなキラッキラなカップルを嘲って笑うみたいに、いつも通り煙を吐き出した。 「バカな子ほどかわいいって言うけど、だめだな。俺は賢い女が好きみたいだ。だから、あんないい男はいなかったのにって、思い出して泣いたらいい。そしたら、馬鹿な女って、笑ってやれるからさ」 私はだけの味方なんで、もしもこの人に何かを言う必要があるんだとしても、言えることなんてこのくらいしかない。 ――アンタはバカな男だよ、ってことしか。 ホント、最高のバカ野郎だよ、神永さんは。 |
画像:HELIUM