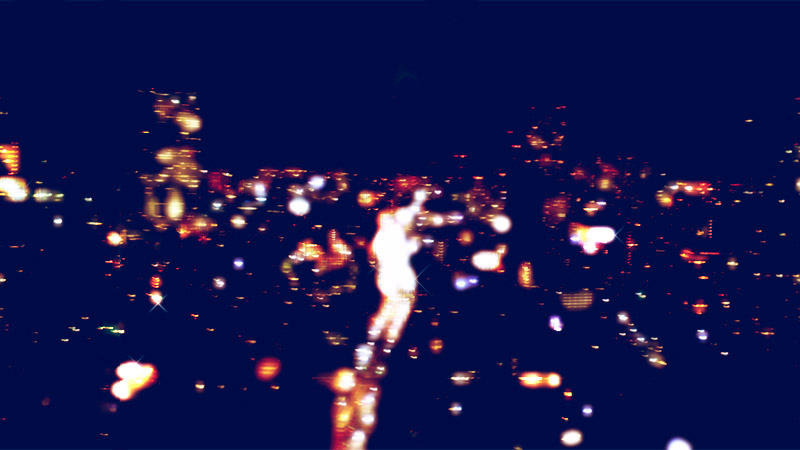
「あれ、田崎はいいの? 待たなくて」 甘利さんは揃った顔ぶれを見て、きょとんと首を傾げた。 「……いいんです、あの人は」 私の硬い声から察することはできるはずだが、甘利さんはにこにこしながら言った。 「へえ。どうして? 今まで俺のこと仲間外れにしてたのに、急に呼んだと思ったら――どうして田崎がいないの?」 いや仲間外れにしようと思ってしたわけじゃなく、ちょっと事が事だったし甘利さんを召喚するのは気が引けてっていうか今その名前出さないでくれませんかね甘利さん分かってるでしょッ?! “あの”田崎さんなしで話し始めようとしてんだから、いなくていいって言ってんだからなんかあったんだって分かってるでしょ空気読んでくださいホント舐めてんのかッ?!?! 「いいんですあの人はッ! 人のことより自分のことッ!! 甘利さんは協力してくれる気あるんですか?! ないんですか?! こちとら深刻な人員不足でこのクソガキまで駆り出すハメになってんですけどッ?!?!」 クソガキ波多野は眉間に皺を寄せて、「あ゛? 俺だっていい迷惑だっつーの」と言って舌打ちすると、甘利さんに視線を移した。 「おい甘利、田崎呼んでこい」 「あ゛ァ?! 呼んでねえんだから呼ぶなッ! 甘利さん行かなくていいです」 甘利さんはにこにこ人好きする笑顔を浮かべたまま、神永さんを見る。 「……どうしてほしい? 神永」という声は、どうにも笑ってなんていなさそうだけれど。 「必要ない」 なんの感情も乗っていないと思ってしまうほど、あっさりした返事だった。それに対して口を開こうとしたが、なんと言えばいいのかも分からず、ただ喉が詰まる。だって、神永さんはもう、“先”のことを考えているに違いないのだから。 すると、波多野が苛立った口調で言った。 「そもそも、いつまでこんなくだらねえことやるつもりなんだ? ――おまえら、のことを一体なんだと思ってんだよ」 聞き捨てならないそのセリフに、私は声を震わせた。もちろん怒りの感情によってだ。 「おいコラそりゃどういう意味で言ってんだ波多野クソガキ……」 波多野は冷たい視線で私を射抜きながら、「分かったような口利く割に、なんも分かってねえから目障りなんだよクソ女」と吐き捨てた。 ……コイツは前々からホンット目障りなことこの上なかったけど、が気に入ってるからって理由だけで、まあ結局のところは見逃してやってここまできている。でも、今この状況においては、見逃してやる理由もなければその気もない。 「……もっぺん言ってみな」 私の視線を真っ正面から受け止めながら、波多野は鼻を鳴らして皮肉げに表情を歪めた。 「何度でも言ってやるよ。おまえらはのことをなんも分かってねえっつってんだよ。もっぺん言ってやろうか?」 思わず手が出てしまった。波多野の胸ぐらを掴む腕は、ぶるぶる震えている。涼しい顔をしている波多野を見ると、私の心はますます高ぶっていく。 ――だから私は、コイツのことが大っ嫌いなんだ。 「……私がアンタのこと大っ嫌いなのは、ぽっと出のくせにそうやって分かったような口ばっか利くからなんだよ。私が、の、何を分かってないって?」 静かに睨み合う私たちの沈黙には、「――分かってやれれば、それでいいのか?」という声は、うるさいほど大きく聞こえた。 「……神永さん、割って入らないでくれます? 私がケンカ売られてんですけど」 「きみだけじゃない、俺も売られてるから買ってるんだ」 波多野から距離を取ると、ヤツはわざとらしく襟元を整えた。くそ、腹立つ……。 イライラしてヒールを鳴らす私をちらりと見てから、神永さんは静かに口を開いた。 「……で? おまえはちゃんのことを理解してるらしいが、それでおまえは何をしてやれてるんだ?」 波多野は迷う素振りなんて少しも見せずに言い切った。たった一言だけ、「そばにいる」と。 私はこの言葉にどきっとしてしまって、その理由にも見当がついてしまうから唇をきつく噛んだ。けれど、神永さんの声はとても落ち着いている。 きっとこの人は、私みたいに後ろめたく思うことなんて一欠片もないのだ。それがどんなことであれ、自分が定めたことだけをただ守ろうとしている。だから迷いなんてものは一切ないし、私に宣言してきたように――きっと容赦もない。神永さんが考えているのは、のことだけだ。 「そばにいるだけなら誰でもできる。――俺は、守ってあげたいんだよ。全身全霊で、何からも」 守ってあげたい。 私はなんでだか、本当になんでだか分からないけれど、泣きたくなってしまった。 私はを守ってあげたくて、ずっと笑っていてほしくて。私は楽しそうなが好きだし、が嬉しそうにしてくれることが好きだ。そして、それを私も共有して、一緒に笑い合っていたい。だから――。 「おまえらのは守ってるんじゃない。の思うことを、ほんとに聞いてやったことがあるか? 過保護にあれこれ想像して壁になったり、なんでも先回りしてやることで“守ってる”って言うんなら笑える話だな」 静かな呼吸をしているはずなのに、私の心臓はこれでもかというほどに大きく、そして激しく音を立てている。 「……人の顔色窺っちゃうが、自分で選べるようにしてあげることの何が悪いの?」 波多野は何もかも見透かしているような顔をして、淡々と言った。 「それが余計なんだっつってんだよ。がそうしてくれって頼んだか? おまえらがいちいち口出しするから、はおまえらの顔色窺ってんだよ」 私は今までと一緒に過ごしてきた時間に、自分が選んできた選択に、きちんと自信を持っている。私はいつだって、に幸せになってほしいと思ってきた。なんでって、そんなの答えはたった一つだ。私にとっては一番の、かけがえのない大親友だから。それだけだ。 確かに、私はの思うこと全部を分かってあげられていないだろうし、聞いたっては肝心なことは言ってくれないと思う。それは認める。が今感じてることだって、私は分かってないよ。だけど、言われなくたってンなことは、本当は、分かってる。分かってんだよ。 だけど、が言ってたように、分かりたいって思うよ。全部なんて言ってくれないことは、が真面目すぎるからだっていうのも分かってる、仕方ない。でもだからこそ、言ってくれない――言えない本心を分かってあげたいと思うことが、そんなにいけないわけ? 私は「そんなことあるわけないでしょ。は素直で嘘が吐けない子なの。真面目すぎてなんでも真っ正面からじゃないと向き合えない子なの」と言いながらも、そんなことを考えていた。 そうしたら私は、私だけがのことを好きで、でも、その私が好きなは、本当のじゃないんじゃないか? なんてことを思ってしまって。 私の後ろめたさが、ここにきて、一番大事な場面で爆発してしまった。 「……手を貸すな心配すんなって言いたいわけ? 無理に決まってんでしょ。そういう子だって分かってるからほっとけないの」 それは、今の私にはドぎつい一発だった。 「そんなにに“いい子ちゃん”でいてほしいか? ……はそう受け取ってんだよ。そうじゃなきゃ、おまえが離れてくって思ってんだよ。俺はそっちのほうが余程いいと思うけどな」 「あ゛ァ?! ……アンタに、アンタなんかに何が分かんのッ?! ぽっと出のくせに……! 私は今までずっとずっとのそばにいたの! 一番近くいたの! ……アンタなんかに、何が分かるってのよ……ッ!」 波多野はうんざりしたような顔つきで、「てめえがいなきゃ、も気にする顔が減って気楽だろ」と呆れたふうに言った。 私は口を開こうとして、でも――。 「自信がないことの表れだろ、ちゃんのは」 はっとして視線を向ける。神永さんは、ただただ優しい顔をしていた。そして当然だって口調で、でも、どこまでも優しい声で言った。 「甘やかしてやれる人間がそばにいないから、周りの顔色を窺って“いい子”でいようとするんだ。何を言おうが何をしようが、それでもいいって許してやれる存在が必要なんだよ。そばにいるだけなら誰でもできる。俺は、あの子を許してやれる」 肩の力が一気に抜けてしまって、私はなんだか笑ってしまいそうになった。いやこの状況で笑えることなんか、ホントならひとっつもないんだけど。ないんだけど。 は〜〜やっぱエリート様ってのは出来が違うのかね〜〜。私はどんだけ自信あるとか言ってみたって、どっか後ろめたいとか思っちゃってる自分が奥底にはいるんだよ。でもそんなの認めたくないから、いつもそれを見ないようにしながら、まるで気づいてないって感じでないもの扱いして過ごしてきてたのに。そういうふうに、自分に都合良くあやふやにしてたのに。その気まずさは確かにあるんだよ今だって。 でもこの人は、後ろめたさなんてホンッッッット欠片もない。欠片もだよ、信じらんねえ。だから波多野も苦い顔してるし、私ももういっそ笑っちゃいそうとか思ってしまうのだ。 「――はい、言いたいことはこれで全部言い合っただろ? もうおしまい。それより、本題に入ろうよ」 甘利さんの言葉に、私はふーっと息を吐き出した。そうそう、こういう話はクールにしないとダメ。もういい大人なんだから、いくら腹立っても癇癪なんて起こすもんじゃないのよ、そうそう。…………。 「……そうですね」 波多野は私の顔をじっと見て、気に入らなさそうな溜め息を吐いた。そして「くだらねえ。俺は帰るぞ」と言って屋上を出ていったが人の顔見て溜め息吐くんじゃねえっていうかそもそも私のほうがよっっっぽどアンタのこと気に入らねえからッ!!!! やっぱあのクソガキ許さない……と舌打ちする私を見て、甘利さんはお茶目に笑ってみせた。それから、ほんの少しだけ眩しそうに目を細めて、まるで言い含めるようにゆっくりと言葉を紡いでいく。 「……ちゃんは確かに、素直で嘘が吐けないし、真面目すぎると思うよ。だから、道を逸れないように見守っててあげなくちゃいけない。俺はきみの言いたいことも分かるよ。ただ、波多野が言いたいのは――」 「分かってます。分かってるからアイツ大っ嫌いなんです私」 私が言ってることはガキくさいことかもしれないけど、そうは言ってもこちとら大人だよ。今更噛み砕いて説明されんでも分かるわ。甘利さんは私のことなんだと思ってんの???? ……とかいうことを、屋上の扉をじっと睨みつけながら考えていた私は、残念なことに結構冷静である。クールダウンどころか燃え尽きたって感じ。だから、強い言葉を使っているくせして、私の声はほんの呟きというような弱々しさだった。 ――でもさ、私はのこと、大好きなんだよ。 人の顔色なんか窺って、その人のための選択なんか私だってもちろんしてほしくない。には自分のために考えて、自分のために選んでほしい。もしそれがが思う“いい子”じゃなくたって、私はのことが大好きだ。 だけど、私はずっとのそばにいたから。が、真面目で誰よりいい子だってことは、私が一番そばで感じてきたことだから。 だから嫌われたくないと思う、“いい子”でいたいの気持ちも分かるんだこれが。 ……いやヘコんでる場合じゃないけどさ〜〜! でもいくら私だからって、いや、ちゃん第一主義者の私だからこそ身につまされる状況でしょどう考えてもッ! でも、今度は溜め息なんかじゃない。私が吐き出したのは、クソの役にも立たない後ろめたさとか引け目じゃなくて、この先に備えてのエネルギーを取り込むための深呼吸の準備だ。 私の、のしたいようにすればいいっていう気持ちは、が“いい子”でいられる選択肢ばっかりを見つけるようになっていたかもしれない。にはそれが透けて見えていて、“いい子”でいなくちゃ、私がを嫌いになるとか、そんな、あるわけないって自信持って言えるバカな話を、信じ込ませていたのかもしれない。 だから私、心の底から言えるよ、。 “いい子”ってなんなの? アンタのこと、私が嫌いになるわけないのに、そんなバカなことクソ真面目に頑張ろうとすんなって。 ……伝える機会は、今まで何回だってあったのになぁ……。 しっかし……波多野にクソ偉そうな口利かれて気づくとか、それが一番情けないわ。アイツほんと許さねえから。 私の考えてることなんて分かっているんだろう。甘利さんは笑った。 「……だよね。まぁ、それでも三好とのことについては、きみの手助けが必要だと思うよ。ここまで拗れちゃってると、ちゃんもいよいよ頑固になっちゃうから」 「甘利さんまで知ったような口利くのやめてもらえます??」 空気の読めない甘利さんは、「あはは。でもまぁほら、近すぎると気づけないことってあるからね」とか言うと、屋上を出ていった。 ……ほんと、うるせえな。 ただ繰り返される朝と夜、それを積み重ねるだけが生きることだった。“日常”なんて言葉を当てはめようにも、あまりにも味気ない。もしかしたら、積み重ねるという言葉すら、もったいないのかもしれない。僕はすべて、その場その場でやり過ごしてきただけなのだから。 それだというのに、あなたが当たり前のような顔をして、僕の存在にかたちを与えてくれたから。いつか、あなたと肩を並べて歩けたらと、無感動な僕が抱くには贅沢すぎる夢を、もしかしたら叶えられるのではないかと思ってしまったのだ。 僕は今まで何も、彼女に与えてはあげられなかった。きっとこうした驕った考え方が、そもそもの原因だったのだ。無感動な人間が人を幸せにすることなどできるはずがないのに、どうしてそんな思い違いをしていたんだろうか。 それでも、あなたが今僕の目の前にいて、僕の言葉をじっと待っている姿を見ると、言ってしまいたくなる。本当は、ずっと言いたくてたまらなかった。毎朝、あなたを見るたびに。毎夜、明日のあなたを思うたびに。 あなたは、いつだって綺麗だと。 「あなたは僕を良い上司だと言ってくれましたが、僕は……そうでないと思います。あなたを評価しているつもりでしたが、僕はそうだとはっきり口にしたことがなかった。それでも、さんは僕についてきてくれましたね」 とびっきりの店を選んで、本当によかったと思う。 僕は普段と変わらぬスーツ姿で、彼女も特別着飾っているわけではないけれど、だからこそ、舞台だけは完璧に整っているべきなのだ。 今日のさんは、よく笑ってくれる。僕を前にすると、いつもどこか緊張していて、ぎこちなかったのに。 ただ、あまり見たくはない顔だ。おかしな話だと思う。僕はいつも、あなたの笑顔を見ていたかったし、できればそれは、僕のすぐそばがいいと思っていたのだから。 さんは口元を緩めて、けれど言葉はしっかり選んでいるようだった。 「それは……、三好さんが、どう思われるかは分かりませんけど……わたしは、三好さんのことを、わたしなりに、尊敬しているので、」 僕は口が上手いほうだと思っていたけれど、どうやらそうではないらしいので、今晩、今この瞬間だけは、あえて言葉を選ぶようなことはしまいと決めてきた。 「僕には、それが一番の賛辞です」 その後が、なかなか出てこなかった。それでも、さんはただじっと僕の言葉を待っている。いつものように。 しかしもう、僕の都合で時間を引き延ばしてはいけないのだ。あなたを、くだらぬ用で引きとめたように。 「……仕事に励めば、あなたは僕を見てくれるから。……あなたには、あなたにだけは優しくしたいと、持てるすべてで、大事にしたいと思うのに、どうしても、うまくできない。どうすればあなたに好きになってもらえるのか、僕には分からなかった。……あなたは僕のほうが嫌っていると思っていたようですが、それは大間違いですよ。本当はあなたのほうこそが、僕を嫌っているんです」 「っそんなわけない!」 彼女がそうして表情を歪めても、僕にはかけるべき言葉など分からない。きっと、僕は持っていないのだ。優しいあなたにふさわしい言葉を。それは本来なら誰もが持ちあわせているべきものだろうが、生憎と人に寄り添ったことなどない人間だ。知らずにいて済んでいて、知ろうともせずにここまでやってきた。 「……そんなわけ、ない。わたしが今まで頑張ってこれたのは、全部、全部三好さんのおかげで、三好さんに、認めてもらいたくて、ただそれだけで、」 だからせめて、僕があなたのためにできる一つだけは、ここでやり遂げなければならない。 「……僕はずっと、あなたを認めていますよ。――あの日、あなたは折れてしまいそうに見えたけれど……必死に食らいついて、ここまでやってきた。……僕が、どんな難題を出したとしても」 「……覚えて、るんですか、」 忘れようはずもない記憶だ。 心細そうにしていた。きっと、辛いのだと思った。不安なんだろうか、怖いんだろうかと、僕は気が気じゃなかった。もしかしたら泣き出してしまうんじゃないか、そうしたら僕は、彼女のために何をしてあげられるだろうか。できたことと言えば、ただ声をかけるだけのことだった。もし僕が、優しい人間であれたのなら、きっと手を伸ばすこともできただろうに。 「あなたが書類をばらまいたことなら、もちろん。……途方に暮れた顔をしていましたね」 ただ、僕は知っている。もしもなどという起きえない現実を夢想してみても、意味はないのだと。どうしてか? そんなものは決まっている。 「……三好さん、あの、観覧車のこと、覚えてますか、」 結局、“もしも”あの時に戻れたとしても、僕は同じことしかできないからだ。 「……さん。僕があなたにできることは、初めから一つだけだったんです」 「え……?」 あなたは、いつだって綺麗だ。 今、あなたの瞳にこの僕だけが映っていることが、こんなにも心を満たしてくれる。あなただけは、いつだって綺麗だ。だから、その瞳に映る僕のことは、僕だけが覚えていればいい。 「あなたは、忘れてください」 僕の身勝手な思いに、もう振り回されなくていい。僕があなたを愛することは、僕の勝手で――あなたに同じものを求めることは、しないから。 三好さんの話を、は一つもしなかった。私も、これまでそれには一度も触れずにいる。……いや触れようもないよね。いっそ三好さんの存在ごと消してるような感じならよかったけど、いつも通りなんだもんよ……。 まぁ大人だし、仕事に障りが出るようなことしないのは当然だけど、気まずそうな素振りだって一つも見せないし、会話の中に三好さんが登場する場面があったとしてもにこにこしている。私はもちろん部署の全員がどうすりゃいいんだか分からず、みんなで緊張している日々である。だって三好さんのほうまでいつも通りだから。 “いつも通り”でいられないのは、私だけだ。 「、だし巻きどうす――何食べたい?」 は私の言葉に、「え?」と目を丸くした。 いや、気にしてるわけじゃないけど。クソ波多野に言われたことなんかを気にしてるんじゃないけど。ただ、ちゃん今日何食べたいかな〜? ってふいに思っただけだし。いつも私がここ行こうって言うところに行くから、お店では好きなもの食べてほしいっていうか…………クソ、腹立つけどめっっっっちゃ分かりやすく気にしてる自分こそに一番ブチ切れそう。 「だから、何食べたい?」 はメニューを見ることもせず、「え、えっと、あ、今日は明太子のだし巻きにする」と戸惑ったような表情で言った。 「え、だし巻き……いや、うん、分かった!」 …………アカン、に好きに選んでもらうための言葉選びができない。センスなさすぎというか、えっ、こういう時どういう感じで何を言えばイイ感じになるの???? 自分でもアカンの丸分かりの態度なわけだから、がそれに気づかないわけがない。……余計にアカン。 「……ねえ、最近どうしたの? なんか、変だよ」 「え? 何が?」 「何がって……なんか、わたしに遠慮してる」 ウッ、だよね、そういうふうになるよね! 「……えっ、何言ってんの〜。そんなん今更するわけないじゃん! どんだけ長い付き合いだと思ってんの? 変なのはアンタのほうでしょ〜? 何言い出すの?」 「長い付き合いだから分かるよ」 じっと私の目を見つめてそう言うと、困ったように笑った。 「……ごめん、わたしのほうこそ、話さなくちゃいけないことあるのに……何も、言ってないもんね」 ……アカン。何がアカンって私はもう一秒も我慢できないことである。 「ッあ〜〜! やっぱ無理ッ!!!!」 「えっ、なに?!」 ドンッとテーブルを一発殴ったと同時に、私の口は勝手に動き出した。 「なんでが謝んの?! 話したくないことなら話さなくていいんだよ!! いやぶっちゃけ親友じゃんなんでも話してよって思うけど!! 思うけど! でもが話したくないこと無理に話させて、そんで傷つけるようなことは私したくないッ!! だけどこんなこと言うとは私の気持ちに沿ってくれようとするのも分かってる!! じゃあ言うなよって言いながら私も思ってるけど、でもここでこれ言っとかないと……言っとかないと、の気持ちが、ホントに離れちゃいそうで、私、アンタの親友だってことが、唯一、私の、ほんとに、大事な、」 かーっと目頭が熱くなって、いやなんかもうあちこちが熱い。なんかもう意味分からん状態になってる。 は慌てて立ち上がって私のそばまで来ると、そのまま屈んで背中を撫でてくれた。 「えっ、えっ、なんで泣くのっ? わたし、別に遠慮したりとか、そんな、してないよ? いつも話聞いてくれて、相談に乗ってくれて、わたしのこと笑わせてくれて、応援してくれて……自慢の親友だって、わたしだって思ってる」 ウワッめっちゃドラマチックな展開じゃんモブなのに私ドラマの登場人物みたい!!!! とか言いたいけど、ダメだ、涙止まんない。 「……私はさ、が何を選んだって、別に嫌いになったりなんかしないんだよ、」 「……うん」 「でも、私が過保護にするから、が自分の思うこと選べなくしてたかなって、」 膝の上できつく握りしめていた手を、がそっと握った。 「そんなことない、そんなことないよ。わたしのこと考えてくれてるって、ずっと分かってる。いつだってわたしの味方だって思ってるよ」 情けない顔を見られるのは、ホントは死ぬほど嫌なんだけど。これは、の目を見て、言わなくちゃ。 「私、“いい子”のじゃなくたって――大好きだよ。アンタのことホントに大好きな人たちは、アンタが“いい子”じゃなくたって大好きなんだよ」 は一度口を開きかけて、でも、何も言わない。だけど分かるまで何回だって私は言うよめっちゃしつこいからね!!!! ともう一度と言わず百回くらいは繰り返そうかと思ったけれど、がほんの少しだけ手に力を込めたのが分かって――。 「……一緒に、いてくれる……?」 …………んもう〜〜〜〜! おバカさん〜〜〜〜!!!! 「〜いるよッ!! 離れろって言われても無理ッ!!!!」 「……そっかあ……」と笑うは、もう困っているふうではなかった。 「……私が言いたいことは、以上」 は黙って、また席についた。それから唇を何度か震わせて、じっと私の目を見つめてくる。 「……、わたし、間違えるのが、こわくて」 「うん」 「いつからそんなこと気にするようになったのか分かんないけど……何をするにも、間違ってたらやだなって、思うようになって」 「……うん」 うつむかないようにしているのが分かって、だから私も、目を逸らさない。目元を赤くして、声を震わせて、でも、私はもういいよ、なんてことは言わなかった。 「……ひろくんが浮気してるかもしれないって、ほんとは、ずっと前から気づいてた。でも、そんなこと言い出せなくて。ひろくん、いつも言ってたの。『といる時は、落ち着く』って。……ひろくんを煩わせるって思ったら、言えなかった。わたしといると落ち着くって言ってくれる人に、そんなこと……。言って、それで嫌われるって思ったら、言えなかったの。結局、カッときて全部ダメにしちゃったけど」 ついに、ぼろっと涙がこぼれた。それでもは、うつむかない。 「でも――三好さんが、いてくれたから。何もかも上手くいかない時、わたしを、見つけてくれたから……っ」 私の涙はもう引っ込んだと思ったのに、枯れはしていなかったようだ。ヤバイ、私この先もう一生泣かないかも。 「……やっぱ私、小田切さんぶん殴ってやればよかった……! 何がなんでもアンタに毒吐かせて、ぶん殴りに行けばよかった……っ!」 「……っううん、あのことは、必要なことだったの! わたしが、変わるべきだったの……! でも、変われなかった……っ。……だから、だから三好さんは、」 頭だけは、しっかり冴えている。 「……、一度しか聞かない。周りなんかどうだっていいよ。大事なのはあんたの気持ちだけ。ねえ、。三好さんのこと――」 「ここで会う時は、泣いてばっかりだなぁ、ちゃん。今日はどうしたの?」 …………。 「え、」 わずかに目を見開くの顔を、甘やかな瞳でじっと見つめながら、神永さんは機嫌良さそうに笑っている。 私はめっちゃくちゃに口元を引きつらせながらも、なんとか「……神永さんこそどうしたんですか?」と努めて明るい声で聞く。いやホントどうしたんですかとしか言いようがないから。 「金曜なら、きみたちはいつでもこの店だろ? だからだよ。――で、ちゃん。明日空いてる? 遊びにいこうよ」 「え、あ、」 言葉が出てこない様子のが落ち着くのを待っていられるほど、状況は甘くない。だって相手は神永さんだ。 「ちょっと待って? 今めっちゃ大事な話してるんでそういうのはまた今度お願いしますさようなら」 神永さんはさっさとの隣の椅子を引いて、当たり前みたいな顔して「ずっと考え込んでたって仕方ないだろ? 外に出たほうが頭もスッキリする」と言いながら、メニューをめくり始めた。 「……何考えてるんですか?神永さん」 ちらりと私に視線を向けると、その唇はゆっくりと綻んだ。 「何って、きみもバカなことを聞くなぁ。――決まってるだろ?」 |
画像:HELIUM