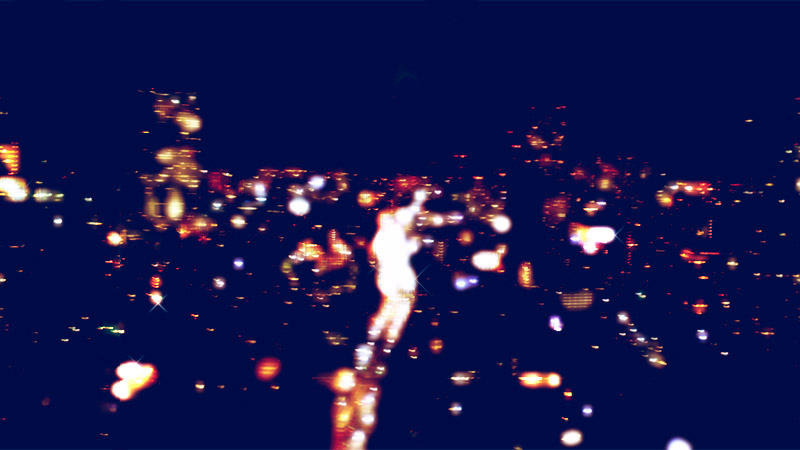
人に向ける感情になど、大した意味はないと思っていた。 結局のところ、この世には二つしかない。簡単なことだ。己にとって、その人間と付き合うことにメリットがあるかどうか。得るものがあればいい。しかし、ないというなら時間を浪費するだけなのだ。 人との関わり合いとは、僕にとって必要なものを得られるから持つものであって、そこに何か意味を見出したことはない。他人に興味などなかった。 ――彼女に出会うまでは、それでよかった。 僕はそういう人間で、それで構わないと思っていたし、必要なことだけで人生には充分だと。 それなのにあの日、彼女が僕のために泣いたりなんてするから、必要か必要でないかという明確な判断基準を、僕は疑うはめになったのだ。それまでなんの不足もなく生きていたのに、急に満たされることがない空洞を見つけてしまった。 それから、何にも満たされることなく、無感動に生きてきた。それは心を揺さぶるような事象にも、物にも――人にも、僕は出会わなかったからだ。 だから、仕事はよかった。やれば分かりやすく成果は数字で表されるし、それが評価されれば社会的立場も向上する。僕には、なんの不足もなかった。 美しいこの思い出が消えてしまうならば、それまで。けれど、僕はそのことを受け入れていた。ただ、そうなるはずだった予定は思いもよらぬところで狂わされて――僕だけの美しい思い出が、現実に蘇った。 あの幼い日の面影をどこかに残しながらも、彼女はもう大人の女性への階段を確実に上っていた。 僕は彼女に心を与えられて、その心を乱されて、こんなにも深い情を持っている。それを恐ろしくも思っていたけれど、与えられた仕事を事務的にこなすばかりだった僕には、今まで見ていたものが一変したことは面白く感じたし、そうして目に映るものはどれにも色が付くようになった。僕はきっと、そのことを喜んでいるに違いなかったのだ。 それを僕に与えた彼女を、どうしてもそばに置いておきたいと思った。僕一人では知ることのなかったものを、彼女ならまた与えてくれる。僕は人に対して初めて、損得勘定のない純粋な好意を抱いたのだ。 損得では振り分けられないところに、彼女はいた。出会ったあの日からずっと、再会するまでにもっと、その思いを募らせるばかりだった。そして再会を果たして彼女との距離が近くなっても、僕は満足することなどなかった。ずっと胸の内に抱いていた感情は、余計に肥大していくばかりで。今この瞬間も、僕は彼女のことが――。 「――だって、田崎さんが言ったんじゃないですか」 資料室の奥から、囁くような声が聞こえた。 こんな時くらい鈍くなってしまえばいいのに、僕は彼女の声を聞き間違えたりなどしない。 「そうだったかな? 言い出したのはさんのほうじゃなかった?」 僕はただ無感情に、取りにきた資料はどこだと棚に視線を滑らせていく。――あぁ、これだ。 手を伸ばしたところで、「……そうやって、上手にかわすばっかりですね」という彼女の言葉に、思わず手を止めた。 「田崎さんは、わたしにああ言ったけど……あなたのほうは、思ってることを人に伝えようとしなさすぎますよ」 「さぁ、どうだろう? けど、それでいいんじゃないかな。俺は――」 そうして仲睦まじく笑い合う二人は、恋人同士だと言われても違和感はないだろう。 どうしてこのタイミングでと思わないでもないが、仕方ない。そういう巡り合わせだったのだ、結局。 「――さん」 田崎の背中の向こうで、彼女は目を丸く見開いて僕を見つめた。 僕の名前をぽつりと呟いて、その後にそっと視線を落とす。 「田崎、探されていたぞ。そろそろ業務開始時間だ、行ってやったらどうだ」 田崎は「そうか」と言うと、さんに笑顔を向けた。相変わらず胡散臭い顔をする男だが、きっと僕より余程――。 「それじゃあさん、話の続きはまた今度」 「あっ、は、はい」 田崎はすれ違う間際、皮肉げに口元を歪めた。視線は、僕を嘲笑っているようだった。 田崎の背中を見送った後、僕はさんのところへとゆっくり近づいた。 「……さん」 「は、はい」 それっきり、僕は何を言えばいいのか分からなくなってしまった。用意していた言葉をそのまま、伝えればいいはずなのに。 「あ、あの、三好さ――」 「すみませんでした」 「……え、」 あぁ、実際にこの目で見ると、なかなかに堪える――そうか、僕は今、傷ついているのか。散々に彼女を傷つけてきたくせに、僕は、傷ついているのか。 まったく、笑える話だ。僕はこうすべきだと納得して、早々に彼女に伝えるべきだとすら思っていたのに。 きっと化粧でうまく隠したつもりだろうが、薄らと赤い痕が浮き出ている。 手を伸ばすと、彼女は肩を揺らしたが、僕の手を拒むことはしなかった。ああ、僕は、彼女のことを信じることができなかったから。その罰が、これなのだ。 「僕は、あなたを泣かせてばかりでしたね」 はっと息を呑んで、それから思い詰めたような表情で、彼女は首を振った。 僕は、あなたにはいつだって笑っていてほしくて、そんなあなたが隣にいてくれることをずっと願っていた。 しかし、そんなことは贅沢だったのだ。僕はあの時、彼女との出会いは思い出として生きていこうと決めて、それでも構わなかったというのに。僕はすっかり、そのことを忘れてしまっていた。 あの日に与えられた心は、やはりあなたがいなければその動きなど簡単に止めてしまうけれど、それでも構わない。 僕は知ってしまった。人を愛するということを。そしてそれは、いつでも求める結果を得られるのではないのを、僕は知っている。 僕は愛しているとこの口で言っておきながら、彼女の言葉を何一つ信じてはやれなかった。そのことだけは変えようもない事実で、僕では彼女にふさわしくないことの証明でもある。 「……み、三好さん、あの――」 「午後は忙しくなるでしょうから、早めにオフィスへ戻ってください。……僕はまだ探し物があります」 背を向けて目の前の棚に手を伸ばすと、「……分かりました」という言葉が返ってきたけれど、その後すぐに彼女は続けた。 「……あの、手伝います、何の資料ですか?」 ――どこまでも、優しい人だ、あなたは。僕にはこれ以上、与える必要なんてないのに。 「……いえ、把握していますから」 「……そうですか。……それじゃあ、失礼します」 目当ての資料がこの棚にあるはずもないのだから、僕はそっと手を下ろした。遠ざかっていくヒールの音が、最後だ。これでいい。元々、僕には過ぎたものだったのだ、心など。なのに、それがもたらす心地良さについ忘れてしまっていた。僕は、与えられたことをこなすことしかできない、無感動な人間だということを。 しかし、これだけは心残りだ。 結局僕は、彼女に与えることは――与えられたものに釣り合うものを、返すことはできなかった。ただ、それだけが。 「――いいんですか? 一応は真面目が売りの爽やか代表なのに、こんなとこ来ちゃって」 私の言葉にいつも通りに笑って、田崎さんは「きみが呼んだんじゃないか」と言って煙草に火をつけた。 っは〜……前に神永さんがこの人を“優男”って言ったけど……確かにそうだわ、この男。 「……どういうつもりだとか、そういうクソつまんないことは聞きませんけど。でも――なんでわざわざ傷つけるようなことしたんですか?! のことは泣かせたくなかったんじゃないの?!」 ……ここで大人しく私なんかに殴られるから、ドラマの登場人物とかそういう、生身の人間じゃないような感じするんだよこの男……と、じんじんする手のひらをぎゅっと握る。……クソ、マジでドラマみたいで、指先がこんなに冷たいのにビックリするわ。 田崎さんは薄らと笑った。 「俺がさんを泣かせたことって、あったかな?」 「なかったですね今までは!」 だから余計に腹立つんだよッ! と怒鳴りつける寸前で、田崎さんが表情を変えた。 「……そうだね」 「……あ゛っ?」 何この男。こんな状況で、なんでそんな顔できんの? ……いやいやいや、この人バカでしょ。 今まで完全無欠の月9人間……というよりもはや神かな?? なんて思ってたけど。なんで私はそこまで信用してたの? って若干思うよね、こんな顔見たら。だってどう見たって、フッツーの男と変わんないじゃん。 ……でも、こんな場面でも笑えちゃうんだから――その辺の男とは、どう考えてもレベル違うわ。 田崎さんは作り物みたいにできすぎた微笑みを浮かべて、「俺が泣かせたとは思いたくないけど――結果がすべてだ」と言って、煙草を灰皿へと投げ入れた。 「……底の見えない人だとは、ずっと思ってましたよ、田崎さんのことは。でも、を傷つけることはないって、それだけは信じてきました」 まぁ私がここで暴くことではないけど……なんつーかホント、誤魔化すことがうまいというか、相手を煙に巻くのが好きっていうか……もうそうせずにはいられない病気でも患ってんのかこの人は……。 はぁ、と溜め息を吐いた私を見て、田崎さんはくすりと笑った。 「俺もそのつもりだったよ。でも……俺は、身代わりなんて務めてあげられるほど――優しい男じゃないから」 「……でしょうね」 ――こんな酷い色男、初めて見たわ。 「泣いてるさんに、手なんて出せるわけもないしね。それで? 俺に聞きたいことって、何かな?」 まだやる気かこの人は……と思いながら、まごまごしてる時間はないのだ。 「もうやめましょうよこういうまどろっこしいの……」とまた溜め息を吐いて、私は腕組みした。 ここまできちゃったら、誰の味方もしない以上、私は私の役割を務め上げなくては。 「まぁいいや、私も優しい女じゃないんで。、なんて言ってました?」 「あはは、きみは本当にさんしか眼中にないね」 「そうです、他はどうだっていいです。だから田崎さんに誤魔化されることもしないです」 田崎さんはじっと私の目を見つめて、「……聞いて、どうするのかな?」と皮肉げに唇を歪めた。めちゃくそ腹立つけど、私は大人だし――何より、の味方だから。 一線越えてないにしろ、田崎さんとの間に“何か”はあったわけで。私はそれを一から十まで知ることはできなくても、せめてが笑っていられるようにはしてあげたいのだ。 クソ調子乗ってる考え方かもしれないけど、私はがそばにいてくれることが、いつだって嬉しい。そして、が私を思ってくれることで、何度も救われてきたから。 私だって、できることをしてあげたい。 「別にどうもしませんよ。ただ、が私に後ろめたく思ってそうなので、今のままほっとけないんですよね。だから、聞ける相手には聞けるだけ全部聞こうと思ってるだけです」 田崎さんは内ポケットからまた煙草を取り出すと、「……そう」と目を伏せた。 これどう考えても残りの昼休みじゃ足りない。いやそれはいいんだけど、私が戻らなかったらが心配する「それじゃあ、俺は聞かせてあげられることはないかな」……し……? 「……あ゛ァっ?!」 田崎さんは人の良さそうな笑顔で、「さんにだって、きみには打ち明けたくないこともあるだろう?」と言って煙草に火をつけた。…………めっちゃ反論したいけどさぁ〜〜! 「……っぐ、い、痛いとこ突いてきますね……」 田崎さんが私に背を向ける。 ……これは……私なんかがどう揺さぶっても、絶対口割らないなぁ……。あ〜〜、クソ腹立つ。 「――俺がもし本当に“王子様”だったなら……きっと、きみにここで話してあげるんだろうけど」 ……ついさっき考え改めたはずだけど、やっぱ違うなこれ。この人ってマジで生身の人間じゃないわ。月9、月9の登場人物。だってそうじゃなくちゃ、おかしい。 「ごめんね、俺は“王子様”じゃなかったみたいだから。話せることは何もない」 「……田崎さんが話してくれることで、が傷つかない選択をできるとしても?」 「ふふ、きみも痛いところを突くね」 フッツーの、その辺の男が言えるわけないでしょ。 「……でも、残念。俺はもう全部――忘れたよ」 こんなクソかっこいいセリフなんてさぁ。 「い、やじゃ、ないから、」 その言葉を聞いて、ふっと体の強張りが解けた気がした。まるで俺のほうが怖がっていたようで、思わず笑ってしまいそうになる。おかしなこともあるものだ。 それはそうと、相手にこんなに緊張されては、こちらも悪戯の一つくらいはしたくなる。 輪郭をなぞっていった唇が首筋にまで辿り着くと、さんの手が、俺のシャツを強く握った。 「――ここで俺を受け入れたとしても、きみが俺を愛してくれることはないんだろうね」 体を起こす俺を見つめて、さんは「……え、」と呟いたけれど――表情を見れば分かる。 「今、誰のことを考えてたの?」 さんは明らかに焦った表情を一瞬浮かべたが、すぐに困ったように眉を下げた。 「だれって……、」 泣かせないことが、すべてだと思っていたのかもしれない。誰にでも、時には必要なことだというのに。 一つだけ。一つだけ言い訳をしてみるのなら、俺はいつだって泣いているところばかりを見ていたからだろう。それだけは、遠ざけてやるべきだと思い込んでいた。本当は誰より、彼女にこそ必要なものだと、今なら分かるけれど。 ただ、そんな言い訳をする気は毛頭ない。俺は今気づいて良かったとは思わないし、どうせなら明日の朝であれば――なんてことを思うから。 「……もう、誤魔化せないところまできてるんじゃないのかな?」 さんは何も言わずに、ゆっくりと体を起こした。 「俺は自分のことに関心がない質だけど――きみは少し、自分のことを分析しすぎだ」 かわいい笑顔の裏では、泣いていることを知っていた。けれど、自分の手でその涙を拭ってあげることはしなかった。俺はどこかで、彼女のことを特別な人間だと思っていたのかもしれない。ただの、かわいい女の子だったのに。どこでそんな馬鹿な勘違いをしたのかなんて、今になって考えることでもないが。 「……自分が他人に心を寄せすぎるきらいがあるのを分かっているから、常に誰かに向ける感情に名前を付けて整理したがる。そういう性質だから、きみはよく気がつく、人を立てられる子なんだろうけど――だから、危ういんだ」 ぼんやりと自分の手元に視線を落としていたさんが、じっと俺の目を見つめた。 あぁ、やっぱりただの、かわいい女の子だ。 「……人の心に寄り添って生きようなんて、驕った考え方だと、思いますか?」 「いいや、思わないよ。それが、きみという人間だから。――でも、きみはそれがまるで“正しさ”だと思い込んでるだろう」 俺の言葉に、さんは息を呑んだ。 「ま、間違って、ますか、」と言うその声は、ひどく震えている。 俺は努めて、優しく笑った。いつものように、とはいかなくとも。 「どうしてそう思うの?」 「だって、」 「真面目すぎるんだよ、さん」 こうするべき、こうしなければならない。そういう固定観念に囚われて、現状を見てのベストを選ぶということが不得意なのだ。これはとことん真面目な人間にありがちなパターンで、珍しいわけではない。ただ、真面目だからこそ頑固で、この癖はちょっとやそっとのことではどうにもならない。 彼女も、そうやって今まで生きてきたんだろう。きっと、これを選べば楽だという選択肢を見つけることは何度もあっただろうに、彼女はいつも“正しい”と思うことだけを選んできた。 「さん、正しさは一つじゃないよ。誰かにとっての正義は、誰かにとっての悪になりうる。それは、まったく同じ人間なんていないんだから、当然のことだ。でもきみは、正しさは常にたった一つで、自分の知っている正しさが他人と違ったと知ると――自分が間違ってると思うだろう」 反論するどころか、言い訳だってしようと思えばできる。けれど、何も言わない。人に悟られたくないんだろう。自分の、心根を。 誰とは言わないが――よく似ている。 「……三好のことが、好き? きみを随分と泣かせてきた男だと思うけど」 さんは自分の手元にまた視線を落として、ゆっくりと口を開いた。 「……わたしが……仕事も、プライベートもいっぱいいっぱいで、どうしようもなくなっていた時……三好さんの言葉が、わたしを助けてくれました。だから、今まで頑張ってこれたんです。……でも、その次に会った三好さんは、もうわたしのことを、嫌ってて、」 「――三好の、その気持ちに沿ってきたの?」 俺のこの言葉を聞いて、さんは顔を上げた。頬を、涙が伝う。何度も。 涙を綺麗だなんて思うのは、きっとこれが最初で、そして最後だ。それから――震える彼女の肩を抱くのも、これが。 「……っわたしが、どれだけ三好さんを尊敬してても、どれだけ認めてほしいと思っても、三好さんはわたしのこと、認めてはくれないんです……! ……それが悔しくて、それならわたしだって、三好さんが思う憎らしい部下で、わたしも、三好さんを嫌いな部下でいようって……でもほんとは――それが、つらくて、かなしかった……っ」 左肩でくぐもるさんの声には熱があるのに、触れたところからどんどん冷えていく。 俺はそっと目を閉じて、ただその声を聞いていた。 「――いちばんに、三好さんに認められたかった、ただ、それだけだったんです……っ! なのに、あの時……っ、三好さんが、あんなこと言うから、」 三好が彼女にあれこれ言うのはずっと以前からだ。時期は今のところはいい。 いつのことなのかはともかく、これまでずっと人を重んじて、他人の意に沿って生きてきた彼女をここまで揺さぶったなら……三好は、一体何を――? 「……“あんなこと”?」 さんは、俺の体から距離を取った。その瞬く間に涙は溢れ返って、ついには、顔を覆って泣き崩れた。 「――『どんな形でもいい、ただ、僕のそばにはいてください』って……っ! わたしあの時、どうしてか、しまったって、思ったんです……! 自分のどこかに、やましい気持ちが、あるって……その時に、思って……。認められたかった、それだけだった、はずなのに、」 俺はふいに口元を緩めて、静かな心の内で思った。 本当に、似ている。不器用なところが、とても。 「……認められたいと思って、相手に好かれたいと思うことのどこがやましいのかな」 「……え?」 「三好がきみに、どんな形でもいいからそばにはいてくれと言ったのは……三好もきみに、認められたいと思っているからだよ。たとえ――あいつが持っているやましさを、抜きにしても」 さんにしてはあまりにも不器用で、ちっともうまくない笑顔だ。けれど、きっとこれが、一番正直な感情なんだろう。本来、感情にラベルを貼るなんてことはできやしないのだ。こういうタイプの人間には。 「……そんな、バカな話、ありますか……? わたしはずっと、三好さんのこと、ずっと尊敬してて……でも、応えてくれなかったくせに」 「……きみは素直な子だと思ってたけど――三好と比べても遜色ないほどには、ひねくれた子だ」 さんは曖昧な笑顔を浮かべてバッグを引き寄せると、お守り袋のような小さい巾着を取り出した。そして、その中身を手のひらに、いかにも大事そうに、そっと落とした。 「……受け取れないって断るか……、さっさと、捨てればよかったのに」 あの子の言葉を借りるようだが――さんのことになると、本当に分かりやすい。澄ました顔して、ただの男だな、あれも。 そして、「……わたしも、バカですよね。大事に持ってるなんて――ほんとに、救いよう、ないなぁ……」なんて言って目を細める彼女も、ただの女の子だ。 「三好が知ったら喜ぶよ。あいつ、さんのことが大好きだから」 さんは唇をきゅっと吊り上げて、笑った。いつもの顔だ。 「まさか。――三好さんは、“二度はチャンスを与えない”んです。あの人のこと、理解したいって思ってたはずなのに……何度も振り払ってきたんだから、もうずっと昔に、終わったことですよ」 「きみはそうやって、また三好の気持ちに――きみが思い込んでいるだけの、ありもしない気持ちに寄り添うの?」 「……わたしが誰かにできることって、それしかないんです」 いつもの顔でそう言われては、俺に言えることはきっと、もうない。 「……きみの心を動かせるのは――いや、もう止そうか。……送るよ」 立ち上がって、さんに手を差し出してしまってから、俺は笑った。さんも、笑う。 「ここで甘えちゃったら、わたし、もう戻れません」 「時には、逃げを選ぶことも必要だと思うけれど――きみは、それだけはしないな。真面目すぎるよ、本当に」 ソファに腰を下ろした俺を、さんは緊張しきった声で呼んだ。応えることはしない。続きは分かっているから、あえて聞く必要がない。 「――言っただろう? “理想の王子様”は、もう終わりだ」 煙草の煙が風に流れていくのを見つめながら、最後に、彼女はどういう顔で出て行ったかな、とぼんやり思った。 「――それなら、無理にでも奪ってしまえばよかったのに……結局、俺の泣き所はあれだったな」 まぁ、思い出せなくていい。思い出したとして、どうということもない。 あんな顔をさせてしまったら、ここでもう、幕引きだ。 「――さん」 いつかはやってくることだったのかもしれない。もしかしたら、もっと早くだったかもしれないのに、今日までやってきてしまった。 人に寄り添いたいと思っていたはずが、わたしは気づけば人の目に映る自分しか見ていなかった。大人になるにつれて、わたしの視界はどんどん狭くなっていったように思う。 でも、ひろくんとのことで、自分の綻びに気づいたはずだった。なのにわたしは、物分かりのいい、いい子でいることに必死だったのだ。笑えるほど、バカな話。あの時に蹴りをつけるべきだったのに、わたしは人に疎まれることが怖くて、好きな人に嫌われることが怖くて、先延ばしにしてきた。気づいていないふりをして。 人の目に映っている自分。そのわたしは正しい人間なの? わたしが間違ったからひろくんは離れてしまったし、うまくいかないことばっかりなのに? だから、三好さんが声をかけてくれたあの時が、本当は最初で最後のチャンスだった。三好さんがわたしに本当に与えてくれたのは、変わるきっかけだったのだ。あそこでわたしは、変わるべきだった。 わたしを見てくれる人はいる。あの時、確かにそう思えた。だから、頑張れた。わたしはその気持ちを繋げて、他人の目に映るわたしじゃなくて、わたしのなりたい自分を見ようとするべきだった。なのに、わたしはそのチャンスを、掴むことができなかったのだ。だから、もう終わり。 「……はい」 三好さんは淡い笑顔で、「今晩、お時間はありますか? 食事に行きましょう」といつになく優しい声で言った。いつもの三好さんだ。わたしがこの顔を向けられるとは思ってなかったけれど。 あぁ、こういう顔をしてくれることを望んでいたのに。今になって、おかしいな。三好さんを素敵だって言う人たちみたいに、わたしは思えない。――こんな顔、見たくなかった。 「ン゛ん?!?!」 隣で咳き込む声に、ついわたしは笑ってしまって――三好さんはそんなわたしの顔を、まじまじと見つめた。 三好さんもきっとこんな顔、見たことないですよね。そうでしょ? だってわたし、あなたの“憎らしい部下”で、“かわいくない後輩”だったもん。 「……はい、分かりました」 「んンン゛ん〜ッ?!?!」 三好さんはただただ優しい顔だ。だからわたしも、笑うだけ。 「……僕とあなた、二人で構いませんか」 「はい、問題ありません」 そういえば、秘書課の美人とはどうなったんだろう。いつも仕事を第一にしてたのに、お昼休みになると三好さん、誰よりも早く休憩に出るようになったけれど。 ――まぁ、いっか。わたしが誰かにしてあげられることって、いつも一つだけだもん。その人の望んでいる、わたしでいること。ひろくんの手を離した時だって、そうだったでしょ? どんなにわたしが望んでも、彼の望んでいたわたしじゃなかったんだから仕方ないって、諦められた。 だから――あの観覧車の思い出だけあれば、それで充分。きれいな思い出があれば、それだけで生きていけるって、わたしは知ってる。 悲しいのも、辛いだなんて思うのも、今この瞬間だけ。 |
画像:HELIUM