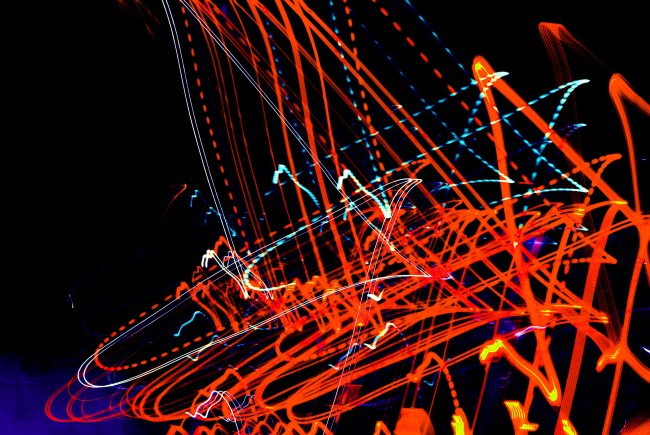
――遊んであげようか。 腹の立つことに、女はそう言った。俺という男、というより、この世のすべての男を貶して嗤っている女だ。初めこそ、俺はちゃんちゃらおかしいと女と同じに嗤っていた。だというのに、その辺の馬鹿な野郎のように躍起になって、ふざけた女の本命の男、つまりは俺こそがこの女を散々に誑し込んでやろうと思ったのだ。 男――少なくともこの俺――は、おまえのような安い女の誘いに乗ってやるほど、落ちぶれちゃいない。そう知らしめてやろうと。ところが、俺のほうがハマっているのだから笑える、いや、嗤われる話だ。これじゃあ本当に、その辺の馬鹿な野郎と変わらない。むしろ、俺のほうが余程馬鹿かもしれないが。 女はいつも決まった席にしか座らない。カウンターの一番端だ。誰をも寄せつけないと言いたげに、一人で紫煙をくゆらせている。 そうは言っても、こんな薄暗いバーで一人で飲んでいる女を放っておく男もそういない。俺が初めてこの女を見かけたときも、頭の悪そうな男が下心丸出しに、隣へ腰を落ちつけようとしていた。まあ、お高くとまっている女はちっとも相手にせず、まるで見えていないとでもいうように、清々しいほど"ないもの"扱いを貫いていたが。横目でその様子を見ていた俺は、下品に舌を打って去っていく男の背中に思わず笑ってしまった。馬鹿な男だと。 女なんてものは似たり寄ったりで、お高くとまっている女ほど案外あっさりと落ちるもんだ。それができない男など、大したもんじゃない。 女が男を袖にする場面を、俺はそれから幾度となく目にした。そのうち、この女はどういう男ならば納得するのだろうかと思うと、ちょいと声をかけてみるのもいいかもしれない。そう思った。 今になって思えば、そんなことをしなけりゃよかったと思う。くだらない男を“ないもの”扱いする女のくだらなさこそ笑えると、高みの見物をしていればよかったのだ。そうすれば、俺が馬鹿な男に成り下がることもなかった。このお高くとまった安い女の機嫌を窺って、ああだこうだと面倒なことを考えずに済んだ。自分にどれほどの価値があると思っているんだか、随分と小生意気な女だと鼻で笑って、そんな女の気を引こうと夢中になる馬鹿な男たちを憐れんでいればよかった。――だというのに。俺はまんまとハマってしまったのだ。この、薄っぺらい女に。馬鹿だ憐れだと見下してさえいた、くだらない男たちと同じように。 どういう気まぐれを起こしたんだか、ある日突然、女は俺を隣に座らせた。だからといって、何があったわけでも何が始まったでもない。ただ隣に座らせて言った。遊んであげようか、と。 「いやぁね、男って生き物は」 女はグラスを傾けて、試すかのような視線を寄越してきた。妖しい光を放つこの瞳に、一体どれほどの男が惑わされてきただろうか。それでも、この女が“一人”を選ぶことはなかったが。どんな男にも靡かないという顔をしておきながら、毎夜たった一人で思わせぶりに現れるのだから質が悪い。この女の目的など知るわけがないし、どういうつもりなんだかももちらん知らない。ただ、そうすることで自分の価値を確かめているように見えるもんだから、薄っぺらい女だと俺は思うのだ。 「俺に言うのか」 愛想笑いの一つでもしてみせれば可愛げもあるが、この女が見せるのは人を小馬鹿にした表情だけである。本当は男がどういう生き物なんだか知りもしないくせして、さも分かっているような口を利く。 煙草に火をつけた俺の顔を覗き込んで、女は言った。 「あなたしかいないもの、わたしには」 ――冗談にすらならない台詞だ。 「よく言う」 溜め息交じりに煙を吐き出すと、「まさか」とくすくす笑った。こちらの台詞だ。本当に、真実俺一人っきりしかいないと言うなら、そんな目をするわけがないし、真っ赤なルージュの唇が歪な弧を描くこともないだろう。――誰にも靡かない女をするので満足ならばそれでいいが、決してそうではないくせしてよくやるもんだ。 “ないもの”扱いされた男とこの女、果たしてどちらが憐れだろうか。 人間、慣れないことをするもんじゃない。無理に演じることほど虚しく、悲しいものはないのだから。この女には、掴める手はいくらでもあったはずだ。それをいらないと切り捨てたのは自分自身だというのに、遊び慣れたふうを装って“ないもの”扱いをしてきたのだ。今更縋れるものもないだろう。しおらしく涙の一つでも零してやれば、同情する男はいくらでもいただろうに。結局のところ、男のほうも身勝手な驕りを押しつけたいだけなのだから。甘い言葉で誘惑して。 ――まぁ、それに乗っかることができるような女なら、いつまでも一人を貫いてやしないだろうが。 「俺はおまえがどんな女か、どの男よりよく知ってる」 女は笑った。俺もくだらぬ男の一人だと、小馬鹿にして。 そうだとも。俺もくだらぬ男だ。その辺にごろごろと転がっている、つまらぬ男。そうでなけりゃ、誰がこんな女を相手をするか。 なれもしないくせに、生意気にも火遊びに夢中になる女のふりなどしているから、本当に欲しいと思うものを手にすることができないのだ。そのことを教えてやる親切な男と出会えず、ここまできてしまったようだが。ただし、過去は過去で、今この女には俺がいる。馬鹿らしいにも程があるが、捨て置いて構わぬ女に夢中になって、俺が与えてやろうかと――与えてやりたいと思ってしまったこの俺が。馬鹿馬鹿しいことこの上ないが、それでいいとここまでやってきてしまった。引き返せないのはこの女だけではない。 嘘偽りなく、火遊びばかりを楽しむ女であればよかったものの、そんな器用なことができるのならばこうはなっていまい。 「やだ、そんなこと言ってどうする気? わたしの一番の男でもないくせに、笑える」と笑う女の目は、照明の光すら映さない。馬鹿な女だ。他の男はどうだか知らないが、俺には分かる。必要ないと突っぱねているように見せて、馬鹿正直に愛を乞う色が宿っていると。 ――認めてしまえば、どれほど楽だか。 「じゃあ何番目にならしてくれるんだ」 鼻で笑ってみせると、女は意味ありげに俺の目をじっと見つめた。 「何番目にならなれると思ってるの?」 似合いもしない派手なルージュが、女の顔には浮いている。その唇には、もっと淡く、薄っすらと色づく程度のほうが似合う。どこまでも馬鹿な女だ。自分のことを知らなさすぎる。何番目? おまえは選べる女ではない。 灰皿に煙草の火種を押しつけながら、「一番しかないなぁ、俺はそれ以外興味がない」と言うと、俺も女の瞳を見つめ返す。 ――そもそもの話。 「それに、他は俺にふさわしくもない」 この言葉を聞くと、女はそっと視線を逸らした。それから、震えた声で言う。 「……もしかして、口説いてる?」 そんな顔をするくらいなら、くだらない遊びなぞやめればいい。乗る気のない誘いなぞ待たなくていい。かえって傷つくばかりだろうに、学習しない女だ。――そう思うくせして、俺もこの女のせいでくだらない男に成り下がってしまった。いかにも難攻不落と言わんばかりのその顔を、ちょっと崩してやったら面白い。たったそれだけだったはずの暇つぶしが、とうとうここまできてしまった。 こうなってしまったからには、もう後には引けない。それはこの女にも言えることだ。 「俺がおまえを口説かない夜が、今まで一度だってあったか?」 女は一瞬、声を失ったような顔をしてみせた。たったの一瞬だったが。それから、慣れたふうを装っているつもりだろうに、どう見たって違和感のある歪な笑顔を浮かべる。不自然に上擦った声で、「アハハ、馬鹿みたい」と言った。 「あんたってほんと、どうしょもない男ね。おもしろい」 ――どうしようもない? それはどっちだか。 「……おまえには言われたくないよ、どうしょもない女のくせに」 どうしょもない女一人に、どうしょもない男が一人。それならちょうどいいだろう。どうせこの女はまともな男なんて選べない。そして俺も、もうまともな女では満足いかないだろう。 もっと早くに、この女のくだらないプライドや、さみしいばかりの横顔を切り捨ててしまっていたら。俺だって、こんなものはただの“火遊び”だと割り切ることができたはずだ。――まぁ、今となってはもう遅いのだから仕方ない。これはどうしようもない女だが、そのどうしようもない女をそのまま、この先も“どうしようもない”女にはしておけない。この女がこれまでに嘲笑って捨ててきただろう男たちと同様に、俺がすくいあげてやろうだなんて馬鹿なことを思ってしまったからには。 ウィスキーグラスの中の氷が溶けだして、からりと音を立てた。 「――こんな生き方、やめようとは思わないのか。つまらないだろ。あっちへふらふらこっちへふらふら、行った先におまえの求めるものはあるのか?」 そういえば、この女があからさまに嫌な顔をしているのは、初めて見た。 「……知ったふうな口利くの、やめてくれる? わたしが求めてるものなんて、あんたに関係ないじゃない」 ――そうであればそのほうが余程よかったと思うが、愛だなんて目に見えない不確かなものをコントロールしようなどと、ナンセンスだ。 そもそも、思うようにできるものなら、おまえも毎夜こんなとこへとやってくる必要はないだろうに。心の奥底では分かっちゃいるんだろうが、こんなことでしか受け入れられないんだろう。ぽっかり空いてしまった穴を見て見ぬふりはできず、だからとそれを埋める方法も分からないがために。 そうでなければ、こんなことは言わないはずだ。 「それに――欲しいってあんたに強請ったところで、くれるわけでもないでしょ」 馬鹿な女だよ、おまえは。 「いつ、俺はやらないって言った。おまえが望むなら、なんだって差し出してやる」 俺は至極真面目に、そして絶対的な自信のもと、そう言った。――が、女は笑った。馬鹿馬鹿しいとでも言わんばかりに。俺から言わせりゃ、まず男を試して自分が傷つかない道を行こうとするほうが、よっぽど馬鹿馬鹿しいが。 俺は人を信じない質だが、だからといってすべてを信じないわけでもない。少なくとも、これは俺のもんだと決めた女なら、たとえ俺を騙そうとしているのが見てとれたとしても、俺は喜んで騙されてやる。女一人に騙されたところで、痛くも痒くもないじゃないか。 「あんた、そんな甲斐性あるように見えない。くだらないこと言うのやめてよね。――あぁ、あんたとなら寝てもいいよ? どうする?」 ただ、人を馬鹿にするのも大概にしろとは言いたい。こちらはおまえにかけているのに。俺がどれだけ心を砕いたところで、この女はこれだ。よくここまで俺を貶めることができるなと、逆に感心すら覚える。 遊ばれたところで――仮にこの女が俺を騙そうとしていたとして――どうということはないが、傷つきたくないくせして傷つこうとするのは気に食わない。それに、惚れた女に負けてやる甲斐性はあっても、貶められて喜ぶほど落ちぶれちゃいない。いくら俺が、その辺のくだらない男に成り下がったとしても、その辺のくだらない男のようにまるっきり負けているわけではないのだ。 恋だの愛だのに対して、フェアでいこうだなんて思っちゃいない。まず始まりはどちらかが負けてやらなくてはならないのだから。俺はもう、その覚悟はできている。だから、馬鹿みたいにこの女を待って、馬鹿みたいに構っているのだ。 ――だというのに。俺がこいつをどう口説こうとしても、肝心の本人がそれを認めようとはしない。 「そうやって自分の価値を自分で落とすの、いい加減やめろ。聞いていて気分が悪い」 舌打ちする前に、煙草に火をつけた。女はさも勝ったかのような顔つきで「へえ? じゃあ帰ればいいじゃない。気分の悪くなる女に付き合う理由、あんたにあるの? わたしも気分が悪くなる男と付き合うシュミはないから、お互い様でいいわ」と言って、グラスに口をつける。 「……少しは甘えてみせりゃ、可愛げもあるってのにな」 ――今夜はどうも機嫌が悪いな。 女が苦く「やぁよ、そんなみっともない真似、死んだってするもんですか」と吐き捨て、そのまま席を立とうとしたところを捕まえる。細い腕がびくりと震えたが、構わず続ける。 「みっともないことがあるか。誰かに愛してほしいと思うのも、誰かを愛したいと思うのも、何もおかしなことじゃない。どうしてそこまでむきになる必要があるんだ。頑なに突っぱねようとするほうが、よっぽど惨めに見える」 それは、あまりにもか細い悲鳴だった。 「……じゃあさっさと見捨ててよ。――人に期待するってのもね、結構疲れるものなのよ」 たとえば、今からこんな茶番は終わりにしようとしたとして。けれど、終わらせようにも土台無理な話だ。だってそもそも、俺たちは何も始まってやしないのだから。なら、どうするか? 簡単な話だ。“まだ”始まっていないのなら、“今”から始めればいい。今夜この場で、俺がおまえに名前をつけてやる。 「お生憎さま。俺はこう見えて甲斐性のある男だもんでね、哀れな女を見つけたら放っておけやしないんだ。――今夜で終わりにしてやるよ」 惨めな女の話は終いだ。ここからは、俺の恋人の話にしてやろう。 |
画像:0501