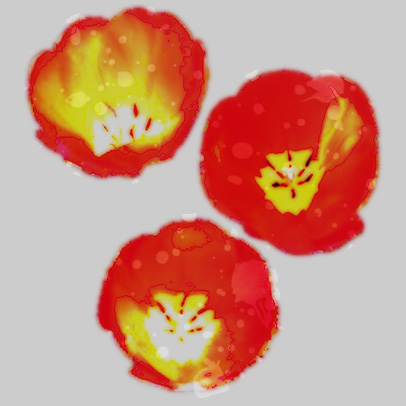
「きみはいつも難しい顔をしているな。何がそうさせるんだ? 俺に聞かせてくれ」 俺の言葉を聞いて、主は嫌なものに遭ったというように表情を歪めた。 日々、驚きを求めてやまない俺と、目の前のこの主殿とはとことん気性が違うので、こういう顔をされたところでどうとも思わない。今に始まったことではないのだ。つい先程も、ちょっとばかし長谷部に悪戯をしたのを見つかって、それはそれはきつくお叱りを受けたばかりだ。なのに懲りもせずにやってきたわけだから、苦い顔をされても仕方がない。 まぁ、こういう顔を見るのが嫌いではないので懲りないわけだが、お堅い主殿はちっとも思いつきやしないのだろう。そういったところが、俺の興味を引いてやまないのだと。 「……いつでもあなたのようにいられるものは少ないと思いますよ」 言いながら俺の脇をさっさと通り抜ける。その気になればもちろん行く手を阻んでしまうことなど造作もないが、ここは譲ってやって後を追いかけるほうがいい。そのほうがずっと嫌な顔をするのだ。いつもちっとも表情を変えないくせして。俺にはそれがおもしろい。皆には、あの主相手によくそんなことができると言われるが、まだまだ尻の青い小娘のすることだ。何から何まで可愛いもんじゃないかと思う。 後を付いていく俺を嫌そうにちらりと見るので、俺はやっぱりおもしろいと思って「きみはいつだってそうじゃないか。何をおもしろいと思うんだ? 何に心を動かされる?」と言う。間髪入れず、主は答えた。 「興味がありません」 俺はまったく驚いちゃいないくせに大仰に「こいつぁ驚いたな!」と目を丸くしてみせた。 「興味がない? きみ、本当に人間か? 俺の知っている人間って生き物は、いつだって好奇心に満ちていて何事をも探求するものと思っていたが」 主は煩わしそうに歩を速めて、同じく早口に「そういう人もいるでしょうね。ただ、わたしはそうではないというだけです」と言ってさっさと自室のほうへと進んでいく。そこまで行けば俺が諦めると承知しているからだ。自室へ近づくと、俺が自分に構うことを鬱陶しく思っている主のため、優秀な近侍である加州清光がこっぴどく叱って――いや、激怒して――追い出すので、さすがに俺も引き際は心得ている。 もうあそこの角を曲がってしまったら、きっと加州が待ち構えているはずだ。 俺は「なるほど。同じ刀剣といえど、俺たちも個性があるわけだ。人間なら尚のことだな。それで? きみは何に興味を持つ?」と今日では最後になるだろうと思って言うと、主はやっぱり「今言ったはずですが。興味がありません」と答える。決まりきった台詞を読み上げているようで心底つまらない答えだ。これで主が、たとえば、あなたに興味があるなんて可愛いことを言ってみせてくれたら、俺は嬉しい驚きでどうにでもなってしまえるだろうに。 「ああ、聞いたさ。心を惹かれるという経験がないんだろう? なら、きみは何に関心があるかと聞いてるんだ」 「同じことです。興味のあるものがないから、おもしろいという感情にも興味がないのです」 ああ、もう角を曲がってしまう。 「なら、俺はどうだ? これでも墓を暴いてまで人間が欲しがった刀剣だ」 「……この戦いにおいては、非常に心強い存在であると思っていますよ」 「そういうことじゃない。俺が欲しいかと聞いてるんだ」 主の答えはいつも変わらない。 「興味がありません」 何を聞いてもこれ一つっきりだ。 「――とかなんとか言っていたころが懐かしいな。きみは俺に興味はないと言っておきながら、こうして俺に連れられて現世を離れることを良しとした。今なら興味があるかい? 俺に」 ぬるくなってきた茶を啜りながら、隣できちっと姿勢のいい正座を崩さない主殿をちらりと見る。まぁ、主と言っても、それももう昔の話だが。 口元を緩める俺を見て主――いいや、は眉間に皺を寄せた。俺の恋女房となってもう随分と経つのに、主殿の面影はまだまだ抜けないようだ。 「……そうでなければ、私は今ここにいませんよ。……あなたは、わたしにもう飽いてしまいましたか?」 言いながら自信なさげに視線を落とすので、俺は内心苦く笑う。 「おっと、余計なことを言ったな。……どうしてそう思う?」 俺の言葉には躊躇うように口を開いて、それからまた閉じてしまった。 けれど、何か決めたというように、ゆっくりと言った。 「……あなたが興味を持ったのは、何にも興味を持たずに生きていたわたしでしょう。わたしは今、あなたにとても興味を持って、きちんとした関心があります。あなたが求めていた驚きとやらは、もうわたしには備わっていないでしょう」 俺は一つ頷いて、不安そうに上目遣いをするに笑った。 まったく、いつまで経っても可愛げのある女で男冥利に尽きるってものだ。この女は俺のものだと、あちこちに触れ回ってやりたい。 まぁ、そんな機会はもうないだろうし、俺はたとえ誰かにそういう機会を与えられたとしたって教えてやりはしないだろうが。 「なるほど。まぁ確かに、俺が興味を持ったきみはもういなくなってしまったな。――だが、俺に関心を寄せてくれたきみのすべてを、俺はまだ知らない。とても興味がある。試しに一つ言ってみてくれ。俺のどこに興味がある?」 「……意地の悪いことを言いますね」 自分では今どんな顔をしているんだか分からないが、がそう言うなら間違いはないだろう。散々に見てきた、うんざりだという嫌な顔をしている。思わず笑ってしまった。 「ははっ、そうかい? 俺は聞きたい。なに、ここには俺ときみとふたりっきりだ。誰にも聞かれやしない。それに誰かいたとして、俺が話して聞かせてやると思うか?」 俺の言葉には考える素振りなんて見せず、すぐさま「そうですね、あなたのことだから」と答える。 「それは心外だ」と俺は肩を竦めた。 「きみのことなら誰かに話してやる気はないぞ。だからこうして隠した。俺以外の誰かに、きみが何かを教えてやるまえに。きみの好きなものや嫌いなもの、知ってるのは俺だけだ。だが、そうは言っても肝心なことは教えてもらっちゃいないんだ。きみほど立派だった審神者が、どうして隠されてくれたんだ? きみがすべてを捨ててもいいと思うだけの魅力が俺にあるなら、俺はそれを知りたい」 はまた、自信なさそうな顔をした。 「……あなたは、たくさんの人間から求められてきたでしょう。それと同じことです」 ずいっとに寄って、顔を近づける。 驚いて体を引きそうだったところを、腕を引いて止める。 俺の視線からも逃げようとするが、もちろん逃がしてなぞやらない。 「そうか。しかし、俺がかつて求められたときは、今のこの姿じゃあなかった。きみは“鶴丸国永”は戦いにおいては非常に役に立つが、興味はないと言ったぞ」 はすぐに俺の目をまっすぐに見た。それからはっきりとした口調で「心強い存在だと言ったことはありますが、役に立つだなんて言いようはしたことがありません」と言って表情を歪めた。 それがなんともくすぐったくて、思わず笑った。俺は、どんな顔で笑っているだろう。 「そうだな、きみは俺を“物”として見ていない」 は眉間に刻んだ皺をますますくっきりとさせながら、そっぽ向いて「……もうこの話はやめましょう」と小さな声で言った。 俺はごろりと寝転がって、そのままの顔を覗き込もうと視線を動かす。 「どうしてだ? たまには昔話だっていいもんじゃないか」 すると難しい顔が目に映って、俺は肩を揺らして笑った。いやはや、本当にいつまでも可愛いことだ。 「……なんだ、照れてるのか」 「違います。お茶を淹れなおしてきますから、大人しくしていてください」 つんとした声だが、もちろんそんなものは痛くもかゆくもない。幼子がぐずっているようなものだ。 思わず頬を緩めながら体を起こす。 「きみを一人にするもんか。俺もお供しよう」 するとは溜息を吐いて、呆れたように「……あなた、変わりませんね。一度何かに興味を持つと、自分なりの答えを見つけるまでしつこくて仕方ないんだから」なんて言ってすっと立ち上がった。 「昔話は終いなんじゃなかったのか?」 さっさと背を向けたその表情は分からなかったが、「意地の悪いひと」という声はいじらしく震えていた。 「ねえ主っ! 俺、今日いっちばーん多く誉取ったんだけどっ!」 毎日のように繰り返している問答のため主を探していたところで、加州の声が聞こえたもんだからその場で足を止めた。 弾んでいる声に応えた声は抑揚なく平淡で、その内容というのも「知っています。立派ですね。ありがとうございます」なんてとんでもなく味気のないものであったから驚いた。 「……そうじゃなくて! もっと他にあるでしょ!」 「……お疲れさまでした。何が欲しいんですか? 好きなものを――」 「違うってば! っあるじのばかぁ!」 どたばたと大きな足音を立てながら遠ざかっていく気配を見送って、俺は後ろから「あーあ、かわいそうになぁ、加州のやつ」となんともない調子で声をかけた。 主はできればそうはしたくない、というように、いやにゆっくりとこちらを振り返ると、「……行儀が悪いですよ、鶴丸」と不機嫌そうに言った。 俺はその様子に大仰に肩を竦めて、それからにやりと笑ってみせた。 「おっと、悪趣味なやつだと思わないでくれよ、たまたまだ。きみを探していた。偶然というやつだな。しかし、きみ、他にもっとあっただろう。加州はきみの初期刀だろう? 扱い方を心得ていないなぁ」 俺の言葉を聞いて、主はぴくりと眉を動かすと、強張った声でぽつりとこぼした。 「……そうで、しょうか……」 なんてこったと思って、俺は目を丸くした。 「……驚いたな。そんな顔もするのか、きみ」 「え、」 「傷ついたって顔をしているぞ」 「、そんな、」という一言のあとには何も続かなかったので、まったくそんな自覚がないのかと思うと、俺はますますなんてこったと驚いた。 それから、この事態を主は果たしてどうするかと、ゆらゆら揺れている視線を追いながら言った。 「加州はきみに褒めてもらいたかったのさ。さすがは初期刀、よくやったってな」 主は難しい顔で俯いて、「……褒めた、つもりですが……」と心底困ったように言うのでまた、なんてこったと俺は頭を抱えることになった。 これは溜息を吐かずにはいられない。 「……きみはきっと審神者としては文句なしなんだろうが、俺たちの主としては些か欠けているな」 すると主は、はっと顔を上げると、切羽詰まったように「どういう、意味でしょうか」と俺の目を見て、今度は視線を外して、というのを何度も繰り返しながら落ち着かない。 俺はその場にどかりと座って、膝に肘をつきながら戸惑った顔を見上げた。 「俺たちは人間が――つまり、現状ではきみがいなければ価値のない存在だ。作り出したのも人間、扱うのも人間だからな。そんな俺たちが一番に求めているものはなんだと思う?」 眉間に皺を寄せながら、「……分かりません」と答えるので、俺はこいつぁどうにもならんと呆れ交じりに「興味がないからか?」と一面真白な庭へと視線をやって、じっと見つめた。 すると、主が思いもしないことを言い出したので、思わず勢いよく振り返ってしまった。 「……わたしは、あなたたちを価値があるとかないだとか、そういった目で見たことがありませんから。……失礼ですが、値打ちがあるだとか、切れ味がどうだとか……逸話を聞いても、あまりぴんとこない。わたしは、自分の目に映っているあなたたちしか知らないですから、なんとも……」 なるほど、と内心頷きながら、さて、どうしたものかと考えながら「へえ、そうかい。なら、きみの知っている加州清光はどういう存在だ?」と投げかける。 主はきっぱりと「清光は、わたしの初期刀です」と言い切った。ちっとも迷わずそう答えたので、俺は結局呆れた溜息を吐く。 「そんなことはこの本丸の誰もが知っている。そうではなくて、きみにとって加州はどういう存在なのかって意味だ」 「……初期刀、ですが……」 頭を抱えながらも、いつもの問答とはまるで違った展開になったので、さてここからどうするか、と思いつつ――結局「……こりゃ重症だな……俺のほうがよっぽど人間味があるぜ……」と呟いた。 いつも俺にはつんけんした可愛くない態度ばかりをとるくせに、今回ばかりはしおらしく「す、みません……」などと情けなく声を震わせるので、俺のためというところもあるわけだが、大事な主殿を思い悩ませることは解決してやらねばと立ち上がった。 「よし、なら俺が教えてやろう」 「は、」 にやりと笑ってみせると、緊張した面持ちで俺の目をじっと見つめる。 「きみにとって、加州がどういう存在であるか――ってのを通して、きみの持つ好奇心を引き出してやろうと言ってるんだ。そうすれば自ずと興味を引かれるものが分かってくる。そうしたら俺にそれを教えてくれ。どうだい?」 主は少し考えるような素振りは見せたが、一つ頷いた。 まぁ、「……わたしのことはどうであれ、清光を、傷つけてしまったことは、わたしの力不足で――」というのは、完全に的外れな解釈だが。 「そういうのが余計なんだ、きみは。いいか、考えるよりもぱっとしたひらめきを大切にしろ」 「は? は、はあ、」 「加州に何をしてやりたい?」 「え、あ、えっと、」 「三、二、」 一、と俺が言う前に、主は慌てて「かっ、買い物に!」と平時よりも大きな声で答えた。 加州は着飾ることが好きで、給金が入ればまず万屋へと出かけていくが、いつもぼんやりと、主と一緒に買い物でもできたら楽しいだろうなとぼやいている。 初期刀でありながらもそう言うのだから、ここまでそういったことはまるでなく、主の日常からしてもとても頼めはしないのだろう。――となると、なるほど妙案である。 「万屋か。喜ぶんじゃないか? じゃ、俺は歌仙を呼んでくる。きみは加州を誘ってこい」 そうとなれば、着飾ることが好きな加州だが、一緒に万屋へと出かけるならば、主も同じように着飾っていれば余計に喜ぶだろう。そういうことに関しては歌仙なんかが適役だろうと、俺は早速行動に移すべくさっさと立ち上がって背を向けた。 「え、え? つ、つるまる、まって、」 「ほら、行った行った」 なんだかんだと後ろで繰り返していたが、そんなものをいつまでも聞いていたら日が暮れる。聞こえないふりを貫いてやった。 「……鶴丸」 あれからしばらくしての、昼下がりのことだった。 縁側でなんとなく庭を眺めていた俺に、主が声をかけたのは。 「きみから話しかけてくれるなんて、これは良い兆候だな。どうした」 ちらりと見上げると、主はやけに緊張した表情を浮かべて、俺の様子を窺うように視線をちらちらと動かしている。それから少し躊躇いを見せたあと、たどたどしくもゆっくり口を開いた。 「……お礼を、言いたくて。……清光のあんなに嬉しそうな顔は、初めて見ました。……わたしが今まで、どれほど至らぬ主であったか、あなたが気づかせてくれました。ありがとう。……それで、」 この先はもう知っていることだったので、迷わず「俺にも礼をしてくれるんだな?」と言うと、主はあからさまに驚いた顔をした。 「え、」 「違うのか? 着物を選んだ歌仙にも、話を聞きつけて髪を結ってやった光坊にもしていたろう」 なぜ俺を最後の最後に回したのかというと、まぁ単純に俺が関わりづらい種類の相手と分類しているからだろう。これまでがこれまでだったので致し方ない。こうして自ら声をかけにくるだけ、関係は進歩したと思っていいだろうとは思うが。 俺がじっと視線を向けていることに気づいて、どこか居心地悪そうに「いえ、あぁ、そうですが……」とぼそぼそ言うので、おかしくなって少し笑った。 「俺から好きなものを頼んでいいか」 そう言うと、意外にも「え? ええ、それはもちろん」なんて言うので、今までの経験からして、俺が何を言い出すかも分からない、無茶をさせられるんじゃないかと警戒してこないのが、俺は何よりも良い兆候だと口元を緩めた。 「きみがいい」 「は?」 「きみがいいと言った」 すると主は途端に厳しい顔をして、真面目な声音で「……鶴丸、今は時期が時期なのです。命だけはどうあっても――」とかなんとか言い出すので、今度は苦く思ってきゅっと口を真一文字に結んだ。 それから溜息を一つ吐いてやってから、「きみのその真面目腐ったところはどうにかならないのか?」と唸って、さらには「ましになったとばかり思っていたんだがな」と続けた。 「す、すみません……」 礼をと思ったのに失敗だ、とはっきり顔に書いているので、可愛いことだと思い直す。しかし、あんまりからかってやってもかわいそうだ。 「謝ることじゃない。俺も言い方が悪かったな。こう言えばいいか? 君の真名をくれ」 今度は主が唇をきゅっと噛んだ。そのまま何も言わないので、俺は構わず先を続けた。 「今すぐにじゃあないし、俺はきみをどうにかしようと――しているが、まぁ悪いようにはしないと約束しよう。嫌ならば断ってくれても構わない。礼だからと言って仕方なしにもらうんじゃ、なんにも嬉しくないからな。ま、戦いが終わるまでによく考えておいてくれ」 主は俺に一度頭を下げると、静かに離れへと遠くなっていった。 「――それで? 答えは出たかい、お嬢さん」 戦いが終わり、いよいよこの夜が明ければ、みな散り散りに――いや、元の場所へと帰る。俺も、主も。 そういうわけで、俺は主を己の部屋へ招き入れた。 ぼんやりとした月明かりと、ゆらゆら定まらぬ行灯に照らされながら、俺たちは静かに向かい合っていた。 俺の言葉を聞いて、主は畳へとじぃっと縫いつけていた視線を持ち上げた。 「……あなたは意地の悪いひとですね」 俺はおどけて、「そうかい? もうきみは俺の主殿ではないからな。俺からすれば、ただの可愛いお嬢さんさ」と笑った。 しかし、そんなことで呼びつけたわけではないのだ。 少しの沈黙をおいてから切り出した。 「で、くれるのか? くれないのか」 主はすぅっと呼吸をしてから、静かに口を開いた。 「……」 俺は思わず、は、と息を吐いた。 「……名は体を表すと言うが……凛としたきみには不釣り合いなほど、随分とまぁ可愛らしい響きの名だな」 主はそれを聞いてむっと顔を顰めたあと、すぐさま「そういった類は散々に聞かされて飽いています」と早口に言った。 その様に少し笑ってしまうと、主は――というただの女は、やはり不機嫌そうに、視線をどことも言えないところへと逸らした。 これ以上はいけないと、俺はさっさと本題へ入ることにした。 俺が本当に欲しいと思っていたのは、何もその名というわけではない。 「……確かに受け取った。それで、俺からの礼なんだが」 「は?」 「きみの魂をもらい受けたんだ。そんな大層なものをもらっておいて、返礼なしなんぞ申し訳ない」 それらしいことを言う俺に、はやはりそれらしく「いえ、初めからそういう約束で――」と首を横に振った。 「俺はきみを、俺の神域へ招待したい。片道切符だが、どうだい?」 は息を飲んで、それからじっと俺へ視線を寄こした。 「きみが嫌だというならそれでいい。名をもらったのは俺だけだ。充分すぎるほどの礼さ。ただ、俺は退屈というものが死ぬほど嫌いでな。俺の興味を引いてやまないきみが、ずっとそばにいてくれれば素晴らしいと思うんだ」 神妙な顔で、堅っ苦しく「……ありがたく頂戴します」なんて言うもんだから、俺はまた笑ってしまった。 「――つるまる、」 ぼんやりと耳に届いた声に、まぶたが重く下がっていたことにやっと気づいた。 ゆっくりと目を開くと、申し訳なさそうにこちらを見つめると視線が合う。 「……あぁ、すまない、眠っていたか……」 掠れた声だったので、どれほど眠っていたのだろうかと思うと、盆に乗っている茶はもうぬるくなっていそうだった。 せっかく淹れなおしてもらったというのに、申し訳ないことをした。 しかし、やっぱりのほうがよっぽど申し訳ない顔をしている。 「すみません、布団を敷いたので……起こさずにいたほうがよかったですか?」 「いいや。……ちょうど、きみの夢を見ていた」 体を起こしてそう言うと、はなんとも言えない表情を浮かべながら「……そうですか。さ、布団へどうぞ」と返してきた。 すると俺もそのまま大人しく布団へ入ってやろうと思えないので、「きみも一緒なら」と目を細める。 「わたしは読みかけの本が――」 「おいおい、つれないことを言うなよ。……、先程の話、もう一度するかい?」 口端を持ち上げてみせると、溜息のように「……あなたの、そういう意地悪なところが嫌いです」とはこぼす。 「ははっ、そうか! よし、じゃあ次は好きなところを言ってくれ!」 ふざけてそう言うと、は躊躇うように唇を薄く開いて、その後「……そうやって、よく笑ってくれるところです」と真面目な顔をするので心底驚いた。 「……そ、うか……。……はは、俺は今ものすごく驚いているぞ……」 「それはよかった。しばらく静かになりますね」 むずがゆい気持ちになりながらも、楽しみを見つけて眠れない幼子のように、俺はの手を取って、力を込めたり緩めたりを何度もはしゃいで繰り返した。 「! もう一度だ! もう一度……いや、俺の気が済むまで、俺の好きなところを挙げてくれ!」 そんな俺の様子を見て、はなんともないように「……時間はたくさんありますから、一日に一つなら教えて差し上げます」とやっぱりなんともない声音で言った。 なるほど、と思った俺は、の指に自分のを絡めて引き寄せると、甘い香りを漂わせている耳元でそっと言う。 「……そうか。それなら、たくさん聞けそうだな。そうと決まれば、早く明日になってもらわないと困る。、おまえも一緒だ」 「えっ、」 跳ね上がる声に笑うと、くすぐったかったのか細い肩までも揺れた。 もう一度耳元で、ゆっくりと囁く。 「俺が眠って起きて朝だと言っても、自分は眠ってないとかなんとかやり過ごすつもりだろう。そうはいかないぜ。きみも俺と一緒に眠るんだ。……目が覚めたら続きを聞かせてくれ」 ふふ、というの笑い声を近くに聞いて、俺も体を震わせた。 「……意地悪なひと」 |
画像:HELIUM