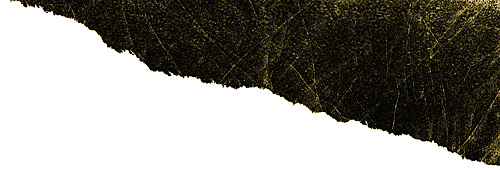
「鶴丸……どこ……?」 闇に溶けいるような細い声音に、誰も拾えないような高さで応える。用心深くいなければいけない。そうでなくては、誰かが俺のしていることをひどく責めたり、彼女の知らぬ――たとえば戦場とか――で、俺を折って消してしまおうという奴もいるかもしれない。心当たりはある。 「ここだよ。開けていいかい?」 俺の言葉に、ぴっちりと閉められた襖はすぐに引かれて、月明かりが彼女を照らし出す。綺麗だ。何にも踏み荒らされていない、神々しいまでの美しさだ。儚げな、触れたらすぐにでも掻き消えそうなその存在感は俺をはっとさせる。俺が守ってやらねばと。 「鶴丸、傍にいて」 「もちろん、君が望むなら」 いいや、君が望まなくとも。そう続けそうになったが堪えた。ほっと息を吐いた彼女に言うことでもない。俺が言わずとも、もう彼女は俺を望まずにはいられないところまできている。それを思うと、俺はどうにも侵してしまいたくなる。この神域を。 「ねえ鶴丸……わたし、ちゃんと審神者として働けている……?」 俺を逃がすまいとでもするように、その細腕は震えつつもしっかりと俺の夜着を掴んだ。俺の方もこの瞬間を逃がすまいと、味わうように深く呼吸し、そっと主の体を抱き寄せる。 「馬鹿なことを言うもんじゃないぞ。君は誰よりも立派な審神者だ。だからこそ俺は戦場で好きに己を振るっても、こうして無事に帰ってこられているんだぜ」 戦場。俺のその言葉に、主はぶるっと体を震わせた。何にも侵されることない真白な彼女は、それを聞いただけで身震いする。血に濡れて帰還した誰かを見たときにも、毎度そうだ。 だから俺は、この小さくてか弱い主を守ってやらねばならないのだ。他の何を差し置いても。それが“仲間”であったとしても、俺はまったく躊躇うことはない。俺が守りたいと思うのは、今日まで積み重ねてきた過去だとかいうものではない。彼女が生まれた時代ですら、特別守ろうとは思わない。大事なのは、こうして俺の腕の中で体を震わすこの女だけだ。これを守れるのなら、過去も未来もいらない。俺が欲しいのは今この瞬間、これだけだ。 「……鶴丸が戦っているのは、わたしのせいなのよ。恨めしいでしょう。それなのにあなたはこうして優しくしてくれるから、それがとても怖いの。……あなたを頼っているくせに、どこかであなたを疑ってるの」 酷いでしょう、と彼女は両手で顔を覆った。 「いいや、何も酷いことなんてないさ。俺は振るわれてこそ価値のある存在なんだぜ。君のために振るえる力があって、俺は満足してる。恨めしいだなんて思ったこと、一度だってない。本当だ」 だから安心して、そのすべてを俺にゆだねてほしい。 そうすれば、そんなことを考えずに済む場所へ、俺は簡単に引き込んでやれる。 それでも彼女は、本当に逃げることはしない。辛い、悲しいと俺にいくら訴えようと、楽な場所――俺のところまでやってきやしない。そうしてくれればどんなにいいか知れないのに。 俺だけを信じて、俺だけをその目に映して、俺だけにすべてを任せてしまえば、どんなしがらみからでも逃げ出せる。俺が守ってやれる。それが一番のはずなのに、彼女はそうしようとはしない。 「……他のみんなもそう。わたしにとても良くしてくれているけれど、本当はどうだか分からないわ。いつか、いつか――わたしを殺せてしまえることに気づいて、そうするかもしれない。そんな考えが頭から離れなくて、最近は笑うことすらとても難しいのよ……」 いざとなれば、俺たちは君を殺せるんだ。そう教えたのは他でもないこの俺だ。侵されない、侵しがたい神域そのものである彼女を守りたいのは嘘ではないのに、その一方で穢すのならばそれはこの俺だと思っているからだ。俺が本当に望んでいることがそれであるのは、もう随分と前に気づいてしまった。初めはなんて愚かしい考えだろうと鼻で笑ったが、今ではそうと言えない。俺は至極真面目に、この女をいつ自分の手元に引きずり込んでしまおうかと考えている。だからそのようになるようにとしているのに、彼女はなんだかんだと俺のところへはやってこない。俺に、その名を与えはしない。それはやはり、彼女が言うように俺を疑っているからだろう。 確かに俺のしようとしていることを考えれば、それは正しい。名は魂そのものだ。俺にそれを与えるということは、俺に彼女をどうにでもしてしまえる権利を与えるということなのだ。俺はその機会をずっと窺っている。君の名を俺にくれと言って、それに頷くまであとどれほどだろうか。 「無理に笑うことなんてないさ。誰も君にそんなことを望んでいない。君は君らしく、そのままでいていい」 「それじゃあみんな、救われないわ。人間の都合で戦うことを強制されているのに、わたしがみんなを振り回していいはずないもの。……やっぱり、みんなわたしを恨んでるわ」 ぶつぶつ呟くように言葉を吐き出していくさまは、彼女の方こそ俺たちを恨んでいるようだ。審神者として俺たちを戦場に送ることを強制されているが、そんなことはどうだっていいのだ。ただ、それを叶えてしまうだけの力が己にあること、それによって俺たちを人の子と変わらぬ存在であるように顕現できること。――それによって本当にこの世に顕現されてくる俺たちを、恨んでいるようだ。 「――たとえ皆が君を恨んでいるとしても、俺がいるじゃないか」 「……鶴丸だって、本当は、わたしが憎いでしょう。正直に言って、お願いよ」 「正直に言っているさ。君には君を決して裏切ったりはしない、この俺がいる」 「嘘よ……そんなの嘘……」 無感情な声は同じことを何度も繰り返した。俺を見上げてはいるが、焦点の合わない視線がゆらゆらと宙を彷徨っている。 「信じる信じないはもちろん君の自由だが、そう疑われては俺も困ってしまうな。これ以上、君の心を慰めてやれる手段が思いつかない」 「……慰めてもらいたいわけではないのよ。……なんて言ったらいいのか、分からない。ただわたしは、あなたを信じたいと思ってるし……ううん、信じてるはずなの……。なのに、心のどこかがそれでは駄目だって言っているようで……」 ――まだまだ先は長そうだ。そう思うと同時に、俺はまだこのときを楽しんでいたいという己がいるのも分かっている。こうして俺にだけその心の内を吐き出す彼女が、心底可哀想で愛おしいからだ。 短刀と戯れているときも、誰かと談笑しているときも、彼女の笑顔にはいつも陰りが見える。そのことにはきっと誰もが気づいているが、何も言わない。それこそが心優しい主に負担をかけないことであると信じて疑っていない。そして、そういう距離を置いておくことで己を律し、彼女のために――人のために心を痛めている彼女に代わって戦うことを誇りとして、戦うことに没頭している。それこそが、自らの主のためであると信じて。 馬鹿な話だ。彼女は戦うことそのものに恐怖を抱いているというのに、それに没頭して戦績を上げてくればくるほど――血に塗れてくるほど、彼女の心を痛めつけているのに。だがそれでいい。俺以外はそうしていればいい。奴らが思い違いをしているうちに、俺は彼女を攫えるように時間を重ねていくだけだ。現在、それだけを。 「辛いことを辛いと感じるのは当たり前のことだ。何も恐れることなんてない。俺を信じろとは言わないが、君が君の感情を騙すのだけはやめろと言わせてくれ。……余計な世話かもしれないが」 「いいえ、そんなことない。……鶴丸は、本当にわたしを責めないでいてくれて、こうしてわたしの話に耳を傾けてくれて……審神者なのに、みんなを守る立場にいるわたしのことを、守ってくれているんだもの……」 「俺は自分に素直なんだ。そうしたいからこうしてる、ただそれだけさ」 あなたにどれほど救われてるか、と彼女の声は震えた。俺が囲っているその体も。それでいい。それでいいんだ。俺は笑ってしまいそうになった。どれほどかかるかと思ったが、これは案外すぐにでも叶ってしまうんじゃないかと。その名が――俺のところへ引きずり込む力が、俺の手に与えられるのは。 「鶴丸、ごめんなさい……わたしがもっとちゃんとしていたら、あなたのこと、頼らなくって済むのに……面倒なことを押し付けてしまって、本当にごめんなさい……」 「いいや、有り難いことさ。主の役に立ってこその俺だ。君は何も気に病むことないぜ」 「でも……」 「つまらないことは言うな。俺は君のところに顕現されて嬉しいんだ。君が主で嬉しい。君が俺を頼りにしてくれて嬉しい。……俺が君を、救ってやりたい」 目が合った。甘く潤んで、何かを期待しているような目だ。応えてやるのは簡単だ。何せ俺が望んでいることだ。君の名をくれ。たった一言、それだけでいい。けれど俺はこの瞬間を楽しんでもいたいのだ。望みがいざ叶うとなると、もう少し、もう少しと思う。完全に俺の手のひらへ落ちてきて、何にも、誰にも踏み荒らされていない――その先、永遠にそうはならない神域を、他の誰でもないこの俺が穢してしまう。その瞬間を夢想して楽しみたい。だからまだ早いと思ってしまう。侵したくないと思うほどに侵したく、侵したいと思うほどに侵したくはない。 「……鶴丸に、わたしの名前を預かってもらえたらいいのに」 「それは光栄だ。何よりの信頼の証だからな」 「でもそうしたら、きっとあなたはこうしてはくれなくなるわ。わたしにはっきりとした憎しみを抱いて、そのときこそわたしを殺してしまいたくなるはずよ。……わたしは、あなたに甘えていたいんだわ」 今度こそ俺は笑った。 「それでいいさ。俺は君のものなんだぜ。甘えてくれて結構だ。ずっとそうしていてくれ。……君が望むことは、俺が全部叶えてやる」 「……ほんとう?」 「俺は君を裏切らないって言っただろう。嘘なんて吐かないさ。何がお望みだい?」 俺が透き通った青白い頬に口付けると、主は俺の背に腕を回した。それから俺の首筋に顔を埋めて、熱く甘い吐息を漏らす。ゾクッと背筋が震えた。 「ずっと傍にいて。わたしの傍から、ずぅっと離れないでいて」 「お安い御用だ。そんなことでいいのかい?」 「そんなことなんて簡単じゃないわ。こうしていつでもわたしを抱きしめてってことよ。憎らしい相手をこんな風に扱うなんて、とても難しいわ」 ここで君を愛しているから簡単だと言うのも、俺にとっては簡単だ。けれど、それでは面白くない。もっともっと、俺を楽しませてほしい。もっともっと、俺の心を絡め取って離さないでほしい。そうしたら俺はますますこの女が愛おしくなって、そのときこそどんな手を使ってでも引きずり込んでやろうと思えるだろうから。 もしかしたら彼女の言う通り、俺は憎んでいるのかもしれない。毎度まるで恋人に囁くように、恋人に触れるようにするくせに、本当にそうはなってくれないのだから。でもそれでいい。だからこその楽しみを与えられていると思えばなんてことはない。この世に――彼女のところへ顕現されて、本当に良かった。こんなにも面白いことがあるのだ。俺はこれを、絶対に手放さない。他の誰にもくれてやるものか。 「主」 「……なぁに」 「本当に辛くなったら、いつでも言ってくれ。俺には君を“守る”力がある。その名を預かってほしいと思ったら、いつでも言ってくれ」 俺が言うと、主は震えた声で答えた。 「わたし……わたし……、ほんとうは、今すぐにでも、あなたに言ってしまいたいのよ。わたしの、名前」 「それは光栄だ。俺もそれを望んでいるからな」 ぼんやりとした月明かりさえ届かないというのに、はっきりと目に飛び込んでくる赤い唇を塞いでしまうことは、とても簡単だった。 「鶴丸」 あれから主は、何も隠すことがなくなった。こうして人目がある中でも、はにかんだ笑みを浮かべて俺の傍へと寄ってくる。鶴丸、鶴丸、と俺を呼ぶ声には、愛おしさが滲み出ているとはっきり感じ取れる。 「どうかしたかい?」 「どうもしてないわ。ただ、あなたの傍にいたいのよ」 「そうかい。それなら縁側で茶でも飲もう」 「ええ」 様々な感情を含んだいくつもの目が、ちらちらとこちらへ向けられている。それがどんなものであっても、俺には何も感じられない。俺にはたった一人、この女だけなのだ。他へ気を取られている暇もなければ、他を気遣う理由もない。主は俺の手を引いて、縁側へ腰掛けるよう俺を促した。 「お茶の支度をしてくるから、ここで待っていて」 「君がそんなことをする必要はないさ。俺が行ってこよう」 「駄目よ。鶴丸こそ、そんなことをする必要はないの」 人で言う、“夫婦”であるようだなと思った。俺をまるで愛おしい男――亭主のように扱って、何より俺を優先して気遣う素振りを見せる。穏やかな微笑みは、まるで俺を包み込むかのようだ。誰かが息を呑んだ。主従関係の逆転を思わせるこれは、きっと一部には信じられない光景だろう。 「鶴丸」 透くような声が、静かに俺の名前を呼ぶ。俺たちを囲う空気が、少しばかり剣呑なものに変わった。もちろん彼女に対するものではなく、俺に向けられているものだ。しかし、どうだっていいことだ。 この本丸にいる、主を大切に思って大事にしようという輩は、彼女に従うことこそが彼女のためになると信じているのだ。彼女が望んでいることならば、誰も俺を咎めることはできない。――戦場に出たとき、どうなるか知れたもんだと思った。俺を折ってやろうという目をしているのが、いくらか見えている。生憎とやられてやるつもりはないし、実際それを為せるものもいないだろう。彼女が、俺を愛しているうちは。 「わたしを置いて、どこへも行かないでいてね」 「もちろん、それが君の望みなら」 俺の言葉にうっとりとした様子で頷くと、“”はしっかりとした足取りで台所の方へと消えていった。するとそこへ、難しい――いや、今にも俺を折ってしまおうというのが見える――顔をして、長谷部がこちらへずんと近づいてくる。 「貴様、一体どういうつもりだ」 「おいおい、そんなおっかない顔をするなよ。どういうつもりも何もないさ。俺はただ主に従っているだけだぜ」 「お前があの方に何か吹き込んで勝手をしているのは分かっている。認めろ。お前のしていることは不敬だ」 「仮にそうだとして、お前に何ができるって言うんだ? 主が俺を望んでいるのに。それに逆らうことこそお前の言う“不敬”じゃあないのか?」 今にも抜刀せんとばかりに、その目はぎらぎらと不穏な光を宿している。しかし長谷部は、その続きを言葉にすることはなかった。返す言葉がないのだ。誰の目からしても、主が自ら俺を求めているのだということは明らかであった。分かりやすいというものではない。分かりきっていることなのだ。畳みかけるように俺は言う。 「お前は――この場にいる誰も、彼女の陰りを見ていたくせに何もしなかったじゃないか。俺が主を慰めてはいけないという法はないだろう。今になって俺に文句を言うのはお門違いってやつだぜ。そんなことを言うのなら、君らが先にそうしていればよかっただけの話だろう?」 長谷部は何も言わなかった。 そこへ、主が戻ってきた。 「……どうしたの?」 その声に振り返ると、寒いとでもいうように主の体は小刻みに震えていた。何度も白い喉が上下する。 「君が気にするようなことじゃないさ。さあ、茶を飲もう。君が淹れてくれるものは格別にうまいから、ずっと待っていたんだ」 笑ってみせると、主は安心したようにほっと息を吐いた。 それならいいの、と言うと、長谷部へ視線を動かした。 「長谷部……どうかした?」 「……いえ、何も」 「そう」 短く端的に答えると、然したる興味も関心もないといった風に、主は俺に笑ってみせた。長谷部が俯いて唇を噛んでいるのが目に入ったが、俺もそんなことには興味も関心もない。何事でもないと、俺もまた笑顔で彼女に応じる。 ああ、愉快だ。俺の欲しいものは手に入ったし、これは時間の問題だ。あとはこのまま、主が――が俺に、今度こそ「どこへでもいいから連れていってほしい」と願うのを待つだけなのだから。あぁ、愉快だ。 俺の元へと引きずり込んでやったなら、俺はもう彼女を二度とここへは返さない。お前たちの大事な主は、もう死んだ。 あるのは今この瞬間の現在だけだ。そしてそれは、俺の手の内にある。 |
暗闇に白