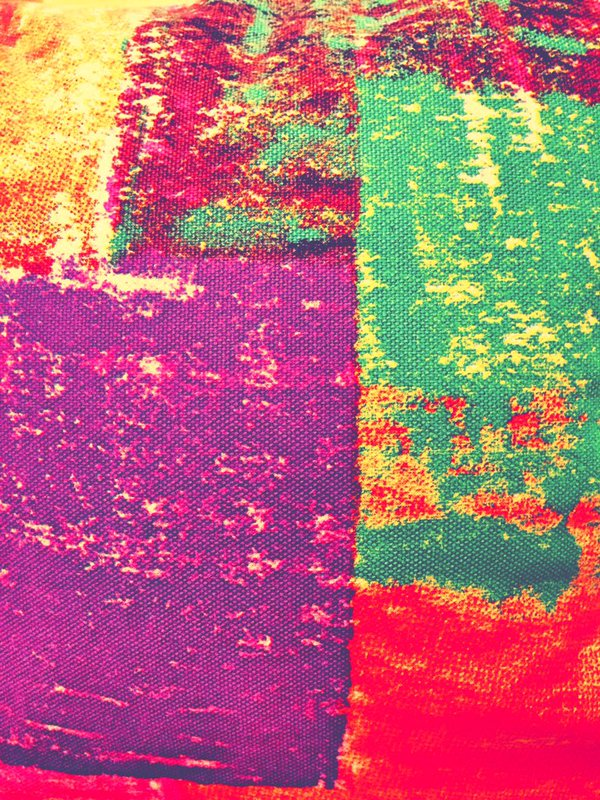
それは主が、初めての鍛刀をすると言った日のことだった。 「ねえ主」 先を歩いていた主の隣に並んでそう声をかけると、主はちらりと俺に視線を移した。 柔らかい眼差しに、胸の内がきゅっと熱くなっていく。 「なぁに?」 「……鍛刀するまえにさ、いっこだけいい?」 「もちろん、なんでも言って」 「……何言っても捨てない?」 主はぴたっと足を止めると、不思議そうに首を傾げた。 「ええ? どうして清光を捨てなくちゃならないの? あなたはわたしの一番の刀なのよ。何があったってそんなことしやしないわよ」 ――何があっても。 その言葉が俺は本当に嬉しくて、主のまえに躍り出て口を開いた。 「……あのね、」 その太刀がきて、主は――はとても喜んだ。多くの短刀たちが、ずっとずっとその名を口にしていたからだ。 粟田口の長兄だというその刀――一期一振は基礎能力からして優秀だったし、更に鍛え上げるためにも、が奴を第一部隊の隊長にと言ったのには驚きはしなかった。 ある程度まで人の体に慣れて、しばらく戦場での経験を積めばどの刀も通る道だ。の一番最初の刀の俺はもちろん、その後すぐにやってきた薬研にしたってそうだったし、の初めての太刀である燭台切もそうだった。だから、何一つ特別なことなんてなかった。 けれど一期一振はそれを告げられた途端、こうして大袈裟なほどに驚いているので、俺にはそれが驚きだった。 「……わ、私を本当に、本当に第一部隊の隊長に置いてくださるのですか」 「ええ、そうです。お任せしていいですか?」 「もっ、もちろんです! あぁ、主殿、それでは近侍の任も、私に、お任せくださるのですね」 俺はこれにも驚かなかった。 他の本丸では、基本的には第一部隊の隊長が近侍を務めていると知っていたし、こちらがそうでないと知ると驚く審神者だっている。けれど、この本丸での近侍はたった一人だ。ずっとずっと変わらない。だって、約束した。 「うちでは近侍を固定しているんです。第一部隊の隊長とは別にして」 「……は、……それは……一体……?」 なんともない顔をして――実際うちの本丸では“なんともない”ことだ――告げたの言葉に、一期一振は声を震わせた。 俺はその様子をそっと見ると、笑って答えた。 「俺だよ。加州清光。この本丸では俺がずっと主の近侍。他の本丸とは違って、特別なんだ」 その時、俯いた一期一振の顔を、俺はよく確認しておけばよかった。 「なぁ、一期。これは刃生の先輩としての忠告だ」 そう言う鶴丸国永の声が聞こえたので、俺はその場でぴたりと足を止めた。どうにも嫌な感じのセリフだし、不吉な予感をさせる声色だ。 鶴丸国永は比較的早くにうちへやってきた。開口一番、「驚いたか?」という言葉には本当に心底驚いて、思わずその場に座り込んだほどだったので、鶴丸さんはおかしそうにけらけらと声を上げて笑った。 あの人はひょうきんなひとだし、いつも何かといたずらを仕掛けてはに叱られているけれど、その実、根はとても真面目でによく尽くしていることを俺は知っている。だからこそ、その鶴丸さんがこんな声でそんなことを言うのだから、ただごとではないのは確かだ。 俺は息を潜めて、そっと様子を窺った。 「……それはどういった意味ですかな」 鶴丸さんの言葉に応えたのは、一期一振だった。 俺はどうしてだかぞっとして、思わず腕をさすった。 二人がどういうふうに向かい合っているのかまでは分からないが、緊迫している。今にもどちらかが己を抜いたって驚きはしない。そんな感じがするのだ。いつも騒がしいはずなのに、どこからも声が聞こえてこない。 「おいおい、“どういった意味”だって? ……それはきみが一番分かっているだろうに、おかしなことを言うな。……いいか、一期一振。審神者に――主に思いを寄せるのだけはやめろ」 どくん、と心臓が大きく脈打った。鶴丸国永は、今なんと言った? 一期一振に、なんと言った? どくんどくん、脈を刻む音はどんどん大きくなっていく。 一期一振の声はどこまでも落ち着いていて、静かだった。 「己の主をお慕いして何が悪いのです。……あなたは、主殿がお嫌いですか?」 「そういう意味じゃない。分かっているだろう。主を恋い慕うのはやめろと言っているんだ」 鶴丸さんのその言葉に応えた「あなたに指図される謂れはない」という一期一振の声は、普段からは想像すらできないほどに凍てついていた。 俺はそれほどよく知っているわけじゃないけれど、一期一振のことを粟田口の良い兄だとはいつも言っているし、もちろんその粟田口のみんながあのひとを慕っている。あちこちで“いち兄”と誰かしらの声が言っているのを聞くのだから、いいひとなんだと思う。遠巻きにでも見る笑顔はいつだって優しいし、仕草だってそうだ。 だからこそ、いくらおんなじ声をしていたって、“これ”が“あの”一期一振だとは思えない。 鶴丸さんの「そうか?」というゆったりとした声は、ひどく場違いだ。けれど同じ調子で続けられた言葉に、俺はますます心臓の音を逸らせた。 「俺は主から信を得ているし――何より、あの加州清光も俺を認めている。俺が奴にちょいとこの話をすれば……どういう意味だか分からないおまえではないな」 一期一振はそれを鼻で笑った。 「脅しているおつもりですかな」 鶴丸さんは飄々と「おっと、そう聞こえたかい?」と応えたが、次の瞬間にはピンと何かが張り詰めた。 「――きみがそう思うのなら、きっとそうだろうな。要は捉え方さ。……きみのその感情が、主に対する忠義であると信じてるぜ、一期一振」 それに何も答えは返ってこないままに、一期一振の気配は消えた。 「――加州」 キン、という音にハッとした。聞き慣れた納刀の音だ。 抜刀していたのだ、二人は。 ごくりと唾を飲み込みつつそっと進み出ると、鶴丸さんの琥珀色の目がゆっくりと俺を捉えた。 「っ、いつから気づいてたの?」 「初めっからさ。……奴もそうだ」 なんともなさそうな顔をしているけれど、その声音は充分に緊張している。 そして俺の声も、震えるのを隠すことなんて無理だった。 「……ねえ、一期さん、どうしちゃったわけ? あんな人だっけ、あのひと……」 「どうやら“あんな”人らしいな。まいったぜ、もっと注意しておくんだった」 鶴丸さんはどかりと、赤い橋の欄干へと腰を下ろした。 澄んだ水の湛えてある池の水面が、きらきらと光っている。 「……どういうこと」 俺の言葉に鶴丸さんが目を見開いた。 こんなことを聞くのは馬鹿だと、もちろん分かっている。 「おい、きみ、あれだけ主のそばにいるっていうのに気づかなかったのか?」 「……言いたいことは分かるけどっ、でもそういう素振りなんか全然なかった!」 俺の言い訳じみた言葉を責めるでもなく、逆に納得したというような顔つきで、鶴丸さんは「だろうな。……賢しいやつだよ、まったく」と溜め息を零した。 呆れているようで、驚いているようだった。 鶴丸さんは俺をちらりと見ると、いつになく真剣な顔をした。視線があまりにも鋭くて、思わず体を引いてしまいそうになった。 「そこでだ。俺は奴にも忠告したが、きみにもしておくぞ。……一期一振の言動にはよく気をつけろ。俺はこれでもう警戒されてしまったからな。……主を守れるのは、きみしかいない」 「……みんなに話したらいいんじゃないの?」 鶴丸さんはゆっくりと首を振った。 「ここで一番の影響力があるのはきみだ。……ずっと近侍だろう。彼女の性格上、こんな偏ったことをするのはどうしてだ?」 「……それは、」 口ごもる俺に、その言葉は容赦なく噛みついてきた。 「加州、忠告だ。主から目を離すな、一期一振の言動に注意しろ。……ま、俺もやることはやるが……主殿が誰より信じて、誰より大事にしているのはきみだ。相応の働きをしろ。とにかく気をつけるんだ、いいな」 言葉よりも、その視線が何度も念押ししているように思えた。 口に出してしまいたいことをなんとか飲み込んで、俺はそれに応える。 「……分かってる。当然だよ。俺は主の特別。一番に可愛がってもらってるんだから」 鶴丸さんは力強く頷いて、「よし、それでいい」と言った。 それから、さも当たり前というように「きみは主の真名を知っている。……悔しいことに、主がそこまでしているのはきみだけだ。だから絶対に守ってくれ」と言うので、俺は飛び退くように距離を取った。 「なっ、なんでそれ知ってるの?!」 いつものよう――いたずらを仕掛けたときのよう――に、鶴丸さんは笑った。 「ははっ、主にな、いつぞや言ったんだ。きみの真名をくれってな。そしたら彼女、こう言った。『清光にしかあげないって約束してるから、だめよ』ってな。……本当に、悔しいほどにきみは愛されている」 伏せられた瞳に応える正しい言葉は、俺が口に出せようはずもなかった。 「……とーぜんでしょ。だからちゃんと、俺が主を守るよ。任せて。主の特別は俺だけだけど……みんなの主は、絶対に守ってみせる」 あれから、一期一振に特に変わった言動は見られなかった。ただ、にどうにかして働きを認めてもらおうと――近侍の座を与えられるようにと、一層励んでいるようには見えた。 至上主義で、『主命とあらば』を呪文みたいに繰り返しては働きまくる長谷部も眉間に皺を寄せるほど、あれもこれもとなんでも仕事をこなした。 鶴丸さんには一期一振に気をつけろと言われているし、そうでなくとものそばから離れることはしない。そしてこの現状だ。なおさら離れる気はない。 けれど、それにも限界はある。 「清光。第一部隊の隊長は一期さんにもう少し頑張ってもらうとして、清光には育成中の第二部隊の隊長をお願いしたいんだけど……」 「え、」 の言葉に思わず声を漏らしたが、出陣命令は当然のことだ。俺はそのための存在だし、が俺の主であることの証明でもある。いつもなら喜んで頷いているところだ。 俺の様子がおかしいことに気づいて、が「あら、嫌?」と眉を下げた。 もちろん嫌なことなんてない。ないのだ。の命だ。嫌なんてことがあるわけない。 けれど、状況が状況なのだ。 「う、ううんっ! 嫌なんかじゃないよ! ……でも、俺が出てる間の近侍はどうするの」 どうやってこの場を乗り切ろうかと考える俺に、は今回の任務の仔細が書かれているであろう紙の上に視線を滑らせながら、「今まで通りよ。清光が留守の時には、ふさわしい人に代行してもらう」と言った。それからこういう場面でいつも言うことを続けた。 「もちろん、清光が選んでいいわよ」 それに俺が答えるまえに、「私にお任せいただけませんか? 加州殿」と一期一振が言った。 俺が呼ばれる少しまえからここにいたようで、襖を引いて一番に目に入ったのがこの浅葱色の髪だった。 何かの報告でここへ来ていたんだろうけれど、すべてが謀られているように感じてしまう。どうしてここにいるのかと問い質してやりたい。あの晩あの場に俺がいたことを承知で、代行であろうと“近侍”を望むなんて、何かあるのだと言われているようにしか思えない。 「……一期さんは第一部隊の隊長でしょ」 一期一振は柔和な微笑みを浮かべて、「本日第一部隊は休みを頂いておりますから、何も問題はありません」と優しい声音で言う。 これに俺が何事か――それが何なのかは思いつかなかったが――を返そうと口を開きかけたところで、がそれを遮った。 「いえ、それはだめです。お休みには休息をとっていただかないと困ります。……んー、清光、どうする?」 無垢な表情で首を傾げるに、俺はきゅっと唇を噛んだ。 「……鶴丸さんに頼む。あのひと、俺の代わり何度もやってるし」 は得心したという顔で、「あぁ、鶴丸」と頷いた。それからくすくすと笑った。 「ふふ、いっつもいたずらばっかりしてるけど、あれでいて真面目だから、書類仕事も休憩の入れ方も上手なのよねえ」 「……じゃ、そういうことでいいよね?」 「うん、お願いね」 ちらりと一期一振の様子を窺うと、表情は俯いていて分からないが、膝の上で固く拳を握っている。 今度はに視線を移すと、優しい顔で笑っていて、喉に何かがつっかかっているような気がした。 「一期さん、お気持ちだけありがたく頂戴します。今日はしっかりと休んで、また次の活躍をお願いします。近頃は随分と鍛錬を積んでいるそうで、みな感心していますよ。わたしも期待しています。ですから、休むべきときにはしっかりと休んでくださいな。これも立派な鍛錬ですよ」 そう言うの声に、慌てたように上がった一期一振の顔は喜色満面で、頬がほんのりと色づいている。 「は、はい……! あ、ありがたいお言葉です……!」 俺はすっくと立ち上がると、「……じゃ、行ってくるね。主、俺がいないからって無理しちゃダメだからね」と言って、襖に手をかけた。強烈なほどに喉の渇きを感じて、今すぐにこの場から立ち去りたいと思った。 の柔らかい声がおかしそうに震えて、「あなたの代わりは鶴丸よ。逆を心配してちょうだい」と背中を優しく撫でる。 俺はどこか、安心してしまった。 「あはは、うん、すぐ戻るから。よーし、頑張っちゃうよー!」 「はぁい、いってらっしゃい。お願いね」 「任せて」 立ち上がって部屋を出る間際、一期一振の様子を窺った。目が、合った。恐ろしい目をしていた。 まるで、俺が斬るべき敵である。そう信じて疑っていないような、憎しみに溢れた目だった。俺はあの時と同じように――けれど今度はその正体をはっきりと理解して、ぞっとした。 早く――なるべく早く、ここへ戻らなくては。 最後の敵を斬り捨てた瞬間、背筋がぞくっと震えた。俺は考えるまでもなく、きっと――いいや、絶対にに何かあったのだと思った。その“何か”がなんであるのかなんて分からないけれど、良くないことだ。 いくら信頼しているあの鶴丸さんにのことを頼んでいるとしても、の真名を知っている――その魂を手の内に収めている俺が、この刃にその血を吸わせて“永遠の一番”を“約束”した俺が感じたのだ。良くないことを。 まさか、まさか。 に任されたというのに、俺は自分の役目を放って一目散に転送ゲートへ走り出すと、本丸へと急いだ。 の部屋へ、滑り込むようにして入った。恐れていたことだ。 いない。いないのだ。この部屋の主であるが。俺の代わりを任せた鶴丸さんもいない。 「っ! どこッ?!」 何の考えもなしに、俺は大事に大事に懐へ隠してきた主の真名を叫んだ。 「なるほど、“”。主殿は“”という名なのですね。あの御方にふさわしい、実に愛らしい響きだ」 「ッ?! 一期一振ッ! なんでアンタがここ――っぐ……!」 背後から音もなく忍び寄っていた影に気づいて声を上げたときには、もう鋭い一撃が急所を突いていた。 対抗すべく己を引き抜こうにも、腕が痺れてしまっている。 床に這いつくばる俺を冷たく見下ろして、一期一振は言った。 「……それは私の台詞です。どうしてあなたが、様の隣に、さも当然という顔をして並んでいるのです?」 そうだ、、、俺の主。 俺だけの、主。 かぁっと目の前が赤く染まるようだった。 「い、ちご、一振……ッ! ……ッ主、あるじ、……ッどこに……ッ!」 「川の下の子、とあなたは自ら言っているでしょう。……下賎があの御方の名を口にするな、穢らわしい」 振りかざされる刃に息を呑んだ瞬間、目の前を真っ白な背中が覆った。 「……穢らわしい? そりゃきみのほうじゃないか。敬うべき主殿を邪な目で見るとは、下賎もいいとこだぜ、一期一振」 鍔迫り合いの耳障りな音で掻き消されそうだったが、俺の声は届いたようだった。 「大丈夫だ、加州。主なら無事だ。なんたって、へし切長谷部に任せてあるからな。……さて、俺はおまえに忠告したはずだ、一期一振。しかし意味のないことだったらしいな。……きみのその感情はどうあっても忠義とは言えない。加えて仲間にこんな仕打ちをしたんだ。――覚悟はできてるな?」 鶴丸さんがどんな顔を――どんな目をしているのか、俺には分からなかったけれど、一期一振の目が一瞬で色を失くしたのは分かった。 いつだって、気高さの象徴みたいにきらきら光っていたくせに。つい今の今まで、燃えるような色を見せていたくせに。 ――俺を殺してやろうと真っ直ぐ射貫いてきていたその目は、もう色褪せて、どこを見ているんだかも分からないほどに虚ろだ。 一期一振はずるりと自分を手放して、その場に崩れ落ちた。 「……どうして、私には許されないのです……。……同じく、様に身体を与えられた……。あの御方のために、同じく尽くしている……。……同じく、心までも捧げているのに……ッ! ……どうして、どうして私には与えられないのです……何が違うと言うのです……」 ――まるで自分を見ているようだと思うと、手を伸ばしそうになった。 鶴丸さんの声が、寸ででそれを制した。 「同じく身体を与えても、同じく尽くされても――同じく、心を捧げられても。……主が唯一、他に与えないのが自らの“隣”だ。それは変わらない。……一期、おまえと加州に違いがあるのだとすれば、それは“忠義”であることと――“恋慕”であることだ」 一期一振が、俺が、何も言えずにいて、鶴丸さんもそれ以上は口を開かなかった。 そこへ、「お待ちください主ッ!!」という鋭くも上擦った声がこちらへ向かってきて、俺はハッと振り返った。 「ッあるじ……、なんで……ッ!」 鶴丸さんは呆れたと言わんばかりに肩を竦めて、「おいきみ、俺は長谷部と大人しく茶でも飲んでろと言ったはずだが?」と視線だけをへ向けた。 鋭い刃の切っ先は、一期一振へ向けられたままだ。 「ここはわたしの本丸ですよ。大事に主が動かずしてどうするんです」 の声は落ち着いている。 鶴丸さんは決して一期一振から注意を逸らすことなく、視線だけがに注がれている。 「主だからこそ大人しくしてろと言ったんだがな。……まぁいい。それで、こいつの処分はどうするつもりだ? 言っておくが、お咎めなしだなんてのは許さないぞ」 鶴丸さんの声には感情らしい感情が窺えず、俺はどきりとした。 のほうも特に声色を変えることなく、「あなたの許しが必要ですか? 主はわたしです」と応えた。 「……一期一振」 の声は、憐れんでいるようだった。 「あ、主殿、わ、私は、私は、」 思い詰めた――浅い呼吸をしながら、苦し気に呟く一期一振に、は言った。 「何も言わずにいて結構。今まで以上に励んでくれればそれで良しとします」 びくっと震えた。 「っそんな……! ……そんなの、そんなの納得いかない……ッ! こいつ、ほっといたら何してたか分かんないんだよッ?!」 「加州と同意見だ。どういうつもりだ。まさかきみもこいつに懸想してるなんて言わないだろうな」 怒りを滲ませている鶴丸さんと、何かを堪えている一期一振。 は冷静だった。 「馬鹿を言わないで。……“一期一振”という名の太刀は刀解処分です。ですが、“粟田口の長兄”はわたしの刀に間違いありません」 の言葉を聞いて、鶴丸さんは面白くなさそうに鼻を鳴らした。 「……とんだ屁理屈だな。……まぁいいさ、きみがそう言うなら。――ただし、これは最後のお情けだぞ、一期一振。主に与えられたこのたった一度、無駄にするなよ」 ――最後のお情け。 それは誰の、誰に対する情けだろう。 「……ッあ、あるじ……ッ!」 振り返らないその後ろ姿を見て、やっぱりもう二度と隣には並べないんだと思った。 「なぁに?」 の声は、ただただ優しい。これはが俺にくれるお情けで、そこには何もない。 「ご、ごめんなさい、ごめんなさい、俺、おれ、約束してもらったのに、なんにもできなくて……ううん、それどころか危ない目にあわせちゃうし、俺……いちばんの資格なんか、ないよね……」 は、ぴたりと足を止めると、ゆっくりと振り返った。 もう、あの頃の――ふたりきりで過ごしていたころのような優しい顔は、俺にはくれない。 ――あの日、まだなんにも知らずにいた無垢なに、俺は何も知らせることなく“約束”させたのだから。 真名だけでは飽き足らず、俺はこの加州清光の刃に、の血を吸わせて“約束”させた。 俺を――加州清光を、“永遠の一番にする”ことを。 この“約束”は、誰も破れやしない。たとえが稀有な能力の持ち主である、審神者だとしても。 は不思議そうな顔で首を傾げた。それから少し考えるように、「……そうね、加州がそう言うならそうね」と言った。 俺にはなんの資格もありはしないのに、心臓が痛い。 何も知らないに、ずるい真似をした俺が、何か望んでいいはずがないのに。 はただ優しい声音で、「だってあなたはわたしの“一番”だもの。そのあなたがそう言うならそうだわ」と言った。 「……は、どう思うの……?」 喉の奥が、ひどく渇いている。 は薄らと笑った。 「わたし? 何も変わらないわよ。加州清光、あなたがわたしの“一番”よ。ずっとずっと変わらない。――だって、約束したじゃない」 は何も言わない。俺が悪いとも、ひどいとも――俺を、憎んでいるとも。 俺はただ投げかけられる優しい声の裏側に潜むそれに気づきながら、ただ笑って、そばに立っていることしかできない。 「……うん。そうだよね、約束、したもんね」 「だからそんな顔しないで。――誰が来たって、わたしの“一番”はずっとあなたよ」 そう、ただ、立っているだけ。 |
画像:剥製