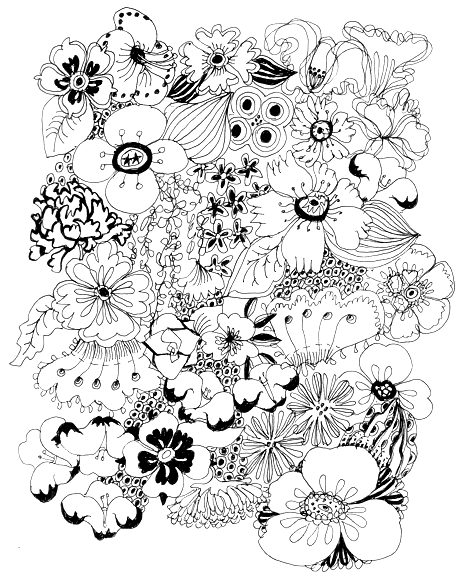
「あっ、ごめんなさ――」 飛び出してきた女のことを、三好はよく知っていた。。この辺りでは有名な豪商、氏の妻だ。あの男には勿体ない美しい女である。その顔かたちというよりも、その顔に浮かべる影のある表情が、どこか遠くを見ているような瞳が。何食わぬ顔で彼女の傍を通るたび、いつも思っていたことだった。 の細い体をその胸で受け止めると、三好は人当たりの良い笑顔を浮かべ、優しく問いかける。 「いえ、構いませんよ。僕のことより、貴女の方こそお怪我はありませんか?」 「ええ、大丈夫です。本当にごめんなさい」 三好の様子に、は心底安心したようにほっと息を吐くと、僅かに微笑んだ。 しかし、視線がどこか落ち着かない。 目を細めると、の表情を一瞬にして見極めた。成程、いよいよ決心したわけか、と三好は思った。目が合う寸でで、また好青年然とした笑顔を作り、彼女の体をしっかりと支えていた腕の力を緩める。 「貴女のような素敵な女性が、自ら僕の胸へと飛び込んで下さったんです。仲間に自慢できます。お気になさらず」 気取った調子の口ぶり、それから悪戯っぽい視線を受けて、も笑った。 「あら……随分と口のお上手な紳士だわ」 「ふふ、事実ではないですか」 「嬉しいことを言って下さるのね、ありがとう」 三好の言葉にはまた微笑するも、それから口を噤んだ。これがただの通りすがりであれば――そもそも出会い頭に女とぶつかるなど、三好にはないことだが――それでは、と簡単に別れるところであるが、三好はそうはしなかった。女の、次の言葉を待つ。すると、淡い桜色の唇が、ためらいがちに花開いた。 「……お急ぎかしら?」 「いいえ?」 は三好の顔を眩しそうに見上げた。 「なら、少しお茶でもいかが? 失礼をしてしまったお詫びです」 「それは願ってもない話だ」 三好はその後、こう続けた。 「ですが、貴女の方こそお急ぎなのでは?」 その言葉に、はさっと顔色を悪くしたが、なんともないような顔で「……いえ、いいのです。どこか素敵なお店でもご存知? なければ、私がよく行くところでいいかしら」と言う。 馬鹿な女だ。そう思いながらも、という女はこれでいいのだ、とも思った。これだから、いいのだ。己の甘さ――必要のない優しさとやらによって、地獄へと身を投じる。その愚かさこそが、彼女の魅力なのだと。 「貴女のようなお美しい淑女がお通いなら、とても良い店でしょう。ぜひそちらへ連れて行って下さい」 「やっぱりお上手ね」 二人は微笑みを交わしつつ、手が触れるか触れないかという距離感で、隣り合って歩き始めた。 「何があったんです?」 しばらく歩いたところで、三好は唐突に口火を切った。 は、訳が分からないという顔をした。 先程までにこやかにしていた三好が、やけに真面目な顔をしているからだ。 それを見て、三好はまた思う。馬鹿な女だと。 「? 何が、とは?」 「おや、逃げていたのではないんですか」 薄っすらと笑う三好の表情に、は背筋が凍るのを感じた。 「っ! あ、貴方……」 どくどくと、心臓の早鐘が耳に聞こえてくるようだ。 じっとりと、背中も湿り気を帯びている気がする。 慎重に言葉を――いや、今すぐここから走り去った方がいいのだろうか? がどうしようかと焦っている様を見て、三好はくすりと零した。 「いえ、僕は御主人の手の者ではありませんよ」 それを聞いて思わず息を吐きそうになったが、はじりっと三好から一歩身を引いた。 「な、なら何処で私を……」 「『何処で』? この辺りで氏を知らない人間を探す方が難しいではありませんか。それは貴女にも言えることだ」 三好はそう言って、後退したに一歩近づく。 「……何が目的です」 震えた声を出しつつも、は視線を三好の目から外すことはしなかった。 三好は人の良い笑顔を浮かべて、それでいて力強く、彼女の腕を自分の方へと引き寄せると「目的、ですか」と耳元で小さく囁く。緊張で体を強張らせているに、またくすりと笑う。 「……そうですね、敢えて言うなら……貴女でしょうか」 「……私?」 眉を顰めるの顔を覗き込む。 「ええ、そうです。言ったでしょう? 仲間に自慢できると」 はきょとんとした顔をすると、それから自分の体から力が抜けたことに気づき、笑った。 「……貴方を紳士だと言ったけれど……どうやら違ったみたい。貴方、おかしな人だわ」 おかしい、とは口元を手で覆って、ふふ、と吐息を漏らす。その姿はまっさらなままの少女のようで、こんな顔ができるんじゃないか、と三好は思った。それからやはり、そのくせあんな男のところへ嫁ぐんだから馬鹿だ、とも。しかし、この女よりも馬鹿な――愚かな者は、他にいる。 「ふふ、そうですか」 に微笑みつつ、三好は背後の様子にすっかり気づいていた。 「……ねえ、貴方――」 「おっと。……さん、失礼」 「――んっ……!」 何事か言いかけたの肩をとんと突き、壁へとその背を押し付けると、柔らかそうな唇を簡単に奪った。が目を見開いている。くぐもった声を漏らしている。勿論そんなことは分かっているが、神経を尖らせ、遠いとも近いとも言い切れない距離の男の姿を、その様子を、三好は注意深く探る。成程、まぁ予想の範囲だ。そう判断すると、の唇からそっと離れる。名残惜し気なリップノイズを残して。しかし、の体は壁へと追いやったままだ。 「……な、あ、あなた、何を……!」 「お静かに。どうやら貴女をお探しですよ」 三好の言葉を聞くと、はひゅっと喉を鳴らして黙った。 「っ、」 視線が忙しなく動き、息苦しそうに胸を手で押さえている。 やはり馬鹿な女だ。全て己が招いたことで、何れかはこうなるであろうことも分かっていただろうに。 意識は後方へとしっかり向けつつ、三好はまるで恋人に語りかけるように言う。 「……氏が自らお探しとは、何をしてしまったんです?」 「わ、私は、」 声を、体を震わすを、じっと見つめる。 「……の家から出ようと?」 ふ、と薄い微笑みを浮かべた三好を見て、はごくりと喉を上下させた。唇を強く噛んで、それは数秒の間だった。ゆっくりと目を閉じ、そして開いた。声は確かに震えている。体だってそうだ。それでも、言葉には芯が通っている。 そうだ、それでいい。 三好は心の中で呟いた。 「――お願いよ、見逃して」 三好は間髪入れず、「何故?」と聞く。 は、視線を落とした。 「……逃げたいの、もう、あの人の傍にはいられない……っ」 「どうして?」 白い頬を、はらはらと涙が伝う。 「も、もう、ぼ、暴力、には……っ、たえられないから……っ! だから、だから、」 その大粒の涙を見ても、三好は薄い微笑みを浮かべたままだ。冷たい指先が、そっとの頬をなぞる。恋人を慈しむような、優しい動きだ。三好の猫撫で声が、「しかし、お一人でどう逃げるつもりです? 貴女には頼れる者はいないでしょう。何せ、相手があの氏ではね」と言う。 「……彼処へは、もう戻れません、戻りたくないのです」 「彼は誰か人を頼むつもりでしょう。それも、力のある相手だ。すぐにでも捕まってしまうかと思いますが」 今度はの唇を、冷たい指先がゆっくりとなぞっていく。 震えているのが、よく分かる。 「……そうだとしても、戻りたくないのです」 「捕まった場合、貴女が苦痛だと感じた以上の屈辱を味わうことになっても?」 は、まっすぐに三好を見つめた。 「仕方ありません。……何もせずに諦めるより、余程いい」 それを聞くと、三好はにやりと笑った。 「成程。……さん、僕に『助けて』と言えますか?」 「え?」 「僕に助けを乞うことはできますかと聞いています」 冷笑的な態度はどこへやら、初めに見せた好青年然とした微笑みを浮かべ、本当に優しい声で、柔らかな口調で話す三好に、は唖然とした。 「ど、どういう意味です? 貴方の仰っていることの意味が――」 の耳元に、三好はそっと囁いた。優しく、柔らかく。 しかし、言葉には芯があった。 「貴女が僕に一言くれさえすれば、僕は貴女をどこへでも逃がしてみせるという意味です」 は、と溜息とも嘲笑ともとれるような声を、は零す。 三好の様々なプライドを刺激するには、十分だった。 「まさか、貴方にそんなこと、」 「『できるわけがない』と?」 「だ、だって、」 「貴女のような素敵な女性をお助けする為なら――僕は、なんだってしてみせますよ」 試すような目で、じっとを見つめる。 の瞳の奥には、不安と、猜疑心と、それから――。 さぁ、どうする? このまま逃げるか? それとも、賭けてみるか。 どっちを選んだって構やしない。 けれど、自分の目に三好は絶対的な自信を持っている。 ふ、とは口元を緩めた。おかしな人、と言うように。 三好も口元を緩める。そして、思う。そうだ、それでいい。 本当に馬鹿な女だ。どうしようもない、馬鹿な女だ。 愚かな女だ。だが、それでいい。 この女は、それでいいのだと。 「……いくらお仲間に自慢すると言っても、する機会がこなければ意味がないでしょう」 「失敗なんてしませんよ。仲間に自慢できなくては意味がありませんからね」 差し出された三好の手に、は自分の手を重ねた。 「……恥をかくことになったとしても、私を責めませんか? ……それなら、助けて下さい。私を、貴方が」 「貴女を責める? 僕が? ふふ、それは恥をかくことになった時、考えることにします。……助けますよ、必ず。僕が、貴女を」 自分を、が選んだ。自らの意思で。誰の為でもなく、自身の為に。 口の端があまりにも自然に持ち上がったので、内心、苦笑を漏らす。 馬鹿で愚かなのは、自分も同じだと。いいや、彼女以上に自分は――。 三好はの手を、しっかりと握りしめた。 街はもう、遠い。 「……そうだわ」 あんなにも、果てはない、どこまで行っても出口はないと思えていた場所は、遥か向こうだ。どうしてあんなところで、一人じっと怯えていたのだろう。今では不思議だとすら、は感じていた。 隣で何ともない顔をして本のページを捲る三好は、呟き程度の言葉をそっとすくいあげた。 「どうかしましたか?」 「貴方、どうして私の名前を――」 「言ったでしょう? 氏の奥様のことなら、誰しも知っています」 は少し間を空けて、「……そうね」と走り回って遊ぶ子供達へと視線をやった。 ちらりと、その姿を三好は追う。 「――なら、貴方のお名前は?」 の言葉に、三好はページを捲ろうとした手を止めた。 「……貴女にお教えできる名前など、僕にはありませんよ」 「……そう」 腕時計を確認すると、三好は「さて、」と言ってベンチから立ち上がった。 が、三好へと視線を戻す。 「ここから先は、お一人で大丈夫でしょう。まさか箱入りの貴女が、街を一人で離れられるだなんて思ってもいませんからね、あの連中は。……これで、貴女は自由だ」 何ともない顔だ。しかし、温かみのある声をしている。 いつも、いつも部屋で泣いて過ごしていた。たまに外へ出てみても、何の気晴らしにもならなかった。それどころか、心の闇は深まるばかりであった。生きていて、何が楽しいのだろう。何の為に、自分は此処にいるのだろう。 もし叶うなら、叶うなら――と何度も、夢見ていたことだった。 「……ありがとう……っ」 の目元を優しく拭うと、三好は笑った。 「いいえ、とんでもない。仲間に自慢できることが、一つ増えただけですよ」 「……ふふ、そうだったわね」 もう一度腕時計を確認すると、三好は「それじゃ、僕はこれで」と名残惜し気にするでもなく、に背を向け、歩き出した。 あの様子では、いつも、いつも泣いてばかりいるんだろうと、すぐに分かった。数えられる程度だが、すれ違うたび、いつも目を腫らしていた。馬鹿な女だ。あんな風に小さくなって生きていて、好きでもない男にいいようにされて、何が楽しいのだろう。好きなように生きる価値がある女なのに、馬鹿だ。愚かな女だ。 もし叶うなら、叶うなら――と何度、想像してみたことだろう。 「三好さん」 三好は、足を止めた。 「……なんです」 ふと視線を地面へ落として、それからゆっくりと振り返ると、三好はの目をまっすぐに見つめた。 も、まっすぐに三好の目を見つめている。 「後で捨てて下さって結構ですから、この場では黙って受け取って」 はそう言って三好の右手を掴むと、それをぎゅっと握らせた。 「……他の男から貰った指輪を、何故僕に?」 三好が薄く笑う。 は、おかしな人、と言うように笑った。 「貴方だからこそよ。私をあの牢から連れ出してくれた、貴方だから。貴方が本当に私を逃がしたのだと、それを見せてお仲間に自慢して」 「だからと言って、随分な贈り物ですね。無粋にも程がある」 「だからこそよ」 「……これでは、忘れるに忘れられませんね」 じっと指輪を見つめる三好に、は少し、ほんの少し口にするのをためらった。 しかし、ずっと――夢にまで見たことだ。それに、これっきりである。 「ええ、そうであるようにと思うわ。……それじゃあ、さようなら」 まず、が背を向けた。 「ええ、さようなら」 三好も背を向ける。 「――お気をつけて」 どちらともが、振り返った。随分と、遠く離れてから。相手の姿など見えやしない。 どうせ、探したところでもう会えない。見つけたところで、もう会えやしないのだ。 二人は、笑った。 |
画像:はだし