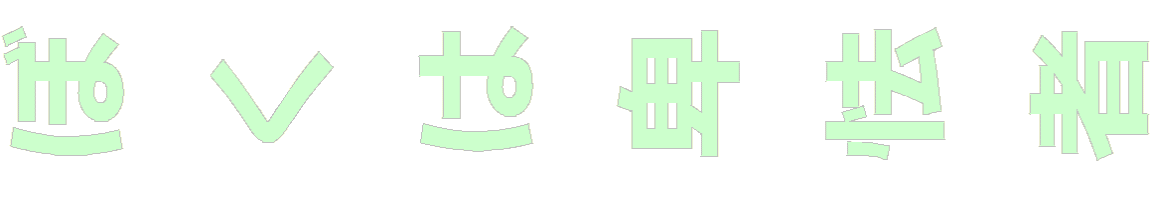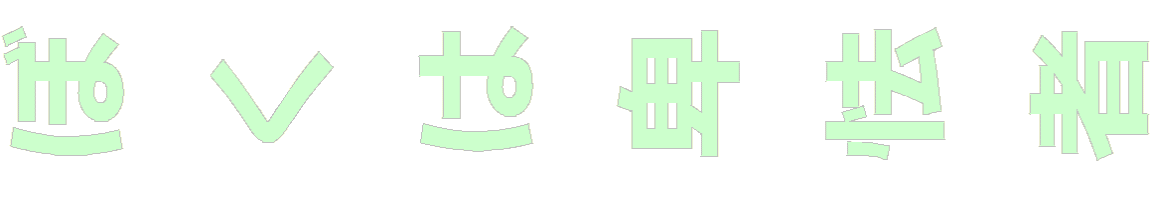傷つけるつもりはなかった、なんていうのは卑怯な男が使う常套句だとぼくは常々思っていた。
そうは言っておいて傷つけるのだから、「そんなつもりじゃあなかった」などと笑わせる。初めから傷つける予定のあるヤツだけが、そんなことを言うのだ。
自分の言動は決して否定しないで、さも何か得体の知れない不思議な力が働いて“そう”なったかのように言って、また相手を傷つける。あまりに無責任で、傲慢だ。
“そういうつもりじゃあなかったから”悪くない、“そういうつもりじゃあなかったから”許してくれ?卑怯な言葉だ。ぼくはもし、誰かにこんなことを言われたら―あくまでイフである。
なぜならぼくは誰かに傷つけられた!などと憤慨したことはないし、当然だが悲しんだこともないからだ―「いい度胸だな。この岸辺露伴によくそんな胸くそ悪い使い古しのチープな
台詞を吐けたもんだ。褒めてやるよ。」くらいは毒づいて、それからこの台詞がどれだけ馬鹿らしくてクソの役にも立たないかってことをよく教えてやるだろう。だからぼくは、彼女が
どんなに泣いたって「傷つけるつもりはなかったんだ」などと言って許しを乞うたりはしない。決して。――そう、そのはずだ。
それなのになぜ、ぼくは言って――いや違う、あくまでも“口走ってしまった”のだ。
ぼくが自分の頭で考えて“言った”んじゃあない。
「…何よ、それ。じゃあ傷つけるつもりがなかったと言うなら、わたしが今こうして情けなく泣き喚いていることに、あなたはほんの少しも無関係だって言うの?
無責任にも程があるわ!」
「いや待て、そうじゃあない!しかしきみはやはり、ぼくの期待を裏切らない女だな。ぼくも“傷つけるつもりはなかった”という台詞についてはまったくの同意見だよ」
きっちり最後まで言い切ってしまってから、しまった!と思った。言うまでもない。険しい顔をしていたは一転、無表情へと切り替わった。これはいわゆる大噴火の前の、タメだ。
参った、こうなるとぼくにも手がつけられない。
もちろん嫌味として「いい性格をしている」と散々に言われるぼくだが、そのぼくすら辟易するのがこのだ。
という女は、理屈が合わないことが大嫌いで実に扱いにくいし、頭の回転が速いせいかそれらしいことを矢継ぎ早に並べたててくるような嫌味な女だ。
出会って最初に抱いたその印象は今でも変わらない。
だからと言って、ぼくはが嫌いなわけじゃあない。だってぼくはこの嫌味なともう3年も付き合っている。対人関係をしているという意味ではない。
男と女の関係を、この嫌味な女と3年も続けているのだ。もちろんそれだけ長く一緒にいるわけだ、喧嘩なんか一度や二度じゃない。
でもは理屈が合わないと思えば、一言謝れば丸く収まることでも絶対に譲らない性格だ。そうなると、喧嘩をすれば謝るのはこのぼくだ。
この岸辺露伴が、嫌味な女に嫌味を返すことすらせずに大人しく。
もちろん付き合い始めの頃はぼくも徹底抗戦だ!とばかりに、「いくらなんでもそれはヒドイ!今すぐやめないと先生とは絶交します!」なんて、
ぼくの唯一の友人である康一くんに詰め寄られるくらいのことはしていた。だが、そうしたところでこのという女はまったく気にした素振りを見せない。
むしろ、「そういうやり方じゃないと自分の正当性を示せないなら、それって本当に正しいのかしら?」なんて涼しい顔して言うのだ。
そう言われたら、いつまでもごねてるのはぼくだということになる。
康一くんはともかく、あのクソッタレの東方仗助にまで大人気ないなどとクソ生意気な口を利かれちゃあぼくも謝るしかない。
康一くんはぼくの顔を立ててくれて、「まァ今回は淡雪さんに譲ってあげて下さい」なんてコッソリ耳打ちしてくれたものだ。
ことあるごとに彼が間に入ってくれたからこそ、3年もぼくたちは一緒にいる。まぁその結果、ぼくは何度も何度も…今もなお淡雪に譲り続けているわけだが。
別れようと思わない自分が心底不思議ではあるが、結局ぼくはこのって嫌味な女がきらいではない。
嫌味な女だと何度も繰り返しているが、ぼくはのそこが気に入っているのだととうに気付いているからだ。
が相手に対して強く出るのは、己の言ったことには決して背かないという絶対的な自信に由来している。
つまり、はぼくと付き合うことに了承した3年前のあの瞬間から今現在、この先ずっと未来永劫ぼくを裏切らない。
だからぼくは喧嘩をしたらまず先に謝ってしまうことにした。
がどんなに口汚くぼくを罵ったとしてもそれは口先だけのことで、彼女はぼくを裏切ったりはしないのだから。
だが、今回に関しては“謝ったから終わり”にはならないだろう。そんなことをもしも言ってしまったら、ますますこの燃え盛る劫火に燃料をやってしまうことになる。
そもそもなぜこんなことになってしまったのかというと、あのクソッタレの仗助のせいだ。
アイツが余計なことを言わなけりゃ、ぼくもあんなバカみたいな台詞を間違って口走ったりしなかった。
ぼくの職業が漫画家だというのはもちろんも知っているし、だからこそ休日にスケッチをしにぶらぶら散歩に出ることに対して何か言われたことは一度もない。
言われたとしても、これがぼくの仕事なわけだから変わらず散歩に出ることだろう。ここまでを理解できる女だから、はいつも黙ってぼくを送り出していた。
時には二人で出かけることもあるが、いくら一緒に暮らしているといっても(言い忘れていたが、ぼくとは去年の暮れから同棲を始めた)いつも一緒に行動するわけじゃあない。
当たり前だ。も自立した立派な社会人であるから暇ではないし、それは極たまのことだった。それでも彼女は、ぼくにくだらない質問をしたりしない。
ぼくのスケッチブックに描かれた女性のことなぞ興味がなかっただけ、ではどうやらないらしいが。この鬼の形相だ、気にはしていたのだろう。
けれど、ぼくが恋愛にどうしても絡んでくる“そういう”面倒事は一切遠慮したいタイプというのも彼女は分かっているのだ。聞くに聞けなかったと想像できる。
まぁつまり、今日ぼくは一人でスケッチに出かけていたのだ。
そしてものすごく想像力を掻き立てられる素晴らしい被写体に出会った(あくまでもぼくの認識ではあれは“被写体”で、“女性”ではない)。
ぼくはスケッチに表へ出たんだから、もちろん描いた。何枚も。色んな角度や表情が欲しいのだ、当然のことだ。ここまでなら、ぼくのよくある日常の話である。
ぼくの不幸、今回の喧嘩の原因はこの後だ。
素晴らしい被写体に出会って、ぼくは上機嫌に家路を急いでいた。頭の中で今にも爆発しそうなインスピレーションを、きちんとした場所でスパークさせるために。
そこへ現れたのがクソッタレの仗助だ。ぼくが急いでると言うのに全く聞かず、強引にスケッチブックを奪ってあの小汚い手でページを捲りはじめた。
ぼくはもう本当に腹の底から怒鳴ってヤツを追い返そうとしたが、ヤツは素知らぬ顔だ。そこでぼくは、「うちでがぼくを待っているから、急いでるんだよッ!さっさと返せよッ!!」
と言った。するとヤツは急に大人しくなって、「じゃあはやく帰りましょーよ、露伴センセ」とぼくの背を押しながらついてくるじゃあないか!
まさかお前、ぼくのうちまで来る気じゃあないだろうなッ!?がいるんだ、遠慮しろよッ!というかは関係なしに、ぼくはお前をうちにあげてやる義理はないぞッ!!
とぼくは色々言ってやったが、あのクソッタレへらへら笑うだけで足を止めもしない。
「ぼくは絶対にお前をうちへあげないッ!いいか、“絶対”だぞ!!“必ず”という意味だッ!!“何があっても”という意味だぞッ!!」
「いいじゃないっすか〜ァ、ちょっとくらい〜。ちょ〜っと茶ァでももらって、サンとお話ししたらすぐ帰るんでェ〜」
道端でこんなようなことを言い合っているところへ、タイミング悪くが現れた。ぼくがスケッチに出かけてからしばらく、彼女も買い物へ出ていたらしかった。
カメユーデパートの中にある洋菓子屋の箱をぶさらげていた。
「あら、今日は早かったわね、センセ。仗助くん、うちへ遊びにきたの?ちょうどよかったわね、ケーキ買ってきたのよ。食べるでしょ?」
ぼくと話すときはいつもツンと澄ました顔をしているくせに、は仗助にはいい顔をする。康一くんが言うには誰にでもそういう“よそ行き用”の顔というのがあるらしいので、
が特別仗助を気に入っているわけじゃあないが。ぼくが「こんなヤツにやるケーキなんてないッ!」「味の良し悪しも分からんヤツにいいものをやるんじゃあないッ!!」
と言っても(が買ってきたケーキというのは、名のあるパティシェの店のものだった)は、「さ、うちでお茶にしましょうね〜」なんて言って仗助をうちへ入れてしまった。
ぼくが建てた!ぼく名義の家に!これだけでとてつもなく不愉快で不幸な話だが、問題は仗助をうちに入れてお茶を飲みながらケーキを食べている最中に起きた。
「それで?仗助くんはどうしたの?」
「ハイ?」
「いやね、めずらしいじゃない。仗助くん、この人のこと好きじゃあないでしょ。スケッチ帰りの露伴を見つけたって、何かしら用がなくちゃあ声なんて掛けないんじゃなあい?」
「おい、ぼくだってこんなクソッタレだいきらいだぞ」
「あぁッ!思い出したッ!!そうなんスよォ〜、いやァ今日ばっかりはこの仗助クンのオトコのカンってヤツがビビッときたんスよねェ!
サン、露伴のヤロ〜サンというこーんな美人なカノジョがいるってぇのに、コレッ!!」
ヤツがバァン!との前に差し出したのは、ぼくのスケッチブックだった。
いつの間にくすねたんだか知らないが、ぼくはうちに帰ってすぐ自分の部屋に荷物を置いていたので間違いなく勝手に部屋に侵入したのだ。それを咎めるついでに、
の仗助を見る目をきちんと正してやろうとぼくが口を開こうとした瞬間、ぼくより早く口を開いていたらしいの声が静かに響いた。
“静か”なのに“響く”なんておかしいだろうが、は声を荒げたりはしていなかった。とても落ち着いていた。それなのに、よく響いたのだ。だからこそ迫るものがあって、
べらべら馬鹿みたいに喋っていた仗助もぴたっと口を閉じた。
「仗助くん、悪いけど帰ってくれる?」
流石のクソッタレ仗助もただならぬモノを感じたのか、そそくさと帰っていった。あれだけうちには絶対あげないと言っていたぼくだが、結局うちにあげて(正確にはが、だが)
ケーキまでご馳走してやった(これもが、だが)のだ。こんな空気にしといて自分だけさっさと退散するなんてせこい真似するんじゃあないッ!と言ってやりたかったが、
まぁできるわけがなかった。なんたって鬼の形相だ。
仗助の間抜けな「お邪魔しましたァ〜」のあと、しばらくどちらも言葉はなかった。口火を切ったのは、今度こそぼくだった。
「あのバカ、一体何がしたかったんだろうな」
まぁ今の状況から見るに、最初のこの一言からもうまずかったんだろう。
「あなたこそ、何がしたいの?」
「…は?」
これもまずかった。
「…スケッチは仕事の一環だし、わたしも今まで特に口出ししなかったわ。そもそもわたしが口出しする権利はないし、
露伴は自分の仕事に対して誠実に向き合ってると思っているから。でもね、理屈はそうでも感情はそうじゃあないのよ。
あなたがどういう経緯でこんな素敵な人をスケッチするに至ったのか、気にならないわけがある?
わたしだって嫉妬くらいするのよ。この素敵な人にあなたはなんて声をかけてスケッチさせてもらったの?
わたしが聞いたこともないような優しい声を出したりするの?
そういうくだらない、とっても面倒な感情ありきのつまらない質問をあなたにしてしまいそうになるのよ。
だから今まで、何も言わなかった。でも、スケッチから帰ってきてあなたが仕事部屋に引きこもる日には、苛々したりするの。
きっと素敵なミューズに出会ったんだわと思うと、いつも胸が張り裂けそうになる。
それでも、あなたが仕事に忠実な人だと知っているから何も言わなかったのよ。
…このスケッチは、あなたが見せようとして見せたわけでもないし、仗助くんも悪意があってわたしに見せたわけじゃあないわ。
これを見せられなくても、わたしはもうこれまであなたのミューズを何度も想像してきたもの。
それが現実として、今回は目の前にかたちをもって在るだけ。あなたがしていることは正しいことで、
わたしが言っているのは自分勝手な筋の通っていない我侭よ。
でも、仕事に誠実で…絵と向き合う活き活きとしたあなたをすきになったのに、辛いとか、悲しいとか、思ってしまう。
そういう上っ面だけの感情に流されてしまう自分が、とっても情けないの」
ここまでは、ぼくにたったの一言すら許さなかった。
そして黙って彼女の言葉を聞いていたぼくは、ほんの少しばかり、彼女をかわいい女だと思った。
いつもツンと澄ました顔でぼくに嫌味を浴びせるくせに、心の中にはそこいらにいる女と変わらない嫉妬なんてものがあるのかと。
きみはいつもお高くとまっているくせに、こんなことで泣いてしまう女だったのかと。
上っ面の感情に流されてしまうのはとても情けないことだと彼女はこの時言ったが、ぼくもそう思う。
なぜって、ぼくもその“上っ面の感情に流されて”つい口走ってしまったのを後悔しているからだ。
そうだ。ぼくは心の内を吐露したを、ほんの少しばかりかわいいと思って言って――いや、“口走って”しまったのだ。
「…ぼくが悪かった。でも分かってくれ、決してきみを傷つけるつもりじゃあなかった。
ぼくはきみの言う通り仕事に真剣なつもりだが、かといってきみが大事じゃないというんじゃあな――」
「なんですって?」
「だから、ぼくはきみが」
「あなたは二人の時間をちっとも作らずにいつでも気が向けばさっさとスケッチに出掛けて、
帰ってきたら気が済むまでずぅっと仕事部屋から出てこないどころかわたしが声を掛けても返事すらしないけど、
決してわたしを“傷つけるつもりじゃあなかった”と、そう言うの?」
「……!い、いや、違う、ぼくが言ったのは“そういう”意味じゃあないんだぜ、、」
「…何よ、それ」
…と今に至るわけだ。まぁぼくとの間柄は世間で言う“恋人”ってヤツだから、こういう場合はやっぱりぼくが悪い。もちろん、仕事をないがしろにしろというのじゃあない。
仕事があって、その仕事がとても忙しくて他人になぞ構っていられないという前提があっても“恋人”をつくるのなら、“恋人”という役割もそれなりにこなせということだ。
これは康一くんの受け売りだが、ぼくもこれは理解できる。
と付き合う以前のぼくは何事もすべて自分だけで完結していたので、全くワケが分からんと思っていたが、今なら分かる。
自分一人でも完結してしまうようなことでも、二人でするから生まれる意味があるということが。
けれど、二人でするからにはやはり意見が合わず衝突することもある。違う人間なのだ、至極当然のことだ。
一人はすべて自分自身の決断で物事が決まるし、他人に対して責任もないから気楽でよかった。
ぼくだけで済んでしまうのだから、ぼくはぼくに対して無責任でいたっていいのだ。
それでもぼくは、一人に戻ろうとは思わない。どれだけ喧嘩をして、どれだけこのぼくが頭を下げなくてはならなくとも。
「大体ね、わたしと同意見と言うのならなぜ言うの?あんなに腹の立つことを。まあ、わたしが心配して食事を作ってもあなたは部屋から出ないし、
声を掛けたって返事すらしないような人ですものね!“そういう”つもりで言ったのよね?傷つくだろうなと思って言ったのよねッ!」
無表情でぼくを責めるの目元は、うっすらと赤い。
「すまない、悪かったよ、だから、ぼくの話も聞いてくれ!」
「なによ、勝手にお話しになったらいいじゃあないですか。わたしだっていつも勝手にしていますよ、あなたが返事をくれなくたってねッ!」
熱中しすぎて、時間の経過が分からなくなることはよくある。ぼくは食べることすら忘れてしまう。けれどぼくがやっと空腹に気づいた時、いつも食事は用意されている。
ぼくはそれを当たり前のように食べていたけれど、そうではないのだ。
「…そうだよな。ぼくは熱中するとそのことにしか目がいかなくなるようなところがあるし、
きみが心配してくれてもその気持ちを踏みにじるようなことをしてきたと思うよ。反省している」
「…でも“そんなつもりじゃあなかった”んでしょ?」
ぼくはを嫌味な女だと散々に扱き下ろしてきたが、本当はまったくそうではなかったのだ。
ほんとうにが嫌味でお高くとまった女だったなら、ぼくらはとうの昔に別れていたことだろう。
ぼくは彼女にとって、長い間とても“卑怯な男”だったのではないか?
そうならば、ぼくもここいらで真実“誠実な男”になってみせなければ。
「待ってくれ、そう言ってしまったことも謝る。でも“そういうつもりじゃあなかったから”許してほしいと謝るわけじゃあないんだぜ。
ぼくがきみを傷つけてしまったことは事実だし、ぼくはあまりにも無責任で無神経だった。
だから“今後そういった言動を一切しない”ときみに誓うために、過去のあやまちを謝罪するんだ」
そう、それでどうやって?とは言った。
ぼくは答えた。
「、ぼくと結婚してくれ」
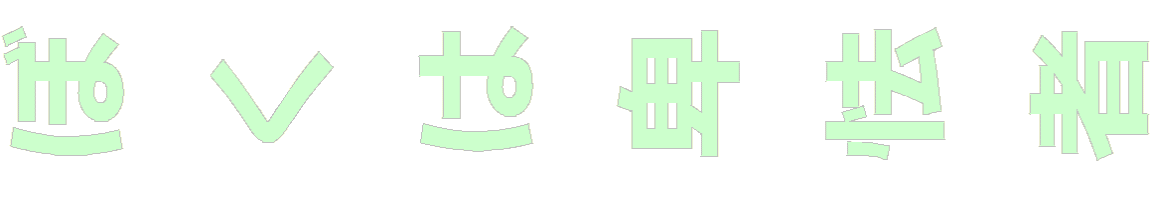
photo:はだし