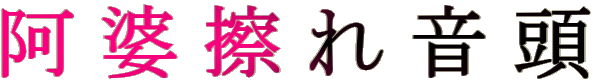どうしてって、女って生き物はみんな美しい。素直で従順な女ならば、オレはこれでもかという程に甘やかして尽くしてやりたいと思うし、はねっかえりのお転婆ならばオレはどこまでも後を追ってみせる。男には理解出来ないような直情的な思考は興味深いし、何よりその“感情”に生きる姿は頼りなく繊細で可愛い。男がどれだけ正論を並べようと、どれだけ論理的に物事を説明しようと“彼女”たちには関係ない。正しいかそうでないかは別で、好きか嫌いかなのだ。洋服が決まらず遅刻したのなら、前日のうちにある程度の予想を立ててあらかじめ用意しておけばいい。そうしたら遅刻はせずに済んだはずだ。“彼女”たちにとってすればそんなことはどうだっていい。確かに遅刻は悪いことだけれど、あなたの為にお洒落しようと頑張ったのにひどいわ。それに、そんなこと言われなくたって分かってるのよ。わたしのこと、好きではないの?嫌いだからそんなに怒るの?これだ。まぁ当然、男の方にはそんな理屈は通用しない。でも、許してしまうのだ。女は感情に生きる生き物だ、というのはオレの自論だがあながち間違いじゃあないだろう。こちらのことなんてお構いなしに、どんな無理難題でも「わたしが好きならできるでしょう?できないのなら、わたしが嫌いってことなのね」なんて酷い台詞をいとも簡単に口にする。でもオレは、女という生き物を美しいと言わずにはいられない。感情というものにこれが正しいと言える正解はないし、ましてや目に見えないものを言葉で明らかにしようというのも無理がある。それに、移ろうものだ。だからこそ、その瞬間に感じたままに生きるということはとても尊いことだとオレは思うのだ。そしていつ変わってしまうかも分からない儚さというのが、また堪らなくいい。それに、今この瞬間この女はオレを好きだと言うが、明日は?明後日は?そういうスリルがあった方が面白い。だからオレは、女という生き物が心底愛おしい。 けれども、その尊く美しい生き物の中で一等好きなのがだ。オレの恋人である。彼女はオレが最も尊敬する女だ。前述の通り、女という生き物はみな等しく美しいものだとオレは考えているが、彼女はその中でも群を抜いている。まず容姿だが、衣通姫もかくやあらんといった具合の美女だ。絹のように白く輝く肌は瑞々しく、触れてみればなめらかで指先に吸い付くようだ。髪も艶があり手入れがよく行き届いていて、手櫛で梳けばさらさらと指の間を心地良く通り抜ける。そして極めつけに、薔薇色の唇だ。ありがちな喩えだが、のは特別素晴らしい。あの唇を目にしたら、どんな男だって虜になる。硬派を気取った身持ちの堅い野郎だって、瞬く間にあの魅惑の唇に噛みついてしまうだろう。そして病みつきだ。けれど何よりの魅力は、の心根だ。誰にでも分け隔てなく、彼女は優しい。困っている人間を捨て置くことが出来ず、悲しむ人間の涙を掬ってやって、寂しがりの傍にそっと寄り添う。オレは女という生き物を尊敬している。だから沢山の女たちを見てきた。過去を振り返れば、やはりどんな女もオレには可愛い姫君だった。彼女達は、美しく尊かった。だがその中の誰より、いいやこの世のどんな女も敵わないだろう女。それがだ。こんなにも素晴らしい、オレの女――――。誰もが羨む、オレだけの姫君。
そうでなけりゃ、オレは彼女のしていることを説明できない。感情に生きるということは常に正しい言動を選ぶということでないとオレは先に言ったし、それが美しいとも言った。だがオレは敢えて言おう。彼女の言動は決して正しくない。は美しい。だが、正しくない。間違っている。けれど間違っていると指摘してしまえば、彼女の存在そのものを否定してしまうことになるのでオレは間違っても「お前は正しくない」なんて口にはしない。だがは、彼女を構成しているもの全てが狂っている。だから間違っているのだ。そうでなきゃ、どうしてだ?はオレを好きだと言うその唇で、他の誰かにキスをする。誰をも虜にする、あの唇で。オレの女なのに、オレを好きだと言うクセに。ほらどうだ?誰がどう見たって彼女のことを正当化できるはずがない。でもオレは、そういう女をあいしてしまったのだ。馬鹿らしいことに。 だから昨日彼女がどこで何をしていたのかなんてこと、オレには関係ない。そう、彼女は―――と言うのもおかしな話だが、女という生き物だ。だからその都度その都度、“感情”のままに行動する。その理由を男のオレが理解なぞ出来るわけがない。けれどオレには前提がある。彼女がどこで誰と何をしていようと、オレは彼女をあいしているし何より大切だというのは変わらない。それに一番大事なのは、どこで誰と何をしようとがオレの女であるという事実だ。だから、そんなつまらないことを知る必要はない。 不毛だと、人は笑うだろう。でも笑われたってオレは一向に構わない。笑いたきゃ笑え。オレだってできるもんなら「馬鹿じゃねえの」と笑ってやりたい。じゃなきゃ可哀相だろう、オレという男が。そしてオレと同じ目に遭っている顔も知らない野郎共も。 けれど、嗚呼、この何の混じり気もない微笑みを見たら。 「ああ、ごめんね、ヒノエ。待たせちゃった?」 美しいあの薔薇の花には棘がある。オレはその棘ごと薔薇を愛そう。そのいじらしさが可愛いと、笑ってやろう。愚かにも、オレはそう考えてしまうのだ。憎くも愛らしい、オレの恋人。見ろ、この女を。道行く誰もがオレを羨み妬む。ちくしょう、やっぱり死ぬほどかわいい。久しぶりのデートに遅刻してきたって、こうしてオレの目の前にちゃあんと姿を現すのだ。散々に振り回して月に帰ったりはしない、オレの姫君。オレはが笑顔になれるというならなんだってしてやれる。たとえコイツが(忌々しいことに)オレの叔父にあたる弁慶とも付き合ってるとしても、だ。たとえコイツが昨日将臣とふたりっきりでどこかへ行っていたとしても(しかもオレとの約束すっぽかして。そうだ、本来なら昨日がデートで今頃はゆっくり部屋で映画でも楽しんでるはずだった。しかも遅刻してきたところから推測するに、朝帰りだったに違いない。勿論、邪推であればいいが)。たとえコイツがオレ以外にも五人、男がいたとしても(弁慶、将臣除く)だ。そうすると男が八人、日替わりで違う男とデート出来る計算だ。一週間が七日と考えりゃ、一人ドタキャンになっても“スペア”がいる。本当によく計算出来てることだ。清純(そう)で高潔(そう)なのは見た目だけで、この女ときたらあっちにふらり、こっちにふらり。気まぐれな猫と言えば聞こえはいいが、世間ではそんな浮気は認められない。が、それを黙認してまでも付き合う馬鹿ってのがいる。……その馬鹿っていうのは、情けないことにオレのことなんだけど。だがあの弁慶もの男癖の悪さを知っていて、しかも(忌々しいことに)甥っ子のオレの彼女だってことを承知の上で付き合っていやがる。あいつも大概、頭がおかしい。今に始まったことじゃねえけど。つまり、どいつもこいつも頭がおかしいってことだ。だいたい将臣の野郎だってオレとが付き合ってることを知っている。アイツもマジで馬鹿。けど野郎のことばっかり責めたって仕方ない。いいや、そもそも悪いのはただ一人だ。美しく儚い生き物だと知ってはいるし、だからこそ尊い。けれどお前はどうして、そういう恋しか出来ないのだろう。どうしてオレの愛情をまっすぐに受け取ろうとしない? きっと聞いてみたところでは曖昧に笑って誤魔化すだけだろう。そんな悲しいこと、オレはこの女にさせられない。だって、“その時”に生きているのだ。言ったら最後、オレとは付き合えない、とか意味の分からない理由でオレなど簡単に切り捨てるだろう。こうして考えてみればみるほど、いいことなんて一つもない。憎らしくて恨めしくて、怨んでも怨んでも足りない。なのに、それでもオレは彼女をあいしているのだ。恋を語る分にはそれ相応の経験も積んできたが、愛を語るにはまだ未熟だというのは分かっている。でもこんなにも狂おしい激情だ。オレはこれを、愛と呼ばずにはいられない。そうでなければ本当に、オレはおかしくなってしまう。狂っているのは、本当はオレの方なんじゃないのか?ずぅっと心の何処か片隅にあった疑問に、自ら答えてしまう。嗚呼、いっそ殺してオレだけの恋人にしてしまいたい。オレの心の中にだけ生きる、永遠の恋人としてずっとあいし続けていたい。彼女は何も言わず、オレの愛の言葉にただ頷くだけだ。なんて魅力的なんだろうか。そんな風に。 けれどオレはまだ、綺麗な言葉で“この時”を飾り立てていたい。オレを好きだと想うの“一瞬”を繋ぎ合わせて時間を刻み、二人の未来をつくりたい。そんな希望を持っている。この大輪の華の色を奪ってしまうのは、どうも気が引けてしまうのだ。女は美しい。女は儚い。女は尊い。その中で唯一、オレがあいする女。 「…お前は今日も可愛いね。その瞳に吸い込まれてしまいそうだよ」 甘い言葉で気を引いて、そのうちに赤い唇を丸ごと奪ってしまうおう。どんどん深みにハマっていくだけだとしても。感情に生きる生き物なのだから、彼女はいつだってどこへなりとも行けるのだ。オレを残して、どこへでも。 「――――本当にごめんなさい、待ったでしょう?…でも、こんなところでキスなんてやめてちょうだい。人目があるでしょう」 「見せつけてるのさ。こんなイイ女がオレのもんなんだってね」 「…ばかね。わたしはいつだってヒノエだけのものよ」 衣通姫もかくや、とオレは思う。完璧だ。どこをとっても、素晴らしく計算し尽されている。 男は―――オレは、この女を放り出せやしないだろう。頭の中では、どう思おうと。 「ふふ、それは光栄だね。さあオレのかぐや姫、今日はどんなお願いをしてくれるのかな?」 「あら、そんな期待されたら…とっておきをあげたくなっちゃうわ」 「おや、オレには叶えてやれないと思うのかい?」 オレがをあいしても、はオレを愛さない。 オレはは心根が云々とぺらぺら訳知り顔で語ったが、あんなのは嘘っぱちだ。誰にでも分け隔てなく優しいのは、が誰をも愛してなどいないからだ。困っている人間を拾うのも、悲しむ人間の涙を掬ってやるのも、寂しがりの傍にそっと寄り添うのも、誰にも執着心がないからだ。 「いいえ、そんなことは少しも思わない。わたしがあなたのかぐやなら、ヒノエはわたしの帝だもの」 よく言うよ。 オレは女には特別やさしい性質だと言ったけれど、お前みたいな女に対する口説き文句なんて本当はたった一つだけだよ。 この阿婆擦れ! |