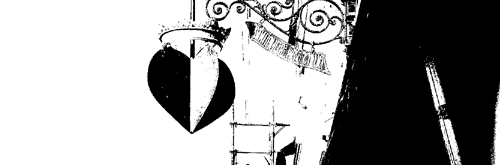
| まず、其の女の話から始める事にする。 其の女と云うのは、此の界隈(かいわい)では「プリマドンナ」と呼ばれている、あの、女の事だ。噂だけでは到底信じられない様な魅力の持ち主、プリマドンナ。彼女は、夜の社交場「レディナイトダンス」と云うナイトクラブの奥で、暮らしていた。時間やルールに縛られる事無く、其処で、生きていた。まぁ、此処らで生きる人間はどれもろくでなしばかりであったから、大抵が彼女と同じ様な暮らしをしていたが。 超がつく有名高級娼婦を置いているナイトクラブ、レディナイトダンス。 其処は夜の社交場と銘打った、マフィアばかりの娯楽施設。 私は彼女を、誰よりも近い場所からいつも見ていたから、どれも嘘でない。 金、欲望、そして愛とが渦巻く夜の闇で、私は見た。 汚れたもの、美しいもの、決して全てとは言えないが、私は、見た。 汚れたものは、彼女が私には見せない様にとしてくれていたから、あまり詳しく話せないかもしれない。だが、儚くはあったが、とても美しかったものはよく知っているから、それは詳しく話す事が出来る。 あれから随分と長い年月が過ぎて、彼女に触れた人間はもう存在しない。 其れでも語り継がれる、プリマドンナ。 レディナイトダンスで生きた、女と、レディナイトダンスに生きた、男達の話。 真っ赤な芳香の口付け 甘い朝の香りで目を覚ました女は、その直後、ひどく気分を悪くした。 隣で、満足そうに眠る男を見つめて、顔を顰(しか)める。 「……フランシス、おいで」 毛並みの整った美しい黒猫が、ひらりとベッドに飛び乗る。 女が喉元を擽(くすぐ)ってやると、その白く長い指先に舌を這わせ、媚びる様に小さく鳴いた。 「フランシス、いい子だから、解かるわね?」 女がそう言うと、猫はベッドから飛び降りた。猫のフランシスは、人の、彼女の言葉を理解出来たかの様に、一声鳴くと、直(すぐ)に部屋を出て行った。 そして女は、誰もがうっとりとする様な甘い笑みを浮かべ、隣で眠る男をベッドから蹴り落とした。 *** 「プリマドンナ、どうしてだい、こんな仕打ち、酷いじゃないか、プリマドンナ、プリマドンナ、」 さっさと着替え始めた女に、男は泣いて縋った。 しかし女は、そんな男の嘆きに耳を貸そうともせず、化粧台へ向かう。 「君の為だけに、何億という金を使ってきたんだぞ、それを君は、」 「レディナイトダンスには、億の額で泣き言を吐く男性は必要ないわ」 口紅の色のみを気にしながら、彼女はそう言った。薔薇、血の色を思わせる真っ赤なルージュは、女の形の良い唇を魅惑的に彩っている。男は其れにうっとりとしてしまうものの、慌てて化粧台の脇に座り込み、女の気を引こうとした。しかし女は、やはりそんな男の健気さなどに興味は無く、さっさと化粧台から立ってしまった。そんな女の冷たい態度に、男は強く歯を噛み合わせる。そして、昂(たか)ぶった感情のまま、女の化粧台を乱暴に蹴り倒した。高級感を漂わせた大きな扉に向かっていた足を、ぴたりと止め、女は視線だけを男へ遣(や)った。 「……どういうつもりかしら。その御化粧台、とっても大事な御方に頂いたものなのだけど」 「!なぁ、俺を捨てないでくれ!何でもくれてやるから、お願いだ!」 プリマドンナ、が溜息を吐いたと同時に、重い扉が音を立てた。其の向こうには、黒のボルサリーノを深く被った男。が唇のみで言葉を形作ると、ボルサリーノの男は、意地の悪そうな笑みを浮かべた。 「フランシスは、躾(しつけ)がなってる良い猫だな」 「勿論ですわ。オーナーがわたくしに御預け下さった猫ですもの」 「……それにしても、最近は躾のなっちゃいねー犬が多くて困ったもんだ」 ボルサリーノの男の鋭い目は、男を、捉えている。 男の浅い呼吸が、室内を支配する。 「っ、き、貴様っ、どういうつもりだ、」 「あ゛ぁ?テメーこそどういうつもりだ。 そのスペッキエーラはウチのボスがコイツにくれてやったモンだぞ」 其処で男は、気付いた。 気付いて、しまった。 何故、男の姿を此の目で捉えた瞬間、思考が其処まで回らなかったのか。 黒のボルサリーノ、鋭い光を放つ、切れ長の瞳。 何より、此れ程の殺気の持ち主となれば、奴しか、考えられないと云うのに。 「ボ、ボンゴ……ぐあっ!……あ、ぁ、」 「遅ぇんだよ馬鹿が」 乾いた銃声に、は嫌な顔した。 錆びついた鉄の臭いが、部屋を満たしていく。 其れに気付いてか、ボルサリーノの男は彼女に歩み寄ると、直様(すぐさま)深い口付けを贈った。 「んっ、ん、ふ、ぁ、っ、」 真っ赤なルージュに染まったであろう己の唇を一舐めすると、もう一度、彼女に小さな口付け。は、ボルサリーノの男、リボーンの首に腕を回すと、今度は彼女の方から口付けを贈った。男の死体など、二人の頭にはさっぱり残っていない。ただ、段々と濃くなってくる錆びた臭いに、時々眉根を寄せるだけだ。 フランシスは二人の様子を見て、 ふらりと部屋から出て行った。 |