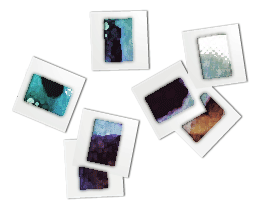
扉の開く音で、わたしの意識はぼんやりと浮かび上がってきた。読書をしていたはずが、懐かしい夢を見ていた。今でも――今までずっと忘れたことなんてない、あの頃の夢を。素晴らしく輝いていた三年間だった。そこで得たものはあまりにも大きくて、時々こうして無意識のうちに溢れ出してしまう。あまりにもはっきりと夢の内容を覚えているので浅い眠りだったのかと思ったが、それにしてはあまりにも安らかな気分だった。 いつも、どんな時でも、わたしを気遣って小さく小さくしようとしてくれているのに、わたしの耳は彼のそんな気遣いなんて知らないとでもいいたげに、その音を聞き漏らすことはない。そろそろと、足音が近づいてくる。わたしはソファからゆっくりと体を持ち上げて、彼がドアノブに手をかけるまえにと立ち上がった。 「うわぁっ、びっくりしたぁ! ってばまだ起きてたの? 寝ててよかったのに」 「ん、今起きたところ」 「起こしちゃった? ……ていうか、その様子だとまたソファで寝ちゃったんでしょ! だめって言ってるのに」 徹くんはちょっと拗ねたようなそぶりで、薄い唇をつんととがらせる。こういうところは、あの頃と何も変わらないなぁと思う。まるで、魔法にかけられたみたいな気持ちになる。そう、魔法。 彼の言動すべてが、まるで魔法でも宿っているかのように人々を魅了していた。女の子はみんな彼に憧れて、男の子はみんな彼についていった。あの頃――そんな魔法にかかっていた日々は、毎日が特別だった。それは今も変わらないどころか、どんどんその魔力は強くなっているような気がする。わたしは徹くんと出会った日から今までずっと、彼が操る魔法を間近で見せてもらえている。幸せなことだ。 わたしには、これ以上の幸福はない。 「今日はどうだったの?」 「んー……うん」 彼にしては歯切れの悪い返事だな、と思った。うまくいかないことでもあったのだろうか。でも何にせよ、徹くんは自分の力でなんとでもできる人だとわたしは知っているから、彼が自分で話そうと言うまでは何も聞かない。 徹くんは大学を出てすぐ、企業チームではなくプロ入りした。彼はやるならとことん極めるひとだから、それもそうかと納得するまでもなく、ごく自然に受け入れた。一緒に暮らすようになったのは、彼の実力が認められて、多くのスポンサーを得てからだ。示し合わせたわけでもなく、どちらが言い出したわけでもなく、わたしたちは買い物のついでに不動産屋に寄って、その日に見学をさせてもらって、すぐこの部屋へ越してきた。それからは、わたしは普通にOLとして働いて、家のことをする。徹くんはひたすら練習に打ち込んで、月に何度かは契約を結んでいる企業でのイベントに参加したり(その中には彼の“サイン会”なんてものもある)、バレー教室の先生をやったり――あと最近はCM出演が決まった――毎日忙しくしている。 わたしたち二人は、そういうふうに暮らしている。 徹くんは初め、わたしにばかり家事を押しつけるわけにはいかない、一緒に暮らすんだから分担しようと言って聞かなかったけれど、わたしの頑なな態度にどうやら諦めてくれたらしく、ここのところ何も言わなくなった。毎日毎日、「もうしつこいな!」とわたしがちょっと声を張るくらいには言ってきたのに。 徹くんが言っていることは分かるし、なんでもいいから何かを彼に頼むことで、罪悪感もぬぐってあげられるのは分かっている。けれどそれ以上に、わたしは“及川徹のバレー”を望んでいるのだ。 徹くんにはいつでも思う存分に練習してもらいたいし、思う存分にバレーのことを考えてもらいたい。そのためにわたしは彼のそばにいるのだ。だってわたしはずぅっと昔から、彼に“先”の舞台まで連れていってもらうと決めているのだから。約束を破られたら困る。だってわたしは、徹くんのかける魔法をすっかり信じている。しかもその魔法は、夢や幻なんかじゃなく、ほんとうに存在しているのだ。だからわたしは徹くんを信じている。 ずぅっと、昔から。 及川徹の大きな手が、その繊細な指先が生み出す、魔法の力を。 「……ねえ、」 「なぁに」 どさっと勢いよくソファに座った徹くんの隣に、わたしも大人しく座る。これだけ長くふたりでいると、今相手がどういうことを考えているかとか、ちょっと予想できてしまうのは残念だ。もちろんそれはひどく曖昧なものだけれど、なんとなく絡めた指先がこんなに震えてちゃ、今緊張してるなぁってことくらいは誰にだって分かってしまうだろう。でも、隣で何でもないような顔をしながらも震えている彼には、こんなにも長くそばにいて、今まさに隣に座ってまでいるわたしの頭の中を想像するほどの余裕はないようだ。 徹くんはきゅっとわたしの指先を握って、体をこちらへ向けた。 「……。長い間、本当にありがとう」 「うん」 「俺、代表入り、決まった」 「うん」 「……“ここ”まで、きたよ」 「うん、そうだね」 会話だけを切り取ったら、きっとなんて淡白な恋人なのかしらね、と彼のファンに言われてしまいそうだけれど、こうなることはわたしの中では決まりきっていたことなので、爆発的な喜びよりも、しみいるような感動のほうが似合っていた。徹くんも、わたしがつらつら言葉を並べることは望んでいないだろう。 「それからね、」 だから徹くんは、わたしに「おめでとう」をねだったりしない。 「うん?」とゆるく返事をして、そういえば帰ってすぐ、徹くん飲み物すら口にしてないな、と思って立ち上がろうとしたところ、「待って、今聞いて」と神妙な声で言うので、元の位置へ座り直した。 すると徹くんはゆっくりと立ち上がって、わたしの足元に跪くと、わたしの膝に小さなリップノイズをたてて口づけた。 「……迷惑とか心配とか、とにかくいろいろ、大変な思いさせて、苦労ばっかりかけてきたけど……これからも、そばにいてほしいんだ」 きゅっと眉根を寄せて、まるで苦しいとでも言いだしそうな顔をしているものだから、わたしは思わず笑ってしまった。 「そんなの当たり前でしょ。じゃなきゃこんなに一緒にいないよ」 徹くんはそれには何も応えずに、跪いたまま、ジャージのポケットからブルーの小箱を取り出して、さらにその中に収められているものを指先でそっと持ち上げて、わたしの左手の薬指に近づけた。今度は、わたしの指先が震えている。 「――だからつまりね、結婚してほしいの」 返事はもちろん決まっていることだけれど、わたしはどういう言葉で応えたらいいのか分からなくて、ただ頷いた。すると徹くんはわたしの唇にそっとキスを落とすのと同時に、しっかりと指輪をはめてくれた。それからしばらくの沈黙のあと、わたしはやっとふさわしい言葉を思いついた。 「うん。……まだまだ“先”の舞台、連れてってね」 *** 代表入りが決まったと聞いた瞬間、あの頃の――俺の高校三年間の中で、一番輝いていた頃のことを思い出した。毎日が、特別だった。岩ちゃんがいて、マッキーがいて、松つんがいて、それから――がいた。 最後の春高、試合が終わってすぐは、なぜだか心は凪いでいた。応援席に挨拶に向かったとき、と目が合った。試合前に少しだけ話をしていた。その当時でも憶測だったし、今となってはもう聞けもしないけど、そういえば中学時代に一度だけ、彼女がきっと泣いただろうと思ったことがあったなぁ、となんとなく思ったのは今でも覚えている。 勝っても負けても、はいつだって涙なんて見せなかった。あの時も、泣くことはなかった。俺はきっとこの先も――いいや、この“先”こそ、彼女の泣き顔を見ることはないだろう。 先生たちにご飯奢ってもらっといて、バカみたいにラーメン食べて、なんでか全員自然と体育館に足が向いて、みんなでバカみたいにバレーをした。はいなかった。俺は、そこでやっと大いに泣いた。みんなで、大号泣した。はあの時間、何をしてたんだろうか。これも今となってはもう聞けないことだ。聞いたところで、どうなる話でもない。 ただ、散々バカやって散々泣いたあとの帰り道、岩ちゃんに言われたことがある。 「お前は多分、じいさんになるくらいまで幸せになれない」 「たとえどんな大会で勝っても、完璧に満足なんてできずに、一生バレーを追っかけて生きていく」 確かに、そうかもなぁとかぼんやり思ったけれど、俺は何も言わなかった。だって岩ちゃんの言う通り、俺はバレーボールを追っかけて生きていきたいのだ。たとえ完璧に満足なんてできなくても。俺は、そういう生き方をしたいのだ。でも、その時には“先”がどこにあるのかイメージできなかった。 でも、俺は今、きっと満足げな顔をしているに違いない。 あの頃はイメージできなかった“先”が見えてきた。 けれど、今度は確信をもって思う。 俺は岩ちゃんが言っていた通り、完璧に満足することはないのかもしれないと。 だって、“まだ”だ。 まだ、この“先”がある。それがどこなのか、この道はどこまで続いているのか、それは分からない。でも、まだこの“先”があることは確かだ。俺は、ずぅっと昔から決めている。 ――“そこ”へ必ず、を連れていくと。 |
画像:HELIUM