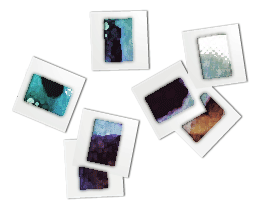
――及川の前じゃ泣けないんだってさ。妬けるよなァ。 なんとなしに、ぼんやり呟くようなその言葉の意味を、俺は知っていた。けれど花巻はそんな素振りを見せたことは一度だってなかったし、俺も直接聞いたわけではないからなんとも応えなかった。 「、及川と同じ大学なんだよな」 はちょっと俯いて、「うん。……いい加減、追いかけすぎかな? あはは」なんて応えたので、自分から聞いておいて俺はどういう反応をすればいいのか分からなかった。花巻の言葉を思い出したからだろうか。ズッとパックジュースの中身を吸いあげると、俺も気づけばなんとなしに呟いていた。 「及川から離れようとか、支えてくの『もう無理』とか思ったことないの?」 はほんの少し驚いたような――面食らったという顔をして、ぱっと俺の顔を真正面から見た。取り繕うように、「ほら、あいつウザいっしょ」と笑ってみせたが、うまく笑えているかは確認のしようがない。 は笑った。俺が――俺たちがよく知っている、なんの混じり気もない笑顔だ。何を気にするでも疑うでもなく、ただ純粋に“信じている”目は、俺にはちょっと眩しくて、思わず目を細めてしまう。この三年間、ずっとそうだった。なんの躊躇いもないの目はいつも頼もしくて、その目に映っている自分は同じく純粋に信じることができた。俺だけじゃない、全員がそうだったと思う。 だから俺は、次のの言葉に、うまく応えられるとは思えなかった。 「そんなこと、一瞬だってないよ。徹くんが目指してる舞台に連れてってもらうって、ずっと前から決めてるもん」 “一瞬”だってない。 数々の勝利を得てきたが、どうしても勝てない試合もあった。そして、最後の最後に経験した敗北は、今までで一番辛いものだった。俺がバレーから離れても、俺がいくつになっても、ふとした時にきっと思い出すだろうとすら思う。それだけこの三年間は、とても楽しくて、とても辛くて、最高の喜びに満ちていた。俺のバレーは、ここで終わるんだなと、ぼんやり思った。大学生になっても、社会人になっても、その気になればいくらでもできるのに。俺にはこの三年間がすべてで、もうこの先はない。ぼんやりとした感覚であっても、確信があった。 けれど及川は――。 あの、お調子者で、それだからよく笑って、いつもなんだかんだと岩泉に殴られて、情けなくて。そして何より、俺たちの最高に頼れる主将だったあいつだけは、この先もずっと、満足のいくまで――いいや、あいつが目指しているところ(それが“どこまで”かは分からないが)まで、を連れていくだろう。及川はそれをに約束していたんだろう。この三年よりもずっと前に。それをも信じて、一体“どこ”なのか分からない“先”の舞台までついていくと決めている。 「……お互い、ほんとに信頼してんだな、お前ら」 「え? うーん、そうかなぁ……普通じゃない?」 だって、先のことなんて誰にも分からない。今日のことはもちろん、それならば一瞬先すら予知できないし、明日のことなんてもっと分からない。自分の未来も想像できなければ、他人の――それがいくら親しくとも――未来を想像することだってできるわけがないのだ。 それなのに、及川はずっと先の未来を見ている。それも、想像なんかではないだろう。あいつのことだ。必ず、その未来を叶えるはずだ。それだけの努力をできる男であると俺は知っているし、それだけの根性がある男だとも知っている。どれだけお調子者と言われて、主将のくせに締まりがなく笑われて殴られて、情けなくても。バレーに対する情熱は、きっと誰にも負けない。だから俺は、きっと及川はとの約束をたがえることはないだろうと思う。俺たちが信じてきたのは、そういう男だ。 けれど、その男に負けず劣らずなのが、このという、一見か弱そうな――どこにでもいるかわいい女の子であることは、きっと俺たちしか知らないだろう。は及川という男を三年(中学を含めれば六年か)を、ずっと支えてきたのだ。誰よりも近いところで。及川のバレーに対する情熱、その姿勢には本当に頭が上がらないが、それゆえにとの衝突も少なからずあったのではないかと思う。それは「バレーとわたし、どっちが大事なの?」なんてものじゃなく、もっと奥深いものだったはずだ。だからこその絆がふたりには存在していて、お互いをこれほどまでに無条件に信頼しあっているのだ。俺たちがいつも、勝利だけを見ることができたその目を持っているのは、だけだ。その彼女はこれから――これからも変わらず、その目に確固たる自信があるというような目で、及川の勝利だけを見つめ続けるに違いない。 そんなふたりの関係が、“普通”だなんてあってたまるか。 そんなこと、簡単にできるもんじゃない。 それでもふたりはお互いを信じている。他人がいくらああだこうだと口を出してみたところで、それは一切変わることはないだろう。もうお互いにお互いを疑う余地すら、きっとないのだ。何を言わずとも、ただ信じている。ただ、信じられている。及川とのふたりには、それだけで充分なんだろう。これまでの時間や経験の積み重ねのうえで、それだけがあれば充分であるという確信がふたりの間にはある。きっと、見ている未来はふたりして同じものなんだろう。 「……なんつーか、もうおまえらはずっとそのまんまだな」 「え? なぁにそれ、成長しないってこと?」 「違うよ。……ふたりしておんなじとこ見て、ふたりしておんなじとこまで突っ走ってくんだろうなっていう」 「えー、なんか深いなぁ。だからちょっと分かんない」 その言葉をそのまま受け取っていいのか、「ほんとは分かってるくせに」と言って、また面食らった顔をさせてやるのとどちらがいいか――と考えたところで、どちらを選んだとしても何も一切変わることはないのだと思い直して、「まぁ深そうに聞こえるけど大した意味はない」と言って笑うにとどめた。 あぁ、こいつらの結婚式まで、あとどんくらいだろう。 連れてく相手、そんとき俺いるかなぁ。 |
画像:HELIUM