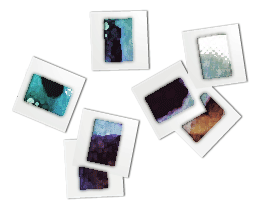
「あれ、帰んないの?」 俺がそう声をかけると、は「うん。徹くんが職員室呼ばれてて。ここで待っててって言われてる」と返してきたので、そうなの、じゃあ俺帰るわ、とさっさと教室から出ていくつもりが、そうはできなかった。 の座る席の前の椅子へ俺が腰を下ろすと、不思議そうな顔で見上げられたのでなんだか笑ってしまった。帰らないの? という言葉がそのまま顔に書かれている。正直で――残酷なほど、素直だ。 「じゃー、ちょっと俺とおハナシでもしよーよ、サン」 俺がおどけた調子でそう言うと、はくすっと笑ってみせた。 「やだぁなにその“サン”って。ふふ、へんなの」 この顔を見れるのは、あとどのくらいだろう。一緒に過ごせる時間は、そう多くはないだろう。俺ととの接点は及川だ。けれどこの三年で、それだけとは言えない関係にまではなっていると思う。友達のカノジョ? カレシのチームメイト? 友達? どれにも当てはまると思うが、本当はどれでもないというのを俺は知っている。俺だけが、知っている。 一人気まずくなって、悪いことをしている気にすらなって、俺は「あ、そういえばさ」と早口に口にした。は今度はきょとんと瞳をまぁるくした。ぱっちりとした二重まぶたがくっきり強調される。 「俺さ、最初迷ったんだよな」 「? 何に?」 努めてなんでもないような顔をして、「いや、及川のカノジョってなると、って呼び捨てで呼んでいいんだか、“サン”て付けたほうがいんだかな〜? って」と笑った。 “及川のカノジョ”。そんなのは知り合ったときから分かっていたことで、それについて俺は特別何かを思っていたわけじゃなかった。へえ、そうなんだ、なんて。それがこの三年のうち、こうまで変わってしまうとは思わなかった。過去の俺に言ってやるならば、「無理だからやめとけ」とこれだけだ。 「そんなのどっちだっていいじゃない」 の表情は、なんでそんなこと気にするんだか分からないというものだ。ホント、どこまでもは及川しか見えていなくて、あんなに女子に囲まれてきゃっきゃしてるくせして、及川もしか見えていない。はただただ真っ直ぐに及川を信じていて、及川もまたそれに応えつづけてきたのがよく分かる。恋とか愛とか、そういうのはもうとっくに超えてしまった絆がそこにはあるのだと、幾度見せつけられたことだろう。 「いや、よくないネ。及川そういうのうるせえじゃん」 「あはは、うーん、どうだろ?」 どうだろう? なんて言いながら、の口元は緩やかにカーブを描いている。その優しい表情が窓からじわりとにじり寄ってくる夕闇の中、白く浮かび上がっているのはどこか幻のようだった。まるで、手が届いてしまうんじゃないか、今なら、今だけなら許されるんじゃないかというような。そんなバカなこと、あるわけがないのに。 喉の奥が詰まるような感覚を誤魔化すように、無理矢理に話を続けようと口を開く。 「でさ」 「うん?」 「お前、大丈夫?」 ずっと思っていたことだった。あれから――最後の春高、準決勝で負けたあの日の夜、ぼんやりとだが覚えている。俺はの夢を見た。詳しい内容は覚えていない。ただ、一度も見たことのない涙だけを覚えている。 三年間、バレー部と――俺たちと深く関わってきて、にもいろいろなことがあっただろう。そんなことは今更聞くことでもないし、俺の憶測でしかないのでなんとも言えない。それでも、間近でずっと応援し続けてきてくれたからこそ、俺たちを心から信じ続けてきてくれたからこそ、きっとそうだろうなと思うのだ。 は、勝っても負けても、どんなときでも泣いたことなんてなかった。及川には泣いてみせたりしたかもしれないし(いや、きっとそうだ)、長い付き合いになる岩泉だって見たことがあるかもしれない。でも、俺は一度もなかった。この三年間、ずっと。だからいくらあれが最後だったとして、は何も変わらないだろうと思っていた。俺たちがずっと見てきた真っ直ぐな瞳から、涙がこぼれるなんて、そんなこと。 それなのに、俺には夢の中でのの涙が、どうしてもただの夢だと片づけてしまえなかった。 「――え?」 はやっぱりきょとんとして、それからきゅっと唇を引き結んだ。 俺はそれを見逃さなかった。 「いや、平気そうな顔してるから」 俺が片手で頬杖をついて窓の外へ視線をやると、震えた「……何が?」という言葉に胸が締めつけられた。何がって、何がって。ずっと俺たちを見守ってきてくれたからこそ、信じてきてくれたからこそ、みんなで全国いくぞって真面目にも笑っても言い合っていたからこそ。 俺が言いたいことなんて、分かってるくせに。 「言ってほしいの?」 ちらっと視線をに移してそう言うと、は俯いて首を振った。 「……だ、だって、おかしいでしょ、わたしが泣くなんて、」 「なんもおかしくないと思うケド。俺らも号泣だったしな」 「……わたしは、ちがうでしょ、」 堪えているものは分かる。呼吸が辛そうで、声が引きつるように震えている。 それでも俺は続けた。 「なんも違わないじゃん。……俺たちのことずっと信じてくれてたってコトはさ、も一緒に立ってたってコトだろ。俺たちと一緒のコートに」 俺の言葉に、がばっと顔を上げた。あの日に見た、泣き顔だ。これでもかというほどに眉根を寄せて、鼻の頭は真っ赤で、ぱっちりとしたまるい目が、ぐしゃぐしゃにつぶれている。 「……お、かしい、なぁっ……! 徹くんのまえでも、岩泉くんのまえでも、泣いたり、しなかったのに……っ」 クッソかわいくない顔してんのに、なんでこんなに愛おしく思うんだろう。 「……変なトコで強がってどーすんだよ」 その後、思わず「……胸、貸してやろっか?」なんて言いそうになったが、それは喉元まできていたくせに止まってしまった。すると廊下からバタバタと足音が近づいてくるのが聞こえて、は「――あ、徹くんだ」と言うと、細い指先で目元を濡らす雫を拭い去った。それからいつもの顔で、「……じゃ、わたし行くね」と言ってスクールバッグを持ち上げた。 「……ん。また明日ネ」 余計なことを口走るまえに、と俺は顔もまともに見ずにひらひら手を振った。が席を立つ。キィと、床が軋む。も俺の顔なんてまともに見ずに、そのくせ、これほどしみるものはないな、という言葉を言い放った。 「……花巻くん、ありがとう。この三年、お世話になりっぱなしだった。――最後の最後まで、ごめんね」 「……バーカ、こっちのセリフだっつーの」 世話になりっぱなしだったのはホントだし、最後の最後まで未練がましくて、「ごめんね」は俺のほうだ。 「? 、目、どうしたの?」 「ちょっとコンタクトずれちゃって……」 「え、大丈夫?」 「うん、でも痛い!」 「え〜、じゃあもう取っちゃいなよ〜」 「……でも今日メガネ忘れちゃったし――」 及川との声が遠ざかっていくのをぼんやりと耳にしながら、俺はいよいよ闇色というような空に視線をやった。 |
画像:HELIUM