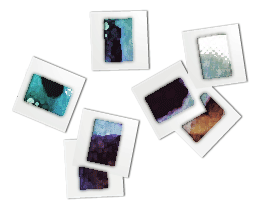
「お前も来ればよかったのによ」 俺がそう言うと、はほんの少し首を傾けてから、「あぁ」と合点がいったというように口にした。試合のあと監督に飯を奢ってもらったのに、バカみてえに腹にラーメン突っ込んで、そのあとバカみてえにバレーしたことは及川から聞いているだろう。監督に連れていってもらった飯は別として、三年でまとまってる中にがいないのは、なんだか不思議に思えた。 「まさか。チームの中にまで入れないよ」 やっぱり及川から話を聞いていたのか、は少しだけ笑った。けれど、その口調はしっかりとしたものだった。俺が「及川がいるだろ」と言うと、ちらりとこちらへ視線を寄こした。真っ直ぐな目だ。俺たちはこの目の中に、いつでも勝利を見てきた。だから、あの場にがいないことを不思議に思ったんだろうと思う。 「そういうことじゃなくて」 はまるで、分かるでしょ? とでも言いたげだった。俺にだって、その意味くらいは分かる。それでも、は“及川の彼女”とだけ表現するには足りない。それほどまでに、チームに溶け込んだ存在だった。俺たちが勝てば喜んでくれる。それは何もこいつ一人に限った話じゃない。応援してくれたひとはいくらでもいる。けれど、それでも心の底から俺たちを信じていたのはで、だからこそ、この三年間での勝ちを一番喜んでくれていたのはなんじゃないかと思うのだ。そしてこの先は――。だから俺は、「……最後くらい――」と言ったのだが、は言った。視線は前を向いている。 「いいの。……最後だから、いいの」 その横顔にかける言葉は思いつかず、俺はただ「……そうかよ」と短く返すことしかできなかった。 中学のとき――及川が不調でヤケを起こしていた頃のことを思い出した。気にかけてやってほしいと、頼まれていた。及川の調子が戻るまでの間、はつかず離れずというような距離感でいたように思うが、一度だけ体育館で見かけた。もう真っ暗で、誰も残っちゃいないだろう時間だった。どうせ及川はまだ残っていると、俺は連れて帰ろうとしていた。 「っだったら分かるだろ! 今のままじゃだめなんだよ!!」 あの及川が、にそんな大きな声を上げているのは、衝撃だった。 奴のを見る目は、いつでも優しかったからだ。 とにかく間に入らなければと思った俺をその場にとどめたのは、の次の一言だった。 「そうだよ、今のままじゃだめ。徹くんひとりじゃなんにもできないんだもん」 は? と、及川はこのときは意味が分からなそうだったが(今でもそうだと言うのなら、もう一度頭突きしてやってもいい)、俺はこれを聞いてすぐには動き出せなかった。 けれど、俺の背中を押したのもだった。 「……でも、わたしは一緒に戦ってあげることはできないから――岩泉くん、バトンタッチ!」 俺がずかずかふたりへ近づいていくと、本当に“バトンタッチ”というように、は迷いなく俺とすれ違った。あの時、俺が送っていくと言ったのをは断った。あの時、何を考えていたのか。いいや、分かっている。及川のことだ。 あの時も、今も。 「で、お前これからどうすんだ」 俺がそう言うと、は「どうすんだも何も……岩泉くん知ってるじゃない。徹くんと同じ大学いくよ」と、真面目な顔をして返してきた。そういう意味ではないと、こいつが一番分かっているだろうに。 「そうじゃなくて」 少し強く言うと、は視線を俺に寄こした。 思わず怯んでしまいそうになるほど、曇り一つない。は言った。 「……大丈夫だよ。わたし、徹くんとずっと一緒にいるもん。もう、あんな無茶はさせない。……まぁしないだろうけどね。……でも、とにかくそばにいる。徹くん、“先”まで連れてってくれるって約束したもん」 がこんなにも曇り一つない目をしているのは、きっとどこまでも及川のことを信じているからだ。誰が――及川本人が、無理だと、できないと言っても、は信じている。及川なら必ず、やってみせるはずだと。 「……いつもそれ言うな」 この目に三年間、見守られてきた。どんなことがあっても。俺たちをどこまでも信じるこの目に、俺たちも自分たちを信じる力をもらっていたんじゃないかと思う。だって約束したんだもん、と言うの目には、やはりなんの曇りも見当たらない。何がここまで、こいつの目を曇らせずにいるんだろうか。 「……及川がそれ破るとか思わないのか」 俺がそう言うと、は一瞬きょとんとした顔を見せると、次の瞬間には思いっきり笑った。 「破るって思うの?」 純粋な笑顔だ。これも、真っ直ぐだ。迷いもためらいも、ましてや疑いなんてどこにもない。 「全然思わねえ。アイツめんどくせえからな。……やるっつったら、やり遂げるまでやめねぇよ」 は、優しい目で「そうでしょう? ……だからわたしも、ずっとそばにいるの。そばにいるったらいるの!」と、もう一度笑った。 「……」 俺の声に何かを感じ取ったのか、はじっと俺の目を見つめながら、なんだか慎重に「なぁに?」と返事を寄こしてきたので、少し笑ってしまいそうになった。俺は難しいことを頼むつもりはない。 「……及川のこと、頼む」 「……やだ、やめてよ……。わたしが好きでそうしたいの。岩泉くんに頼まれなくたって、そうする」 は目に見えるほどうろたえて、頼りなく視線をさまよわせた。けれどそれもあっという間のことで、また――いつもの、真っ直ぐとした目で、「……でも、ありがとう」と言った。 「は?」 思わずそう口にした俺に、はほんの少しだけ笑った。 それから、一つ一つ丁寧に、言葉を続けていった。 「今まで……徹くんと一緒にずっと戦ってきてくれて、ありがとう。徹くんのこと支えてくれて、ずっと頼りになる相棒でいてくれて……徹くんのこと、信じてくれて、ありがとう。徹くんをあんなにかっこいい、すごいセッターにしてくれたのは、岩泉くんだよ」 「……ノロケは他でやれ、他で」 俺がそう言って目を逸らしても、は構わず続けた。 「岩泉くんがいてくれなかったら――あの時……どうなってたか分からないもん。わたしにできることなんか、ほんとにちょっとで……ううん、わたしじゃ何もしてあげられなくて――」 「バカか、お前」 「え?」 さすがに黙って聞いていられなかったので一言投げると、は驚きましたと言わんばかりの表情をしているので、こちらのほうが驚いた。今まで――この六年間、自分が何をしてきたのかまったく分かっちゃいない。 「……及川が――及川が、俺の自慢の相棒で、ちょうスゲェセッターなのは、お前がそばで支えてたからだ。この六年のこと、感謝してる。今までずっと、一緒に戦ってきてくれたのは――お前も同じだ」 俺の言葉には目を丸くして、それから、安心したように目を細めた。なんだか、眩しそうにも見える。実際、眩しく見えているのは俺のほうだろうが。 「……岩泉くんにそう言ってもらえたら、それで十分だよ。……わたし、少しでも……役に立ててたかな?」 「少しどころの話じゃねえよ。あのバカの面倒見れんのは……お前しかいねえ」 「……うん」 ほんの少しの沈黙のあと、俺は言った。 「……ただし、この先に戦うことがあれば、俺は絶対負けねえからな」 「徹くんも同じこと言うと思う」 こんな話、クソ真面目にするもんじゃねえな、と思いつつ頷くと、が「……岩泉くん」と言うので、「おう」と返事した。 「……わたしの中のエースは、ずっと岩泉くんだよ。北一の時からずっとお世話になってるけど……、あえて言わせてね。――青城での三年間、本当にありがとう。……お疲れさま」 だから、クソ真面目にするもんじゃねえっていうのによ。「……おう」と返した声は震えてはいなかったと思う。けれど、鼻の奥がツンとしてたまらなかった。 俺と及川は違う道を行って、はこれからもずっと――これまでの六年間と変わらず、及川の行く道を一緒に駆け抜けていくだろう。この先も及川を信じて、及川の道を切り開く手助けをしていくだろう。本人はそんなことないとかなんとか、またバカなことを言い出すだろうが、これは変わらない。この六年間、そうであったのだから。 が及川を信じるのと同じように、俺は及川とのこの先を信じている。 |
画像:HELIUM