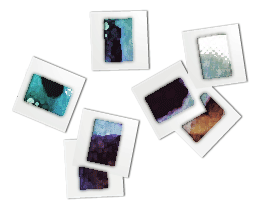
自分の限界はここだというのに気づいたとき、俺は絶望を覚えるよりも先にどこかで納得してしまった。俺がどれだけ努力を重ねたとしても、持って生まれた才能には追いつけない。 どれだけ“今”の先を望んでも、そこへは行けない。 努力すればいつかは越えられると信じるだけの気力なんて、もうどこにもなかった。 どれだけ練習を重ねても勝てない。 そこへ俺を追いかけてくる、信じられないような才能の塊が現れた。 もう俺の行き場なんてない。このままでいて、行き着く先はどこだ? 想像がつく。 ただ現実に打ちひしがれて、汚い地面に這いつくばって唇を噛んでいる俺が見える。 何度もそうして同じことを考えるのに、俺は結局諦めることはできない。 どれだけ辛い思いをしたって、どれだけ悔しい思いをしたって。 「徹くん」 俺は思わずボールを取り落とした。もうどこにも、誰も残っていないだろうと思っていた。時計なんていちいち確認しないので正確な時間は分からなかったけれど、俺がボールで床を叩く以外に音はないし、外は真っ暗。体育館の光は爛々としていて、目に痛いくらいだ。現れた彼女の体からは、なんだか寒々しい匂いがするようだった。 「……ちゃんか。びっくりした……っていうかなんでこんな時間まで残ってるの」 腰を折り曲げて、ボールを拾おうと床に視線を落とすと、「わたしのことより自分のことだよ。……無理して体壊したらどうするの」と彼女ははっきりとした口調で言い放った。 俺の不調を知っていながら、よくそんな口利けるもんだな、と思った。 彼女が一番、俺の気持ちを分かってくれていると思っていたのに。煩わしいな、と思った。 「無理なんかしてないよ。ごめんね、送ってあげたいけど、俺もう少しやっていきたいんだ」 ボールを掴んで体を持ち上げながら早口にそう答えると、俺はまたネットの向こう側へ視線を向ける。あそこには、越えなければいけない壁――いいや、倒すべき相手がいる。それに、俺に迫ってきているものもいるのだ。前にも後ろにも、俺を打ちのめす現実しかない。 俺はとにかくボールに触っていなければ――できる限り、前へと走っていなければ落ち着かない。それが徒労で終わると、どこかで分かっていても。でも俺は、負けたくない。勝ちたい。それだけだ。だから、できることは全部、できないことも全部、俺はやらなくてはならない。 「――何をそんなに焦ってるの?」 その言葉は体育館に大きく響いたような気もしたし、俺の耳元で小さく囁かれたようでもあったし、俺の頭の中に直接投げかけられているようでもあった。 「……え?」 「徹くんが今してることは、余計に自分を追い詰めるだけだよ」 俺は思わず笑った。喉の奥が乾いていた。 初めて、彼女のことを、そんな――まるで軽蔑するような――目で見た。胸がざわざわして、身の毛が逆立つような、汗が急激に冷えていくような感じがした。 今は彼女に近づいたらだめだ。自分でも何をしてしまうか分からない。 そう思ったのに、俺の体は向けられた言葉に愚直に反応して、ずんと彼女に詰め寄った。 きっと、怖かっただろうと思う。自分より大きい、しかも男にそんなふうに近づかれたら。 それでも俺は自分のことしか頭になくて、「……ちゃんに何が分かるの? 俺が好きでやってることなんだから首突っ込むなよ」と、自分よりもずっと小さい女の子を冷たく見下ろした。すると彼女はなんともないような顔で、「いや。徹くんに全国連れてってもらうんだもん。首突っ込む」と言った。俺はもちろんカッときて、細くて頼りないその両肩を乱暴に掴んだ。 「っだったら分かるだろ! 今のままじゃだめなんだよ!!」 彼女の目の中にいた俺は、とても情けない顔をしていた。 今にも泣きだしそうで、もうすべてのことを諦めていて、もう希望はないという顔だった。 彼女は俺の手を振り払うでも、痛いと泣くでもなく、ただ静かに笑った。 「そうだよ、今のままじゃだめ。徹くんひとりじゃなんにもできないんだもん」 「……は?」 「……でも、わたしは一緒に戦ってあげることはできないから――岩泉くん、バトンタッチ!」 ハッとして振り返ると、眉間にこれでもかというほどに皺を寄せた岩ちゃんがいて、俺は反射的に彼女から手を放した。岩ちゃんがずかずか俺に近づいてくる。それと入れ違うように、彼女は俺から距離を取って背中を向けた。 「じゃ、わたし帰るから」 「おい、危ねえだろ。送ってく」 その背中に岩ちゃんが声をかけたけれど、「大丈夫。そこのおバカさんに喝入れてくれるだけで十分!」と言って、軽く手を振って帰っていった。静かな微笑みだけが、俺の目の裏にしっかり焼き付いた。 今思うと、、あの時きっと――泣いてたんだろうな。 俺は一人じゃない。 そのことに気づかされてから、自分の限界をここだと決めつけるのは“まだ”早いのだと信じるようになってから、俺の世界は拓けたような気がする。一緒に戦ってくれる仲間がいる。 俺を――俺たちを信じてくれる人がいるのだ。俺が――俺たちが勝つたび、誰よりも嬉しそうに笑ってくれる人がいるのだ。俺が見ているのは“夢”でも“目標”でもない。その“先”にあるものだ。俺たちは勝って、勝って、勝って、全国へ行く。 彼女を、“先”の舞台まで連れていく。必ずだ。 絶望? そんなものはどこにもない。あるのは、希望だけだ。俺は何かを嘆くほど、まだ何かをしていない。“まだ”、俺には“今”よりももっと“先”があるのだ。それを掴むためなら、どんなに情けなくたってみっともなくたって、辛くったって苦しくったって、俺は何度でも立ち上がれる。這いつくばって何が悪い? また立ち上がるなら、それでいいじゃないか。 俺は何度でも立ち上がってみせる。 「徹くん」 俺を懐かしい記憶から呼び起こしたのは、他でもない彼女だった。あんななっさけない彼氏のこと、見捨てずにこんなトコまで付き合っちゃうんだもんなぁ……お人よし。 「――」 柔らかい笑顔を浮かべて、は俺のそばへ駆け寄ってきた。 「よかった。探してたんだけど見つからないから、試合前には会えないかなって――どうしたの?」 「……んーん。ちょっと、中学のときのこと思い出しただけ」 俺の言葉に、は何か思うところがあったようで少しためらうようなそぶりを見せた。それから、「……そう」とだけ言った。かと思うと、「――時間ないと思うから、一言だけね」と俺の目を真っ直ぐに見つめてくるので、どきっとした。また、あの静かな微笑みがよみがえってきそうだ。でももう、あの頃の俺じゃない。あんな顔、もうさせないってずっと前に誓った。 「うん。なぁに」 「全国、連れてってね」 それはただ“確信”している言葉なんだなと思って、俺は笑った。お願いとか、だから頑張ってとか、そういうんじゃなく、“そうなる”とすでに確信しているんだなと。 きっと誰より俺を――青葉城西というチームを信じているのは、だ。 「そこはさぁ、『徹くんっ、がんばってね! 大好きだよっ!』とかじゃないの?」 「そんなことは言わなくても分かってるでしょ?」 おどけてみせる俺に、はちっとも笑わず、視線を逸らすこともなかった。 こんなに信頼されちゃあ、やるしかないよねって話だ。 「……ま、俺たち強いからねえ〜。……烏野も白鳥沢も、両方ぶっ倒す」 「うん、分かってる」 その目には本当に混じりけない“確信”しかないのに、俺は「だからなんにも心配しないで観てて」なんて言って、やっぱり俺よりずっと小さいの頬をそっと撫でた。はほんのちょっとだけ笑って、それから「心配なんて最初からなんにもしてない」とはっきり言い切った。だって、信じてるもん、と。 「あはは、だよね。じゃ、俺そろそろみんなのとこ行くね」 なめらかな頬を撫でる手をとめた俺に、は一度は「うん」と返事したのに、すぐさま「……徹くん。やっぱりもう一言」と言って俺の足をとどめた。 「ん?」 ちょっと俯いた顔を覗き込もうとするより先に、が顔を上げた。 その瞳の奥には静かに炎が揺らめいている。――そう、まるで闘志みたいに。 は言った。 「……思いっきりだよ」 一緒に戦ってあげることはできないから。 まさか。いつでもどんな時でも、一緒に戦ってくれたじゃないか。 俺の目の奥にも、きっとおんなじものが宿っていて、それをも見ている。 「――――言われなくても」 どんなことがあっても、みんなで一緒に越えてきた。 俺一人じゃどうにもならなくても、みんなでならどうとでもできた。 みんなとなら、どこまでだっていける。 だから今度こそ連れていく。 約束した、“先”の舞台まで――。 |
画像:HELIUM