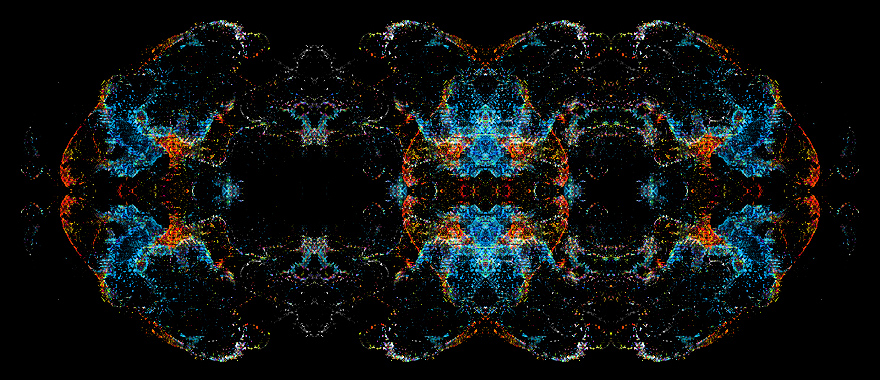
神戸大助という男と、どう出会って、どうしてこんな関係になったのだったか。過去を探ろうにも、もう思い出せない。気がついたら、この男と肌を重ねることが当たり前になっていた。出会いすらまともに思い出せないのなら、どうしてこんな関係になったのかだって知れたものだ。どうだっていい。 けれど、不思議だ。どう始まったか分からないなら、終わりだっていつくるんだか分からない。そんな当たり前のことを、わたしはさっぱり忘れていた。 「出ていけ」 「……なんですって?」 気怠げに髪を掻き上げて、「二度も言わせるな、出ていけ」と彼は冷たく吐き捨てた。いつもと変わりない声音なのに、どうしてだか、どこまでもわたしを突き放してやる気でいるのだと分かってしまう。昨日の晩は、そんな素振りちっとも見せなかったくせに。どういうつもりでわたしを呼んだんだと、お綺麗な横っ面を張ってやったって構わないだろう。 ただ、こういう時、女って悲しいものだ。 「わたしにも同じことを言わせないで」 ――理由が分かってしまうから。 「……おまえとはもうこれっきりだ」 でしょうね、分かりますとも。 わたしがそう言ってやったら、この澄ました顔をちょっとは歪められるんじゃないかと思ったけれど、彼に限ってそんなことはないだろう。だから尚更、もっと上手いやりようがあったでしょうに、と思う。あんた、ちょっと馬鹿になったんじゃあないの? ――でもきっと、そういうものなのよね。わたしには到底、分からないけれど。 さっさとベッドからおりて、まずはシャワーを浴びなくてはと髪をまとめる。 「……何よ、他にいい女でもいた? あなたみたいなのに付き合ってやれるような、都合のいい女が」 わたしがそう言うと、いつもの抑揚ない調子のくせして「あれとおまえを同じにするな」だなんて噛みついてくるから、嫌な男。別に意地悪したわけじゃあないのに。でも、わたしは決して良い女ではないから、やられた分はもちろんきっちりお返ししてやる。 「……へえ、本気なんだ、その女は。遊びじゃなくて、本気で好きなの、へえ、あなたが」 振り返って、澄ました顔をよぅく確認する。眉間に少しだけ、皺が寄っている。へえ、そう。そうなの。あなたでもそういう顔、できたのね。わたしにはこれまで、一切見せなかった顔。いや、この男はそう簡単に感情を読ませてはくれなかった。なのに、今は手に取るように分かる。 ――きっと怖いんでしょうね、わたしのことが。そうは認めないだろうけれど、愛しいと思う女を見つけたのなら。 わたしたちの間には、信頼どころか信用だってなかったのだから、それも当然だ。そう納得できてしまうのもまた、女の悲しいところだわ、とふいに思った。 「だったらなんだ、おまえには関係ないことだろう」 「そうね、ちっとも関係ない。……わたしに興味のない男なんて、大嫌いよ」 どう出会ったんだかも、どうしてこんな関係になったのかもちっとも思い出せやしないけど、時間だけはそれなり重ねてきた。それでも、この男はわたしを自分には関係ない女だと、今この瞬間――いや、もしかしたら今日より、いいえ昨晩より、ずっとずっと前からそう思って使っていたんだろうとはいい加減に分かる。別に、何を期待していたわけでもないけれど。だって、わたしもずっとずっと前から、この男はそういう人間なんだと思っていたから。 自分勝手に、自分を押し通す人間だった。人を思いやるだとか、そういう繊細なことはまったくしない男だった。必要ないと思えばなんだって冷酷に切り捨てて、でもそれに対して何を思うでも感じるでもなく…そう、感情らしい感情を持っているとすら、思えないほど。 だからわたし、きっと安心してたのよ。信頼も信用もなくても。むしろその冷酷さだけが本当なんだと思えば、そっちのほうがよっぽどよかったんだわ。今こうなって、やっと気づいた。恋だか愛だか知らないけれど、まるで普通の人間みたいなことをするんなら、わたしにこの男はもう必要ないんだと。 そうだ。この男にわたしが必要じゃなくなったんじゃない。わたしに、この男は必要じゃなくなったのだ。 だから、もうこの神戸大助という無価値な男は、今すぐ忘れ去ってしまって構わない存在に成り下がった。そう、もういらない。 「そうか」 ただね、やっぱりね、それなりに重ねてきた時間のすべてなかったことにするなんてのは、どうしたって腹が立つでしょ。だって、わたしを置いてくってことじゃない。同じ穴のムジナだって、安心してたのに。わたしだけ置いてって、自分はさっさと歩き出しちゃうなんて、ずるいでしょ。 やっぱり、引っぱたいてやればよかった。それで気が済むとは思えないけれど。 「……あなたも、わたしと同じだと思ってたのに」 「どこが」 「誰も信じないし――誰も、本気で愛さないと思ってた」 何か考えたような沈黙の後、言った。 「……そうだな、俺もそう思っていた」 ベッドに乗り上がって、恐ろしいまでに整った顔を眺める。どこをとっても、腹が立つほど、そう、憎らしくなるほどに美しい。わたしだって、できる限り自分に手をかけてやっているけれど、この男はそんなことにちっとも興味がないから、関心なぞ持っちゃくれなかったけれど。 「ね、あなたを本気にさせた女って、どんな女?」 でもきっと、その女のことなら、全部気になって仕方ないんでしょうね。前髪を一センチ切っただけでも、綺麗だなんだって言うのかしら。この男が。ほんの少しも想像できない。そんなセリフは一度だって聞いたことがないし、言うようにだって見えない。いや、言わない男だったはずだ。わたしだけにじゃなく、どんな女にだって。でも、変わっちゃったんだって分かるわ。 そう、変わらざるをえなかったんだわ、と思った。この男が、ほんとうに心から求めた女を、そばに置くためには。 「聞いてどうする」 だってそうじゃなくちゃ、こんな顔をするわけがない。きっと、わたしがそのかわいいカノジョに会いにでもいってみたら、たったの一度だって変えられりゃしなかったこの美しい顔を、わたしが、歪めてやることができるんだろうか。 ――そんなことを考えたって、つまらないことこの上ないのにね。 「どうも? ――ただ、わたしにぜーんぶ黙っててほしいなら……そうね。最後にもう一度だけ、抱いてよ」 大助は、抑揚なく呟いた。「……つまらない女だな、おまえは」と。うん、そうね、わたしもそう思う。 「つまらなくて結構よ」 きっとわたしは、この先どう頑張ったって今のあなたみたいにはなれない。だって恋だの愛だの、まるっきり人を信じるなんてこと、できっこないもの。それにね、つまらなくって結構よ。だって、今日までにあなたの気を引けなかったのは、他の誰でもないわたし自身のせい。ただ、惜しくはなるものじゃない。これまでずっと、わたしのものだと思ってたのに。少なくとも、人の顔が分からなくなるほどの、濃い色した夜だけは。 だから、つまらなくっていいわ。こうなりゃ全部おんなじよ。――あなたに愛してもらおうなんて、もう思わない。 |
画像:はだし