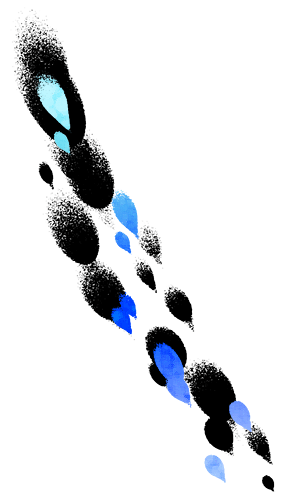
――深夜、みなとみらい。 「二十三時、四十九分! 暴行で現行犯逮捕です!」 そう言って、女は左馬刻の手首に錠をかけた。 しかし、手錠をかけられている当の本人、碧棺左馬刻は、その手首を女――の眼前に掲げて言う。 「だァからよォ、お嬢ちゃん。暴行もクソもねえのよ。分かるか? あえて言うんならアレだよ、セートーボーエーだわ。先に手ェ出したのはこのクソダボで、俺様は被害者なんだよ、被害者」 浮かべている表情は実に面倒そうで、今まさに逮捕されたというのに、焦りも不安も見られない。それどころか、呆れたとでも言い出しそうである。 まぁ、左馬刻にとっては本当に呆れた話なのだが。 しかし、左馬刻を“逮捕”したはムッと眉間に眉を寄せ、「何が正当防衛ですかっ!」と声を上げると、自分がこの目で確認した“事実”をますます興奮したように言い放つ。そのすぐそばで、地面に“転がされた”まま、腹を抱えて呻く男を指差しながら。 「肩がぶつかったところで、あなたがこの人に殴りかかったんじゃないですか! わたし、ちゃんと見てたんですからね!」 これは確かに、紛れもない“事実”である。が、ここはヨコハマ。彼女が身を置いていた中王区とは勝手が違うのだ。 左馬刻は飄々と「おー、見てたんなら分かんだろうがよ。ぶつかってきたのはそこのゴミクズで、俺様はぶつかられた。被害者じゃねぇかよ、あ?」と、の言葉を鼻で笑った。は肩を怒らせて、我慢ならないとばかりにさらに声を張り上げる。 「っ、か、肩がぶつかっただけでしょ! それに対してあなた何したんですか? 殴るしっ、蹴るし! 言い訳のしようがない暴行罪ですっ! 逮捕です!」 一方的に――左馬刻にとっては、だが――謂れない逮捕などされても困る。というより、そもそも、自分はヨコハマの王様である。自分が煩わしいと思う面倒事に時間を使う気はない。 「……あ゛? めんどくせえなァ……」と溜め息まじりに呟いてから、“いつものように”処理させるしかないようだ、と首を鳴らした。何せこの女、職務に真面目だ。自分の知っている警官とは大違いである。 ともかく、この女の相手をしていては(どうせ一時的だけれど)檻の中である。 こういう面倒は、いつもの男に丸投げが早い。 「オイお嬢ちゃん、銃兎呼べや銃兎。テメーじゃ話になんねえわ」 は訝しげに眉を寄せて、「……じゅーと……? ま、まさか、入間さんのこと言ってます……?」と神妙な口振りで言った。左馬刻はニヤリと唇を吊り上げる。 「おー、そうそう、イルマジュート。呼べんだろ、同じポリ公なんだからよ」 は非常に不服である、という表情を浮かべながら「絶対にそこから動かないように!」と鋭く言い放ちつつ、スーツの内ポケットからスマホを取り出す。 こんなモン引っかけたまま、どこ行くっつうんだよ。 それどころか、“一仕事”終えた後の一服すらできずにこんなことになったのだ。口寂しい。左馬刻はイラッと舌を打った。煙草が吸いたい。それもまぁ、少しの辛抱で済むだろう。スマホを持つ手にさらに手を添えて、電話越しだというのに何度も頭を下げているを見つめながら、左馬刻も手錠をかけられたまま、器用にもジーンズの尻ポケットに突っ込んであるスマホを取り出した。 左馬刻が言う“ジュート”――入間銃兎は、からの連絡を受けてから十分もしないうちに、姿を現した。眉間に皺を寄せ、神経質そうに眼鏡のブリッジをくいっと持ち上げる。 「なんですか、わざわざ私を呼びつけて」 「おー、わざわざあんがとよ、悪徳警官」 そう言って、左馬刻は手錠のかかった手首を見せつけるようにその眼前に突きつけ、「つーかよォ、てめえンとこの教育はどうなってんだァ? あ? 誤認逮捕だよ、誤認逮捕。文句あんならそこのお嬢ちゃんに言えや」と鼻を鳴らした。 から連絡を受けた時点で、凡そのことは想像できていた銃兎は、深々と溜め息を吐いたあと、腕を組んで左馬刻を睨みつけているに視線を移した。 「……さん、これは一体どういうことですか? 大体の予想はついていますが、一応聞いておきましょう」 銃兎の言葉に、は勢いよく細い指先を左馬刻に向けた。そして、「こっ、この人! この人、わたしの目の前で、人を殴ったり蹴ったりしたんですっ! 暴行で現逮です! な、なのにっ、」と必死になって訴えるが、銃兎はそれに対して「ふむ、そうですか」と一つ頷くだけだ。銃兎はこの逮捕劇について、まぁこんなところだろうという当たりをつけているので、事情はどうだっていい。それに加えて、が見たという“事実”も。 銃兎はもう一度、眼鏡のブリッジを持ち上げた。 「……それで、さん」 聞いた話ではあるが、入間銃兎というのは非常に優秀な警官である。そう信じて疑っていないは、「はいっ」とはっきりした返事をしたが――が見た“事実”による結果は、彼女が手錠を取り出すより前から決まり切っている。 銃兎は柔らかい口調で、「その暴行の被害者はどこですか?」とに向かって微笑んだ。 左馬刻、テメェまためんどくせえこと引き起こしやがって。いい加減、チンピラですらないその辺の悪ガキみてえな真似すんじゃねえ。テメェの立場ってもんを少しは考えらんねえのか、クソ。心の内では、そんな罵詈雑言ばかりが飛び交っているが。 おかしな質問だ。そう思いながら、は転がされていた“被害者”のほうへ視線を滑らせた。――しかし。 「えっ、そこに――え?! な、なんで……?」 が見た、左馬刻による暴行の“被害者”の姿は、そこにはもうなかった。唖然とするに、左馬刻が意地悪く笑いかける。 「ほォらな、被害者なんていねェのよ」 確かにその場にいた“被害者”は、しれっとした顔をしている左馬刻が、すでに片付けていた。正しくは、が銃兎へ連絡するために自分から目を離した時、近くにいる舎弟を呼び出して“片付け”させたのだが。 青ざめるの表情を面白そうに見つめながら、左馬刻は芝居がかった大袈裟な口調で「ま、あえて言うならこの俺様だわな。当たり屋に遭うわ、こうやって誤認逮捕なんざよォ」と言うと、悪徳警官に視線を移して「……なァ? 銃兎」と、唇をニヤつかせた。 銃兎が深い溜め息を吐く。 「はあ……。さん、ここは私が引き受けますから、どうぞ署にお戻りになってください」 実に紳士的な態度だったが、は納得いかないとばかりに肩を怒らせ、興奮気味に声を張り上げた。 「そっ、そういうわけにはいきません! だってわたし、この目で確認しましたっ! 肩がぶつかっただけのことで、殴る蹴るの暴行だなんておかしいです! 警官として、見過ごすわけにはいきませんっ!」 そんなクソ真面目で“まとも”な理屈が、この街で通用すると思っている。なんとも“まとも”だ。――が、ここではそんなもの、通用しない。 銃兎は肩を竦めて、「……そう言われましてもねぇ……被害者だという人物はいませんし、それらしき通報もありませんから、現状どうにもできませんよ」と言った後、さらに「それに、さま――こちらの男性の証言では、むしろ誤認逮捕というわけですから……」と、わざとらしく眉を下げる。 すると、の目がすっと細まり、これまでのビクついた態度が一変した。 「……わたし、この人に入間さんを呼ぶように言われたんです。彼、入間さんと同じチームですよね、ディビジョンバトルでの。それを抜きにしても、随分と親しくなさってるようだと署内で聞きましたけど」 クソ、と心の内で悪態をつきつつ、銃兎は小さな子どもを相手にしているかのように、柔らかく口端を緩める。 「仰るとおり、この碧棺左馬刻とは付き合いがありますよ、何せ同じチームのメンバーです。知らぬ相手ではありませんよ。しかし……一体どこからそんな話を聞いたんです?」 は厳しく眉根を寄せて、「彼が問題を起こした時、いつも入間さんが間に入っては釈放していると聞いています。……どうなっているんですか?」と、自分よりずっと背丈のある銃兎を見上げた。そして、「場合によっては、わたしも中王区のほうに報告をしなければなりませんが」と言うではないか。 さすがの銃兎も、ひやりとした。ヨコハマというこのシマでは、大抵のことはなんとでもできる。しかし、そこに中王区が介入するというのであれば、話は変わってくるからだ。 ただ、ここで露骨に顔色を変えるわけにはいかない。それこそどうにもならなくなる。めんどくせえこと引き起こしやがって、と銃兎はまた心の内で左馬刻に対して毒づきながらも、柔らかな微笑みを崩すことはしなかった。 新米であるという話ではあったが、このという女は、確かに“あの”中王区からやってきたいわゆるエリートだ。なっていないと思わせることもあれば、任せた仕事によっては不慣れですと言わんばかりのぎこちなさもある。それでも、今の社会において――しかも中王区からやってきた――女の不興を買ってしまえば、もはや慣れた“揉み消し”など通用するはずもないのだ。 ここは慎重にならなければならない。 「……どうもこうも……問題がないと判断されたための釈放です、何もやましいことはありませんよ。もちろん私の独断ではなく、上の指示です」 いざという時がやってきたとして、自分の代わりに誰を差し出してやろうか。微笑みの裏側で算段する銃兎だったが、その必要はなかった。あれだけ頑なに“事実”にこだわっていたが、すっかり落ち込んだ様子で「……そう……ですか、」と呟いたからだ。何をどう捉えてそうなったのかは分からないが、大事になってしまうことは避けられそうだ。 銃兎がひっそりと息を吐いたところで、それまでニヤニヤと二人のやり取りを見守っていた左馬刻が、に詰め寄り、未だ錠がかけられたままの手首を突き出した。 「――さァて、これで分かったよな? お嬢ちゃんよ。あんたがしたのは誤認逮捕、俺様は無罪だ。とりあえずはこのクソうっとうしいモン、外してくれるよなァ?」 は俯きながら、左馬刻にかけた手錠を外した。左馬刻が実にわざとらしく、両手をぶらぶらと振ってみせる。 絶対におかしい、こんなことは。自分の目できちんと、この男が一方的に暴力をふるう様を確認したというのに、勘違いだなんてあるわけがない。 それでも、ひどい暴行を受けたと一目で分かった被害者は、どういうわけか消えてしまったし、それに関する通報もなければ他に目撃者もいない。そうとなれば、これ以上の追及はできないだろう。理屈では分かるが、は決して納得したわけではない。 唇を噛んでだんまりするの顔を覗き込み、左馬刻は笑った。 「……何か言いてえことがあるよなァ?」 絶対におかしい。状況的にどうにもできないことは分かっているものの、確かにこの碧棺左馬刻という男がやったことは“事実”だ。それなのに、そんな事実はないと言い張るのであれば、それが通用するだけの材料――自分が目にした事実を覆すもの――を出してみろと思うが、も出せる証拠を持たない。つまり、勝ち誇った表情を浮かべる左馬刻に手錠をかけたことは、悔しくて悔しくてたまらないとしても――誤認逮捕ということになってしまう。左馬刻の態度は、を苛立たせるには十分すぎる。 がなんとか絞り出した「……う、」という呟きは、まるで喉の奥に何かが引っかかっているかのようだった。それを見て、左馬刻はますます意地悪く唇を歪める。 「どうした、なんもねえのか? ポリ公のくせに、ゴメンナサイができねえのは問題じゃあねえのか? あ?」 銃兎が溜め息を吐いた。 ――この場に頼れる人はいない。 言葉にされずとも肌で感じたは、ついに折れた。 「……っも、」 「も?」 は深々と頭を垂れて、「……申し訳……ありません……」と、なんとか口にした。顔を上げることはできない。またこの男の、自分をからかうようなニヤついた表情を目にしたら、とてもじゃないが感情の爆発は抑えられないという自覚があるからだ。 しかし、当の左馬刻にはの心境などを推し量ってやる気はないし、むしろいいオモチャを手に入れたと余計に面白がっている。 「何に対して謝ってんだか、俺様によォく分かるように言ってくれや。何に対して申し訳ねえんだ?」 は決して顔を上げることはしまいと、自分のパンプスのつま先をひたすらに見つめる。 それからしばらくの沈黙の後、本当は少しの間違いもないと思いつつも、「ごっ……、誤認、逮捕で……失礼をしてしまって……申し訳、ありません……」と、彼女にすれば不本意極まりない謝罪の言葉をなんとか、なんとか口にした。 ところが、これを聞いた左馬刻は実に機嫌良さそうに、「おー、分かりゃあいいのよ、素直な女は好きだぜ。あんた、顔も体もそう悪くねえしな」などと言ってまたをからかうものだから、はついにカッと顔を赤らめ、二人のやり取りを静かに傍観していた銃兎のほうへ、鋭い視線を向けた。 「〜っ入間さん!!!! やっぱり誤認とは思えません! 女性に向かって、こ、こんなっ、こんなこと言うんですよ?!」 銃兎はさも申し訳なさそうに頭を下げて、「申し訳ありません、見ての通り、粗暴な人間なもので……」と返した。そして、この騒動の処理をするには、の存在は邪魔である。 「さん、ここは私に任せて、先に署にお戻りください。後はすべて私が処理いたしますので」と続けた。 そもそも、は左馬刻に手錠をかけたことが誤認などとは思っていないし、それに加えてとんでもなく不愉快な思いをさせられたのだ。彼女が「っ、失礼します!!」と声を荒げ、その感情を表すかのような足取りで去っていったのも仕方ない。 その背中を見つめながら、銃兎は何度目か分からぬ溜め息を吐いた。 「――で、実際のところはどうなんだ」 煙草に火をつけた銃兎を横目で見て、左馬刻も煙草を取り出す。やっと火をつけることができた煙草の味は、なんともうまいもんだと紫煙を吐く。それから、あえて抑揚をつけず、言った。 「ウチに楯突いたシャブ中が、ちょうどよく俺様の目の前に現れてくれたんでよォ……ちィっとな。そのゴミクズはもう片付けさしたわ」 銃兎の眉がぴくりと反応したのを確認しながらも、左馬刻はけろっとした顔で「あ、俺様も聞きてえことあるわ」と言うので、今度は一体なんだと銃兎がますます眉をぴくつかせる。左馬刻は言った。 「あのお嬢ちゃん、普段はどこいんだ?」と。 銃兎はいよいよこの男は狂ってやがると思いつつ、「はァ? ……あの女、ああ見えて中王区から来たエリートだぞ」と、つい先程の出来事を思い出し、げんなり……というよりも、いつものような些細な問題ではないんだよ、分かってんのかこのクソチンピラ……と、面倒事などという言葉で済ませられないと暗に忠告する。 「……こっちからすりゃ邪魔くせぇが、ここらの治安がどうのと首突っ込んでこられてんだよ。余計な真似すんじゃねえ」 しかし、銃兎のその忠告が左馬刻に響くことはなかった。 「あ? 余計かどうかは俺様が決めることであって、オメーは関係ねえだろうがよ。――とにかく、あの女、気に入った。おまえ口だけは無駄に立つんだから、連絡先の一つや二ついいじゃねえか。オラ、さっさと寄越せうさポリ公」 額を押さえて深い溜め息を吐きながら、銃兎はスマートフォンを内ポケットから取り出すと、「……知りませんよ、何があっても」と言いつつ、の連絡先を画面に表示して左馬刻に押しつける。 受け取った左馬刻は「おー、上等上等」と返し、自分のスマートフォンにの連絡先を素早く登録した。そして、好戦的な光を目に浮かべて、乾いた唇をぺろりと舐める。まさに、獲物を見つけた獣の表情だ。 左馬刻は笑う。 「一月……いや、半月でモノにしてやっから、楽しみにしとけや」と。 |
画像:IRUSU