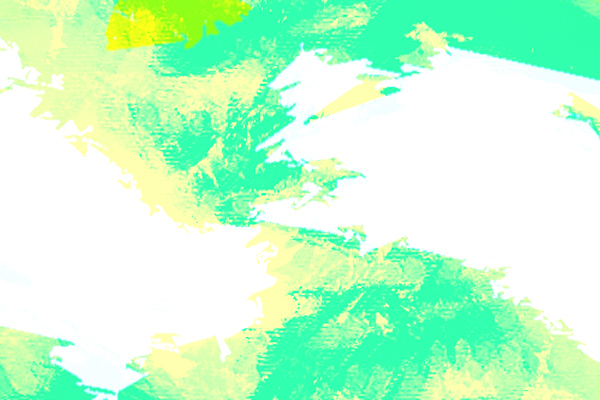
「……ね、このままどっか行っちゃおうよ」 俺の言葉に、ちゃんはスマホをいじる手を止めて俺を見た。眉間に皺が寄っている。 “俺”が“こんなこと”を言うのは“おかしいこと”なんだから、仕方ない。 けど、俺には分かってるんだからいい。ちゃんなら、分かってくれるって。彼女だけが、俺を知っているんだって。 「は? どっかってどこ? っていうかわたし、これから友達と――なに、どうしたの?」 そう言いながらちゃんが通学バッグへと伸ばした手を、俺はぐっと握った。 ちゃんは大きな瞳を見開いて、俺をじっと見る。今、俺は一体どんな顔をしているんだろう。 その目を見返しながら「どっか、俺のこと誰も知らないところ、行きたい」と言った俺の声は、とても歪んで耳の奥に響いた。 ちゃんは少し間を空けてから、そっと目を伏せた。俺は彼女の手を放すことができない。 「……山本くんと獄寺くん誘えば? 喜んで付き合ってくれると思うけど。ふたりともつーくん大好きじゃん」 なんてことないように言っているふうだけれど、ちゃんはもうこちらを見ようとすらしない。 本当は、分かっているのだ、彼女は。俺が言っていることの意味も、言いたいことの意味も。けれどそれを良しとしてしまったらいけないとも分かっているから、こうやって突き放す。それは俺だって分かっているけれど、それでも俺にはちゃんしかいないのだ。 だから俺は、彼女の言葉に「ちゃんは?」と返すことに何の躊躇いもなかった。 「大好きだけど、この歳になって探検ごっことかする気ないよ。男の子たちでやってください」 そうは言っても、ちゃんはやっぱり俺を見ない。 「……あのふたりじゃ、だめなんだ」 「なんで?」 「俺のこと、知ってるから」 そうだ。あのふたりは、俺を知っている。俺がこれからどうなる人間なのかを、知っている。そして、あのふたりはそれを誇らしく思っていて、俺に期待している。俺には不相応な期待を寄せていて、俺を完璧な存在にしようと思っている。 俺はそれをよく知っていて、その気持ちに応えたいと思う気がないわけではないけれど、そんな人たちを失望させたくない。だから、言えるわけがない。ここへきて、俺には無理だとか――嫌だとか。 「……わたしもつーくんのことならよく知ってるけど。幼なじみじゃなかったっけ? わたしたち。しかもお隣さん。未だにいっつも一緒」 ちゃんはそう言って、ゆっくりと俺へ視線をもってきた。 そうだ、ちいさいころからずぅっと、ちゃんは俺のそばにいてくれた。どれだけ俺が意気地なしかというのも、誰より知っている。だから、俺が言いたいことなんてすべて分かっているのだ。それでも、知らぬ存ぜぬを通す気でいる。 俺の不安だって、感じている恐怖だって分かっているのに。 俺はとても弱くて、だからたくさんのひとたちに影響が及ぶような力を手に入れたところで、どうにもならない。むしろ、俺みたいなやつの悪いところが、みんなにうつってしまうかもしれない。それなのに、なんてことない顔をしていられるわけがないし、そういう重圧には人一倍弱くて、だからこそこうして逃げ道を探そうとしているのだ。 ちゃんは全部全部分かっている。 俺は、俺のそういうところを知っていても、ずぅっと一緒にいてくれるちゃんのことが、すきだ。 「ちゃんは特別だよ。俺のこと知ってても、嫌わないでくれるから。ね、だからどっか行っちゃおうよ」 誰がなんと言っても、ちゃんだけは俺のそばにいてくれて、いつだって味方してくれた。身長なんか、もうずぅっと昔に俺は越してしまって、ちゃんより大きくなったのに、未だにちゃんに手を引いてもらわなければ、まともに歩くことだってできない。だから、俺はたとえ逃げようっていうときにだって、こうして彼女の手を借りなければどうにもできないのだ。 ちゃんは呆れたような溜め息を吐いて、「……へんなつーくん」と言ったかと思うと、俺が握る手をそっと外した。 「……しょうがないなあ、ちょっと友達にラインするから待って」 「そんなのいらない。もうここには戻ってこないもん」 そうだ、もうこんなところへは、戻ってこない。 「はあ? ちょっとつーくんほんとにどうしたの? 具合悪い?」 でも、そんなことができるわけないってこと、俺はよく知っている。全部全部、知っている。 けれど、知っているからといって、それならそうかと思えるほど、俺の出来は良くないのだ。 「……どっか行っちゃうことができないなら、このまま……時間が止まっちゃえばいいのに」 小さく呟いた声に、ちゃんははっきりと言った。 「そんなことできるわけないでしょ。ねえ、ほんとにどうしたの? 春にはイタリアに――」 「、行きたく、ないんだ」 そうだ、行きたくない。俺は、行きたくない。どこへも。何もいらないから、どこへも行きたくない。それがもし悪いことなら、俺はそれを理由にして行かない。 行けないのだ。俺じゃ、いけない。イタリアへ行ったところで、俺に何ができる? 俺じゃ、いけない、ふさわしくない。周りが何をどう言いつくろっても、俺の本質は変わったりなんかしないのだから。俺ではだめなのだ。 なのにみんなが言う。俺じゃなくてはいけないのだと。 ちゃんは俺の顔をそうっと覗き込むと、「日本離れるの、寂しいんだ」と言って笑うと、椅子を引いてそこへ座った。 俺は思わず、ちゃんの目から視線を逸らしてしまった。 「その気になればちょこっと帰ってくるくらいはできるでしょ? 何がそんなに嫌なの?」 ちゃんは、俺のことをよく知っている。 「……全部だよ。……俺の意志じゃない、こんなの……。そんなやつがボスなんて、誰もついてこない。俺だって、たくさんの人を引っ張っていけるなんて思えない。なのにみんな、俺のことをボスだって、まるで俺をちゃんとしたやつみたいに扱うから、」 指の先が、痺れたように震える。息が詰まって、苦しくて、いっそこのまま死んでしまえたらいいのにと思った。 そうしたら行かないで済む。そうしたら俺は、誰かの期待を裏切るまえに、何も悪いことをしないままでいられる。 ちゃんは両手を組んで、そこへ顔を乗せた。ふぅん、という興味なさそうな声にどきりとする。 続きを聞きたくなくて、俺はぎゅっと目を閉じた。 「自信ないんだ? ちゃんとボスやれるか」 「、そうじゃない、そうじゃない、なりたく、ないんだ」 誰かの期待を裏切るまえに――ちゃんの期待を裏切るまえに、俺はどこかへ行かなくてはいけないのだ。でも、それもひとりじゃできない。俺はどこまでも意気地なしだ。 ちゃんが、ふ、と笑う声がそっと背中をやさしくたたいたような気がした。 はっとして目を開くと、やさしい眼差しが注がれている。 「そんなことないでしょ。だってつーくん、今までずっと正しく生きてきたよ。まぁ、幼なじみのひいき目あると思うけど、つーくんはつーくんの仲間守るためとか、つーくんの中で決まってる……うーん、信念? みたいなの貫いてきたじゃん。それをこの先もずっと続けていく。これだけでいいんだよ。みんな、そういうつーくんのことが好きで、だからついていこうって思ってるんだから」 子どものように座り込んで、大声で泣いてやりたい気持ちになった。 そんな、そんな正しく聞こえるようなこと、ちゃんの口からだけは聞きたくない。 「じゃあなんでちゃんはついてきてくれないの」 俺が言うと、ちゃんは表情を厳しくさせた。 「……その話は何回もしたじゃん。ムリなの。ダメなの」 「なんで」 ちゃんは唇をきゅっと引き結んでから、鋭く言い放った。 「なんでって、それも何回も説明したでしょ? ……わたしがいると、つーくんこうやって弱音言うでしょ。だから行かないって決めたの」 俺がイタリアに行くということは、俺から話すまでもなくちゃんは分かっていたし、その理由も、周りの大人たちが言う必要性とやらも理解していた。 それなのに、一緒に来てはくれないという。俺だけじゃない、周りがどんなに一緒に行こうと言っても頷いてはくれなかった。 俺はそれをとてもさみしく思って、同時につらくて仕方なかった。置いて行かれてしまうと思った。 「リボーンはちゃんに来てほしいってずっと言ってる」 「それはうれしいけど、でも決めたものは決めたし――そもそも、わたし並盛から出るよ」 俺の口からは、ただ「え……」という情けない声しか出てこなくて、それでもちゃんは構わず続けた。 「大学、他県の女子大に入る」 頭の中でぐるぐると繋がっているはずの思考回路というやつが、すべてぷっつりと切られてしまったみたいだ。よく、理解できない。 だから言葉だけがぽろぽろとこぼれる。 「な、並大にしたって、言ったじゃん……なんで……」 「……つーくんが、ちゃんと大人になるまでは会わない」 「な、にそれ……なんだよ、なんだよそれっ!」 怒鳴り上げて、その場に蹲った俺に降ってきた声は、どこまでも冷静だった。やさしいとは、思えない。 「ぐずぐず弱音言わなくなって、そうやって一時の感情に振り回されることがなくなるまでは会わないってことだよ」 「一時の感情なんかじゃないっ! 俺はっ、……おれは、」 ひどいことは言わないでほしい、俺は一時の感情なんかじゃなくて、俺なりの考えがあって――ときちんと説明したいと思うのに、言葉は何一つ出てきやしなかった。 すると、俯く俺の頬へそっと冷たい手が触れた。 それはとてもやさしい声をしていて、俺はやっぱり子どもみたいに、駄々をこねていたいと思った。 「……つーくん。つーくんが思ってるほど、つーくんはもう子供じゃないんだよ。ちゃんと大人になってきてるの。だから、こんなところで躓いちゃだめだよ。つーくんはみんなに愛されてて、みんなつーくんが大好きだから一緒にいたいの。……わたしだってそうだよ。でも、つーくんのためにはこれがいいの」 「……そんなの、そんなの、」 嗚咽が漏れ出てしまいそうなほど、涙が頬を濡らしていくのに、不思議と心は凪いでいる。 どうしてだろうと思ったけれど、俺はいつもこうしてちゃんに手を引かれてきたのだと思い出した。 「――だからほんとのほんとに大人になれたとき、迎えにきて。そしたらわたし、喜んでついてく。イタリアでも、地球の裏側にだって。……それじゃダメなの? つーくんが頑張れたら頑張れただけ、ずーっと一緒にいるって約束する」 右腕を目元に押しつけて、そのままごしごしとこする。 「俺は、今ちゃんにそばにいてほしいのに、」 「今? 一緒にいるじゃん」 そっと腕を外されて、見上げた顔は、いつも通りにこにこ笑っている。 「そうじゃなくて……っ分かってるくせに、なんでそんな意地悪ばっかり言うの……?」 「でもわたし、つーくんに嘘ついたことなんて一回もないよ」 そんなこと、俺が誰より一番よく知っているのに、それでも俺は彼女の言う通り子どもだから、「そうだけど……でも、」とうまい言い訳を探すことをやめられないのだ。 だって、ひとりぼっちはさみしいし、強く生きていくのには、いろんなものが必要だ。 俺に必要なのは、ちゃんだ。 「だから、つーくんが大人になったら結婚しよ」 「……え、」 「わたしがつーくんのこと、もらってあげる。全部、ぜんぶ」 ぽろっと一粒こぼれたと思うと、ぴたりと涙は止まった。 「……なにそれ、へんなの」 すっと肩の力が抜けて、まるで溜め息みたいな力のない声だった。 ちゃんはにこにこしながら、「だってつーくん、大人になったってわたしにプロポーズなんてできないでしょ、ヘタレだもん。だから逆プロポーズしといてあげるの」と言って、俺の涙を冷たい指先でぬぐった。 それからちゃんは真剣な目をして、じっと俺の目を見つめた。 「……もう一回言うけど、わたし、つーくんには嘘ついたことないよ」 俺はゆっくりと立ち上がって、ちゃんの手をきつく握りしめた。 あぁ、俺のほうがずぅっと大きくなったのに。 「……うん、分かってる。……約束だからね、絶対だからね、」 「うん、約束。……気が済んだ?」 ちゃんは俺の手を、俺と同じくらいの力で握り返してきてくれる。 それでも、俺のほうが力が強くなったんだろうなと思うと、どこかおかしく思えて笑ってしまった。 「……なぁんか引っかかる言い方だなぁ」 「こっちは友達との約束ドタキャンするはめになったんだからね。また沢田くんとなんたらかんたらって言われちゃうよ、まったく」 「俺とウワサされるの……嫌なの?」 あはは、と俺の言葉を笑うと、ちゃんはにやりと笑って「じゃあつーくんはわたしに逆プロポーズされたこと、みんなに知られてもいいの?」と意地悪なことを言う。 「それは、困るなぁ」 こんなに情けないようじゃ、誰かにとられてしまうかもしれないから。 ちゃんは俺の答えなんて分かっていたように、「でしょ?」と言って、それからなんとも自然に「じゃ、帰ろ。今日は特別に手、繋いだまま帰ってあげる」と俺の手を握る手にぎゅっと力を込めた。 「……ウワサされたくないって言ったのに」 「嫌ではないよ。ただ煩わしいだけ。つーくんとわたしって、そういうのじゃないでしょ。……別れるだなんだなんて一切無縁だもん。いちいちコソコソされるのが面倒なだけ」 俺の小さな、情けない呟きすら拾って、全部認めて味方してくれるちゃんが、俺はすきだ。 「……じゃあ、繋ぐ。……今は、ずっと離さないでとは言わないから……だから、俺が迎えにいくまでは、誰のものにもならないで」 けれど、それは俺だけで、ちゃんはそうじゃない。 俺は意気地なしだから、ちゃんのそばにずぅっといたいし、ずぅっとそばを離れないでいてほしいけれど、「……むずかしいこと言うなぁ……」と困ったように言うちゃんは、俺みたいなやつの手を引いて歩いていけるひとだから、俺なんていなくったっていい。 ただ、俺は出来の悪い聞き分けない子どもだから、「……むずかしくなんかないよ。だって俺はそうできる」と駄々をこねることくらい、なんてことない。それによって引き受けることになるどんなものより、今目の前にあるものを取られてしまうほうがよっぽど嫌なのだから。 けれど、そういうズルさも全部認めて許してくれるちゃんは、俺を咎めたりしない。 「……つーくんのそういうところ、好きだよ。そのまま大きくなってね」 「それじゃあ答えにならないよ」 「あはは、まぁほら、先のことは分からないから。……でも、約束は絶対に守るよ。だってみんながいくらつーくんを好きでも……わたしがいちばん好きだもん」 だから俺も、駄々をこねてイヤイヤをしているだけでは、いられない。 ちゃんに好きになってもらえる――ずぅっとずぅっと一緒にいてもらえる未来を、歩けるように。 「……うん。……ちゃん、絶対絶対迎えにいくから、絶対絶対待っててね」 「うん、待ってる」 俺は初めて、ちゃんの手を引いて歩いた。 定例会議だっていうのに、急に延期だなんて何がどうしたっていうんだろう。 ディーノさんはここぞというとき、とても頼りになるひとだけど、相変わらずどこか抜けてるひとだなぁ。でもそこが憎めないから、たくさんのひとがあの人についていくんだと、俺はよく知っている。情けない情けないなんて言って、みんなディーノさんのことが好きだ。 しかし、いつも時間が押すことばかりの会議がそっくりなくなってしまったとなると、いつものお決まりなだけに時間をどう使えばいいか分からない。けれど、まずは愛すべき家族へ、ただいまのあいさつが先だ、と歩いていた。 この時間だと、もう眠ってしまったかな? と思っていたところで、子ども部屋のドアから声が漏れてきた。 「――父さまは母さまのこと、だいすきなんだね」 かわいい息子の声に、優しい母親の声が答える。 「そうじゃなかったらあなたは生まれてないもの。もちろんそうよ」 「じゃあ母さまは?」 「え?」 「だっておはなしを聞いてると、父さまばっかりが母さまをだいすきみたい」 どきりとして、ドアノブにかけた手が止まってしまった。 ふふ、と柔らかい笑い声がやさしく背中をたたく。 「あら、そう? 母さまも父さまのこと、大好きよ。そうじゃなかったら、せっかくお仕事が決まったっていうのに、なーんにも分からないイタリアになんてこなかったし……父さまが迎えにきてくれるって信じて、イタリア語の勉強なんてしなかったわ。それに、こうやってあなたを生むこともなかった。父さまも母さまも、あなたのことが大好きよ。父さまが母さまを大好きだから、母さまが父さまを大好きだからあなたがいるの。だからわたしたちはあなたがかわいくって仕方ないのよ」 ぐっと手に力を込めて、ゆっくりと扉を押し開けた。 「――なんの話をしてるの?」 「父さま! おかえりなさい!」 ぱぁっと顔を輝かせて、座っていたベッドから飛び降りてこちらへと走り寄ってくる。 その小さな体を受け止めると、柔らかい声で「おかえりさない。今日は随分と早かったわね。会議だったんじゃないの?」と言いながら、ちゃんもこちらへとやってきた。 「うん、その予定だったんだけど……肝心の相手――ディーノさんが急用だって言うから……」 「……あの人はいつまでも幼心を忘れないひとね」 あんまり優しく笑ってみせるものだから、つい大人げなくも「……俺には大人になれ大人になれって口うるさく言ってたのに、ディーノさんはひいきするんだ」と言うと、ちゃんは肩をすくめた。 「あら、そんなつもりないわよ。若々しくっていいわよね、って話」 「俺のほうが若い」 「そんなこと分かってるわよ。そんなことよりほら、ただいまのキスがまだよ」 ちゃんがそう言うと、かわいい我が子は腕をめいっぱい広げて俺を見上げている。 「父さま、だっこ!」 抱き上げて頬にキスをする。 「……ただいま。いい子にしてたかな?」と俺が言うと、元気よく「うんっ! いい子にしてたよ! ね、母さま!」と返事をするので、ちらりとちゃんを見る。 ちゃんは優しい目でにこにこしながら、「うん、とってもいい子にしてた」と言いながら、俺の腕の中ではしゃぐ丸い頭をそっと撫でた。 「それはよかった。で? なんの話をしてたの?」 俺の言葉に目をきらきらさせながら、「父さまと母さまがイタリアにくるまえのおはなし!」と言うので、聞こえていた話の断片からして、どのくらいの時期の、何の話をしていたのかはっきりと分かってしまった。 「……はあ、そんな情けない話、普通子どもに聞かせる? 威厳のある父親でいたいんだけどな」 溜め息を吐きながらも、遠い昔のころが懐かしく思えるのは、俺が変わったからだろう。 だから、ちゃんの「いつも強くてかっこいい父さまにも、若いころはあったのよって話よ」という言葉にも、俺は素直に笑顔を浮かべることができる。 ちゃんが、ふと視線を落とした。 「……この子が大きくなったら、きっと同じことで悩む日がくるわ」 「……そうだね」 俺が、ここへきて、俺のやるべきこと――俺にしかできないことを見つけるまで、随分と情けない時間を過ごした。 それでも、俺にだってできた。時間がかかっても、何度も立ち止まっても。 「――でも、つーくんがこうやって“大人”になってわたしを迎えにきてくれたんだから、この子もきっとそうなるわ」 けれどそれは、俺一人でできたことなんかではないのだ。 誰だって、一人きりでは生きていけない。俺はそのことをよく知っている。 「……んー、そうだなぁ……ちゃんの息子だから、そもそも悩んだりしないんじゃないかなぁ……」 あはは、と俺が苦く笑ってみせると、ちゃんは大真面目に「あなたの息子なんだから、何があったって乗り越えられる。悩むことって大事よ」なんて言うので、俺はまた笑ってしまうところだったけれど、続いた「……わたしだってあのとき、随分と迷ったもの」という言葉には笑えなかった。 「え……」 「……つーくんを、ほんとに行かせちゃっていいのかな、やっぱりわたしがついていったほうがいいかな、とか。……わたしのことなんか忘れて、迎えにはきてくれないかも、とかね」 俺はびっくりしてしまった。 ちゃんは不安になったりだとか、悩んだりだとか、そんなこととは無縁だと思っていた。彼女が鈍いとかそういうことではなくて、ちゃんはいつだって強くて、いつだって俺の手を引いて、先を歩いていてくれたから。だから俺も、ここまでやってくることができたのだ。 それに俺はずぅっとちゃんのことがだいすきで、迎えにいかないなんてこと、あるわけがないのに。そんなことくらい、ちいさなころから一緒だったちゃんが、いちばんよく知っているのに。分かっているのに。 ほんとうに不思議だと思ったので、「迎えにいったじゃないか、ちゃんと。……そんなふうにはちっとも見えなかったけどなあ」と素直に言うと、ちゃんは困ったような顔をして、それから優しく目を細めた。 「でも悩んだの。……つーくんが行っちゃう日、わたし見送りしなかったよね」 「……あぁ。……ちょっと……だいぶ傷ついたなあ、あれ」 日本を離れる日、俺は搭乗時間の本当にぎりぎりまでちゃんの姿を探したけれど、とうとう見つけられなかった。きっと来てくれると、最後まで思っていたぶん、とてもつらかった。 今思えば、それがあったからこそ、俺は今日のような日を迎えるために頑張ることができたのだ。 ぎゅっと、俺の腕の中の宝物を抱きしめる。 ちゃんもそうっと手を伸ばして、やっぱり優しく撫でた。 「それも、悩んだからだよ。つーくんが“大人”になるには、わたしも“大人”にならなくちゃいけなかったから」 呆けた声しか出なかった。 「……え?」 「だってそうでしょ? つーくんが立派な“大人”になるって分かってたもの。あんなこと言っといて、わたしが成長してなかったらダメに決まってるじゃない」 ――そんなこと、思いもしなかったなあ。 思わず笑ってしまった。 俺は幼くて幼くて仕方なかったけれど、ちゃんだって同じく、年相応に幼かったのだ。 そんなことにも気づかないほど、俺は自分のことだけで精一杯だったけれど――今は、守るべきものがある。たくさん、たくさん。 「……ふふ、そっか。……ね、俺たち――俺は、“大人”になれたかな」 ちゃんも「ふふ」と笑い声をこぼして、それから「誰より素敵な“大人”よ」と言ってそっと俺の胸元へ視線をやった。 「……うん」と返事をしたところで小さな寝息が聞こえて「――あれ、寝ちゃった?」と言いながら、あぁ、ちょっと重くなったかなぁと感慨深い思いに心がきりりと締まる思いがした。 「つーくんが帰ってくるまで眠らないって頑張ってたから、顔を見たら安心したんでしょうね」という言葉に、俺は一層強く、守るべきものがたくさん増えたなぁと思った。 あのころはそれをとても怖いことだと思っていたけれど、本当はこれほど幸せなことなどないのだ。今なら、分かる。 「……いつか、この子も“大人”になる日がくるんだよね」 「そうよ。……楽しみだね、つーくん」 「そうだね。――この子も、いつか見つけるのかな」 俺にとっての、ちゃんのような存在を。 「? 何を?」 どんなことがあっても、大切なもの守る。 これを決意する勇気を与えてくれるような、強さを与えてくれるような存在を。 「なんでもない。さ、ちゃんからはまだおかえりのキスがないけど」 「――ん、おかえりなさい、つーくん」 俺は、俺のことをよく知っている。 意気地なしで、一人じゃなんにもできない情けない人間だ。 だからこそ、俺は俺のできることを精一杯にやり遂げて――支えてくれるひとたちのことを、大事にしていかなくちゃいけない。 俺がもし、あのころよりも成長できたのだとしたら、それはちゃんのおかげで、この先まだ強くなる必要がある俺に力を与えてくれるのもまたちゃんだ。 そして、次へとつなげていく。 |
画像:はだし