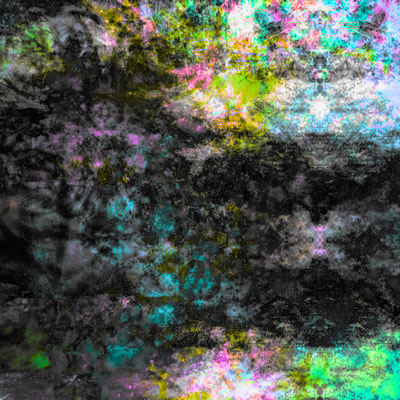
「そんな顔されたところで、俺はどうにもする気ないけど」 こんな人目のある場所で別れ話なんかして、誰か知り合いに見られでもしたら堪ったもんじゃねえなと思いつつ、まぁ手軽にスパッと話を済ませて縁を切るのには、ファミレスで結構だろうということで、俺はココにしたわけだ。 こんなふうに未練ったらしく泣かれるんだと分かっていれば、もっと他に場所を考えたかもしれないが今更遅い。 「そ、そんなの分かってます……っ! で、でも、」 「“でも”も“だけど”も散々聞いた。おまえが何言っても、俺はもう付き合ってく気ないんだよ。何回同じ話させるわけ? 俺もそうヒマじゃないんだけど分かってんの」 という女は、汗臭い男どもばっかりの伊達工ではちょっとしたウワサになるほどの美少女だった。近隣の女子高に通う生徒は駅へと向かうとき、必ず伊達工のまえを通るのだが――その中でもいちばんの美少女と言うのがこのだった。 俺の向かいに座って、こうしてはらはら涙を流す姿だって見苦しいもんじゃなく、いじらしささえ感じられる。間違いなく、美少女だ。それは女の好みにアレこれうるさいと言われる俺も、認めている。 けれども、それももう飽きたなって話なのだ。 「……そんなのわたしが、一番よく分かってます……」 こういういじらしい健気なところを、最初こそかわいいと思っていたが――それが段々とうざったく思えてくるようになったのだ。 こうして泣かれたところで、周りからの視線で居心地の悪さは感じてもそれだけだ。この女に対する感情はすでにない。 「なら俺の言いたいこと、いい加減分かるよな」 長話をする気は元よりなかったので、テキトーに持ってきていたジュースの入ったグラスの中身を、手慰みにぐるぐるとストローでかき回す。 はか細い声で、「……はい……」と返事をすると、すくっと立ち上がった。 思わずその姿を見上げると、さっきまでの涙はなんだったのか、はまるで興味がありませんというような顔をしている。それから続けて言った。 「――二口センパイって遊びやすいひとだって聞いたから引っかけたんですけど、案外めんどうなひとなんですね。ヒマないって言っておいて、わざわざ呼び出して別れ話とか。あ、律儀って言ったほうがいいですか?」 しおらしく、いじらしい健気な女。それがだ。 ――そのはずがこの女、今なんて言った? 「……は?」 「じゃ、わたし帰りますね。今までありがとうございました。それなりの暇つぶしにはなったんで、一応はお礼言っときますね」 上質な革の通学バッグを手に、は小さくお辞儀した。そんなん俺は求めちゃいない。 俺が知っていたはずの“”という名前の女は、こんな女ではなかったはずだ。 しおらしく、いじらしい健気な女。それが“”だ。 「ちょっと待てよ。それどういう意味なわけ?」 テーブルを離れようとするの腕をぐっと掴んで引き止めると、もううんざりだ、という顔をした。きっと、さっきまで俺がしていた顔だ。 はだるそうに溜め息を吐いて、けれどまたソファへと座り直した。 それからやっぱり俺にはもうまったく興味がない様子――見間違いでもなんでもないらしい――で、窓の外へと視線を向けたまま口を開いた。 「え? そのままですけど。お互いに遊び程度に付き合ってたわけだし、別れるのにもサッパリしてていいですね、こういうの。じゃ、帰ります。部活で疲れてるとこ、付き合わせちゃってすみません。でももう関わらないんで、その点は安心してもらって大丈夫です」 ここまで言うと、今度こそという感じでは腰を持ち上げた。 「……おい。じゃあ何か? おまえ、俺とのことは全部遊びだったって言いたいわけ?」 俺の言葉には不思議そうな顔をして、「え? それ以外になんて聞こえるんですか?」となんの罪悪感もなさそうに答えた。更には「この辺りではいちばんのイケメンて聞いてたので、まぁ退屈しのぎにはいいかなぁって。イイ男連れて歩くのって気分いいし。二口センパイだってわたしと似たようなもんでしょ? どうせ連れて歩くならカワイイ子がいいっていう。お互いに満足したんですから、それでよくないですか? で、もう別れたいんですよね。わたし別にセンパイに愛情もなければ執着もないんで、全然大丈夫です」と続けたので俺は開いた口が塞がらなかった。 「……は? いや、じゃあ今までの――っていうか今してたやり取りなんなの?」 はまた不思議そうな顔をした。その顔をしたいのはどう考えたって俺のほうで間違いないはずだ。まったく状況が飲み込めない。 「? 別に意味とかはないですけど。ただそういう演出あったほうが楽しいし、これをネタにして次の遊びに役立てようかなってくらいで」 「……いい性格してんな、おまえ」 俺のこの言葉の何が琴線に触れたのか、はまたソファへと座り直した。 もう冷めてしまっているだろうに、ティーカップの中のなんとかティーをティースプーンでくるくると遊んでいる。 「え? 二口センパイがそれ言うんですか? アハハ、おもしろい」 どうにも心の底からおもしろいと思っているように見えたので、俺らしくないなと思いつつも、「……さァ、ちょっとでも俺のこと好きだって思ったことあんの」と聞いてしまった。 その答えを考えてみようかと頬杖をついてみたところで、こんなイカれた女の言うことなんざ理解できないだろうが。 多少の期待はあっさりと破り捨てられたわけだから、真面目に考え始めるまえでよかった。 「ないですよ、そんなこと。ただ伊達工に“二口堅治”ってイケメンがいるって話を聞いたんで、ちょっと引っかけてみようかなぁって。まぁアレですよ、興味本位ってやつ。でもまさか付き合えるとまでは思ってなかったんで」 はティーカップを口元へ運んで中身を含んだが、なんとも言えない顔をした。 俺もテキトーに選んできたジュースを飲んでみて、炭酸が抜けてしまっていてマズイ、と苦い顔をする。 「俺もこの辺りじゃ有名な“”っていう美少女がいるっていうから、まぁ付き合えたらおもしろいかなって思っただけだけど。……そういう態度取られるとさァ」 ちらりと“”を見ると、やっぱり有名とまで言えるほどの美少女であることには変わりない。 伏せた瞳にかかるまつ毛とか、それが落とす影、淡いピンクの唇、白く透き通っている肌。どれも一級品と言っていいだろう。 「じゃあか弱い感じでもう一回別れ話します?」 まぁこの感じだと、“黙っていれば”という前置詞が必要であることは間違いないだろうが。 「なんだよか弱い感じって」 すっかりただの砂糖水になったグラスの中身をぼんやりと見つめながらそう言うと、はそれらしく「『わたし……っ二口先輩のためならなんでもしますっ! だから、だから……別れるのだけは、絶対に……いやです……』みたいな? あっはは! うっざいことこの上ないですねー、やばい。どうします? やってみます?」なんて薄ら笑いを浮かべた。 ――こんな顔は一度だって見たことがなかったなと思うと、どうにも、胸の奥に何とも言えない感情が湧いた。 あえて名前をつけようと頭を捻るなら――触れてみたい。これだ。 「……俺が知ってる“”って、そういううっざいことこの上ないような女だったけどな。……まぁでも、カワイイからなんでも許してやるかって気になるような、そういうか弱さっていうか……守ってやりたいって思うような女だった。……おまえ、誰なわけ?」 俺の探る視線をものともせず、はむしろそれを鼻で笑った。 「ハァ? 誰って……今二口センパイが言った女の性格を真反対にしたのが、ホントの“”ですけど。そっちこそどなたです? 二口センパイって、そういうめんどくさいこと言うようなひとでしたっけ?」 いや、だからそっちこそどなたです? って話をしてるんだよ、と思いつつ、この小生意気な性格だ。あれだけ従順に、何事においても俺を最優先して健気に尽くしていた相手を“めんどくさい”と言うんだから、こちらが多少なりとも引いてやる態度でいなければ今度こそさっさと帰ることだろう。それでは困る。――困ると、思ってしまった。 「……さぁな。自分ではそこそこ根性曲がってるタイプだって思ってたけど、おまえには敵わない気がしてきた。……つーか、初めから全部そういうつもりで、こういう終わり方しようって算段で付き合ってたわけだ。この俺と」 俺のこの言葉を聞くと、はこれでもかというほどに表情を歪めたあと、やっぱり鼻で笑った。それからにやにやと笑いながら、「ウワッ、“この”俺とか言っちゃいます? やばい、めっちゃ笑えますね。どんだけ自分に自信あるんですか? わたし正直二口センパイには顔以外に興味なかったし、今でもその認識変わらないんで笑っちゃいますね」と言って、本当に「アハハ」と声を上げて嘲笑するので思わず片手で顔を覆った。 その様を見てだろう。は凍てついた感情のない声で「まぁいいじゃないですか、どうせもうこれで終わりなわけですし」と言ってのけた。 ――それでは、俺は困る。 「……ま、おまえはそれでいいかもしれねぇけどさ。――気が変わった」 顔を覆っていた手をずらして、そっとへ視線を送った。 きょとんとした顔は無防備で、そういえば、はいつもどこかオドオドとした顔ばっかりしてたっけな、と今更なことを思った。まぁ、実際俺が思っていた“”という女は存在していなかったわけだし、俺は本当の“”のことなど何一つ知らないのだから当然だろう。 こんな顔をするのか、と思うと、ますますこのまま話を進められては困る。 「……ハイ?」 「今の俺には興味ないし、執着もないって言ったな、おまえ」 は俺を気遣うような素振りすら見せず、「はぁ、そうですね。まったくその通りだし取り繕う必要もないですし、本心です」と悪びれることなくはっきり言った。 どう考えたって俺が言うようなセリフじゃないが、たとえば。 「――例えばだけど。俺がここで『がそばにいてくれるなら、なんだってする』とか、そういう、別れるくらいならなんとかかんとか〜っていうようなこと言ったらさ、おまえどうする?」 「え、気持ち悪いなぁって思いますけど」 まぁそれはそれは素早い回答だったもんで、眉がぴくりと引きつったのが分かった。 しかし、次の瞬間には口端がきゅっとおもしろいほど簡単に吊り上がった。そうだ、俺はそういう男だった。 「……へえ? おまえ、マジで生意気もいいトコだな。……ちなみに、俺は自分に楯突くような女って心底うざったいと思うし、この世で一番嫌いなタイプなんだよな」 興味なさげに「へえ」と応えるに、「だからさ、」と俺がにこりと笑ってみせると、今度はが眉をぴくつかせた。 「――チャンにこういう小生意気な態度取られて、その上こんなクソ腹立つ話聞いちゃった以上は別れてやる気なくなった」 「……二口センパイってヒマなんですか?」 ハッと人を小馬鹿にしたあと、は首を傾げてにこりと笑った。クソ、顔だけはかわいい。 「テメーその辺でブチ犯してやろうか」 「然るべき対処しますよ、その場合」 まぁごもっとも、と思いつつ、俺は頬杖をついてじっとの目を見つめる。 その目からは、何を思ってこんなことしてんだかという理由は分からない。まぁ、俺はこの目の前の女のことを何一つ知らないのだ。これもやっぱり当然のことである。 溜め息を吐きながら、「……かわいくねーヤツ。今までのカワイイ俺のカノジョはどこ行っちゃったワケ?」と言う俺に、は笑顔を崩さない。 「いやだから初めからそんなのいないんですって」 ここまでくるといっそ清々しいなと思うが、まぁこんなクソ生意気な女に今の今までずっと騙されていたのだと思うと、まぁ腹が立つもんは腹が立つ。 「ホンットまんまと騙されたとかしか言いようないよな。……クソ、マジ腹立つ」 は腕を組んで顎を上げた。 この負け犬、と見下されているようでますます腹が立つ。 「この人見る目ないんだなぁ、かわいそう。っていっつも思ってましたよ、わたし。まぁでも、なんにも知らずに『俺のこと好きだもんな』とかドヤ顔かまして好き勝手する二口センパイには毎度笑わせてもらってました。二口センパイって騙されやすいひとですよ、ほんと。今後は気をつけてくださいね。危ないですよ」 「……『わたしが守ってあげますから』とかないの、おまえ」 「え? わたしたち今別れ話してるっていうか、別れるってことで話まとまりましたよね? なんでわたしが二口センパイなんか守ってあげなくちゃいけないんですか? もうなんにも関係ないのに」 “関係ないのに”。 俺は確かにこの女の言動にひどく腹を立てているが――いるのに、ああそうだな、じゃ、サヨナラと言えない。 そうなってしまったら困る。触れたいと思った感情の行き場は、もうたった一つしかないのだから。 「おまえも大概鈍い女だな。別れる気なくなったってさっき言ったよな」 「え? 二口センパイってバカなんですか? わたしそれに頷いてないですけど。せっかく身長と顔だけは恵まれてるんですから、センパイの言う“カワイイ”カノジョ、見つければいいじゃないですか。二口センパイのワガママなんでも聞いてくれて、隣に置いとくだけで満足できるカワイイ女の子」 「おまえこそバカじゃねえの? 確かに俺、従順な女って好きだけどさァ……それより、俺に絶対屈しないって顔してる女を落とし込むほうがよっぽど好きなんだよ」 “”と言う女は、気持ち悪いものでも見た、というような嫌悪の感情は、相手を気遣ってその場はなんとか取り繕う。そういう優しさは持ち合わせていないらしい。 まぁ俺もそういうタイプなので人のことを言えないが――この顔でそういう顔をされると、まぁ堪えるものがある。 「ウッワ、ほんと性格悪いですね。取り柄って身長と顔しかない……」 「うるせえな、見た目だけで根性はとことん歪んでるおまえにだけはとやかく言われたくねえよ」 は薄く笑った。 「――でもそんな歪んだ女に縋りたくなっちゃってるんですよね。……かっわいそ」 その通りなので、「……他に言いようねえの? 俺がこれだけ譲歩してやってんのに」と言うと、はますます嫌悪感あらわな顔をした。 「譲歩って。二口センパイ、自分の立場分かってます? わたし、センパイにはもうカケラも興味ないっていうか……初めから“こういう”予定だったんで、譲歩“してやってる”とか言っていいと思ってるんですか? やっぱバカ?」 ぐっ、と思わず言葉に詰まってしまった。 実はクソ生意気だったこの女には、クソ生意気だと散々に先輩たちに言われている俺は“問題外”らしい。まぁ、やっぱりこれも俺も同じタイプなのだ。よく分かる。 「……じゃあ俺の“カワイイ”“カノジョ”でいてくれんなら、まぁ大体のことなら聞いてやるから。……どこも行くなよ。俺ンとこいて」 本当は“なんでも”と言ってもよかった。俺がもしの立場だったとして、どうするかなんて知れていることだが、その知れてるようにはなっていない。 なんでだよという話なわけだが、自分でもよく分からないあやふやな感情が俺を呑み込んでいるのだ。まぁつまり、俺はこのクソ生意気な顔してクソ生意気な暴言吐きまくる女の、このひねくれた部分にこそ触れてみたいと感じている。 思っていた女と違ったからだとか、今度は俺がやり込めてやりたいとか、そういうのとは違う。自分で言うのは癪だが、そういう性格をしている自覚はあるので(自覚がないヤツよりはマシだと思っている)。 ただ、好き勝手ばかりする俺に散々付き合ってきて――そしてこういう別れ方をしようと考えていて、でもなんだってそんな面倒なことをするのかという理由が知りたい。 の心の核に触れてみたいのだ。 「うっわ、投げやりもいいとこですね。気持ちが全然感じられないんですけど。……もういいじゃないですか。めんどくさくないですか? どっちにしろお互い遊びで始めたことだし、二口センパイもそもそも飽きたって思ったから別れようって思ったんですよね? なのにいざ別れ話になって、わたしの本心知ったからって『これからも付き合ってこう』ってどう考えてもおかしいですよね。それでなんでわたしのこと引き止められるって思うんですか? マジでバカなの?」 こんだけクソ生意気でクソ腹立つこと言われてんのにも拘わらず。 「……そんな顔されたってどうにもできねえっていうか……。……どうにもしたくない。そう思っちまったんだからしょうがねえだろ。別れ話、ナシ」 「だからそういう自分勝手なとこどうにかなんないんですか? めんどくさいな。……じゃあ聞きますけど、わたしがこのまま二口センパイと付き合ってて、何かいいことってあります?」 ――それにしても、俺と似てるったらねえな、この女。 そのセリフまんまのこと、俺も言うだろうなっていう。 「じゃあ俺も聞くけど、何を叶えてやったらいいワケ?」 「あ、まずその上から目線、やめてもらえます? 心底腹立つんで」 「……分かった。つまりチャンのご機嫌取り頑張ればいいワケだ」 「その嫌味っぽいとこもムリ」 いつも俺を相手にしてる先輩らの気持ちがちょっと分かってしまったような気がして、まずいジュースを一口飲んだ。 まぁ今はそんなことは関係ないし、と気を取り直しつつ「……具体的にどうしてほしいとかねえの?」という俺の言葉に、が「……とにかく自分本位に動くのやめてください。ウザいんで」と返したきたので、関係ないことまったくねえなコレ、とやっぱりジュースを一口呑み込んだ。ただの砂糖水と思うと、舌がおかしくなりそうだと思った。 はまるで他人事のような顔をしながら「あといちいち嫌味っぽいこと言うのも生理的にムリ。二口センパイってホント身長と顔しか取り柄ないんで、ただ黙っててくれるなら隣歩くくらいなら許してもいいですよ。っていうかそれ以上はムリ」と言うと、俺を窺うように上目遣いをした。かわいい顔してかわいいことしてるはずが、ケンカふっかけられてるようにしか思えない。 なのに、俺は譲ってやるのだ。 のことをイカれた女と言ったが、これはどう考えても俺がイカれてる。 まさかこんなアホみたいなこと、俺が言う日がくるとは思わなかった。 その辺の、なーんも取り柄のないフッツーの野郎が言いそうなセリフ。相手のことなんも楽しませてやれてないくせにエラッソーな野郎のセリフ。……。 「それじゃ付き合ってるとは言えないだろ」 は呆れた溜め息を吐いて、「いや、だから別れ話してたんじゃないですか。何高望みしてんですか? そういうとこがムリなんですってば」と言うと、テーブルに肘をついて傷みのない毛先をくるくると弄びはじめた。 ぐっと唇を噛む俺の情けないこと。 「……じゃあ百歩譲って、隣歩くの許して。とりあえず、今はそれでいい」 俺の言葉に、は噂になるほどの美少女――らしい笑顔を浮かべた。 「……へえ。そんなにわたしのこと好きですか?」 クソ、腹立つなマジで。 そうは思っても、まぁつまりはそういうことなんだろう。言い訳のしようがない。マジでイカれてる。 「……そうらしいな。今まで散々大人しかったおまえに盾突かれ――ワガママ聞いてきてくれたおまえのコト、今度は俺が大事にしないとダメだなって思ったから。……一緒に、いたいって、思ったから。……そんだけ」 「……そういうこと言えるんですね。うん、ならあと少しくらい付き合ってもいいですよ。ただし、これも結局二口センパイのワガママなわけですから、わたしがその気なくしたら今度こそ別れてくださいね。これだけは譲りません」 はやっぱり他人事というような感じで、今この瞬間も、この後も、その先のこともまるで考えていない顔だ。 どうせ、という自分の予想は外れない。外れるわけがない。そういう顔だ。 にやりと俺が笑うと、も同じように笑ってみせる。 「――それで上等。おまえが『飽きた』って言うまえに、マジで落とし込んでみせる」 「まぁ、やるだけやってみてくださいよ。わたしも今まで散々好き勝手してくれたセンパイの情けないところ、存分に楽しませてもらいますから。――楽しみですね、どうなるか」 「……その生意気な口、また塞いでやるよ」 「あ、早速減点。……今ならまだ間に合いますけど? 負け戦って分かってるんだし、傷は浅いほうがいいでしょ?」 「何言われたって“カワイイ”“カノジョ”、手放す気ないから。また『二口センパイ、好きです』って何度でも言ってもらうことにする。……“そのとき”になって、『やっぱりだめです』って逃げるなよ、チャン」 薄く笑っているこの顔こそが、きっと“”だ。 思わず舌舐めずりでもしそうになった。 これがきっと、この女の心の核だ。 「なんだっていいですよ、別に。わたしホントそういう……なんにも中身ないくせに好き好き繰り返すだけのちゃんちゃらおかしい遊び楽しんじゃってる――バカみたいな脳内麻薬にハマってる人間、大っ嫌いなんで。二口センパイがどういう決意しても、どういう言動取ったとしても、わたしそれに浸かる気ないんで」 どういう理由で、なんてのはこれからきっと分かっていくことだろう。 俺が触れてみたい目の前の女は、本当はどういう顔をするんだろうかと思うと、そのときが待ち遠しくて仕方ない。 どんな顔で、俺を好きだと言うだろう。 「尚更いいじゃん。……おまえが小馬鹿にしてるその“脳内麻薬”ってヤツ、ハマると怖いよ? 今の俺がいい例だろ。……どっぷり浸からせてやるよ。『二口センパイ好き好き〜っ!』って」 「……想像するだけで吐き気する。まぁ、なんでもいいですよ。――ただ、わたし負ける勝負はしない主義です、何があっても。いくらバカでも、意味分かりますよね?」 クソ生意気な顔をして、人を小馬鹿にした態度、声音で吐き捨てた。 「――っとにムカつく女だなチャン? ま、俺もそれで引き下がるような男じゃないから、その辺りはヨロシク。……おまえが負け戦には挑まない女なら、俺は勝負が終わるまでは諦めない男なんでね」 がうんざりという顔で「二口センパイもホントにうっざいですね。じゃ、わたし帰りますね。もう疲れた」と言って立ち上がったので、俺も立ち上がる。 「じゃあ送る」 さっさと歩き出したの手を取ろうと、後ろから静かに近づく。 ――が、あれだけのことを言う女なわけだから、見事なまでに俺の下心を察知したらしい。 振り返ってたった一言。 「……ほんっとうっざ」 |
画像:十八回目の夏