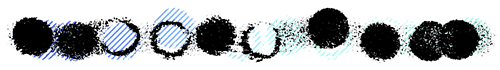
その人は時たま体育館を覗きにくる人で、そのときには必ず差し入れをくれるから名前は知っていた。 「見つかっちゃったのが影山くんでよかったぁ。月島くんとかなら弱味握られるってことだから、とっても困ったもの」 言われていることの意味は全く分からなかったが、つい先程までさんが(確か)女子バレー部のキャプテンと話しているのは見た。 「わたしが大地と付き合ってるの知ってるよね。わたしね、誰にも邪魔されたくないの」 「はあ」 「だからね、釘さしておこうと思って」 体育館で見るこの人は、いつもにこりと人の良い笑顔を浮かべていて、俺たちが差し入れを食べている間、キャプテンに控えめに寄って話をしている。それを田中さんと西谷さんが「さすが大地さん! 彼女もいい人だよな〜! 部活に差し入れくれるし、あんな優しそうで可憐でよぉ!」なんて話し合っている。キャプテンもちょっと照れくさそうにしていて、それを見ている限りでは確かに田中さんたちの言う通りだと思う。でも、今目の前で笑っている人が“可憐”とは思えない。いつもと同じように笑っているはずなのに、何を考えてんだか分からない目をしている。唇のカーブがほんの少しいつもより強い。俺は曖昧に返事をしたが、それはこの人が――さんが怖かったからだ。田中さんや西谷さんが言う“いい人”、“可憐”な人には到底見えなかったからだ。 「結ちゃんてね――あぁ、さっきの女バレのキャプテンの女の子。あの子ね、大地のこと好きなのよ」 なんと返したらいいのか分からなかった俺は、生返事で応えた。 居心地が悪い。そんな俺の様子を知ってか知らずか、さんは言葉を続ける。 「それでね、あの子ってばそれをわたしが知ってるって気づいてないのよ」 「……すみません、話がよく……」 なんだか喉の奥がひどく乾いている気がした。これ以上聞いてしまったら、俺はとんでもないことの“共犯者”にされてしまうのではないかと。さんの笑顔はどこか歪で、俺が見たことのあるものではなかった。それでもきっとこれは可憐でいるんだろう。俺にはよく分からないが、その目はとても優しいからだ。 けれどさんの声の調子は鋭く、まるで敵を見つけ、それを排除するのだと言わんばかりだった。そしてそれは本当だった。 「釘をさしたって言ったでしょ? 『わたしね、結ちゃんと大地くんが仲良くしてるの見ると、ちょっと妬いちゃう』って釘を差したの」 「? そんなことしなくても、さんてキャプテンと付き合ってるじゃないスか」 馬鹿な俺はそう聞いた。 瞬間、さんの目がぎらっと光ったような気がして、背筋に悪寒が走った。 「そうよ。けど、ムカつくじゃない。自分の男が他の女に好かれてるのなんて」 その理由を説明されても、恋愛なんてしたことのない俺には分からないだろう。けれど現状をさんがとんでもなく不快に思っていて、どうにかしてやろう――多少汚い手を使ってでも――と考えているのは頭ではなく体で理解した。 さんは「結ちゃんてわたしの“親友”だから、『そうだよね』だって。笑っちゃうよね、アハハ。わたしは結ちゃんのこと、そんな風に思ったことなんて一度もないのに。少なくとも、あの子が大地のことを好きだって分かるまではね」と言って、何もいじっていないんだろう綺麗な黒髪を指先で遊んでいる。俺はこの場から逃げ出したい一心だ。でも、ここでさんの話を聞かなかったら――どうなるんだろうか。そう思うと、俺は一歩でさえ足を踏み出すことはできなかった。それほどまでに、さんの目は恐ろしかった。 「つまり何が言いたいかっていうとね、影山くんが見たこと、今聞いたこと全部忘れてほしいの」 見たことはともかく、自分から話を聞かせたくせしてなんて難題を押しつけてくるんだろうかと思ったが、頷く以外にはなかった。さんは可憐な笑顔を見せて、「よかった、見つかっちゃったのが影山くんで。本当にね」と言って何事もなかったかのように校舎の中へ戻っていった。俺はしばらくその場から動けなかった。 「影山ァ」 「? うっす」 キャプテンに声をかけられたときには、俺はもう数日前のことなどすっかり頭から抜け落ちていた。 けれどそのことも予想していたのか、さんは周到だった。 キャプテンは人の良い、何事にも動じないというようなカラッとした笑顔で言った。 ほんの少し照れたような顔をしたので、俺はそこでギクッとした。 さんの光った眼差しが脳内を駆け抜けていった。 「悪かったなぁ。こないだが影山に迷惑かけたって聞いて……」 「……いえ、なんでもないです」 「いや、から言われたんだよ、謝っといてくれって。『バレー以外のことで煩わせるようなことしちゃってごめんね』だってさ。アイツ、おまえに何か相談したのか?」 相談も何も……と思ったが、もちろんそんなことは言えやしない。特にこの人には、絶対。だからさんは俺にまで“釘をさして”きたのだ。よかった、見つかっちゃったのが影山くんで。本当に。さんの声が聞こえてきそうなほど、俺は身震いしそうになるのを堪えるしかなかった。 キャプテンは困ったような顔をして、「そんなにおまえを困らせるようなこと言ったのか? アイツ。ったく、しょうがないね……。なんか困ったことがあれば俺に言えって言ってんだけど……」と頬を指でかいた。 あの人が困ったとして、誰かに頼らなければいけない場面など俺には想像できなかった。何せ“釘をさす”のがここまで上手い人なのだ。何かが起こるまえに、その芽を摘み取ってしまうに違いない。 するとそこへ、「こんにちは」という声が聞こえた。 誰のものかすぐに分かって、やっぱり俺は身震いしそうになった。 「あぁ、ちょうどよかった。今、影山に伝えたとこだぞ、おまえの伝言」 「ありがとう。それで、この間のお詫びとお礼にって思って……差し入れ持ってきたの」 「いつも悪いな。あ、それはそれでいいとして、おまえ後輩に迷惑かけてどうすんの? 困ったことがあれば俺に言えっていつも言ってるだろ」 そう言ってキャプテンはさんの頭を小突いたけれど、それは意味あんのかな、と思うほど優しいものだった。いつもキリッとしていて頼りになるキャプテンだと思っているし、なんの曇りもない真っ直ぐな人だ。それがどうして、こんな人に――さんみたいな人に捕まってしまったんだろう。あの女バレのキャプテンのほうがよっぽど――と思ったところで、さんと目が合ってしまった。心臓を握られているかのように、どくどくと高鳴ってその動きが分かる。さんはくすっと笑ったあと、可憐な笑顔でキャプテンの手をするっと握った。 「ごめんなさい。でも、ちょうど影山くんがいたから、話を聞いてもらいたくって」 「だから、それを俺にしろって言ってんでしょうが」 「だって影山くん、わたしが“困ってる”ところにちょうど来てくれたから……」 “困る”? この人が? まったく想像がつかない。だってこの人は自分で何もかもをどうにでもできてしまう人だ。あのとき、たまたまそこに俺がいて、たまたま話を聞いてしまったから――もしこういう場面になったとき俺が何かぽろっと零さないように、“釘をさした”のだ。こういういざというときのため、万一のため。 ちらっと視線を寄こしてきたさんに、俺は頭を下げた。 これはもう挨拶とか、大丈夫です、なんていう意味じゃなく、その場に膝まづくようなもんだ。 「次からはちゃんと俺に言えよ。先輩なんだから、おまえが話を聞いてやるくらいでなきゃダメでしょうよ」とキャプテンが言うと、さんはまた可憐に笑った。 「うん、大地くんにはなんでも全部話す。ふふ、優しいね」 「……人がいるとこでそういうこと言うのはやめなさい」 そこへ田中さんと西谷さんが駆け寄ってくるのが見えたので「じゃあ、俺は――」と離れようとすると、さんが「影山くん」と俺の名前を呼んだ。俺の足はまた、縫い付けられたように一歩たりとも動かなかった。 「……はい」 「本当にありがとう。影山くんのおかげで助かっちゃった。あ、差し入れ、遠慮なく食べてね。……それから、これも」 さんがそう言って俺に差し出してきたのは、きれいな紙袋だった。「それ、お礼だから。影山くんにだけだから、みんなには内緒よ」と意味ありげな視線で俺を真っ直ぐ射抜いた。 差し入れに飛びつくいつもの騒がしい声は、どこかぼやけて聞こえた。 家に帰ったあと、部屋できれいな紙袋をあけた。中にはどうやら手作りらしいマドレーヌが入っていて(きれいに個装されている)、とりあえずは一つ取ってぺりっとその袋を開けて口に放り込んだ。うまい。 次から次へと手が伸びて、最後の一つを食べ終えたとき、底に紙が入っているのに気付いた。 なんだろう。――読まなければ、いや、でもこれを読んだら。あの日のような緊張が背筋を駆ける。 また身震いしそうになる体を押さえつけながら、二つに折りたたまれたその紙を開いた。 “影山くん、本当にありがとう。” 俺はその一文にそっと息を吐いた。なんだ、本当にただの礼か、と。 しかし次の一文で凍りついた。 “本当によかった。見つかっちゃったのが、影山くんで” もし俺以外の誰かがあの場に――たとえばさんが嫌だと言っていた月島だとか――がいたなら、どうしただろう。そうだ、月島ならサラッとかわすこともできたのかもしれない。それが俺はどうだ? こんなにも情けなくうろたえて。でも、それでも――と思ったところ、吐き気がしてたまらなかった。ごみ箱を引き寄せる。 けれど何も吐き出せはしなかった。 |
画像:IRUSU