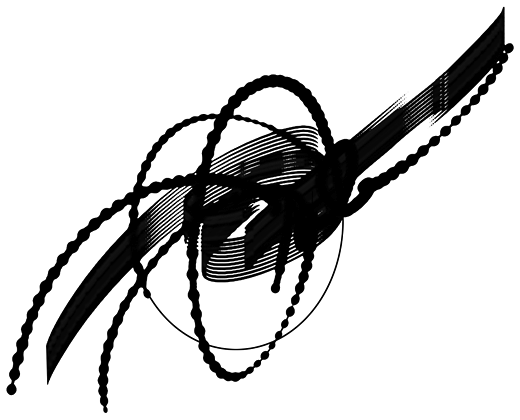
潔癖症、と言っていいだろう。という女の子――今はもう女性か――は、昔から――俺たちがまだ高校生だったころから、人との接触を極端に嫌っていた。だから彼女は、本当は心底嫌だろうにそんなこと今は構っちゃいられないとばかりにゴミ箱を漁っていた。そして小さな声で、「うそ……」と呟くと脱力して、「信じらんない、汚い、こんな、こんな、やだ……ほんと汚い、やだ……」とぶつぶつ呪文のように繰り返した。 「そんなに嫌だった? 俺と寝たの。散々かわいい声で喘いでたのになぁ」 笑い声を含んでそう言うと、彼女はキッと俺を睨みつけた。 俺はずぅっと昔から、彼女に恋をしている。というこの潔癖症の女の子からは、とっても迷惑な話だろうけれど。でも俺だってそうだ。好きな相手にキスもできないっていうんじゃそのうち飽きる。そう思っていた。でも人の感情とはままならないものだ。あれから十年経った二十八歳現在、恋人はいない。恋人にするのは、ずっとこの人と決めていた。そしてその運命を決めるのは、今朝だと。 「どうしてこんなことになったのかなんてもういい。でも、もう今後一切わたしに関わらないで」 「関わらないでって言われてもね。……ねえ、もし子供できちゃったら、どうする?」 俺の言葉に彼女は顔を真っ青にした。そうだ。昨日の晩、俺とは同じベッドで寝た。この状況からして当たり前の話だけれど、睡眠をとったという意味ではない。“そういう”意味で寝た。だから潔癖症の彼女が一心不乱にゴミ箱を漁っていたのだ。ちなみに俺は子供ができたら……と言ったが、避妊はきちんとした。でも、彼女が寝入ったあと、ゴムの口を開けて出したモノをベッド脇のゴミ箱にティッシュに丸めて投げ入れた。ゴムはありがたくもホテルの廊下に設置されていたゴミ箱に、きっちりビニール袋に入れて捨てた。妊娠の可能性はないと言えるだろう。けれど、この反応だと本当に俺に都合のいいように事態は進むかもしれない。“子供”という単語、これ一つで。 「……バカなこと言わないで。……そんなことあるわけない」 「どうしてそう言い切れるの? 分からないじゃない」 「あるわけない!! こんな……こんなの……」 彼女はごみ箱を漁っていた格好のまま、脱力したままだ。それでも唇にだけは強い意志が見てとれた。血が滲んでいる。弱々しく自分を抱きしめる腕は、時折寒そうに――いや、体をひっかくように上下する。 そこまで俺のことが嫌? と聞こうかと思ったが、当たり前だろうからやめておいた。そもそも人嫌いである彼女に、こんなトラップを仕掛けたのだ。彼女からしたら、これは最悪な現実だろう。けれど俺にとってはこれ以上にないチャンスである。 昨晩の同窓会にさんが出席すると聞いたときは、本当に心底驚いた。友達がいないわけではなかったけれど、あまり積極的に人と関わろうという子ではないのは分かっていたからだ。なのでその話をなんとなしにしてくれた幹事の女の子は、「なんか意外な感じだよね」と言っていた。俺は「そうだね、さんてこういうの嫌いそうなのに。でも卒業してもう十年も経ってるわけだし、いろいろ変わったんじゃない? 女の子って気づいたらころっと変わっちゃうからね〜。ほら、キミも昔よりずっとキレイになったでしょ?」とにこにこ笑っておいた。 さて。“子供”で彼女の気持ちを揺さぶる間に、俺のことを好きになってもらわなければ。だってそうなれば何もかも済む話だ。俺は彼女を手に入れることができるのだから。それに、ここまでずっと一途に想ってきた女の子――やっぱり女性と言ったほうがいいのかな――を不幸せにするつもりもない。俺のところへきてくれたら、何不自由なく、なんでも望みを叶えてあげよう。でもそのためには、彼女に俺を好きになってもらわなければ。 支度もろくにできていないまま、さんは部屋を飛び出していった。 「はい」 「久しぶり、さん。――同窓会の夜、アレ以来だね」 「な、なんで番号知ってるの……!」 「なんでって、きみのお友達に聞いたから」 それよりさぁ、と俺は言葉を続ける。ひどいよねえ、と。 「せっかく俺たちの子どもができたっていうのに、パパに連絡ナシなんてさ」 俺がそう言うと――きっと顔を真っ青にして――さんは金切り声を上げた。どこにいるか分からないが、そばに誰かいるとしたらきっと驚いているに違いない。 同窓会の夜、会話にこそ参加していたが、やっぱり口数は少なかったので、きっとそうだ。あぁよかった。これで彼女は俺を受け入れるしか……いいや、その懐の奥深くに招き入れるしかなくなった。 さんはやっぱり金切り声を上げて、違う違うと叫んでいる。 耳が痛い。鼓膜がぶるぶる震える。 「そんなっ、そんなっ……アンタとの子どもなわけない……ッ! 絶対違うわ、違う!!」 「そう言われてもね。実際、妊娠してるのはホントでしょ? さんに聞いたんだ」 彼女が息を呑んだ。それもそのはずだ。さんというのはさんの一番のお友達で、さんは懐に入れたぶんだけ、彼女に信頼を寄せている。きっとさんにだけ相談していたんだろう。一夜限りの関係で妊娠してしまったなんて、親にも――よく知りもしない同級生なんかにも――到底相談できる内容ではない。だからこそ俺はこの方法を取ったわけだけど、こんなにうまくいくとは思ってなかった。まさか本当に、俺の子を孕んでくれるとは。 俺はあの夜、眠ったさんのすぐそばで、自分の都合のいいように細工をした。そう、細工だ。でもそれはあくまでもさんに「これは現実だよ」と知らしめるための細工であって、それは逃げ道を絶つためだけのものだ。避妊はした。これは本当だ(もちろん言っていないけれど)。けれど、それは嘘だ。避妊はした。そう、一回だけ。“それ”以外のこと? それはもちろん俺だけが知っていればいい。 「ねえ、子どもをおろそうなんて考えてないよね」 尋ねるようでいて、俺は確信を持って言った。できるわけがない。淡白そうに見えて、実は情に厚いさんが。俺は彼女のそういうところが好きなのだ。ひたすらバレーボールを追っかけてたころから、ずっと。こんなに愛すほどに関わりがあったわけでもないので、何がそうさせたのか、どうして彼女以外のひとではだめなんだろうかと、何度か考えたことがある。でも彼女を手に入れることができたら、そんなことはどうだっていいと、毎度思ってはすぐ考えるのをやめた。だって俺はもう、彼女の存在なしに自分が在ることが不思議なくらいなのだ。その理由なんて考えてみたところで、俺にはもう他の選択肢なんてない。欲しいとも思わない。 さんの声は震えていた。しかしそれは、鋭く冷たいものだった。 「……おろすわ。記憶にない人との子どもなんてわたしは愛せないし、あなたのことだってそうよ」 「さんは絶対におろさないよ。だから俺のことを受け入れるしかないんだ」 「嫌よ……嫌……ッ! あんな汚いこと……あんな……」 もしかしたら泣き出しているかもしれない。悲痛な声色をしている。けれどそれでいい。“あんな”夜のことをきっと彼女は何度も夢に見て、俺の“あんな”言葉を思い出しては身を震わせていたに違いない。それでいい。情に厚い彼女が子ども――“あんな”かたちで孕んだとしても――を自らの意思で殺すことなどできやしない。俺は努めて神妙な声を出してみせた。 「汚いことなんて言わないでよ。せっかく俺たちの子どもができたのにさ」 「そんなの関係ない!! こんな酷いこと……」 今、どんな顔をしてるんだろう。こうかな? ああかな? 想像してみるだけでとっても楽しい。顔が見られないの、残念だなぁ。そう思うと、くすっと笑えてきてしまった。 「ひどいと思うなら、尚更だよね。子どものためにも父親は必要でしょ?」 俺の言葉に、さんは短く溜息みたく「……いらないわ」と呟いた。 「あなたみたいな父親ならいらない。だからもう構うのはよして。……生んだとしても、わたしが一人で育てるわ」 今度は、さめざめと泣いているような感じだった。なんにせよ、悪い気分ではないなと俺は思った。だってあの澄ました顔したさんが、こんなにもかわいい声で泣いている。俺のせいで。そう、俺のためにだ。俺が俺のためにしたことで、さんが泣いている。ねえ、ちゃん。そうやって甘く囁いてみるのもいいかと思ったけれど、そんなのは今後いくらでも機会があることだ。俺は笑った。 「ふぅん? ……でもいずれかは必要になるはずだよ。娘か息子か分かんないけど、“パパ”はどこ? って聞かれるに決まってる。さん、なんて答えるの? おまえは過ちで生まれちゃった子よ、なんて言えるの?」 俺の言葉に、いよいよ絶望したのが伝わってきた。声に覇気がない。 「……じゃあどうしろって言うの……? わたしがあなたを愛せるわけない。でも、愛し合っていないことを子どもが知ったら……知ってしまったら、」 「簡単だよ。俺はもうさんのこと、愛してるもん。それに、今きみのお腹にいるのは、俺の血を分けた子どもなんだよ。愛情なんてあとから自然と生まれてくるよ。かわいい、俺たちの子どもを見たらね」 さんはなんとも答えなかった。 「やっぱり俺のだっこじゃ泣き止まないねえ。、代わって」 いくらあやしても、一向に泣き止む気配がない。 心底触れるのが嫌だという顔を俺に見せるくせに、母親であるの顔はとても優しい。 「……汚い手でこの子に触らないでって言ってるの、もう忘れたの? 毎日言ってるはずだけど」 「そんなこと言ったって無理でしょ。がずっとこの子に張り付いててやれるわけじゃないんだから」 あのとき言ったように、は俺を愛さなかった。だから俺は、自分の子どもの世話を満足にさせてもらえない。俺ととを繋げてくれた子どもが、かわいくないわけがない。おまえがいなかったら、きっと――いいや、絶対に――彼女とこうして一緒になんてなれるわけがなかったのだから。なんて愛おしいんだろうね、おまえは。にあやされているのを見ながら思う。 が俺を愛すことがないのは本当だろうと思う。 でもそれは対象を変えて俺にも言えることだ。 俺は自分の血を分けたこの赤ん坊を、愛すことができていない。 俺ととを繋げてくれたことには感謝しているけれど、ただそれだけだ。それ以上の感情を抱くことができない。かわいいと思わないわけではないが、それは俺だけでない、の血も持っているからだ。俺は彼女を愛してる。彼女しか見えないまま、こうなったのだ。俺は彼女以外、愛せない。けれどそんな素振り、のまえでは一切見せたことはない。この先もそうだ。だっては、子供を愛している。愛せないと言って金切り声を上げていたくせに、散々愛すことはできないと言っていたのに。 でもこれはいいことだ。散々愛すことはできないと言っていた赤ん坊を、は今愛している。それならきっと、俺のことも愛す日がくるだろう。はそれを認めなくとも。ベッドを共にしたのはあの夜一度きりで、手のひらさえ掴むことを許されていなくとも。 「ねえ、どこか出かけよう」 かわいい俺たちの子に向ける視線とはまったく違う、愛情なんてこれっぽっちも感じられない鋭い視線を、は俺にまっすぐ向けた。 「……この子を連れて行けるところなんて限られてるでしょう。出かけるなら一人で行って」 そんな視線、もう慣れっこだ。俺はちっとも気にせず笑ってみせた。それから「それじゃあデートにならないでしょ。ほら、“かわいいチビすけ”はウチの親に任せてさ」と言って、そっと近づく。は素早く俺から距離をとると――これもうまくなったもんだ――さらに表情を厳しいものにした。声音は冷たい。 「どうしてそんなことをしなくちゃならないの。嫌よ」 くすっと笑うと、が表情を変えた。何かに――俺に怯えたような様子だ。そんな顔をしなくったっていいのに。俺がすることにはいつだって理由があって、その原因はすべてきみだってだけなんだから。 「……きみが言い出したことじゃないか。両親が愛し合ってないことを知ったら、って」 赤ん坊をベビーベッドに寝かせたは何も言わず、リビングから出ていった。支度をしてくるに違いない。そのうちに、万一「行かない」と言われるまえに、ウチの親に知らせておこう。母親は俺たちの子供をとてもかわいがっているから、きっと喜ぶに違いない。もちろん、俺たちの仲がいいことにも。 にあやされて機嫌を直したらしい神様からの贈りものが、俺の顔を見た瞬間、表情を変えた。親子ってほんと、似るもんだ。まだこんなに小さいくせに、そっくりだ。でも、この顔は怯えているというよりも――。 「あぁ、ホント、幸せだね。全部おまえのおかげだよ、ありがとう」 ――憎んでるみたい。 こんな大きな泣き声を聞いたら、は飛んで戻ってくるだろう。そのまえにさっさと電話をかけてしまおう。泣き声が電話口から聞こえたって、「お母さんと離れるのがさみしいのねえ」なんて言って、でも「夫婦の時間は大切だから、私が責任もって面倒見るから遠慮しないで」とかなんとか、母さんは無意識にうまく俺をアシストしてくれることだろう。だって、この“神様からの贈りもの”は、本当は神様がくれたものなんかじゃないというのは、俺とだけが知っていることだ。母さんに言われたら、も頷かざるをえないだろう。 バタバタと足音が近づいてくるのを聞きながら、受話器を取って実家の番号が登録してあるボタンを押した。 |
画像:irusu