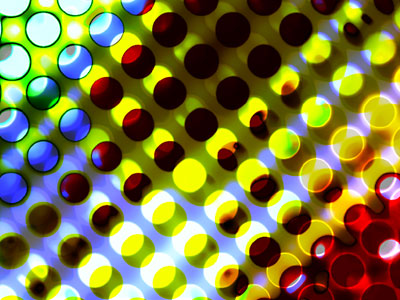
なんという言葉で表すのがいいのか、俺には分からない。ただよく分からない――外国のダンスミュージックなのか、いわゆるヒップホップ?――音楽がガンガンと鼓膜を叩きつけるように流れている。それから、この閉鎖された空間の照明は完全に落とされて真っ暗なのに、ギラギラした――ミラーボールってやつなのかな? これも分からない――とにかく、ボール状のなんだかが、色とりどりの光を放ちながらぐるぐると回って、きらびやかだ。俺は夜といえば、ゆったりとしていて、それがどこかしんみりさせて、物静かなものだと思っているから面食らってしまった。これも夜の一つなのは分かるけれど、俺にはあまりにもまぶしい。目がチカチカする。 「やぁ、最近の若い子ってこわいねぇ……。こんなとこで遊んでるんだもんなぁ」 感心するなぁ、すごい。というのと、こんなところで遊んでいて、親御さんはどうしてるんだろう……いや、そんなことよりも居心地が悪くって仕方ないな、と隣で“らしい”恰好をしているにこそっと耳打ちした。 “らしい”恰好というのは、こういう――若者が集まるクラブでも浮かないような……「さぁ、どうぞ?」と言わんばかりの、スキがありありと見てとれる恰好のことだ。もちろん、俺もいつものスーツというわけにもいかないので、「年齢考えると、ちょっとなぁ……」と気後れするラフな――と同様、“らしい”恰好をしているわけだけれど。少しでもこの場に馴染まなければ、ここへやってきた意味がない。 「ちょっと、年寄りくさいこと言わないでよ。わたしたちだってまだ若いでしょ」 は不機嫌そうにそう言うと、長い髪を横に流すようにかきあげた。白い首筋が、ギラギラした光に照らされて、なんとも言えない。ごくっとしそうなのを誤魔化すように、「ここに来てる子たちと比べたら、もう“おじさん”と“おばさん”じゃないの?」と笑う。はさらに顔を歪めて、「やめてったら」と言って腕組みをすると、指先で腕をトントンとして苛立ちを露わにした。それから「そんなこと言われるなら、この仕事受けなきゃよかった」と続けるので、俺はしまったと思った。ちょっとした冗談のつもりだったのに。 「ええ、そんなこと言わないでよ。俺だってと一緒じゃなきゃこんな仕事いやだ」 「……ふん、“おばさん”とじゃ有力な情報は得られないんじゃないの?」 一度こうなるとは強情で、なかなか機嫌を直してはくれない。俺は慌てて「悪かったよ、はまだまだきれいな“お姉さん”だ」と言ってその頬にそっと手の甲をすべらせた。は俺の手をさっと払ったけれど、表情はいくらかマシになっている。 「……まぁいいわ、とにかく証拠を押さえることに集中しましょう。別れて探ったほうがいいわね。男と女、ふたりでいたらうまくいかないわ。……あなた、目立つしね」 目立つしね、と言ったは、俺を頭のてっぺんからつま先まで、品定めでもするように視線を動かした。そんなふうに彼女の視線を浴びると、なんとも言えない気持ちになった。それを誤魔化すように、この場がそうさせているだけだと自分に思い込ませるように、「ひとりでこんなところ、落ち着かないなぁ……」と首の後ろに手をやって苦笑いする。はそんな俺の様子を見て、呆れたような声を出した。 「それなら獄寺さんにでも任せればよかったのに。ビジュアル的には一番似合ってない? 彼」 まぁ確かにそうだし、その予定だった。隠すことでもないし、隠そうとしたところで無駄だ。俺は正直に「最初はそのつもりだったよ。俺はこういうの向いてないし、そもそも『下見なんかで行くな』って言われたしね」と言いながら、やっぱりこんなところは落ち着かないなぁと周りを見回した。そして視線が戻ってきて、改めての姿を見ると、ついつい「……でも、きみがこの仕事受けたって聞いたから……」と隠しても無駄なことは分かっていても、口には出すまいと思っていた本音が飛び出てしまった。だっていくら仕事のためであって、それはこの場にふさわしいものであるからというだけで俺のためでない、彼女にその気はないと分かっていても、「さぁ、どうぞ?」という恰好なのだ。勘違いしたくもなるし、そもそも俺は――と思ったところで、がくすっと笑った。 「……相変わらず好きね、わたしのこと」 隠そうにも隠せない、隠したところで意味がないと分かっていても、こうもはっきりバレバレでいるんだと思うと、ずっと昔に過ぎ去った思春期に立ち返ったような気持ちになる。 「……さっさと終わらせよう」 「はいはい、じゃあわたしはあっちの見るからに『“取引”してます〜』ってとこから行くわ」 「え? それなら俺が――」 はあからさまに「バカなの?」とでも言いたげな顔――実際そうだろう――で、「はぁ? それこそあなたが行くところじゃないわよ。あのね、わたし“情報屋”なの。本業よ。素人が一緒じゃやりにくいわ。あなたは適当にテーブルについて、若い子とお酒でも飲みながら世間話でもしていてちょうだい」と溜息をついた。 「それじゃあ俺が来た意味ないだろ」と俺が言うと、シニカルな笑みを口元に浮かべて、意地悪くは言った。俺の耳元に、そっとその唇を寄せて。 「バカね、“世間話”にも色々あるでしょ?」 「……分かったよ。危ないと思ったら――」 「何度も言わせないで。わたしはこれが本業なのよ。ヘマなんかするわけないでしょ」 いくら情報屋で、こういう潜入捜査なんてものはの十八番なんだと分かってはいても、平気な顔をしてのんびりしていることなんてできない。これがの仕事なのは、俺が一番よく分かっているとしてもだ。は“ボンゴレ”が――つまり“俺”が、一番信頼している情報屋なのだから。つまり、今回のことを彼女に頼んだのは俺だ。けれど、情報屋としての腕を信頼していても、本人にすら分かってしまうほど――彼女のその役割を考えると、当然かもしれないが――惚れこんでいるひとなのだ。心配なものは心配だし、だからこそなんとか都合をつけてついてきたわけだ。けど、勝手をすればまたの機嫌を損ねてしまうし、今度こそそっぽ向かれたままになってしまうかもしれない。はぁ、と溜息をついた。 「――ねえ。……ねえ。ねえ、おにいさん……おにいさんってば!」 「え……あ、俺?」 危ない、まったく気づかなかった。こんなことがに知れたら、と思うとヒヤッとした。だから素人が――と言って、次の機会がやってくることは永遠とこなくなってしまうかもしれない。今回だって、一番の難色を示したのは他でもないだったのだから。 目の前の少女――見た感じ、まだ十代だ――は、にこりと笑って俺の隣へ座った。こんなところ――少なくとも、俺にはいいところだとは思えない――には似つかわしくない、かわいい女の子だ。彼女は笑顔のまま、「他に誰がいんの? ね、おにいさん、ひとりなの?」と言って首をかしげた。……最近の若い子って、ほんとにこわいなぁ……なんかオレ、ナンパでもされてるような気分だったよ。――なんてに言ったら、彼女はどんな反応を見せるだろう。この想像は少し楽しいな、と思って、俺はちょっとためらいがちに「……うん、そうだよ」と答えた。すると少女は顔を明るくさせて、「へー! 意外! あ、ねえねえ、それならなんか飲ませて!」と俺の腕を掴んで、そっと寄り添うように近づいてくると上目で俺を見た。この場面をが見たら、なんて言うかな? うん、この想像も悪くない。 しかしいくらに言われたからと言っても――使える“世間話”はこの子とはできないだろう。まぁ飲み物を奢ってやるくらいなら構わないだろうから、少し適当に話をして、他のテーブルへ移ろう。そう思った俺は、「……ソフトドリンクならいいよ。きみ、まだ未成年だろう」と言ってドリンクメニューを差し出した。もちろん、ソフトドリンクのページを開いて。すると少女はあからさまに不機嫌な表情を浮かべて、「はァ? ココきてんのなんかみーんなそうじゃん。ケチくさいコト言わないでよ〜」とメニューは受け取らず、ひたすら俺にくっついたままだ。 「そうは言われてもね」 と返しながら、さて、どうしたものかなぁと思考しようと頭が働きだしたところへ、少女は言った。 「それにさァ、アタシだけが悪いコトしてるみたいな言い方するけど、おにいさんだってそうでしょ?」 「え?」 「あー、しらばっくれるの? あ、それか初めてなんだ? ココ、未成年にアルコール出すのなんか当たり前だよ。それで酔っちゃって、なーんにも分かんなくなっちゃってる子にヤバイもの売りつけたりとか、男に――」 なんてことだ。こんな“少女”と有益な――それこそ今日の目的に手の届く――“世間話”ができてしまうとは。今聞いたところを、なんともない顔をしながら頭の中でザッとまとめると、こういうことになる。 「つまり、ココでは未成年にアルコールを提供してるどころか、ドラッグ撒いたり……女の子に、乱暴したりすることがまかり通ってるってこと?」 俺の質問に興味を示した様子はなく、少女は俺からドリンクメニューをひったくると、あちこちページをめくりはじめた。その片手間に話してあげる、というような調子で、彼女は「まぁそんな感じ。アタシは自分で飲める量ちゃんと分かってるし、アブない目に遭ったことなんてないけど。ただ楽しいから遊びにきてるだけ。だからウワサで聞いただけどね」と言った。信じられない。まだ未成年で、何事においても正しい判断、自分にとっての最善を選べるだけの分別もついていない子どもが、なんの危機感も覚えずこんなところへ出入りしている。それも、“ボンゴレ”が取り仕切っているこのシマで。俺は思わずその場で頭を抱えてしまいたくなった。 ……ドラッグのことはどうにでもできる話だ。そもそも今回のこの潜入は、その確固たる証拠を押さえること。これで手にした証拠をもとに店を摘発する、という計画のためだ。だけど、女の子の件に関しては、俺たちではどうにもできない問題かもしれない。まず、そういう――口に出したくもない下劣な行為を強いられたという本人から事情を聞けない以上、そのときの状況、状態は分からない。そしてこれを把握できずに事を進めるのは困難だ。けれどそんなこと、話したくもない内容だし、“ ボンゴレ”のシマで起きたことだ。こちらから協力を頼めるはずもない。……この店でそんなことまで起きているなんて、俺は知らなかった。この少女からはまだ引き出せる情報があるだろうと判断した俺は、愛想のいい笑顔を浮かべてみせた。 「でも、ウワサになってるくらいなら、きみもココは危ないところだっていう認識くらいはあるんだろ? どうして通うのをやめないの?」 「どうしてって、言ったでしょ? 楽しいから。ね、おにいさんも遊んで――」 少女の言葉を最後まで聞くほど、待ってはいられなかった。俺に――ボンゴレの血に備わった、時におそろしいほどの勘が鋭く冴えわたった感触を、背筋が感じ取った。 「――! ごめん、ちょっと席を外すね。また話を聞かせてくれる?」 うなじの毛がこわばるようで、俺は慌てて椅子から立ち上がった。ガンッと音を立ててそれは倒れたが、そんなことはどうだって構やしない。俺は人混みの中をかき分けて、こっちだと呼ばれるほうへと走った。 「え、う、うん……えっ?! まっ、待って、そっちは――ッ!!」 背後から聞こえた声は、言葉の意味までは捉えられなかった。 「ッ!!」 ドンッとドアを蹴破ると、はすました顔で「あら、遅かったわね」と言って、趣味の悪いドギツイ色をしたソファにゆったりと腰を下ろした。それから思い出したというように、「やることはすべて済ませたわよ。コレ、ドラッグ関係者のリスト。それから、暴行を受けた女の子たちのリストもあった。クズのすることってどこまでもクズね」と髪をかきあげると、そのリストというのを俺に放ってよこした。 俺にはそんなこと、今はどうでもよかった。本人はなんともない顔をしているが、その恰好が問題だ。確かに、「さぁ、どうぞ?」と言わんばかりの恰好をしていた。この場に馴染むために。そして“らしい”振る舞いをしてみせることで、相手のスキを作り出し、そこから必要なものを盗み取る。初めからそういうことになっていた。そのことは俺も承知していた。けれど、先ほど聞いてきた少女の話、の発言、が俺によこしたリスト――そこから推測できることなど、たった一つしかない。 「……その恰好、どうしたんだ。今回きみに頼んだ任務は、“このクラブで行われているドラッグ売買の証拠を押さえること”だったはずだけど」 脈が速くなっている。心臓が、おかしなリズムを打っている。怒りなのか、動揺なのか、どちらの感情が暴れ回っているんだか、今の俺には判別できそうもないと思った。いや、その両方であるから判別など不要なのかもしれない。は薄く笑っている。それから「どうって……別に? もちろん頼まれた仕事は完璧よ。今、確認する?」なんてふざけるように言った。 「その恰好はどうしたのかって聞いてるんだ」 俺がもう一度強く言うと、は肩をすくめた。 「他にも気になることがあったから、その情報収集のためにちょっと演技しただけ」 「……一応聞くけど、どんな演技?」 やっぱり、は薄く笑っている。 「ありがちなものよ。『ちょっと酔っちゃったみたい……』ってここへ連れてってもらって、コトが始まるまえにサクッともらうものもらっただけ」 なんてことない顔をしているに、俺はカッと頭に血が上った。 「コイツらのやってることを分かっていて、どうしてそんな危険な方法を取ったんだ!!」 「……“世間話”してろって言ったのはわたしだけど、余計な話まで聞いてきたのね」 は仕方ないとでもいうように溜息をついてみせたけれど、俺がどう思うと勝手だし、どう思われたところでそれにはなんの関心もないと言わんばかりだった。俺はそれにますます感情がたかぶって、それでいて声はいくらか落ち着きを取り戻していた。それでも、腹の底から冷たく吐き出される低い声だというのは、自分でも分かった。 「……俺は、聞いてないぞ。ここで――そういうことが行われている事実なんて」 は俺の言葉に、「でしょうね」と短く答えると、床に落ちている衣服をざっと漁って、その中から煙草を見つけて笑った。一本取り出し、それに火をつけるとちらりと俺を見る。 「これはわたしが独自のルートで手に入れた情報で、今回ボンゴレから頼まれた任務内容には含まれていないものだもの。わたしがわたしのためにやった仕事よ。手柄には興味ないから、摘発のときには持っていっていいわよ、そのリストも」 「俺が言いたいのはそういうことじゃないッ! きみに何かあったら――!!」 目的は果たした。今はすぐにでもここを立ち去って、話はそれからすればいい。頭ではそう分かっているのに、俺はやっぱりカッときてしまって、それでもこのままでは――と思っていたところで、「アランッ!!」という若い声がして、俺が蹴破ったドアへとが視線を投げやった。俺もつられてそちらへ目を向けると、ああ、なんてことだ。あの“少女”だ。 「この善良なひとに“悪いコト”教えちゃったのはあなた? お嬢さん」 そう言う唇は、意地悪く三日月をかたどっている。 「、その子はまだ未成年で――」 俺の声には声音を鋭い調子にして、「関係ないわ」と言い捨てた。 「そこで転がってるアランという男はただの手駒よ。このクラブで起きてる悪さは、全部そのかわいいお嬢さんの仕業。ま、元締めはどうやら違うみたいだけど」 「……なんだって?」 床に転がった男、と言われて、あぁ、とやっと気がついた。どれほど動揺していたのか、あからさまだ。ここで本当にやっと落ち着きを取り戻した。 いやしかし、いくらが言うことであってもそんなこと、と思って“少女”の姿をもう一度よく確認すると、「……あーあ、ホント最悪」とかわいい顔が歪んだ。 「近々ボンゴレが動くらしいって話が上から流れてきてたから、注意してたのに。まさかおにいさんみたいなキレイな顔した男が、ボンゴレの関係者だったなんてね。失敗しちゃった。おにいさんもいいカモにしてやろうと思ってたのに。アランってバカで扱いやすいし、アタシの代わりにうまく捕まってくれると思ってたのになー。アタシのためならなんでもするなんて言っておいて、ほんと使えない男」 “少女”――いや、このクラブの責任者である以上、そんなことは言っていられない――は、すらすら話した。そしては“少女”に優しく語りかける。その表情に、俺はほんの少し――だとしても確実に――ぞっとしてしまった。 「ふぅん、かわいいお顔で随分なことを言うのね。それで? ドラッグのことは金でしょうけど、女の子たちに対する所業の理由は?」 本当におかしいと思っているのか、笑い声が響いた。 「アッハハ! 理由? そんなの特にないけど。でも困るでしょ? わたしが上に立つことで、不満を持つバカが出てくる可能性があるって。だからそういう不満を発散させるのに、ココへくるバカな女を使ってあげただけ。何か問題ある?」 「問題があることが分からないなら、あなたもバカな女の一人ね。……いい? お嬢さん。アンタがしてきたことは、誰にも許されないことよ。……本当ならアンタにも同じ目に遭ってもらうところなんだけど――」 の言うことはもっともだったけれど、そんなことを許すわけにはいけない。俺たちが同じことをしてしまう。それは俺たちが目指すところではない。 「、それは――」 俺の言葉なんてまったく耳に入っていない様子で、は言う。 鋭い視線は一点――いや、一人から動かない。 「……でも、わたしはアンタみたいなバカ女に成り下がる気は生憎とないの。処断は他に任せるわ。……ただし、忘れないことね。わたしはもう、アンタの情報はすべて手に入れたわ。どこへ逃げても、何をしても、すぐに分かる。次にもし、まだバカな女として生きてるアンタを見つけたら――迷わずわたしが殺してやるから」 床に煙草を放って、ヒールのかかとで火種を押しつぶした。 「じゃ、わたしはこれで帰るわ。いいわよね」 手鏡を覗き込んで口紅を引き直すに、俺は声が震えた。 「……、どうして……」 ぴたっと手を止めて、切れ長の瞳が俺をとらえる。は、薄く笑った。 「『どうして』? 簡単な話よ。こんな状況ではなかったけど、わたしも“被害者”になったことがあるから。ただそれだけ」 「……なん、なんて……今、なんて言った……」 「わたしが“情報屋”なんてものをやっているのは、ああいうクズを――わたしを辱めた男を見つけて、この手で殺してやるためよ。だから、これはわたしがわたしのためにやった仕事なの。……質問はそれだけ?」 何事も返せなかった。そんな俺を一瞥して、カツカツと高いヒールを鳴らしながら去っていく後ろ姿に、どういう言葉をかければいいのかなんて、まったく分からなかった。ここで、追いかけていいものなのか。俺が触れてもいいものなのか。これもまったく分からなかった。ただ、きっと俺の目はがみせた昏い色を――いいや、怒りに燃え盛る色をしているに違いない。 走って、背中を追いかけた。こんなふうに、かよわく見えたのは初めてだ。 タクシーに乗り込もうとするの腕を掴むと、は驚いた様子で俺をじっと見つめた。 「ここは“俺”のシマだ。きみは、俺が心底惚れてるひとだ。――好きにしてくれていい」 は「あなたきっと、何があっても好きね、わたしのこと」と言ってくすっと笑うと、俺の束縛を優しく解いて、タクシーに乗り込んだ。そしてそれは、すぐに夜の街へと消えていった。 |