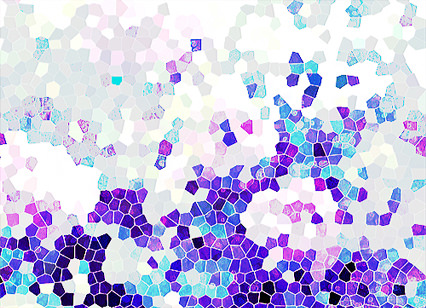
「好きだよ」 オレの言葉に、彼女は微笑んだ。どこかで分かっていたことだが、こんなかたちで確信を得たくはなかった。 彼女の微笑み方ひとつで、今何を考え感じているのか分かるほど、長くそばにいた。だからオレにはそれで充分だ。オレの恋は、ここで終わりなのだ。けれど、頭では理解できても心はそうかと頷かない。恋心は、もう昔に愛に変わっている。オレは遠くないだろう未来というのを確かに感じていたし、言葉にはせずとももちろんだってそのつもりだと当たり前に思っていた。できることなら今ここで、問いただしてしまいたい。オレの何がいけないのか、どうしたらきみにもう一度好きになってもらえるのか。 ――もう一度? 馬鹿な話だ。彼女は別れ話をしている。 「……理由を聞いても?」 オレがそう言うと、は少し驚いてみせた。それから「そんなことに興味あるの?」と言った。 それではまるでオレがに関してなんの興味もないような言いざまだ。まさか。 「きみには今、聞いておかなければいけないことがたくさんありそうだね。」 そう言って、両手を組んで前かがみに座っているソファからオレが前のめりになると、はどこに感情をおいているのか分からない表情で「そうなの?」とローテーブルのソーサーにまだ温かい紅茶の入ったカップを戻した。それから「あなたがそう言うならきっとそうね。なんでも聞いて」とオレのほうへ体を向けた。 どうしてこんなふうに向き合っているのか不思議だ。今日もいつもと変わらない週末のはずで、温かい紅茶をふたりで飲みながらお互いの話を少しずつして、それからふたり寄り添ってベッドで深い眠りに就く――そういう当たり前が、今、姿を変えようとしている。いや、当たり前なんてものはこの世に存在しない。それをオレはもう知っていたはずだ。ぼんやりと思考しながら、そんなことはどうであれ、聞かなければいけないことは決まっているのだ。答えを聞けばまたすぐに――とそっと目を伏せた。 「オレの何がいけない」 あまりにも率直すぎたかなと思ったが、まずそう聞く以外には思いつかなかった。はまた少し驚いた様子をみせて、「いけない? あなたが?」と次には不思議そうな顔をした。不思議に思っているのはこちらのほうなのにな、と思いながらも、オレは「そうだ」と簡潔に応えた。は「そんなところひとつだってないわよ。あなたはいつだって正しいし、わたしを導いてくれるひとよ」と言ってまたカップに手を伸ばした。まだゆらりゆらりと湯気が立ちのぼっている。 「質問を変える」 「ええ、どうぞ」 「きみには今、オレがきみに寄せる想いと同じものを抱く相手が、いるのか」 「どういう意味だか分からないわ」 「そうか。それなら質問を変えよう」 どういう意味だか分からないと答えたの表情からして、オレに注いでくれていたものの受け手が変わってしまったというわけではないのは分かった。それなら? 「――どうすれば、オレはきみにもう一度好きになってもらえる?」 「……ばかね、そんなことを言い出したら終わりよ」 カップをまたソーサーに戻すと、はそっとソファから立ち上がってバッグとジャケットを腕に掛けた。その表情は彼女の髪が隠してしまって窺えない。オレも立ち上がった。彼女の体をそっと引き寄せる。細い肩に顔を埋めながら、もう“今日で最後”だなんて言わないでほしいとだけ願う。初めに感じ取ったはずだ。これから始まるのは別れ話だと。それでもオレはの言うことに応じる気は一切なかったし、も最終的にはこんな馬鹿な話はすぐに引っ込めるだろうと思っていた。これまで積み上げてきたものを考えればそうであるのが当然だと思っていた。 ――そうでなければ、オレはどうすればいい? 「オレの“これ”は、相手を変えてまで、オレの中で生き続けることのできる感情ではない」 オレの言葉を聞くと、はオレをそっと突き放して、はっきりとオレの顔を見て笑った。オレを慈しんでくれている、彼女の優しさはすべてオレに向けられていると実感できる微笑みだ。それなのには、「そんなことはないわよ。いつかはまた別の人を好きに――愛するようになるわ」と言う。 「……意味が分からない。オレは今きみが――が好きだ。他の誰かなんて、」 「人はいくらでも人を好きになれるのよ。……わたしは征十郎に対して、ちょっと欲張りすぎちゃったの」 「どういう意味だ。オレはなんでもきみに許す。きみが与えてくれたすべてを、オレもきみに与える。今までずっとそうしてきたじゃないか。何に不足を感じるんだ?」 不足なんて、ちっともない。ちっともないのよ。はそう言ったが、別れの意思をはっきりと浮かべた眼差しのまま、「……“好き”だけじゃうまくいかないことってたくさんあるのよ」と言って、さらには「……こんなありきたりなこと、あなたに言う日が来るなんて思わなかった」と続けた。 “好きだけじゃうまくいかない”。確かにありきたりだ。オレも聞いたことはあるし、読んだこともある。実際にそのさまを見たことだって。けれどそれがオレたちに当てはまるとは思えない。昨日まで――いや、こんな話を始めようというまえまでは、いつもと何ら変わりなかった。オレには今の先が見えている。今と違った関係性で、今とは違った幸せを噛みしめているオレと彼女の姿が。けれど彼女にその気がないというなら、それはどうしてだ? ありきたりな話だと彼女は言うが、ありきたりだからなんだっていう? ありきたりではあるが、それにオレたちが当てはまるとは限らない。いいや、そんなことがあるはずはないのに。 「どうして“好き”だけじゃいけない? その想いがないのなら、うまくいくものだってうまくいくわけがないだろう」 「――“好き”だけでは辛いのよ。そこに“愛”が育たない以上は、いつかはうまくいかなくなるの」 の言葉に、オレは言葉に詰まった。 「……“愛”……? 愛だって……?」 それから少し間をあけて、「それならオレはもう――」と口を開いたところで、は言った。 物憂げな、切ない目だ。彼女の感情がどこにあるのか、やはり分からない。その感情の姿かたちも。 「いいえ、征十郎とわたしとの間にあるのは、学生時代からの恋心で、今の現実にふさわしい感情じゃない。もう、あの頃のようにはいられないの。征十郎とわたしの間にあるのは、幼かったころの無邪気なわがままよ。今のわたしたちはもう前進して、今に見合った理性を、相手との間に育てなければいけないの。あの頃みたいに、好きにお互いの手を引き合ってあちこちへはいけない。お互いのわがままだけを通すことなんてできない。これからは、相手と手を取り合って、同じペースで同じところへ向かって、相手の意思を尊重するだけの余裕を持たなくちゃいけないの。……わたしがそうできるのも、征十郎がそうできるのも、お互い相手が違うわ」 そうだ。オレととの間にはいつだったか恋が芽生えて、それをふたりで大切に、慈しんでここまで育ててきた。オレの姿、格好と同じように、“これ”も姿を変えていった。昔と今が違うというのはよく分かっている。のことを好きだったころは未熟でいて、付き合ってからのオレも青く成熟していなかった。今ならそうでないと言えるか? そんなことはない。けれど過去のオレよりも、今現在のオレは文字通り大人になった。もうくだらない子供じみたことで彼女を傷つけることもなければ、先を憂いて悩ませることも泣かせることもないだろう。それだけの成長はしてきたつもりだ。それなのに彼女は、オレでは駄目だと言っている。彼女の言葉から感じ取れることを受けて、オレの胸がどれほど軋んでいるのか知りようもないのだ。仕方ない。だからこそ言葉があるのだとオレは知っている。 揺らがない意思の浮かぶ瞳を直視するのは辛い。はオレと“別れ話”をしているのだ。 オレを嫌いになったのではない、愛さなくなったのではないのが分かってしまう。 それなのに、彼女は“別れ話”をしているのだ。真っ直ぐに見つめ返すことが、一体どうしたらできる? オレの目を見て何か感じ取ったのか、は黙って隣をすり抜けていきそうだった。 「待ってくれ、。きみは勘違いしてる。オレがきみに抱いてるのは、もう子どもっぽい感情じゃない。先の見えている――愛情だ。きみを、愛してる。……オレはきみと――」 オレはと――彼女と、どうなりたいんだろうか。いや、彼女を愛しているんだ。ずっとこのまま、ふたりで過ごしていきたいことに間違いはない。それなら――いや、違う。けれど、オレが見ていた未来というのは、ありきたりで、恋人たちみんながいつかは手に入れる、新しいかたちの愛で、それはオレとの間にも成り立つものじゃないか。 それなのに、どうして続きの言葉が出てこないのだろう。 は仕方なさそうに笑って、「それを言う相手は、わたしじゃないわ。……きっとわたしも、あなたを愛してるけど……きっとこれは違うのよ」と向き直って、オレの頬にそっと手を伸ばし、愛おしいと指先が語りかけてくるように優しく撫でてくる。こんなに、こんなにもオレは愛されているのに。 「……そんな曖昧な答えで、オレが納得すると思うか?」 頬をすべるの手に自分の手を重ねてみたが、彼女の手はいつも通り温かかった。いつのときもオレの隣にあった温もりだ。これからも、これからだって。そう思うのに、オレはザァッと走馬灯のように過ぎ去っていく過去の記憶を彼女の瞳に見つけながら、それをぼうっと眺めるしかできない。 は分かっていたとでもいうように、くすりと笑った。何度も見てきた顔だ。 ただ、随分と大人びてしまったなと思った。それもそうだ。これは“別れ話”なのだから。 オレも彼女も変わったのだ。 「いいえ、思わないわ。でも、このまま一緒にいても辛いわ。先が見えなくなってしまったとき、あなたと過ごしてきた時間を否定するようなことは――絶対に、絶対にしたくないの。だからお願い、ここで終わらせて」 「……そうか。それなら、もうオレにきみを引き止めることはできないんだな」 オレの言葉にはやはり、くすりと笑った。オレが納得してしまったのにすら、気づいてしまっている。 オレがもっと馬鹿な男で――いや、そうでなくとも何も分からないふりをしてしまえたなら、彼女はどうしたろう。 考えても詮無きことだが、どうしてもそんな考えが脳裏をよぎる。 もう、声を聞きたくなったときに聞くことはできないし、会いたくなったときに会うこともできない。 週末にオレの家で温かい紅茶を飲んで、語り合うことももうない。 同じベッドで、深くて柔らかい眠りに就くことも。 「……そんな言い方しないで。これはふたりのための“さようなら”よ」 「……そうであることを祈るしかないな。――好きだった。愛してる」 別れの挨拶としては上出来じゃないか、と思った。少なくとも今のオレには。 オレはいつか、彼女の言う通りの誰かを見つけるのかもしれない。 「ずるいひと。……わたしも、あなたが誰より好きだった。きっと、愛してる」 ゆっくりと去りゆく後ろ姿に、心の中でそっと呟く。 「けれど今はまだ、誰よりきみを愛しているんだよ」と。 |
画像:846。