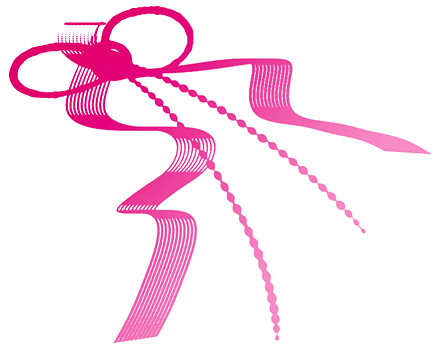
「あの、はなまきくん……」 本人としたらちょっと俯いているだけかもしれないが、なにせ身長差が身長差なので、こちらからするとつむじしか見えない。それでも大体どんな顔をしているのか分かるし、何を言いたいのかなんてのは丸っきり分かっているけれど、まぁ言わない。「ん?」なんて言って、さも親切に話を聞いてやるかのようだ。いや、もちろん話は聞くが、聞かずとも分かっていることを聞き出そうとしているので、これは大分意地の悪いことだろうなと思う。もちろんそんなことにサンは頭がいっていないだろうし、俺もわざわざ、分かってるよなんてお優しくはないからこうなっているのだ。というか単純に、俺はサンの困っているところが好きだ。 「あの……」 「なぁに」 「……あっ、あのっ! ………あの……」 尻すぼみに消えていく言葉に、俺はおかしくなってしまったけれど、笑ったらかわいそうだ。いや、なら続きを促してやれって話なんだけども。逃げ出そうにも前方には俺、背面には壁、左右は俺の腕が固めているので逃げ出すことは不可能だ。女の子の細腕でどうにかできる鍛え方してないしネ。 「あ、あの……わ、わたし、はなまきくんのこと、す、すき……だ、けど、あの、そういうんじゃなくて……」 「そういうんじゃないって?」 「え? ……えっと、つまり、あの、つ……つ、きあい、たいとか、そういう“好き”じゃなくって、あのっ、」 きょろきょろ視線をさまよわせているようで、小さな頭がフラフラ左右に振れる。俺が今何をしているかというと、好きな女の子を口説こうと中庭で壁ドンしてるわけである。こうでもしないと、サンは俺の顔を見ただけでも逃げ出すように、体になんかのシステムがインプットされてるらしい。誰がインプットしたのかは分かってる。アイツはマジで邪魔くさいにもほどがある。 「うん、知ってる。だからこうやって口説こうとしてるんじゃん」 そう言って俺が屈んで顔を覗き込むと、「……っそ、そういうの、や、やめてほしくて、あのっ、」とサンはぎゅっと固く目を閉じた。頬から目元、耳元までがほんのり赤く染まっている。これがどういうことだか分からないなんて本人だけだ。だから俺は遠慮なくずかずかと踏み入ることにしている。荒療治でもなんでもしないと、蝶よ花よと過保護に育ってきたサンには伝わらないし、自然の流れに任せていたら自覚すらしてもらえないまま卒業、サヨウナラが目に見えているのだ。俺は何にも負けない。 「なんで?」 「な、なんで? なんでって……えっと、えっと、と、とにかくわたし、こういうこと、やめてほしくて……」 「ふぅん。で、“こういう”コトって?」 「だっ、だからっ、だ、だからっ……あの、なんていうか、あの、」 「んー、キスしてもい?」 「それ! それですっ!! そういうのやめてほしいのっ! あとこういう体勢も嫌で――あ……」 ニヤッと笑った俺にサンは顔を青くした。人間相手になんかネコちゃんみたいでカワイイね、なんて思ったけれど、それもまぁ俺へのサンの警戒の仕方といえばそんなもんなのであながちハズレってわけでもないな、と思い直す。サンがネコちゃんだとして、それなら俺はなんだろう? 喉ぼとけがくつりと上下する。 「やっとフツーにしゃべってくれた。サンさ、俺と話すときいつも敬語使うよネ」 「えっ、あ、ご、ごめんなさい……?」 いつの間にか俺を見上げて見つめているまるい瞳は、ほんの少し驚いたように見開かれている。俺が怒ると思ったのか、無理矢理に何かされると思ったのか。まぁどっちでもいい。いや、よくはないけど――今後の評価に関わるので――このきょとんとした顔は初めて見るので、心のシャッター押しまくるのに忙しい。 俺は努めて平静の顔(たぶん)で、「謝んなくていいケド、敬語はヤメテくれる? 同い年だし、俺サンのこと好きだし、もっと気楽にいこーよ。ていうかちゃんて呼んでもいい? 名前カワイイよね」と本腰入れて口説く態勢を取っていくことにした。 「は、はぁ……。っ?! や、だ、だめです! 名前で呼ばなくっていいです!」 「あ、敬語。ね、次敬語使ったらちゅーしちゃうぞ」 そう言って顔を近づけると、ちゃんは顔を真っ赤にして「?! それもだめで……だめっ!」と叫んで俺の胸を押し返した。おそらく全力だろうけど、なんてか弱いんでしょうか。ほんとネコちゃんみたい。 勢いでキスできちゃったとして、それはそれで自覚を促すに効果はあるかと思うが、やっぱり女の子のファーストキスには夢がなくっちゃダメだよネ。レンアイなんて(誰かサンのせいで)ほんっっとーに無縁だったろうから、ちょっとやりすぎじゃね? ってくらいの少女マンガ演出があってもいいとすら俺は思っている。もう付き合ってからの話してんのかよって、俺はもう付き合う未来しか見えてないから当然である。 「おー、危なかったネ。俺としては残念」 顔を両手で覆っても、耳まで赤いからぜんぶ見えちゃってるよ、なんて指摘したらどんな顔するかな? といたずら心が芽生えてきて、俺はそっとその耳に唇を寄せ――「うわっ、マッキーまたやってる! ちょっと! うちのイジメるのやめてくれるっ?! おーよしよし、怖かったねえ、ちゃん。大丈夫だよ、徹くんがきたから安心だよぉ〜」出た。ちゃんをひたすらレンアイから遠ざけて蝶よ花よと過保護にしてきた誰かサン。 「うぅっ! とーるくんおそい! ばかぁ!」 厄介なのは、その誰かサン――及川を、ちゃんが心底信用して信頼していることだ。まぁ幼なじみなので仕方ないが、ただの幼なじみにしてはいき過ぎている。だってもう俺ら高三。でも及川に甘やかされてきたちゃんの“男”の基準はどうやら及川らしいので、及川には俺に見せたことのない甘い笑顔を浮かべたり、潤んだ目で見上げたり、舌っ足らずに“とーるくん”なんて呼んだり正直羨ましいことしかない。それでもふたりの間に恋愛感情はないのだ。あったらいくらなんでも攻略は難しい。そう思わせてくれるほど、このふたりの親密度は高い。でも“恋愛感情がない”、“男の基準は及川”。たったこの二点さえあれば、俺にはそれで十分だ。 恋愛感情がないのはふたりが小さなころから、岩泉を入れて完全に“幼なじみ”で過ごしてきたからで、その上、男の基準が及川であるということは逆にいえば及川以外の“男”を知らないのだ。生物学的な話でなく、ただ単純に恋愛対象として見ることのできる“男”を知らない。それなら話は簡単である。俺がその恋愛対象として見ることのできる男になればいい。それは今日までのアタックで十分伝わっている。証拠がちゃんの反応だ。なので俺の予定が変わることはないのだが、及川はライバルにはならなくともジャマであることには変わりない。 「ごめんねぇええ! 先生に呼ばれちゃってたんだよぉ〜。……で、うちのかわいいお姫様になんか用なのマッキー。それなら俺通してくれる?」 ずいっと俺を指さして、その顔でそんな顔すんなっていうヤンキーよろしくなガン飛ばしてきたので、俺はちゃんの耳にかぶりつきたいのを我慢して、「なんで及川通さなきゃなんないの? っていうか毎度毎度おまえどっから湧いて出てくんの? ちゃんセンサーかなんか付いてんの? まぁいいやチョット今ちゃん口説いてるトコだから帰ってくれる?」とシッシッとあしらった。すると及川はキィ! なんて昔の少女マンガのオンナノコみたいな声を上げた。 「それ! それだよ!! 怖がってるんだからヤメテ!! 幼なじみの危機を察知して何か悪いコトある?! 俺はこれで数多の害虫を駆除――ていうかなんでいつまでも壁ドンしてんの?! かわいそーにちゃん! 怖かったね……。ほらほら、徹くんのとこおいで〜」 「う、とーるくん、」 ちゃんの目にじわぁっと涙が浮かんだが、ここでゴメンねいってらっしゃいなんてしたら、今日も逃げられてしまう。そろそろガッツリ進展してくれないと、卒業も待ってはくれない。 「ハイ、ストップ。そんなの許すわけないデショ。ちゃん俺のコト好きだもんネ」 そう言って及川のほうへ向いた顔を指先で俺に向かせると、ちゃんはおもしろいくらいぶわっと顔を赤く染めた。そんな顔するくせに、「そういう好きじゃない」なんてよく言えるよネって話だが、それもこの及川が元凶である。ちゃんは悪くない、以上。 「この及川さんが幼なじみのちゃんがマッキーを好きになるはずありません。ねっちゃん!」 「おまえ一度と言わず二、三度死んでもう生まれ変わってくんな」 「ヒドッ!! それがチームメイトに向かって言う言葉かね!!」 「ちゃんと俺の恋路ジャマするからにはおまえは敵」 「あのね! その肝心のがマッキーのこと怖がってるんだからほっとけるわけないでしょ!?」 やれやれまたうるせえのが突っかかってきて、これじゃあまともに口説くものも口説けん……。しかし俺はにこっと人の良い笑顔を浮かべた。いいコト思いついた。サンはちょっとびくっとして警戒するような、でも興味はあるようななんとも形容しがたい、うずっとした顔を見せた。 「あ、そうそう。それなんだけどさ、ちゃん、俺のどこが怖いの? 俺怖がられるようなコトした覚えないんだケド」 「う、」 こう直球で聞いたことはないので、ちゃんが戸惑っているのがよく分かる。う、と言葉に詰まったあと何も吐き出せない様子で、ちらちら及川に助けを求めるよう視線を送っている。 「よし、全部言っちゃえ! そしたらマッキーも大人しく諦めるから!!」 「チョット及川ホントどっか行って」 俺と及川がやいやい言い合っているところ、「だ、だって……」というか細い声が亀裂を生んだ。ピシッと固まった及川をよそに、俺は「だって?」と続きを促す。するとちゃんは両手を組んだり外したりを繰り返しながら、地面をじっと見つめて口を開いた。 「は、はなまきくん、おっきいし、」 「及川と変わんないケド」 そう言って俺は地面にしゃがみ込んで、ぱっと降参するかのように両手を上げて手のひらをひらひら見せる。今度はちょっと俺のほうへ視線を向けて、ちゃんは「そっ、それに、よく分かんないことで、かっ、かわいいとか、そういうこと、言うし、」と警戒心丸出しの様子だ。そこへ及川が「はいつもかわいいよ。及川さんが保証す――」とか余計な茶々を入れてくるので、俺ははっきりと通るような声で「ホントにかわいいって思ってるから言ってるだけだケド」とちゃんのまるい瞳を捉えようと視線を動かす。ちらちら動きすぎてまったく捕まらん。と思ったら、バチッと視線が合った。 ちゃんは少しためらうように口を開いたり閉じたりを繰り返したあと、「あ、あと、ああいう、こと、平気でする、し、」と、ふるふるとした声で言うので、やっぱり警戒心の抜けないネコちゃん相手にしてるみたいだなと思った。けれど怯えさせてしまっているとしても、俺はここで引き下がるわけにはいかない。 「あー、壁ドン? だってほっとくとちゃん俺のコト見ただけで逃げようとすんじゃん」 そう答えて、俺は立ち上がってちゃんの目にまっすぐ視線を送る。けれどやっぱり逃げられてしまって――「だからそれはマッキーが怖いから!!」と及川がきゃんきゃん甲高い声をあげる。 「ホンットおまえうるっせえな及川」 ホント、ホンットこれじゃあどうにもならない。と思ったところで、見慣れた姿を見つけた。おお、神様とやらは俺をまだ見捨ててはいないらしい。 「岩泉!」 「おー、どうした……ってまたやってんのかよおまえら」 「ちょっと及川回収してってくんない? 話進まないんだよネ」 俺がそう言ってため息を吐いてみせると、岩泉の眉間にぐっとしわが寄った。それからギラッとした目で俺を射貫くと、「……いいけど、おまえ分かってんだろうな花巻」と静かに言い放った。それに対して俺は心底誠実に答えた。「分かってる。俺今回ホントにマジだから」と。 すると岩泉は「……見てりゃ分かる。確認だ。……オラッ及川! さっさと行くぞ!!」と及川の襟首を引っ掴んで引きずっていこうとする。……やっぱりおまえってば男前だよな。腕相撲勝てなくてもいい気がしてきた。しかしそこできゃんきゃんうるさい及川がまた「えっちょっと岩ちゃんのこと見捨てるの?! あんなうるうるした目で――」なんて言うもんだから、岩泉の鉄拳が飛んだ。「イテッ」という及川の情けない声とともに、ふたりは去っていった。それにちゃんは見捨てられた――やっぱりネコちゃんみたいな反応を見せた。 「えっ、とおるくんっ、は、はじめく――」 まるい瞳がうるうるとしている。ちょっとやりすぎたかなぁと思わないでもない。なんだか急に罪悪感のようなものが襲ってきた。思わずちゃんの目から視線を逸らしてしまった。けれども、このままでは何もないままにサヨウナラがきてしまって、こんなにも好きになった女の子ともう二度と会えなくなってしまうのかもしれないのだ。俺は、何にも、負けない。 何を言おうかと迷いに迷って、俺は「そんなに俺のこと怖い?」と確信を突く質問をした。するとやっぱりちゃんは言葉を詰まらせて、「え、あ、」と戸惑うさまを見せつつ、何も言わなかった。俺はたたみかけるように、「目、見て言って。俺のこと、怖い?」となるべく優しい声で、と努めて言った。ちゃんは視線を地面にじぃっと縫いつけて「こわい、よ……」とか細い声で返答をくれた。それから「だって、はなまきくんの言ってること、信じられな――」い、と続くまえに俺は口を開いた。 「シュークリーム食べに行こう」 「……え?」 いいコト――これである。もうこれしかない。なんだっていい。とにかく足がかりさえ掴めれば、あとはどうとでもする。その自信さえも失ってしまうくらいなら、初めから彼女のことを好きになどなっていない。これは本気の恋だ。俺が俺のぜんぶを賭けている、正真正銘の本気の恋だ。そういうもんはぜんぶ日常に与えるスパイスであって、あってもなくてもいいものだと思っていた俺に、初めて本当の恋を教えてくれたのはちゃんだ。本人にその気はなくとも、俺にはこうして彼女を口説くに充分な理由だ。他の誰にも、渡したくない。これを恋だと呼ばないのなら、何が“恋”なのか俺はきっと、ずっと分からないままだ。 俺はまたその場に屈むと、「俺コワくないよ。シュークリーム好きだし」と言った。もちろんちゃんは訳が分からないという顔で「??? うん?」と答えた。にこりと――いや、ニヤリと俺は笑った。 「ちゃん甘いもの好き?」 「? うん。好き」 「俺も好き。じゃあ両想いだネ」 「?! なんで?!」 これが屁理屈で道理に適っていないのは重々承知だ。けれど足がかりってヤツを見つけるためには、そこからちゃんの懐に飛び込むには必要な屁理屈である。俺は何にも負けないのだ。これはそういう“恋”だ。 「甘いもの好きなやつに悪いヤツいないし、コワいやつもいない。俺コワくない。ちゃん甘いもの好き、俺も好き。はい、オッケー。今度の月曜に行こ。俺のイチオシのシュークリーム食べ行こ」 「……え、えっと、」 ちゃんはやっぱり訳が分からないという顔をしている。でもだからこそここで押し切ってしまえば、あとはどうとでもなる。俺はどうとでもしてみせる。今度はにこりと笑ってみせて、「行こう? それでいきなり付き合ってとは言わないから、ちゃんの都合イイ日にデートしよ。で、とりあえず口説くだけ口説かさして。……絶対好きにさせてみせるから」と言って、まるい瞳を捕まえた。 「あ、はい。……は、はい?!」 「あ、敬語使った。ちゅーするよ?」 「?! も、もう! はなまきくんの、ば、ばか……っ」 そう言うとちゃんは走って逃げていった。あーあ。あーあ。こんなんじゃ絶対に口説き落としてやるしかないよなァ。 あっははは、かーわーいーでやーんの。 |
画像:irusu