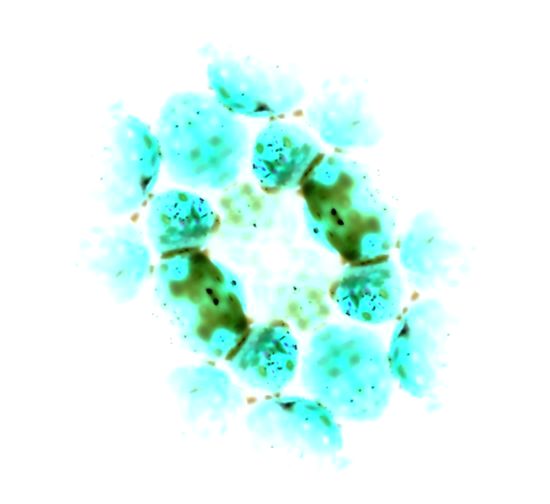
| 赤葦せんぱい、赤葦せんぱい、と俺のあとを追いかけてくる姿はとても健気で、これはもう時間の問題だなと自覚はある。俺の目を見上げてくる瞳はいつもきらきら輝いていて、あまり使わない表情筋が多少仕事をしているのは彼女の存在があるからだ。 「どうかした?」 「いえっ、赤葦せんぱいが見えたので、つい……」 「……そう」 俺より一つ年下のこのという女の子は、どういうわけだかバレー部のマネージャーになってからずっと、赤葦せんぱい赤葦せんぱいと何かと俺に声をかけてくる。それを不快に感じたことは一度もない。つまり満更でもないのだ。誰でも人に好かれて嫌な思いをするやつは、そうそういないだろう。俺も単純にそうで、このさんをかわいい子だと思っている。マネージャーの仕事も一生懸命にこなしているし、細やかな気遣いもできる優秀なマネージャーで、プレイヤーの先輩たちはもちろん、マネージャーの先輩たちもとても喜んでいる。 それはともかくとして、俺はどうやらさんを“そういう”感情で気にしているようで、休憩中だとか、彼女が一人重いものを持っていたりするとすぐに手を貸してしまう。そこから先輩方には俺の気持ちを見抜かれてしまって、散々にああだこうだとうるさいことを言われているわけだが、俺は今彼女とどうにかなりたいとは特別思っていない。俺には今はバレーがあるし、俺たちを全力でサポートしてくれているさんにも同じことが言えるだろう。赤葦せんぱい赤葦せんぱいと、俺のあとを追いかけてくれるだけで十分に優越感を味わっているのだ。もちろんいずれかは“そういう”関係になれたらいいなとは思っているが、まだそのときではないな、というのが俺の見解だ。……そんなことしてるうちに、さんを他へ取られたらどうにもならないけれど。 さんはにこにこ、ちょっと幼さも残した顔で俺の顔を見上げている。 俺が何か話し出すのを待っているようだ。 「……マネージャーの仕事はどう? 慣れてきた?」 「先輩たちのおかげで、大体は掴めてきました! でも足りてないところがたくさんで……まだまだ勉強中です」 「そう。十分にやってると思うけど」 「……赤葦せんぱいは優しいです。もっとこう、『まだまだ甘いぞ!』って言っていいんですよ?」 「いや、本当のことだから。皆さん褒めてるよ」 「うう、ご期待に沿えるようがんばります……」 「向上心があっていいね。助かるよ」 俺がそう言うと、さんはぱぁっと目を輝かせて、「赤葦せんぱいに褒められるの、わたし一番うれしいです!」と俺の両手をぎゅっと握った。びっくりしたけれど、それはもう予想外のことだったので大人しく受け止めてしまった。こんなときこそポーカーフェイスでいたい。……どこかいつもと違う――変な顔をしていないだろうか。 「わたし、がんばります! 先輩たちのサポート、できることは全部やります。だからたくさん勝ちましょうね!」 「うん、もちろんそのつもりだよ。……ありがとう。いいマネージャーが入ってくれて嬉しいよ」 俺の言葉に何故だかさんは顔を真っ赤にして、俺の手をさっと解放した。そしてその手をそのまま自分の頬へとやって、「えっと、えっと、」と言葉を詰まらせた。 「よっ、用もないのに急に声なんてかけてすみませんでした! えっと、きょ、教室戻りますね!」 さんは脱兎のごとく去っていった。 さんは部活で選手からマネージャー、みんなに可愛がられている子だ。俺の気持ちを知っている人たちは、その輪の中へ入れ入れとうるさいが、俺はそういうのはあまり得意ではないので、休憩中にそっとその様子を見つめるだけだ。にこにこ笑う姿は、やっぱりとてもかわいい。けれどどう接近すればいいのか、仲を深めることができるのか――告白をしたとして、受け入れてもらえるだろうかということを考えると、何かしらアクションをしなければならないことは重々承知である。しかし今の関係は部活の先輩後輩というだけで、いくらさんが俺を慕ってくれているとしても、それは俺が望んでいるかたちではないだろう。そこを利用して近づけばいい話なのに、何ヒヨってんだよ赤葦。なんて木葉さんなんかにつつかれるが、失敗したときのことを考えると、今のまま、慕ってもらえている先輩というポジションのほうがよっぽどいいのではないかと思うのだ。俺の一方的な思いで気まずい空気を作りたくないし、何よりさんが俺と距離を置くであろうことが怖い。かといって、このままではいけないのも分かっている。他の誰かに、というのが一番許せないからだ。今、彼女の心の中どこかしらに、俺が存在しているのに。時間の問題だ。 「赤葦せんぱい、ドリンク足りてますか?」 「あぁ、大丈夫。ありがとう」 ちょうど彼女のことを考えていたところで本人が声をかけてきたので、内心驚いた。さっきまでは木兎さんたちに囲まれてやいやいと(いつものように)構われていたのに。輪から外れていた俺が気になったのか、本当にドリンクのことが気になったのかは別として、嬉しかった。 「赤葦せんぱい、今日のセットアップすごく調子良さそうですね」 「……よく見てるね。うん、今日はなんだかボールがいつもよりしっくりきてる感じがして」 「でもあんまり無理しないでくださいね。オーバーワークとか」 「その辺りはちゃんと分かってるよ。……気にかけてくれてありがとう」 「いえっ、マネージャーですし!」 「そうだね」 「ヘイヘイヘーイ! まだ話は終わってないぞ! 昼休みに二年から告られたって話!!」 「だからその話はもう終わりです! 大体どこから聞いてきたんですかっ!」 青天の霹靂とはまさにこのことだ。 どこの誰だか知らないが、とりあえずは俺と同学年の誰かが、彼女に「好きだ」と言ったのは。それが本当なんだというのは、さんの顔を見れば一目瞭然だった。顔中、真っ赤に染め上げている。それから助けを求めるかのように、潤んだ瞳で俺を見上げた。 「赤葦せんぱい……」 「……木兎さん、そういうことには首を突っ込まないであげて下さい」 「そんなこと言ったって赤葦だって気になるだろ! ……そうだ! おまえと同学年なら心当たりあるか?!」 「ありませんし、あったとしても教えません」 答えながら、一体どこのどいつが……と俺は考えていた。心当たりがありさえすれば、その後の行方を知ることも容易だろうに。さんの反応を見る限り、オーケーしたんだろうか。それとも保留? どちらにせよ俺に分が悪いのは確かだ。オーケーなら終わりだし、保留ならば彼女が答えを考えているうちに、相手に押し切られて付き合ってしまうかもしれない。時間の問題だ。俺がバレーときちんと両立して、彼女を大事にする決意ができるまではと思っていたが、そんな悠長なことを言っていられる場合ではない。 「……とにかく練習に戻りましょう。木兎さん、それだけ元気があるならスパイク練もまだいけますよね」 「おぉ! いけるいける! 赤葦! いいトス頼むぜ!」 「分かってます」 コートへ戻ろうと背を向けてから、ちらっと振り返ると、さんはなんとも言えない顔をしていた。あんなにからかわれて、いい思いはしなかっただろう。話題に気づいていれば、助けに入ってあげられたのにな、と思った。 本当は、その真相を知るためだと分かっているのに綺麗事だ。 「あの、赤葦せんぱい」 「何?」 「あの、昨日の部活のことなんですけど、」 さんの言いたいことは分かる。昨日の休憩中に木兎さんが騒いだ、さんに二年男子のどいつだかが告白したというあれについてだろう。けれど会話に入っていなかった俺が何か言えることもないので、ただ「……何か問題あった?」とだけ言った。さんは「いえ……ただ、」と言葉を詰まらせ、そのあとを続けようというのが見えないので、「木兎さんたちの言うことなら、何も気にしなくていいよ」俺からも注意しておくから、と俺なりに気遣ったつもりだった。するとさんは急に困ったような顔で目尻を赤く染めた。 「……それは大丈夫です。あのときちゃんと説明したし、木兎さんたちも『そうか』って言ってました」 「じゃあどうしたの? 他に嫌なことあった?」 気遣い(のつもり)が間違っていたのか、何かしらがさんにそんな顔をさせて――その原因が俺だと思うと、会話の流れを蒸し返して、一つ一つ確認したいとすら思った。時間が止まったかのような錯覚まで覚えるし、そういったことを感じる心のすべてが痛い。 実際に痛みを感じるわけでもないのに、“心が痛む”という表現には、表現としては理解できるが実際のところ経験したことはなかったのでピンときたことはない。けれど今なら分かる。この現象こそ、心が痛んでいるのだ。 さんは赤くした目尻に透いた涙を浮かべて、「……あ、赤葦せんぱいは、全然気にしてなさそうだったから、わたしには、興味ないのかなって……。わたしが声かけたり、すぐに赤葦せんぱい赤葦せんぱいってついて回るの、ほんとは迷惑なんじゃないかって……思いまして……」とゆっくりとだが言い切ると、ほろっと雫が頬をつたった。 なんと答えればさんが泣かずに済むのか、さっぱり見当がつかない。彼女は俺を慕ってくれていて、俺だっていつも彼女のことを気にかけていたはずなのに。とにかくこの状況を打破するためには、さんが何を考えて涙まで流すのかという原因を突きとめなければと思った俺は、愚かにも「……俺が気にしてないことって、さんに関係あるの?」と言った。さんは驚いた――というより、激しくショックを受けた様子で「えっ、……いえ……な、いです……。すみません、急に声をかけて……」と言うと、素早く俺を背にして走り去っていった。 彼女が走り去るのをぼうっと見つめながら、俺はゆっくりゆっくり理解していた。彼女はあのまま、どこへ行くのだろう。彼女を好きだと言った男に、慰めてもらおうとするかもしれない。俺ではない男が、あの小さな体を抱き寄せて、俺が言ってしまいたいことを甘く耳元で囁くかもしれない。そうだ。これは嫉妬だ。 嫉妬心を好きな女の子に対してあんな風にぶつけるなんて、ひどいことだ。その罪悪感と、これまで築いてきたものの崩壊が恐ろしくて、俺はひたすら部活に打ち込んだ。もちろん、自主練にも。あの木兎さんに、「赤葦、まだやるのか?」と言わせるほどに。さんと俺とは部活の先輩後輩というのを抜きにすれば、何もない。部活中はお互いにやるべきことだけをやって、会話らしい会話もせずにいた。用事があるときは他のマネージャーに頼んだ。さんも俺には近づこうとしなかったし、前のように――あの日以前のように声をかけてくれることも、俺の後ろをついてくることもなくなった。そういったことで覚える“胸の痛み”はここ一週間、そうして乗り切ってきたけれど、もう無理だ。けれどどうしようもないことだと、体育館にひとり最後まで残ることが習慣化されつつあった。 誰も残っていないはずの体育館で、その声は大きく聞こえた。 「……あ、赤葦せんぱい、」 久しぶりに声を聞いた。俺のための声を。 その瞬間に俺はもうどうにも制御しきれない思いが溢れてきて、「……この間、『俺が気にしてないことって、さんに関係あるの?』って言ったけど」とさんには唐突だろうに口火を切った。「さんのことで気にしてないことなんて、一つもないよ」そうだ。たったの一つだってない。あんな風に八つ当たりして、それですっきりするでもなくさんを傷つけただろう――というような余裕さえなく、自分勝手に傷ついていた俺には。 「それ、は、どういう意味で……」 青白いようにさえ見える顔が、怯えたように俺を見上げる。今俺は、いったいどんな顔をしているのだろう。さんには、彼女の言うような“優しい”せんぱいでいたいのに。けれど、優しい“せんぱい”のままと決められるのが心底苦痛だと感じたから、俺はあんな真似をしてしまったのだ。 ふぅっと一呼吸おいて、頭の中を整理するようにゆっくりと言葉にしていく。 「俺と同学年で、バレー部に関係ないような男とどこで関わって、告白されるまで深い仲になったのかとか、さんがそれになんて答えたのかとか、気になることしかないよ」 さんが、「え、」とほんの少し表情を変えた。唇を少し開いたり、かと思えば優しく噛んだり、なんだか落ち着かない様子だ。俺は思わずくすっとしそうになったけれど続けた。混乱しているようなので、ちょっと――かなりかみ砕いて。 「簡単に言うと、俺はさんのこと好きだから、さんのことで興味ないことなんてないし……さんがいつでも俺のこと見つけて声かけてくるの、嬉しいよ。……さんこそ、それってどういう意味?」 「え、えっと、えっと、あの、」 さっきまでの顔色がうそのように真っ赤な顔で、はっきりしない言葉を何度も繰り返す。 俺の目をまっすぐ見つめたままのくせに、本当、はっきりしない人だ。 俺もその期待の滲んだ目をまっすぐに見つめ返して言った。 「俺のこと嫌いじゃなければ……赤葦せんぱい赤葦せんぱいって、これからもついてきてくれるなら、俺と付き合ってほしい。バレーが中心の生活なのはさんも分かってると思うけど、ちゃんと――大事にするから」 「わ、わたしでいいんですか? ……わたし、ずっとずっと、赤葦せんぱいしか見えてないです。告白なんて、もちろん断りました。でも……」 食い気味に返事をしたさんに、今度こそ俺は笑った。彼女のまえでは、本当によく仕事をするものだ。 「さん“で”いいじゃなくて、さんじゃなくちゃ嫌なんだ。俺しか見えてないって言うなら――俺の告白を断る理由は、ないよね?」 「なっ、ないです!」 「よかった。……本当に、時間の問題だったな……」 「え?」 「いや、何事もシンプルが一番だなって」 自分の気持ちを一つに見定めて、それをまっすぐ伝えるシンプルなことが、何よりの最善策だ。『シンプルイズベスト』先人の言葉にはそれなりの理由があるものだな。いつまでも俺のそばを離れずにいてくれるだろう人が、今までよりずっと深い意味でそばにいてくれる。 シンプルイズベスト、何事もこれに限る。 |