愛していると何度言ったとして、あなたはなにも本気にはしてくれないのだろう。ぼくがぼくとして、これ以上はないというほどにあなたを愛していても。それでもいい。ぼくはこの人に愛を囁くことほど幸せなことはないと思っているからだ。ぼくが彼女を思う心は、いつまで経ったって消えることはないだろう。ぼくが死ぬという瞬間、きっと思うのはあなたのことだ。 いつかぼくも彼女も老いて、なんにも分からなくなったとして、それでもきっとぼくはあなたが愛おしいはずだ。この世から消え失せる瞬間にすらそう思うだろうと確信しているのだ。そうに決まっている。きっとそうだから、ぼくは何度でも言おう。あなたを愛していると。そのとき、あなたもきっと心から言ってくれるだろう。ぼくを、愛していると。 ぼくが彼女のことを知ったときには、もう人のものであった。それも忌むべきことに、彼女が愛しているのは、ぼくの父親であった男だ。父であった男――ぼくにはその男の記憶などないし、その男を父親だとも認めていない。そいつがぼくのそばにいたとしたって、ぼくに興味など持たなかっただろう。いや、持ったかもしれない。けれどそうだったとして、きっと普通の親子のような関係は築けなかっただろう。だからぼくにはそんなことちっとも関係ないと思ったが、彼女は――は違った。もうどこを探したっていやしない男を、今でも愛している。存在するというのなら、ヤツの亡霊ですら愛すかもしれない。彼女の愛は、盲目だった。ぼくなど少しもその目に映っていないようだ。いや、実際そうなのだ。彼女の瞳は、黒曜石のような色をしている。ぼくもかつてそうであったけれど、ぼくのはこんな輝きを放っていなかった。 あの男の面影をぼくに見つけて笑うときのみ、彼女の暗く澱んだ真っ黒な目に光が射す。きらきら輝く。黒曜石だ。ぼくを通して見る男を思って。それを気に入らないと思うのは至極当然の感情であるとぼくは思っているが、そんなことは彼女に関係ない。はぼくを愛している。光に透けるような金色のこの髪を、彼女は愛している。ぼくがもっているもので、唯一彼女が好きなものなんじゃあないだろうか。そんなことを聞く勇気なんて、とてもじゃないが持ち合わせていない。けれど、ぼくはそれでも彼女へ愛を注ぐことをやめたりなどしないし、彼女からの愛を望むことも諦めたりしない。ぼくはぼくとして、彼女を愛する権利がある。他の誰でもなく、このぼくの意思で彼女を愛する権利がある。 愛しあった昨晩の名残が、ぼくの頭を甘く思い違いさせてくれる。彼女はいつのときも可憐でかわいい人だけれど、闇夜に浮かび上がる白い体がベッドの上で跳ねるときは一層だ。ぼくの腕の中で、ぼくの鼓動を、息遣いを感じて切なげに見上げてくるその瞳はきらきら光っている。ぼくが彼女を離すまいときつく抱けば抱くほどに、彼女の瞳は輝く。いつまでもこの時間が続けばいいのに、などと願ってしまうほどに。 けれど、いつまでもこうしていてはもったいない休日だ。ぼくはまだ眠っている彼女を起こさぬようにと、慎重にそこから抜け出した。 ダイニングにやってくると、まずカーテンを開け放った。目にまぶしい太陽の光を一身に受けて目を細める。黄金色の太陽。その温かさをこの体で感じることができる。それはぼくがあの男とは違うという、なによりの証明だ。 あの男に気持ちのいい感情を抱いたことなど、一度だってない。それがぼくがぼくである確固たる、確実な証拠だ。ぼくは、ジョルノ・ジョバァーナだ。他の――あの男じゃあない。 「また先を越されちゃった。ジョルノくんは早起きが得意ね。わたしは夜型だからかしらね、あなたより先にと思ってみてもできないわ」 今にもまた眠り出しそうな声で言いながら、彼女は対面式のキッチンのカウンターのほうへ置いてある脚の長い丸椅子に腰掛けた。「まだゆっくりしていてもよかったのに。おはようございます」とぼくが朝の挨拶をすると、彼女もそれに応えた。 そうだ、紅茶を淹れよう。彼女のために。ぼくは朝といえばコーヒーのほうが好きだけれど、彼女は紅茶を好んで飲むので、こうしてふたりでゆっくり迎えた朝にはそれがいい。ぼくは棚から茶葉(アールグレイだ)の入った缶を取り出した。すると、「ジョルノくん」とぼくの名前を呼んで、彼女はなんだか嬉しそうに笑った。そのかわいい笑顔にぼくも嬉しくなって、「なんですか、さん」と応じた声は少し弾んでいるように思った。紅茶の準備をする手を止めて話を聞いてあげようとすると、彼女はますます嬉しそうに笑った。黒曜石だ。「そうしてわたしのために手をとめてくれるところ、あの人とおんなじね」と言って。 「わたし、ジョルノくんの手ってとっても好きよ」 その言葉には返事をしないでいると、彼女は身を乗り出してぼくの手に触れた。まるで愛撫するかのように、するするとぼくの指先をくすぐる。こんなにかわいい顔をぼくに見せてくれるのに、それはぼくに向けられたものではない。彼女の目の前に立っているのは、このぼくなのに。けれど、それだって構わない。だって彼女の温もりに温もりを返せるのはぼくだけだ。ぼくの指で遊ぶ、ぼくのよりもずっと白く細い指をそっと握り返す。 「ぼくもあなたの手が好きですよ。ぼくのより繊細で、きれいだ」 「……ふぅん」と彼女は言うと、「あの人はそんなことちっとも言ってくれなかった」と続けて唇を不満げに尖らせた。 「さんの手は、とてもきれいです。ぼくは、好きだ」 ハッキリした声音できっぱり言い切ると、彼女はその澱んだ目でぼくを見た。 「ねえ、わたしのこと愛してるってほんとうにそう?」 は、とぼくは吐息みたいな笑い声を零した。愛してるかって? 「ぼくほどあなたを愛している男なんて、この世に存在しない。ぼくはさんだけをずっと愛してきたし、これからもずっとそうだ」 指の間に指を差し込んで、ぎゅっと力を込める。じんわり合わさる手と手はどちらも温かい。こんなにも近くにいるのに、温もりを温もりで返せるのはぼくだけなのに。その瞳はいつも遠くの――ぼくじゃあない男を見ているのだ。ぼくの目には、この人しか映っていないのに。この先も他の人をこの目に映そうだなんて、これっぽっちも思っちゃいないのに。 は機嫌のいいとき、いつももうとっくに死んだ男の話をする。彼女は決して決定的な言葉は口にしないが、黒曜石の瞳は言っている。あの男を過去も今も愛していると。ぼくはその瞳をみるたび、たまらなくなる。けれど、それを口に出したら、ぼくらの間に埋められない溝をつくるだろう。だからぼくはじっと耐えて、真剣な顔をしてただ頷くのだ。時折、そうですか、なんて相づちを打ったりなんかもして。ふつふつと湧く怒りも、じわじわ広がっていく悲しみにも気づかない振りをして。 ぼくは彼女を健気で一途な女性だなと思うことがないわけじゃあない。もうとっくに死んで、そしてその男がどんな男であったかを抜きにすれば。いや、どんな男であったのだとしてもこうまで愛を貫いているからこそ、健気で一途なのだ。彼女がどこまであの男のことを知っていたのか、ぼくは知らない。けれどこうして彼女が自由にしていることを考えれば、きっと何も知らなかったのだろう。黒曜石の瞳に、あの男はどのように映っていたのだろう。けれど、それは誰にも知りえないことだ。それに、もうあの男はこの世にいない。考えてみたところで何も生み出しはしないことだ。ただ悲しいことに、だからといってぼくは「そのままでいい」とは言えない。あんな男にそれだけの思いを注ぐのなら、ぼくにおんなじものを――それ以上のものをくれたらいいのに、と思ってしまうからだ。 「あの人はね、いつだってわたしをそばから離したことなんてないのよ」 「そうですか」 「とっても、愛されていたと思うの」 ぼくのほうがずっとあなたを愛していると言うのは簡単だが、彼女はそれを望んでいやしない。だから本当は、こうして可憐に笑うぼくだけの恋人に「愛してる」と言うのは、とてもむずかしいことだ。それにぼくが何度そう言ったとしても――彼女にはぼくの百回の「愛してる」よりも、思い出の中でのみ存在する死人のたった一回の「愛してる」のほうが大切なのだ。けれど、だからこそぼくは言う。口先だけの言葉だと思われたって構わない。比重など問題ではないから、「あなたを愛してる」と何度だって囁く。いつか、いつか――そう思いながら、甘い唇にこうして優しいキスをするのだ。 「……でも、あの人は最期のときだけ、わたしをそばから離したわ」 ぼくはまた、「そうですか」と返事した。それ以外の言葉を口にしたら、もう何をしてしまうか分かりきっていた。きっとぼくは彼女にひどいことを言ってしまうし、ひどいことをしてしまう。どうしてですか、なんて不毛な問いかけをしてしまうに決まっている。 それでもいいとぼくは心の底から思っているはずなのに、どうして? だなんて馬鹿げているじゃあないか。 彼女はぼくの目をじっと見つめながら、繋ぎ合った手はそのままに、反対の手をぼくの頬にゆっくりと滑らせた。澱んでいる。その目はどこを、何を、誰を見ているのだろう。真新しいこのキッチンの向こう側にいるこのぼくか、遠い異国の屋敷に暮らしていた過去の亡霊か。 彼女は恨めしそうに言った。 「それからね、ひどいのよ」 「……一体何がです」 理由なんて今更聞かなくとも、この話はもう散々に聞かされている。けれど、こうして聞いてやらないと彼女はいつまでも遠い記憶の世界から戻ってはこないのだ。そしてそのまま、そこへ身を投じてしまうんじゃないかと恐怖を抱かせる。 「あの人、最期にだけ、今みたいな優しいキスをわたしにくれたわ。いつもわたしにくれるキスは、唇が切れてしまうようなのばっかりだったのに」 そのとき、たった一回きり。彼女はそう言うと、指先でぼくの唇をなぞった。それから、「ひどいわよね、ほんとう」と言って、ぼくの手から逃げ出した。 ひどいのはあなただと彼女を責めるより、こんなものだとぼくは納得した。彼女にとってぼくという男は、所詮あの男の代替でしかない。そんなこと、今誰より彼女のそばにいるこのぼくが、分かっていないわけがない。だからこそ、こうして彼女の話を聞いて、その心の在り処を確認するのだ。ある日、彼女がぼくをぼくとして見るようになって、ぼくとおんなじだけの愛情を返してくれるんじゃないかと。それと同時に、ぼくの心にも言うのだ。ぼくはぼくとして、この人を愛しているのだと。 彼女にぼくのことを愛しているかと言うことはしない。聞くだけ無駄だと分かっている。知らない振りをしたほうがマシだ。ぼくが彼女のことを愛してると言う限りは、きっと永遠に等しい時間だけそばにいてくれる。そのことだけははっきりしているのだから、それでいい。どんな形であれ、彼女はぼくのものだ。この先いつまでも、ぼくが、彼女が死んでしまうその日までは。 ぼくは出会ったときから彼女のものだ。どんな形であれ、これは幸せだ。誰かが笑うとしても、これはぼくたちの幸せだ。だからぼくは平気な顔をしていられるし、どんなときであれ彼女のそばにいられる。彼女だってかわいいぼくだけの女性として、笑ってくれる。それでいいじゃあないか。その甘い瞳が、ぼくにぼくじゃあない男のことを思って輝くとしても。 ぼくはまた、紅茶を淹れるために手を動かすことにした。今は何も言いたくない。そうですか、なんて相づちもしてやらない。これだけで充分にひどいかなと一瞬思ったが、本当に一瞬のことだった。こうしたことにはこの先も悩むのだろう。けれど、いつの日にかなんとも思わなくなるはずだ。ぼくが、そうしてみせる。彼女の心から存在していない亡霊など追い出してしまって、ぼくだけがそこに在るように。時間など、これからどれだけでもある。それに、ぼくらを邪魔するやつはいない。 ぼくと彼女は、明日には正式な夫婦になる。 あの男が成したくても――いや、それはどうだっていい。ぼくがどうしても手に入れたかったものが、ようやく手に入るのだ。これから彼女の目に映るのは、このぼくだけだ。 きっといつか、その目は光を受けてきらきら輝いているに違いない。 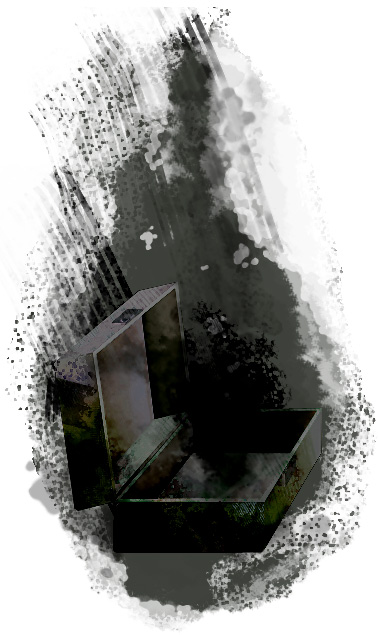 |