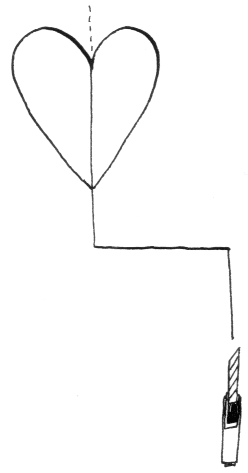
「、午後には姉さんが来るって言ったよね」 僕が言うと、はびくりと肩を揺らした。それが気に入らないと思って、僕は彼女の長い髪を掴みあげた。いつもそうだ。いつもいつもいつも。いつも、この女はいつでも僕の機嫌を損ねることしかしない。いや、できないのだ。そういう愚かしい女なのだ。僕の大好きな姉さんと違って。 「いっ、痛い! 恭弥さん!」 「君が僕に何か主張することは許可してない」 「……すみません、すみません……」 が床に額を擦りつけている姿がひどく浅ましく思えて、ぱっと手を放した。ゴツン、と鈍い音が響いた。気分が悪くなる音だ、いつ聞いても。空っぽの頭をしているくせに、さも何か詰まってるように聞こえる。 「分かったならいいんだ。昨日業者を入れたといえど、もう一度掃除は確認してよね。姉さんが来るんだ。すべて完璧でなきゃいけない」 僕のたった一人の姉さん。 僕が唯一大事に守りたい、大好きな姉さん。 でも僕はあの人が憎い。 僕がこの女と結婚することを喜んだ姉さんが、憎い。 僕は結婚することなんかまったく望んじゃいなくて、でも姉さんが持ってきた縁談だからと仕方なく出向いただけで、こんなことになるとはちっとも思っちゃいなかった。 さんほど恭弥に相応しい人なんていないわ、恭弥さえ良ければ一緒になるべきよ。姉さんは言った。姉さんがそう言うなら、僕に選択肢はなかった。僕の尊敬する、最愛の姉さんが「そうすべき」と言うならそれが正しいからだ。でもやっぱり、僕が大事にしたいのはどうあっても姉さんだけだった。世間からすれば、きっとは“良き妻”なんだろう。姉さんさえもそう言ったのだから。でも、いくら“良き妻”であっても、この女じゃ僕を癒してくれない。僕には姉さんでなくちゃだめなのだ。 姉さんに奨められるまま、このという女と一緒になってみたけれど、何もかも姉さんに劣ったくだらない女だった。だから僕は結婚後すぐ、に誓わせた。僕に主張しないこと、僕に指図しないことを。そして何より、外では“良き妻”でいること。姉さんの前では殊更に。は初めこそ反抗したが、今では僕の人形だ。 が姉さんにとって“良き義妹”であるなら、僕はそのよりも“良き弟”で――の“良き夫”でなければいけない。だって姉さんはそれを望んでいる。 「さん、お久しぶりね。恭弥、元気にしてた? あぁ、さんがいるんだもの、何も心配することないわね。ふふふ」 二時頃、姉さんは大きな荷物を抱えてやってきた。今日ここへ来たのは、イタリアへと旅行に行っていた土産物を持ってくるとのことだった。玄関先でその大荷物を受け取ると、姉さんは笑った。 あぁ、これだ。僕がずっと欲しくてたまらないものは。僕が守って、愛して、ずっとそばにいてほしいと神様に願う、神様に願いたい、神様に誓いたいたった一人は。やっぱり僕には姉さんしか――姉さんしかいない。僕を大事にして慈しんでくれた姉さんにだって、僕しかいないはずだ。あぁ、いくらこの現状が姉さんの望みであったとしても、僕はやっぱり姉さんのそばにいたい。今の生活は億劫でつまらないし、姉さんがいないというこの一点ですべてが不幸だ。 は僕の言い付け通り、“良き妻”の顔で「さ、お義姉さん、お上がりになってください」と先導して姉さんをリビングへと招いた。 それからしばらく話をしていると、ふと姉さんから表情が消え失せた。どうしたの、と僕が声をかける前に、姉さんは僕の頬を力一杯に張った。それからぽろぽろ涙を流して、「さん、ごめんなさい。今までずっと辛かったでしょう」と僕の目の前でを抱き寄せた。愕然とした。ちがう、違う。そこにいていいのは僕だけだ。姉さんは僕だけの姉さんで、なんかはまるっきりの他人で、姉さんが愛していい人間じゃない! 「もういいわ、あなたは何も心配することないのよ。手続きはこちらで進めるし、あなたのことはわたしが何をしてでも守ってあげる。わたしと一緒にイタリアへ行きましょう。いいわね?」 「でも、それじゃあお義姉さんにご迷惑をおかけするし……“お義兄さん”にだって申し訳ないです。まだ“新婚”だっていうのに……」 「言ったでしょう? あなたは何も心配することなんかないの。あの人だって分かってるわ。……可哀想に。これも全部わたしのせいだわ……。わたしがあなたと恭弥を引き合わせたんだもの……本当にごめんなさい、いくら謝っても足りないわ……」 どういうこと、どうして姉さんはそんなくだらない女に頭を下げるの、どうして久しぶりに会えたっていうのに、僕を抱きしめてくれないの。姉さん、イタリアへは旅行に行くって、そう言ったよね。 新婚? どういうこと? 僕の知らないところで、誰と、何を。 そういった思考は一瞬のことで、僕は拳を振り上げた。 そこへ! という男の声がして、その姿を現わした。 「あぁ、ディーノ、わたし、わたし取り返しのつかないことを……!」 「今は何も考えなくていい。……久しぶりだな、恭弥」 「……人の家に無断で押し入るって、あなたどういう神経してるの?」 「そうせざるをえないだろうと判断したからだ。、、先に表へ出てな」 その言葉に姉さんは余計に泣いて、ひしと女を抱きしめた。そのとき、僕は見た。女が誰にも気づかれないよう、姉さんの肩越しに僕に向かって中指を立てたのを。その瞬間、すべてを理解した。あの女は僕の知らないところで姉さんと連絡を取り合っていて、僕の話をしていたのだ。僕を悪者扱いして、僕のことを“悪い夫”だと悪し様に言って泣きついていたのだ。 そして姉さんは僕に嘘を吐いて、イタリアでこっそりと目の前の金髪の男と一緒になったのだ。僕に黙って、結婚なんて馬鹿な真似をしたのだ。誰より賢く美しい姉さんをたぶらかしたこの男を、そして何より、姉さんを味方につけて僕を嗤うあの女を、僕は許してはいけない。僕の感情は一気に昂ぶった。 「……これは、どういうことだい?」 「……すみません、すみません、恭弥さん、すみません……」 「、を連れて早く外へ出ろ」 「……ええ、もうこんなところへ彼女を置いておけないわ……。さん、立てるかしら?」 「“お姉さん”、本当にごめんなさい……」 「何を言うの。恭弥とのことはどうであれ……あなたさえ良ければ、わたしはずっと“あなただけの”姉よ。さあ、行きましょう」 姉さんに手を引かれる女は、姉さんがまるで本当の姉であるかのようにぴたりと寄り添った。あの女の目的は、初めから僕の姉さんだったのだ。僕の、“僕だけの”姉さんを僕から取り上げるために、僕と一緒になったのだ。そもそも姉さんはどこからとの縁談を持ってきた? 僕がしていることをなんとなく分かっていただろう姉さんが、どうして自分で自分の身を守れないようなその辺の女と僕を引き合わせた?誰だ。こんな企み、一体誰が。 「この間、いつものカフェでとっても素敵なお嬢さんとお知り合いになれたわ。わたしと趣味が合ってね、いつか恭弥にも紹介したいわ」 「恭弥、姉さんね、しばらくイタリアへ旅行に行こうと思うの。人に勧められたのだけど、とってもいいところなんですって。そこへは彼女の旧知の方もいらっしゃるというし、とっても楽しみだわ」 「ねえ恭弥、少し話したいことがあるんだけれど……お見合いをしてみる気はない? とっても素敵なお嬢さんよ」 「さんほど恭弥に相応しい人はいないわ――」 あの女が……あの女が! 空っぽの頭をしているくせに音がすると思ったら、そうか! そうか! 邪まな思いが詰まっていたから、あんな気分の悪くなる音がしたんだ! 僕は何か、なんとか、離れていく姉さんの背中を引き止めようと、その女の本性を伝えなくてはと言葉を探していたけれど、間もなくその背中がくるりと反転した。 「……恭弥、あなたは本当にわたしの大事な宝物だったわ。でも、それがいけなかったのね。わたしはもう二度とここへは来ないし、実家とも縁を切るつもりでいるわ。これでお別れよ」 あなたは本当に、本当によくできた弟で、自慢の弟で、世界で一番大切だった。一体どこで間違えてしまったのかしらね。姉さんはそう呟くように言ってまた背を向けると、今度こそ振り返らなかった。 姉さんに置いて行かれた僕は、男に言った。誰の企み? すべて姉さんの言った通り、従ったのに。僕の何が間違ってたって言うんだ。すると男はニタリと笑った。僕に中指を立てたあの女と同じ顔だ。 「初めから全部だよ、恭弥。もうアイツはオレのもので、アイツはもうお前の姉貴でもない。なんて言うんだっけな……あぁ、“ご愁傷さま”」 |
画像:はだし