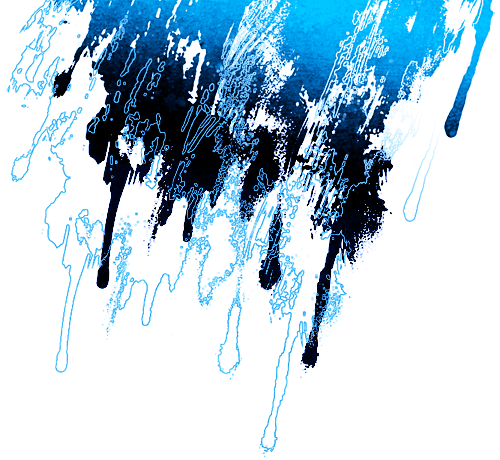 「ちょっと徹くんヤバイ頭おかしいよ」 この女が無遠慮に部室に立ち入るのは、もう今に始まったことではない。そして俺は注意する気もない。そんなことをして飛び火してきたら、散々な目に遭うことが分かりきっているからである。これは大局を見て俺が折れるべきところだ。そう割り切ってからは特に何も思わなくなった。つまり以前は散々コイツにああだこうだと言ってきたわけだが、それでもまったくこの女は聞きゃあせず今日というわけである。……たまに部室が片付いていることもあるし、これは間違っていない。 ちら、と確認する。顔は笑っている。目は笑っていない。 「元からそうだろ」 「知ってるけどヤバイの。聞いてとりあえず」 パイプ椅子にストンと腰を落とすと前のめりになって詰め寄ってきたので、「なんだよ」と聞いてやるような振りをした。すると今度は本当ににっこりと笑ってみせて、嘲るように言い放った。 「徹くん私のこと好きらしいよ」 「そんなこと全校生徒知ってる」 「何それ気色悪ッ」 まぁ二重の意味で気色悪い。 全校生徒に知れ渡るほどの及川のこの女――への入れ込みようだとか、自分の男――及川を徹底的に痛めつけるがちっとも悪びれずにいるところが。いや、違う。お上品な顔をしておいてエグイのその“手法”も気色悪いので、三重の意味だ。でも、そんなことは二人が付き合い始めてから今日までずっと続いてきていることなので、なんの感情も湧かない。 及川とが付き合い始めて一月が経って、最初の騒動には驚きも怒りも混乱もしたが、俺が間に入ったところで解決するわけでもないし、そもそも二人に解決しようという気がないのだ。巻き込まれないように事を静観――まぁ適当に流しておけばいいのだ。俺はそのことを四度目でやっと学び、そしてやっとそういう立ち位置を手に入れた。 これが何度目の騒動であるかはもう知ったこっちゃないが、内容は知っている。朝からあちこちでこの話をしているのだ。今回ももちろん、及川がにハメられた。簡潔にまとめると、及川が他の女と寝た。 その“他の女”は(俺にはサッパリ理解できないが)及川のファンで、その女をが及川の元へと送り込んだ。三ヶ月前に。これはほんの一部の人間しか知らないことだが、及川はその少し前から禁欲を命じられていた。この話をしていたときの及川は、「ちゃんね、俺のファンの子たちにヤキモチしてるんだよ。だから、ちゃんが言うなら愛の証明としてのお預けくらいヨユーヨユー!」と笑っていた。で、そのファンの女と寝たわけだ。 現場を押さえたとき、(が言うことを信じるのなら)偶然にも居合わせた俺は溜息を吐きたくなった。そして同じく(が言うことを信じるのなら)偶然にも通りがかった花巻と松川が、ヤバイ!! という顔をしつつも、スルーできない状況に冷や汗を滲ませながらその場に突っ立っている中、小さく肩を震わせ、目に今にも零れ落ちんとばかりの涙を浮かべ、「徹くん、信じてたのに……ひどい……。……別れよう」と言ったはまさに女優だった。俺はこれに四度も騙された。余談だが、花巻なんかは一度はのことを好きにまでなった。悲劇である。 エグイのは、がそうなるようにと送り込んだ刺客が「及川さんのっていうか……さんのファンなので、こうやって抜擢されてうれしかったです〜!」であったということ。さらに、の足元に崩れ落ちている及川の目の前で「それじゃあ約束通り……」なんてにべったりひっついてツーショット撮ったこと(撮影係にされたのは松川)。そもそもが「ちゃんごめんなさぁい!!」と大泣きする及川を見たいがために、三ヶ月以上前からいろいろ仕込んでいたこと。まぁつまりすべてである。 「そんでどうすんだよ、別れんのか」 ぐずぐず鼻を啜る音がドアの向こうから聞こえてきたのでそう言うと、は心外そうに言った。そしてちらっとドアに目をやると、ほんの少しだけ口元が緩まった。 「は? 別れないよ」 「……お前のその歪んだ愛情表現、どうにかなんねぇのか」 俺の言葉に今度は口元を不愉快そうに歪めると、「歪んだって言い方失礼なんですけど」と言って腕を組んだ。 「歪んでるだろ。アイツ今その辺の女子に慰められてんぞ、きっと」 外からガタッと物音がした。何してんだかな、と思って溜息を吐いた俺には楽しげに言う。その顔は子供のように無邪気で、そうしていれば可憐な乙女とも見えなくはないなと思う。この女の正体を知っているので思うだけであるが。 「サンてヒドイ〜! 及川クンてばカワイソウ〜! 私が慰めてあげる〜! って?」 「そうだろ。アイツの周りはそういうのしかいねぇだろうし」 この話はいつまで続くんだか、と帰り支度を始める。一瞬、の顔が歪んだ。しかしそれは本当に一瞬のことで、また可愛らしい顔――顔だけで何考えてんだかは想像したくない――をして、「あはは、そうだったらおもしろいねえ」なんて言って笑った。もうすっかりコイツと及川の関係には関わりたくない。俺は四度もこんなくだらないことに巻き込まれて、心底そう思っている。だが、ふと思ったのだ。 「なんで及川と付き合ってんだよ」 なんでそんな質問するの? というような驚いた顔だ。 いや、誰だってそう思うに決まってる。 と及川の関係は肩書きこそ“カップル”だが、の及川に対する数々の悪魔の所業からしてとてもそうは思えない。少なくとも、好きだと思っているようには。しかしはなんの躊躇いもなく、即答した。 「好きだから」 「……どこが?」 あんな仕打ちしといてよく言えんなお前。 その言葉は喉元まできていたが飲み込んだ。 は笑って、これまた即答した。 「顔。特に泣いてるところ」 碌でもない理由だ。けれどまぁ、及川はたとえそうだとしたってこの女を手放す気なんてないだろう。 ドアの向こう側からは、相変わらずぐずぐず鼻を啜る音が聞こえる。こそこそ泣くくらいならさっさと中入ってくりゃいいものを、情けねえ男だな、と思った。けれども、あんだけ溺愛してる彼女から「好きなところは顔」と即答されたんじゃ僅かばかり同情もする。でも俺はこの“傍観者”というポジションを守りたいので、そういう態度は一切取らないようにしているのだ。もう巻き込まれるのはごめんだ、ということである。 「別れる気ねえならとっとと回収してこいよ、公害だぞ」 「ねえ黙って聞いてればなんなの二人して!!」 バンッ! とドアが押し開かれると、やっぱりガキみてぇに顔中を情けなく濡らした及川が現れた。素早く中へと入ってくると、またバンッ! と音をたてて扉を閉めた。 するとはパイプ椅子から立ち上がって、にこりと笑った。黙って笑っていればいいのにな。そうすれば――とまた思いながら、ビニール袋に使ったタオルを入れてバッグに突っ込んだ。 「盗み聞きとかお行儀悪いよ? 徹くん。そういう人きらぁい」 「ウン分かったもうしないちゃん大好き!!」 「オイ、まず鼻拭けよグズ川」とティッシュを差し出す。 「アリガト岩ちゃん。ちゃんほどじゃないけど好きグフェ!!」 ちょっとばかし心の中では同情したが、ムカつくもんはムカつくので一発ぶん殴った。 「ねえ」とが言うので振り返ると、やっぱり笑っている。 及川は、お前忠犬かよと言いたくなるくらいには笑顔満面でに駆け寄った。 「なぁに? なぁに、ちゃん」 早く言って言って! なんでも言って! 馬鹿らしい言葉が聞こえてきそうだった。 「私、許さなさいからね」 ここでやっとは笑うのをやめた。及川はというと、顔を真っ青にして「許してくれないの?!」とに詰め寄る。いくらの仕組んだことといえ、他の女と寝といてどの口が言う。 面倒なことになる前に帰ろうと思ったが、何を思ったのか俺は余計に面倒なことになりそうだというのに口出ししてしまった。 「“また”彼女捨ててファンに手を出したゲスが何言ってんだよ」 俺は四度この二人の騒動に巻き込まれたが、その四度のすべてが同じように女絡みのことだった。その後の騒動も及川が他の女と寝たというのばかりである。 及川はまた情けなくも今にも泣き崩れそうに目に涙を溜めて、「それ!! それ!!!! ヒソヒソされた!!!! しかも“また”って!!!!」とに手を伸ばしたが、その手は届くことはなかった。 「事実だろ」 俺がそう言うと、及川は一瞬だけ眉根を寄せて「じっ……まぁ、そうだね、うん。事実だよネ!」とへらっと笑った。ちらっとに目をやると、興味なさげにスマホをいじっている。 及川を何度も情けないと言ったが、本当に情けないのはの方であることを俺は知っている。このボケが選んだのはお前だろ、と四度は言った。それでも聞かなかったこの女に、同情の余地はない。 「徹くん」 「ハイ!」 「もうしないよね? ごめんなさいは?」 その言葉にシュンと肩を落として、及川は情けない声で「ちゃん、ごめんなさぁい……。もう俺しないよ、ほんとだよ」ともう一度に手を伸ばした。今度こそその手を受け入れたは、頬に添えられた手に手を重ねた。 はどうしようもない女だが、それを見抜いていながら同じことを繰り返している及川も同じだ。 「次も引っかかったら、今度こそ別れようね、徹くん」 「次は引っかかんないもん! えへへ、ちゃんだぁいすき。ね、迎えにきたの。かえろうよ」 次“も”引っかかったら。つまりは、同じことをまたやってやると言っているのだ。そして次“は”引っかからないと答えた及川も、それを承知している。だからコイツらはどうしようもないのだ。 こんなつまらない方法でしか愛情を確認できないも、それを知っていながらその思惑に乗る及川もどうしようもない。けれど、二人はこれで成り立っている。こうすることでしか成り立たない関係とまでは思わないが、多くの人間を巻き込んでまで付き合い続ける神経は分からない。は及川を好きで、信頼もしているはずだ。だが信用はしていない。そのことを知っている及川は、自分が注ぐ、おまえの願いならなんでも叶えてやるという“愛情の証明”として、他の女と寝ていることにしているのだ。の思惑に乗って、何度も何度も。愛情を認めてもらうまで。馬鹿にもほどがある。そしてそのことを、は知っている。だから何度もくだらないことを仕掛けるのだ。 「岩泉くん、私たち帰るけどどうする?」 「さっさと帰れ」 俺の言葉に振り返ったは肩を竦めると、「ごめんねぇ」とちっとも悪いと思っていない調子で言った。ごめんと思うのなら素直な恋愛してろという話だ。 「じゃあ岩ちゃん、カギよろしく」 へらへらしているが、腹の内では何を考えてんだかなと思った。思ったが、それを知りたいとは思わない。せっかく“傍観者”という安全なポジションに納まったのだ。余計な面倒はそれこそごめんである。 ただ、思うのだ。 こんなくだらねえ“ごっこ遊び”をやめたとしたら、コイツらは幸せな恋愛ってやつができるんじゃないかと。それをも及川も望んでいると思いたいが、どちらの腹も読めない以上、言ったところでどうにもならない話である。もしいつか――そんなこと、俺には分からない。分からないが、“傍観者”であるはずの俺は思うのだ。どうせするなら、二人でまともな恋愛にしろと。けれど、これで成り立つ幸せらしいカップルには、何も伝わらないだろう。 だから俺は、今日も明日も明後日も、自分の身の安全だけを考えるのだ。 |