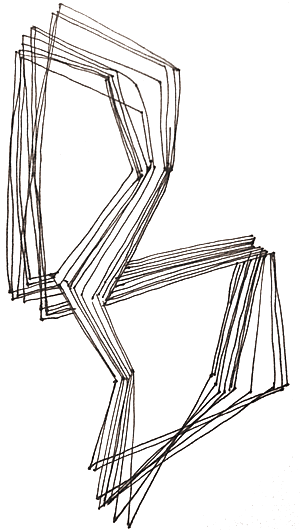
| 「今どこ?」 バスケ部で同窓会をしようと言い出したくせに、急に仕事の飲み会が入ったと黄瀬は欠席したので、にとってみたらその電話は予期せぬものだった。騒がしい昔馴染みの輪から少し離れ、ちょっと掠れた恋人の声に耳を澄ます。向こうから聞こえる音にも騒がしさが混じっていて、これは大いに盛り上がったことだろうとは思わずくすりとしそうになった。 「今? もう帰るとこだけど……黄瀬くんは?」 「今さくら台ッス」 さくら台? とは思った。黄瀬は渋谷で飲むと言っていた。渋谷から神奈川のさくら台までは乗り換え一回、四十分もあれば着く距離ではあるが、黄瀬とさくら台が結びつくようなことはない。しかも現在、二十二時である。黄瀬は仕事場の飲み会はいつも最後まで参加するので、早くとも終電、遅いときには朝帰りが常である。一体どうしたというのだろう? と小首を傾げた。するとやはり掠れた声で、まるで乞うように黄瀬が言った。 「ねえ、迎えにきて。一人じゃ帰れない」 こちらはそれぞれ明日が早いということで、今まさに解散するところである。迎えにいくこと自体にはなんの問題も感じなかったが、本当に一体どうしたというんだろう。こんなことを頼まれるのは付き合ってから十年、成人してから五年だが初めてのことだった。 「え、そんなに飲んじゃったの?」 「いいから早く」 「それはいいけど……。じゃあさくら台の駅でい――」 いい? その言葉を最後まで言い切ることはできなかった。ぷつりと、突然電話が切れてしまったからだ。一人では帰れない、迎えにきてほしいなんて言い出すくらいなのだから、余程酔っていて誤って切ってしまったのかもしれない。アルコールに強いほうではない黄瀬だが、飲んでも呑まれるタイプではない。きちんと自分が摂取できる量を把握している。だからいつも飲み会のあと、しっかりした足取りでの家までやってくるし、その後もこうだったああだったと機嫌よく話をしてくる。 まぁ何にせよ、待ち合わせ場所を決めなければ合流できない。 は着信履歴から黄瀬へと電話を掛けた。 「、どうした」 「あ、赤司くん……。き、黄瀬くんが、」 「涼太?」 「迎えにきてって連絡してきたんだけど、詳しい場所言わずに電話切れちゃって……。掛け直しても繋がらないの……」 黄瀬の着信から十分ほど経ったが、何度掛け直しても応答がない。 黄瀬の身に何かあったんではなかろうかと、は顔を蒼くした。そこへ声を掛けてきたのは赤司だった。少し離れたところでは、早めに解散と言っていたはずが全員、輪になって話し込んでいる。話の内容はまったく聞こえなかった。どくどくと嫌な心臓の音だけが頭に響く。 スマホを握りしめて俯くに、赤司はまったく表情を変えずに言った。 「そうか。……涼太はどこにいるんだと言ってた?」 「さくら台にいるって……」 聞かれたことに答えることはできたが、それだけだった。の頭の中は黄瀬のことでいっぱいで、周りの喧噪も仲間たちの談笑も、赤司の声さえぼんやりとしか届かなかった。 そんなに、赤司はもちろん気づいていた。この男はずっと昔――中学生のころから、そういったことを見抜くのがうまかったし、私情でもってのことは特に気にかけていたからだ。 「ならとりあえずはさくら台へ行こうか。この時間では一人じゃ危ない。僕が一緒に行こう」 事もなげに言った赤司の声に、はしっかり反応した。 「え」 それから、「ありがとう。でも大丈夫。みんなだってそろそろ帰るし――」と言葉を続けたが、赤司はそれにかぶせるように「大丈夫だよ。真太郎に伝えてくる。少し待っていてくれ」と言って、しばし離れた。赤司くん! と呼び止めるの声は届いたはずだが、彼は振り返らなかった。 「……どうだ?」 「ダメ、全然出ない。……どうしよう、何かあったのかな、」 電車に乗り込んでさくら台駅に着くまで、二人の間に会話はなかった。は変わらず黄瀬のことで頭がいっぱいだったし、赤司もそのことをよく理解していたからだ。 はここまで一切不安を口にすることはなかった。しかしあれから一時間以上たっても連絡がつかないので、とうとう赤司に訴えた。まるい瞳がほんの少し潤んでいて、夜の闇を眩しく照らす街灯に光っている。その目を見ても、赤司はやはり表情を変えはしなかった。 「仕事先の飲み会なんだろう? もし具合が悪いとすれば一人きりではないだろうし、アイツのことだ、そう心配することじゃないさ」 「でも……」 赤司の言葉を理解できないことはなかった。黄瀬がどういう男であるかを一番よく知っている。その自信を、この十年でしっかりと感じてきている。けれど、ここまでくるともう何を言われても不安は拭えない。 黄瀬は連絡はまめで、たとえ用事がなくたって――お互い一人暮らしのはずが、ほとんど二人暮らしの状態であったって――いつも時間を見つけては何かとに何らかの方法で連絡してくるくらいだ。それが用あっての連絡に応じないだなんて、何かあったとしか思えなかった。 するとそこへ、ずっと握りしめたままでいたスマホがぶるぶると震えたので、はハッとして画面を確認するより早く指先をタップさせた。 「! 今どこっ! 遅いよ!」 繋がった瞬間、不機嫌そうに子どもような文句を言い放った黄瀬に、は安心するよりも前にざわざわとしたものを感じた。自分一人であったなら冷静に対応しただろうし、もちろん素直に安心もできただろう。しかし、今は赤司と一緒だ。まったくの他人ではないが、黄瀬ととの問題には無関係な人間である。そんな彼を巻き込んでのことだ。自然との声は冷たくなった。 「……黄瀬くん」 「なに、早くきてってば」 勝手な言葉に、は「知らない!」と怒鳴った。 「一人で帰ればいいでしょ! わたしは赤司くんと帰る!!」 「ハァ?」 自分が呼びかけたメンバーの中には赤司もいた。確かにいたが、なぜここで彼の名前が挙がったのか。黄瀬には分からなかった。ただ、気に入らなかった。それがそのまま言葉にも声音にも出てしまった。 は肩で息をしながら、乱暴に通話を打ち切った。その様子ですべて察知した赤司は、彼にしては珍しく少し躊躇ったあと「送るよ」と短く言った。は今気づいたというような感じでさっと表情を変えると、慌てて口を開いた。 「えっ、あ、ごっ、ごめんなさい、つい……! 大丈夫! 付き合わせちゃってごめんね。あとは大丈夫だから。本当にごめんなさい」 一度頭を下げると、は申し訳なさそうに眉をハの字にして言った。赤司はそれでも表情を変えずに、「いや、構わない。……行こう。寒いだろう」とくるっと駅の方角へ体をひるがえした。彼はそうすると口にしたことを変える男ではない。それを黄瀬と同じ年月だけ――黄瀬との関係とは違うが――見てきていたし、感じてきたのだ。は分かっていた。 「ほ、本当に大丈夫だから!」 「なら、少し付き合ってくれないか」 「え?」 赤司がを連れだって歩き、辿りついたのは小さな公園だった。遊具はなく、“さくら台第五公園”と書かれた石碑と、古びた木材のベンチがあるだけだ。広場と言ったほうが似合いかもしれない。 ベンチに腰掛ける二人の手には、缶ビールがある。 この季節に相応しく、その缶には商品名と一緒に桜の花びらが舞っている。 「寒いだろうと言っておきながら悪いね」 赤司の言葉に、はくすりと笑った。しかし、表情は情けないものだった。 「ううん。途中コンビニ寄ろうなんて言ってビール買うから、ビックリしたけど」 中学時代、みんなで買い食いしようとコンビニに立ち寄ったことは何度もあった。しかし、その中に赤司がいたことは一度だってない。真面目で品行方正な緑間さえ、時々は加わっていたのに。けれど確かに赤司にコンビニエンスストア、なんてものは似合わないと思っていたし、今もそのイメージは変わらないままだ。は素直に驚いていた。 ざぁっと冷たい夜風が吹いて、は「……ここ、すごいね、桜」と外灯に照らし出され、昼間とはまた違った深い趣のある桜の木を見上げた。たった一本だが、圧倒的な存在感がある。 「あぁ。君が、気に入るかと思って」 赤司がどういう意味でそう言ったのか、その意図をは量りかねた。いや、終始暗い顔をしていたので、少しでも励まそうとしてくれているのかもしれない。そうすぐに結論づけたが。 何も答えずにいると、赤司は着ていたジャケットを脱いで、の肩へとかぶせた。 「着てくれ。寒いだろう」 「いっ、いいよ! 赤司くんが寒いでしょ!」 「いいんだ。春物のコートじゃ防寒にならない。僕は平気だよ」 風は冷たいけれども、陽があるところでは暖かい気候になってきている。しかしそれは“昼間”の話である。朝晩はまだ寒いので、いくら新調したからってスプリングコートは失敗したな、とはひそかに思っていた。肌寒いとも感じていた。だからといって、好意を無にしてしまうにしてもそれを受け取ろうなんて気はちっとも起きなかった。いいよ、いや受け取ってくれ。このやりとりを何度か繰り返した。今、は赤司のジャケットに皺がついたりしないだろうかと気にしながら、それを肩にかけている。 「涼太とはうまくいっているか?」 黙って花見を静かにしていたところ、赤司は唐突に沈黙を破った。中学時代同じくバスケ部のマネージャーを務めていた桃井に散々せがまれたので、それについては随分話したつもりだったけどな、とは思ったが「え、うん。まぁ、付き合いも長いし、特別こうっていうのはないけど仲良くしてるよ」と言って缶ビールに口を付けた。なんだか気まずい。赤司とそういう話題は、の中では結びつかなかった。 「そうか」 それからまたしばらく沈黙が続いてしまったので、は「あ、赤司くんはそういう……なんていうかな、好きな人とかいないの?」と気まずさを取っ払おうと口を開いた。向こうから話をふってきたのだから、同じような質問を返したって構わないだろうと判断しての言葉だった。 「今はもういないよ」 今はもう――。ということは、いつだかは知れないが以前にはそういう人がいたというわけだ。にはやはり赤司とそういうことがイメージできなかったので、これにも驚いた。 今日の赤司くん、なんだかイメージと真逆のことばっかりだなぁ。 飲んでいたときはいつもと変わりないように見えたし、さすがにもう酔いは醒めているだろう。青峰のようにがぶ飲みしていたわけではないが、それなりに飲んでいた赤司が缶ビール一本で酔っぱらうとは思えない。でもまぁ、少しずつであるにしろ、結婚なんてものも目に入ってくるような年齢になってきているわけだし、赤司くんもそういうことに気がいくのかなと思ったので、「そっかぁ。赤司くん、素敵な人なのにもったいない」とは言った。本心だった。赤司は中学時代とても人気のある男の子であったし、高校でもきっとそうだったに違いない。大学でだって。それなのに好きな人がいないだなんて、彼を求めてやまないたくさんの女性が泣くことだろうなと素直に思ったのだ。 「……本当にそう思うか」 なんだか神妙な調子の声だったので、桜から目を離し赤司を見た。 「え? う、うん。だってすごく優しいし、器用だし、こんなにパーフェクトな人なんてそういないもん」 すると、赤司は言った。 「優しいのはだからだよ」 くすっとは笑った。赤司くんがそんな冗談言うなんて、時間ってすごい。そう思った。「そんなこと言われたら、きっとどんな女の子もイチコロだよ」と言うと、赤司はじっとの目を見つめて「でも君はそんなことないだろう」とそれに応じた。 「そりゃあね」 今度はあはは、とが笑ったところで、「!」と若い男――黄瀬の声がした。 「……と、赤司っち」 赤司を見ると眉間に皺を寄せ、ずかずかと二人のそばへと近寄ってきた。 「……二人してココで何してんスか」 不機嫌さ――もしかしたら怒りかもしれない――をちっとも隠さずきつく言い放った黄瀬に、赤司は涼しい顔で「あぁ、涼太。随分と遅かったな。連絡もせずにどこをほっつき歩いていた?」と言って缶ビールをそっとベンチへ置いた。その様を見て、黄瀬はますます眉を寄せた。 「……、帰るよ」 黄瀬がそう言っての腕を掴むと、そのまま無理矢理に立たせようとしたのでは抵抗した。どこもなんともなさそうな黄瀬の姿を目にして、は安心した。安心はしたが、やはり怒りはあった。人を心配させて、赤司までも巻き込んでしまうことになったのに、その態度はなんだと。 「ちょっと黄瀬くん! 赤司くんは心配してくれて――」 まだ最後まで終わらないうちに、黄瀬はキッとを睨みつけた。ずっと昔から、黄瀬はにだけは一度だって――ケンカをしたときさえ――そんな目を見せたことはなかったので、はびくりと肩を揺らした。 「オレ以外の男と二人っきりになったりして、何考えてんの? しかも赤司っちとかマジありえないんスけど」 しかし黄瀬の言い分が言い分なので、も同じく眉間に皺を寄せ、負けじと黄瀬を睨み返した。 「何言ってるの? だから赤司くんは心配してくれたんだって言ってるでしょ?」 「そういう言い訳聞きたくない。いいから帰るよ」 その言葉に、の感情は一瞬にして昂ぶった。怒りの感情だ。自分の腕を掴んでいる黄瀬の手を強引に振り払うと、「……言いたいことだけ言って一方的に電話切って、それから一切連絡してこなかったくせになんなの?!」と怒鳴った。それに対して黄瀬は、「酔ってたんだからしょうがないじゃん。だから迎えにきてほしかったのに」と言ったあと、さらに「赤司っちと一緒とか」と続けた。の怒りはますます高まっていった。 「だからそれ何?! ごめんとかないの?! もういい!」 それから、「黄瀬くんは今夜はうち帰ってこないで! 自分の家戻って!」と黄瀬を押しのけた。驚いた黄瀬は簡単によろけた。どんなときでも――が一人暮らしを始めてからほとんどの時間を――彼女の部屋で共有してきたのに。 は赤司の手を引いて、黄瀬の横をさっさと通り抜けようとした。黄瀬は困惑したのと同時に、胸のむかつきを覚えた。もちろん彼の答えは、「はっ? 何言ってんの?」と、これしかなかった。 「赤司くんっ、行こっ!」 「あぁ、送るよ」 「それならうち泊まっていって。もう電車もないでしょ? わざわざ付き合わせちゃったから」 「……それなら、そうさせてもらおうかな」 黄瀬を置いてけぼりにと赤司は言葉を交わしていくので、胸のむかつきは喉までも広がり、そのまま吐き出した言葉へと繋がった。 「ちょっと待てよ! 何考えてんの!」 「うるさい! 黄瀬くんにはもう関係ない!!」 赤司の手を引くの腕を、黄瀬はもう一度掴んだ。ここでマヌケに二人を見送ってしまったら、もう後戻りはできないと感じた。赤司はなんの感情もないような顔で、「涼太、乱暴はよせ」と冷静に、しかし冷酷に言い放った。もちろん黄瀬は大人しく引き下がったりなどしない。 「赤司っちは黙っててくれる?! アンタ関係ないだろ!」 「お前が彼女に危害を加えるとすれば、僕はそれを止めなくてはならないだろう。分からないか?」 黄瀬はの腕を掴む手に力が入ったのに、自分でも気づかなかった。ただ、彼女を引き止めなければ。ここで見送ってしまったら――そのあとのことなど、想像すらしたくなかった。 「っ! 帰ろうってば! 赤司っちのことなんかどうだっていいっしょ!」 この言葉に、は初めて怒りの他の感情を見せた。 「どうだっていいのは黄瀬くんのほう! ……黄瀬くんだって、わたしのことなんかどうでもいいんでしょ……。だからあんなに心配したって、電話したって、気づいてくれなかったんじゃない! 気づかないんじゃない……!」 「それは、」 言いかけたが、何を続ければいいのか分からなかった。その様子を見て、はますます悲しいという顔をした。そして今にも泣き出しそうに「涼太くんのばか! きらい! だいっきらい!!」とまるで悲鳴のように声を張り上げた。赤司の手を握る手に力が入った。も、そのことに気づかなかった。赤司だけが、それに気づいていた。 黄瀬は掴んでいる細い腕を自分のほうへと引き寄せると、「待ってって! ……ごめん。謝るから、赤司っちと帰るとか、きらいとか、言わないでよ……」と弱々しく呟いた。はそんなことには応じなかった。 「やだ! 涼太くん、わたしのこと全然分かってくれないじゃない!」 「い、今分かってなくても! これから頑張るから!」 慌てて言った言葉は逆効果だった。は更に手のひらに力を込めた。 湧いて溢れる感情は、悲しみであったが怒りでもあった。 「もう何年付き合ってると思ってるの?! これからって何! バカじゃないの?! 赤司くん、もう行こう」 「……」 「何よ! っあ、ご、ごめん、赤司くん……!」 に呼びかけたのは、黄瀬ではなく赤司だった。 は一瞬で冷静になって、ぱっと握り込んでいた彼の手を放した。 「いや。……涼太も頭が冷えてきたようだし、少し二人で話せ。帰る家はその後に決めればいい。僕は失礼するよ」 「でっ、でも、」 の声音は、まるで母親に置いていかれそうな子どものようで、行かないでと訴えるようだった。 そんな彼女に赤司はほんの少し、優しく表情を和らげると、「……そんな顔をしなくても、何かあれば連絡してくれればいい。どこへでも行くよ。……それじゃあ」と言って、一人公園から出ていった。するとその場はと黄瀬の二人きりである。緊張感のある沈黙があった。それを打ち破ったのは黄瀬だった。 「……なんで赤司っちと二人?」 の腕を解放すると、黄瀬はベンチへすとんと糸が切れたかのように腰を下ろした。俯き小さくなる黄瀬に多少なりとも平常心を取り戻したは、「……黄瀬くんからの連絡なくて、ちょっとパニックなっちゃって、そしたらついてきてくれたの。黄瀬くんこそ、なんで連絡くれなかったの?」と隣へ同じく腰を下ろした。俯いたまま、黄瀬はぽつりと言った。 「最初に連絡したのは覚えてるけど、その後のことはちょっと記憶曖昧で……」 「……じゃあなんでここに来たの?」 黙り込む黄瀬に、は「ちゃんと答えてよ」と厳しく言った。それに黄瀬はますます小さくなって、「……が、怒ってると思って」とますますヴォリュームを下げた。は呆れてしまったという顔をしたが、もう黄瀬を怒鳴りつけようとは思わなかった。 「当たり前でしょ」 しかしはっきりとそう言うと、放っておいた缶ビールを飲んだ。もうとっくに味気ない。 思わず顔をしかめる。すると、黄瀬はこれまでのことをぽつぽつ語り始めた。 「……さくら台まで来てほしかったの、ココの桜、二人で見たかったからで……」 「え?」 「こないだの撮影で、一本しかないけど、さくら台にある小さい公園の桜がスゲーって聞いたから」 は今日初めて黄瀬に対して笑顔を浮かべた。それは黄瀬の目に直接は映らなかったが、くすりと小さな笑い声を、その耳は確かに受け取った。 「……なにそれ」 「今日も飲み会、一緒に行けなかったし……お花見だってなかなか予定合わないし、昼間、人すごいっしょ」 黄瀬は顔を上げると、桜の木を見上げた。二人笑ってこれを見たかったのに、自分のせいでおじゃんにしてしまった。これ以上悲しいことってないかもしれない。そんなどん底の暗い思いは、小さなものではあったが漏れた溜息に込められた。そして、の次の言葉にさっと蒼ざめた。 「……赤司くん、こうなるの分かってたのかなぁ」 「は、」 の表情を確認しようと視線をやると、彼女は優しく微笑みながら桜の木を見上げている。 「だって、もう黄瀬くんのこと許しちゃってるんだもん」 黄瀬と視線を合わせると、は「ふふ」と機嫌良さそうだ。それを見て、黄瀬はますます顔色を悪くしていった。はそれに気づかないふりをした。もしここで何か――そう、何かを言ってしまったなら、後戻りできなくなることを分かっているからだ。黄瀬が必死に自分を引き止めた理由を、も同じく感じ取っていた。 「いや、あれは――」 「黄瀬くんがここに来るのまで分かってたりして――」 しかしのほうは怖がることなく、黄瀬に笑いかける。それを見て黄瀬は、彼女の自分より随分と小さい手をきつく握りしめて、「もう、赤司っちの話はいいから――もっかい、名前呼んで」とかぶせるように言った。 「……涼太くん」 泣いてしまいたい気分になった。もしそれが本当になってしまったら、それは嬉し涙であるのか、悲しく冷たい涙なのかは分からない。ただ、この手を放したらいけないし、二度とこんな隙を見せたらいけないと強く思った。 「あと、きらいも取り消して」 「涼太くん、好き」 お互いの気持ちを確認することに、二人はなんの躊躇いもなかった。二人はずっとこうでいたい。時間が巻き戻ることなど起こりえないし、仮にそんなことが起きたとしても今と変わらない。思うことは一緒だった。 「うん。……うん、オレも好き。……んち帰ってもいい?」 「……いいよ。その代わり、明日はずっと一緒にいて甘やかしてくれなきゃいや」 「うん、一緒にいるし、ずっと甘やかす。……帰ろ」 黄瀬の骨張った大きな手からは、力が抜けた。夜はまだ深い。 はちらっと桜の木を見上げたが、手を引かれる感覚に誘われて考えることはやめた。 |