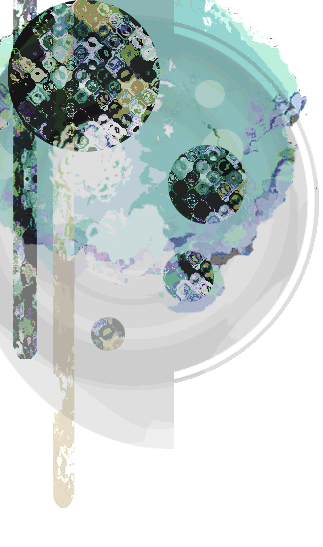 最終電車に揺られるまま
最終電車に揺られるまま
最終電車に揺られているうちに、ふと昔のことを思い出した。 いつだったかなんてことはもう忘れてしまったし、その女の子の顔さえも分からない。 ただ、夏のくせして涼しい夜だから、ちょっと感傷的になっているだけだ。 ああ、そうだ……あの日も、涼しい夜だった。確か、確か八月の頭だった。 俺はなんでだか一人で夜道をとぼとぼ歩いていて、なんでだかいつもは通り過ぎるだけの近所の公園で、古臭いベンチに腰かけて星を観察していた。そうしたら女の子がやってきて、夏とはいえ暗いのに、一人で危ないなあと思っていると、その子は黙って俺の隣へ並んだ。それから、多分しばらくはお互い黙ったままでいて、でも突然……そう、突然、突然その子は泣き出した。 「どっ、どうしたの?!」 びっくりして、知らない女の子なのに咄嗟に声をかけてしまった。その後すぐに、ああどうしようと思っていると、彼女もびっくりしたようにこちらを向いて、俺の顔をじっと見た。俺も見つめ返した。 少しすると、彼女はまたじわあっと目を潤ませて、とてつもなく大きい泣き声を上げた。 「ちょ、ちょっとまって! ちょっとまって! お、俺が泣かしたの?! ちょ、ちょっとまって!」 俺はそんな感じのことを言ってベンチからさっと立ち上がると、彼女の足元に屈んだ。 「どうしたの? えっと……ど、どっか痛いとか?」 聞こえてんのかな? と思うくらいに泣きじゃくる彼女の表情は、その小さな両手に覆われて窺い知れなかったけれど、とても悲しい顔をしているんだろうってことは想像できた。こんなに泣くんだから、その顔を見てしまったらうっかり俺まで泣くんじゃないかとすら。 それから……どうしたんだっけ……? あぁ、もうあと二駅か。 昔のことなんて思い返すと、知らず知らず時間が経ってしまうものだな、と思っているとドアが開いた。 「うう、ひっ、く、ふ、ううう」 なんでまたこんなとこで……と思うほど、その人は大号泣だった。 ああ、綺麗にしてたんだろうメイクがあんなに……。 ひぃひぃ言いながら、その人は俺の向かいの席へストンと座った。この車両には俺の他、誰もいない。終電といえど、こちらの方向へ帰る人はとても少ないのだ。どこかの車両では、一人で贅沢に座席を使って眠りこける酔っ払いが絶対いる。あ、駅前の弁当屋ってまだやってたっけなあ……腹減った。コンビニはそろそろ飽きたしなあ……。 ……それはともかく、気まずい。 俺がそんなこと考えてる間もずっと、その人は泣いていた。 あと一駅。 「……あの、どうかしました……?」 そのまま放っておくのもな、こんな時間だし、何より女性だ。 何かトラブルかもしれないし、これからトラブルに見舞われるかもしれないし。 そう思って声をかけると、俯いていたその人はパッと顔を上げて俺を見た。そして首を傾げたかと思うと、「うっ……ふ、ええっ、ひっ、ひっ、うああ、ううっ、ううう、ひぃっ、」とかってさっきよりももっと激しく嗚咽を漏らしはじめたので、ギョッとする。 「えっ、だ、大丈夫? あーっと、ええ、ちょっと待ってな、ハンカチ! あるから! ね?」 スーツのポケットからハンカチを取り出して、手に握らせる。アイロンかけてあるやつでよかった。 「……どうしたの? 最寄り、どこ?」 もう、それ以外にかけてやれる言葉がなかった。俺も次で降りなきゃいけない。終電なのだ。でも、こんな人を放っておくこともできない。……タクシーかぁ。痛いな。でも仕方ない。腹を決めた俺は、彼女の隣へと腰を落とした。 そういえばあの子も、こんな感じだったな。ずーっと、俺が何言っても泣いてて。 あ、思い出した。あの子が泣いてたのは確か……。 「ふられっ、ふ、ふられ、」 そうだ。それだ! 「彼氏に振られた?」 「そ、そうっ、そうなっ」 また激しくしゃくり上げる。 「あー……そりゃ参ったなあ。でもほら、もう最終だべ? 最寄りどこ?」 「も、もう過ぎちゃ、ひ、ひっ、う、って、あの、か、かれっ、彼氏、のっ」 「えーと、さっき乗ってきたとこが彼氏んちの最寄りで、自分の家の最寄りはもう過ぎちゃってるんだ?」 「そ、そうで……ううっ、う、ひっ、あっ、ふうっ、」 あーっ、思い出した! 「か、彼氏に、ふられちゃって……」 その子はそう言って、頬の涙を親指で拭っていた。 俺はそのくらいでそんな、と思ったけれど、この子にとってはものすごい悲劇なんだと思えば納得できた。 「家どこ? もう暗いし、送るよ」 「でも……」 「いいから。あー、俺、菅原。菅原孝支。この近くの烏野高校の三年。俺がもしなんかしたら、学校でも警察でも届けていいから。今の君を一人で帰すの心配だし、送らせてよ」 そしたらその子はやっと笑って 「……ありがとう、菅原くん。わたしの名前は……」……。 名前は……名前は……なんだったかなあ……。 そうだ、俺はその日からしばらく、帰宅する途中必ずその公園に立ち寄っては、また彼女に会えるんじゃないかと淡い期待を抱いていた。結局、あの一度きりだったけれど。 家の前までは行かず、近所だという所で別れたので、家も分からなかった。流石に今日知り合ったヤツに家の場所なんか教えられないだろうと思ってそうしたのに、後でものすごく後悔したっけな。 制服は見たことないものだったし、あの子も振られたという彼氏のところから帰る途中、あの公園で泣いていたのかもしれない。 「……家、どこ? 送るよ」 「……え?」 俺は思わずそう言ってしまった。 彼女もそれを聞いて驚いたのか、全部引っ込んだみたいにポカンとした顔で俺を見た。 ……あれ? 俺は首を傾げた。 この顔、どこかで……? 「あの、ありがとう……。……どこかでお会いしたこと……」 ○○駅、○○駅。ドアが閉まります。ぴんぽん、ぴんぽん。バタン。 結局そのまま終着駅まで乗ってしまった。思い出話って、これだから……。 でも、あの日の続きが始まった。 そうだ、彼女の名前は、というらしい。 |